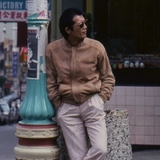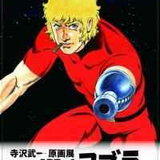八甲田山のレビュー・感想・評価
全78件中、1~20件目を表示
白の恐怖・・・雪山に呑まれた行軍。
天は我々を見放した!
当時、流行語にもなって、話題作だった本作品。でも、何故か縁がなくて今に至ったのですが、今回BSで放送されたことから、初めて全編鑑賞しました。
スゴイですね〜!まさにこの一言です。
3時間弱の本作品、一気に魅入っちゃいました。殆どが雪山での撮影の為、変わり映えの無い画面が延々と続くのですが、目が離せなかったですね。惹きつける魅力、見せ付ける迫力に溢れてました。
昭和の名優たちの勢揃いって感じでしょうか。懐かしいあの顔が、あれもこれもと登場し、あれ、この人も出てたんだ!なんて、驚きもチラホラ。
高倉健さんが渋い、北大路欣也さんが若い、加山雄三さんがカッコいい、三国連太郎さんの怪演、どれもこれも見応え十分でした。
そして軍隊の話ですから、男達の殺伐した映像ばかりの中で、女優陣の美しさが際立ってました。加賀さん、栗原さん、秋吉さん、ホンっと昭和を代表する美人女優にウットリです。
実際に起こったことの映画化なんで、結末も分かってるんですが、見事なドラマ化だったと思います。
八甲田山の雪中行軍については、テレビの特番で実際の写真も見たんですが、ホンっと凄絶ですね。生き残った人も、凍傷で手足が無いとか、凄惨な場面が生々しかった。
軍隊が厳しいってのも分かるけど、雪中行軍なんて単なる訓練なんだから、それで死んじゃったら元も子もないんだけどね。
CG全盛の昨今で、生の迫力。恐ろしい雪山が、まさにそこに在るって存在感に圧倒された一本でした。
貴重な若い命が、短慮な指揮で奪われる
ツタヤでは借りて観れるがサブスクでは配信していない邦画の傑作
1977年公開作品
過去数回鑑賞
TSUTAYAレンタルDVD鑑賞
なぜかサブスク配信されていない数ある日本映画の名作の一つ
原作は『劔岳 点の記』の新田次郎
監督は『ゼロ・ファイター 大空戦』『日本沈没(1973)』『海峡』『小説吉田学校』『動乱』の森谷司郎
脚本は『羅生門』『生きる』『七人の侍』『蜘蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『私は貝になりたい(1959)』『切腹』『日本沈没(1973)』『砂の器』『八つ墓村(1977)』の橋本忍
1902年に実際に起きた八甲田雪中行軍遭難事件
山岳遭難事故としては人類史上最悪
210名中199人が死亡
迫り来るロシアとの戦争に備えての冬季訓練だった
その出来事をもとに新田次郎が小説化
それを原作に映画化された
暗い内容で映画会社の中には制作に反対意見もわりとあったという
しかしこの年1番の大ヒット映画
映画作りを推し進めた側もヒットを確信していたがここまで大当たりするとは想定外
船頭多くして船山に登る
中間管理職の悲哀
多くのサラリーマンに受けたと聞く
高倉健が主人公のようだが実際の主人公は名台詞を残した北大路欣也
一歩譲ってダブル主演か
二人の名優の顔ヂカラがすごい
台詞がなくても顔だけで勝負ができる
それに加えて三國連太郎の悪辣ぶりもなかなか
緒形拳や加山雄三も出てたんだな
漢たちの映画であり女性俳優の存在感はかなり薄い
栗原小巻加賀まりこ秋吉久美子
嗚呼あと一応だけど菅井きん
久々に観たがそういえば出ていたなって感じ
それにしてもこの頃の秋吉久美子は可愛いな
賽の河原という縁起の悪い地名が登場する
実際のところ多くの軍人の遺体が発見された場所で事故からしばらくして名付けられた地名なようだ
青森神田連隊が目指した田代は今でも温泉は沸いているいるものの宿泊施設は廃業し廃墟となっているそうだ
吊り橋は崩壊し温泉地には辿り着けない状況
2031年完成予定の駒込ダムに沈む運命
残念でならない
青森県もなんとかしたかったがなんともならなかったのだろう
険しい山に温泉地はあるもので交通の便の悪さから閉業した温泉地は東北の各地にある
その点でいえば秋田県東成瀬村と岩手県一関市の境目にある須川温泉なんてまだ恵まれている方
なんとか生き残った山田正太郎は全ての責任は自分にあると回復すると心臓のあたりに拳銃を当てて自害している
東電の上層部は誰も責任を取らず自分は悪くないと主張して裁判官もそいつらの味方
雲泥の差だ
嘆かわしい
日本に侍はもういない
なんだよサムライジャパンとか
配役
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊長の徳島大尉にに高倉健
徳島の幼少期に石井明人
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の田辺中尉に浜田晃
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の高畑少尉に加藤健一
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の船山見習士官(気象観測担当)に江幡連
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の長尾見習士官(隊員の疲労度調査担当)に高山浩平
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の倉持見習士官(装備点検担当)に安永憲司
青森第五連隊の長谷部善次郎一等卒の兄で弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の斉藤伍長(歩測担当)に前田吟
元山峠から銀山への行軍中に転倒し捻挫したため野営中は現地の民家に泊まり行軍隊を外され汽車で弘前に帰営する弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の松尾伍長に早田文次
徳島大尉の命令で捻挫した松尾伍長を背負う弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の川瀬伍長に吉村道夫
小山二等卒と共に行軍実施前の宿営地交渉と経路事前調査担当の弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の佐藤一等卒に樋浦勉
佐藤一等卒と共に行軍実施前の宿営地交渉と経路の事前調査を担当した弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の小山二等卒に広瀬昌助
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の喇叭手の加賀二等卒に久保田欣也
佐藤一等卒・小山二等卒と共に「行軍本番前の経路事前調査と宿営地・案内人・消耗品・食糧調達交渉」を担当した弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の一等卒に渡会洋幸
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の曹長に原敬司
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の見習士官に北村博之
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の見習士官に塚田一彦
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の見習に広尾博
弘前歩兵第三十一連隊・雪中行軍隊・第一大隊第二中隊の見習士官に佐藤健二郎
第四旅団司令部で行われた「日露戦争に備えての雪中行軍作戦会議」終了後「八甲田山の雪中行軍で両隊をすれ違う形にしよう」と提案した弘前歩兵第三十一連隊の連隊長に児島大佐に丹波哲郎
徳島大尉の上官にあたる弘前歩兵第三十一連隊第一大隊長に門間少佐に藤岡琢也
雪中行軍作戦会議において弘前の徳島大尉と青森の神田大尉をそれぞれの指揮官に指名した弘前第八師団第四旅団長の友田少将に島田正吾
「日露戦争に備えての寒地教育訓練確立」を目的として青森第五連隊と弘前第三十一連隊への「八甲田雪中行軍」を友田少将と共に提案した第八師団参謀長の中林大佐に大滝秀治
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二大隊第五中隊長の神田大尉に北大路欣也
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二大隊第五中隊第一小隊長の伊東中尉に東野英心
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二大隊第六中隊第二小隊長の中橋中尉に金尾哲夫
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二大隊第七中隊第三小隊長の小野中尉に古川義範
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二大隊第八中隊第四小隊長の鈴森少尉に荒木貞一
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第一大隊および第三大隊選抜特別第五小隊長の中村中尉に芹沢洋三
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・中隊本部所属の野口見習士官に山西道広
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の藤村曹長に蔵一彦
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第五小隊所属の谷川曹長に森川利一
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第五中隊第二小隊所属の村山伍長に緒形拳
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第一小隊所属の高橋伍長に海原俊介
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・第二小隊所属の渡辺伍長に堀礼文
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊・中隊指揮班所属の江藤伍長に新克利
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の平山一等卒に下條アトム
徳島隊の斉藤伍長の弟で青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の長谷部善次郎一等卒に佐久間宏則
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の小野中尉の従卒に浜田宏昭
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊のソリ隊の兵卒に大竹まこと
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の井上見習士官に仲野裕
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の裸で凍死する兵卒に原田君事
雪中行軍の目的を履き違え「弘前三十一連隊に勝つため」にすり替えて大惨事を招いてしまう雪中行軍随行大隊本部第二大隊長の山田正太郎少佐に三國連太郎
当初は八甲田雪中行軍に参加予定はなかったが山田少佐の命令による随行隊に付くこととなった倉田大尉加山雄三
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の沖津大尉に玉川伊佐男
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の永野三等軍医に竜崎勝
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の田村見習士官に日和田春生
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の進藤特務曹長に江角英明
青森歩兵第五連隊・雪中行軍隊の今西特務曹長に井上博一
連隊長の津村中佐に小林桂樹
連隊本部所属の木宮少佐に神山繁
遭難救助隊の隊長の三上少尉に森田健作
遭難救助隊伝令担当の花田伍長に伊藤敏孝
神田大尉の妻の神田はつ子に栗原小巻
徳島大尉の妻の徳島妙子に加賀まりこ
斉藤伍長お長谷部一等卒の伯母に菅井きん
宇樽部村の村民の滝口さわに秋吉久美子
熊ノ沢部落の村民の沢中吉平に山谷初男
熊ノ沢部落の村民の福沢鉄太郎に丹古母鬼馬二
熊ノ沢部落の村民の沢田留吉に青木卓
熊ノ沢部落の村民の大原寅助に永妻旭
田茂木野村の村長の作右衛門に加藤嘉
宇樽部村の村民で滝沢さわの義父の滝口伝蔵に花沢徳衛
三本木の宿の主人の鈴木貞雄に田崎潤
中里村の老人に浜村純
徳島隊と共に10泊11日の雪中行軍を行った東奥日報の従軍記者の西海勇次郎に船橋三郎
観ていて本当に凍てつく空気を感じた
感想が次から次に湧き出る
午前十時の映画祭で鑑賞しました。ずっと観たかった映画で、テレビ放送しないかなと待っていましたが映画館で観ることができるなんて!!と期待大でした。
役者さん、音楽、映像、どれをとっても素晴らしく、観る前はちょっと長いかな…と思いましたが、あっという間でした。高倉健、北大路欣也、三國連太郎、…今の俳優でこの映画を作ったとして、あの重厚さは出せるでしょうか?でも小説原作で史実とは少し違うそうなので、史実に近いリメイク版も観てみたいような…
また、女優さんは少ないですがどなたも光るような美しさ、可憐さでした。
色々なことを考えさせられる映画で、観てよかった、と久しぶりに大満足な作品でした。
大竹まことはどこにいた?
銀世界は死の世界
私は見て良かったかな
旦那いわく、雪中をずっと歩いてるだけの映画との意見、まぁ確かにそうなのですけどね。
エンタメでは無いので、ストーリーに謎解きやドンデン返しなどを求める人には向きません。
人間の愚かさやエゴ、自然の恐ろしさなどを改めてかんじました。
現代社会はITで何でもこなせるようになり、人間が昔よりすごくなったように感じるけど。それも錯覚なんだと改めて思ったり…
強大な自然現象の前では人間はこんなにも無力なんだなと思いました。成すすべもないです。
戦争の練習のための雪山での命がけの練習、なんとも悲しい時代だな、とも思いました。
小学生のときにテレビで途中まで見ていたので、改めて映画館で見れて良かったです。きれいに修復された映像も良かったですよ。
あ!秋吉久美子さん、めちゃ可愛いです!
実話をもとにした名作
登山が趣味なので、八甲田山雪中行軍遭難事件は知っていたのもあり、生まれる前の作品ですが映画もずっと観たいと思っていました。いつかネットで観ようかなと。
そして、4Kリバイバル上映されていることを知り、家から少し遠かったですが足を運び鑑賞。
その結果、はやり大スクリーンで観て本当によかったです。
最近邦画をよく観るのですが、ここまでの映画って最近はなかなかない気が…。
自然の恐ろしさを感じつつ、山や自然は移り変わる景色や時代、生き物たちを見守り続けている…そんなことも感じました。
八甲田山雪中行軍遭難事件はリーダー論でもよく使われたりしますが、極限状態での判断がどのような結果になるのかも改めて学びました。
シナノ企画
長い…と観る前は思ったけど
映画館出た直後の現世界がより平和に感じた
冒頭からまず出演者が濃くて驚いた。笑
無謀で無計画、無知と無策など世の中にある「無」を全て並べ立てても足りないくらいの「無」の連続。途中から演技とはいえ言うことやることが腹立たしくて、三國連太郎自体が嫌いになりそうなくらいだった。笑
昔の軍人は階級上がっていくと無知で無謀な人だらけで持っているものは役に立たないプライドだけだもんなー。
日本が戦争に負けた縮図を見た気がした。
そういや「勇気ある撤退」っていつから使われるようになったんだろう、なんてことも脳裏をよぎりました。
大隊長(三國連太郎)が案内人を断った辺りから(結構早い)、イライラして自分の心の声がバッカジャナイノ?バッカジャナイノ?と連呼し脳内に響き渡るので集中が途切れがちになるくらい(笑)、その同じタイミングから「これ撮影してる方も相当命懸けでは?」と思ったらもう気になり出して止まらない。
雪中行軍の話は本でも散々読んでいるので、あの雪山に入ってからどうなるか?はもうわかってたし、映画に描かれてない酷い話も見聞きしてたから、映画でどうなるかと期待したけど思った以上に演者が迫真の演技だった。
いや、雪山ではあーにもなるか(苦笑)
それに昔の俳優さんはなんというか全身全霊で演じてるのをヒシヒシと感じます。
いやあの撮影は本当に大変だったろうな…とカメラマンとか撮影隊全体の心配もしてきちゃうくらいでした。
噂に聞いていた映画「八甲田山」は噂以上の凄さと迫力でした。
リーダーシップと
「日露戦争を前にして軍首脳部が考え出した、寒冷地における人間実験がこの悲惨事を生み出した最大の原因」(新田次郎)
こういう映画だったのか!まるで知らなかった!徳島大尉(高倉健)は豪放磊落であり慎重な人物として描かれている。冒頭の会議シーンで山田少佐(三國連太郎)は煙草ばかり吸っている唯一の者でいけ好かない奴だとすぐわかる。山田には雪の中へいち早く消えて欲しいと本気で思った。だから途中で「自分の思い通りに行く!」と隊から離れた村山伍長(緒形拳)は雪山を知る人間として正しい判断をした、どんな思いが脳裏にあったか分からないが。こういう映画を初めて見て途中でかなり泣いた。猛烈な吹雪と極寒で白しかない中、低体温症による幻覚や幻聴で、春の到来、菜の花やツツジの暖かい色、田植え、稲の緑、夏の川遊び、秋の収穫、弘前のねぷた祭りと色鮮やかな白昼夢を彼らは見る。
真面目で優秀で信頼厚い神田大尉(北大路欣也)は山田少佐ゆえに想定外の立場に追いやられる。山田少佐、早く死んでくれと思ったが、上司だから若い人達の援助と犠牲を得て生きて戻る。最期がどうであれ、フィクションであれ、あまりに現在の日本と同じじゃないか。
徳島大尉の雪山対策の諸々は緻密に練られており隊員への指示は的確で具体的だった。雪山の恐ろしさを知る生まれ育ちがものを言うのだろう。どんな行程でも常に案内人をつけていた。歩数を数える役目の斎藤伍長(前田吟)は歩きながら「1、2、3・・・」と数え百までいったら豆をポケットに入れ次は2から始める。医務担当の者、喇叭担当の者もいる。徳島大尉が惜しげもなく事細かく教えてくれたことを神田大尉は心から嬉しく受け取り、指揮官として同じように計画し実行したかったに違いない。無念だったろう。
反省でありびっくりしたのは日露戦争で日本が勝った!それが西欧を驚かせた!程度しか知らなかったことだ。日本史授業でも八甲田山の惨状は多分教わらなかったし自分も知ろうと思わなかった。支配権を握る側が発言権の弱い側の判断や価値観を押しのけるのは今も同じだ。この雪中行軍隊員で日露戦争に行った者は「全員戦死」の文字が最後に流れショックを受けた。それで第五連隊の悲劇を知る者は闇に葬られうやむやにされたのか?戦争に勝とうが負けようが兵士は死ぬ、若者が死ぬ。
芥川也寸志の曲は素晴らしかった。同じモチーフでも、苦しい第五連隊は短調で重く、第三十一連隊では明るく前へ進めと励ます音楽だった。映画を見てから原作本を読み数日してまた映画館で見た。
おまけ
新田次郎『八甲田山 死の彷徨』から:徳島大尉はさわ(秋吉久美子)に案内料五十銭玉一個を与えて、「案内人は最後尾につけ」と大きな声で怒鳴った。「もう用はねえってわけかね」さわ女が言った一言は、それを聞いていた隊員たちの心を打った。隊員たちは心の中で彼女にすまないと思った。
新田次郎氏から、権力構造への感受性無しに上澄みで感動なんかしてないよね?と言われた気がした。
雪だるまが
軍事訓練でここまでするのか?命を何だと思っているのだ…。
50代の私ですら、上官のパワハラや夫婦の在り方、暮らしぶりに隔世の観でした。
同時に、日本人の美も感じましたが。
20代の人たちには、この映画は時代劇かもしれませんね。
スキー場で、何回かホワイトアウトを経験したことがあります。
本当に、白い闇に包まれ、方向感覚は麻痺します。
それでも、パニックにならなかったのは、ここはゲレンデで、周りにたくさんの人がいるとわかっていたから。
けれど、自然の山の2キロは、季節、天気、高低差、山での経験値によって、死につながると実感しました。
私は、本格的な登山はしたことがありませんが、山はナメたらあきません。
昨年4月中旬、弘前・奥入瀬・青森のルートを、2泊3日で車で旅しました。
弘前は葉桜、奥入瀬は新芽がまぶしく、青森に抜ける時に通った八甲田山は銀世界でした。
道路の除雪は完璧で、昼間通る時はノーマルタイヤでOKでしたが、道路の両脇に積み上げられた雪は、2メートルくらいありました。
途中の酸ヶ湯温泉の宿は、雪に埋もれていました。
あの山を1月にこえるなんて、改めて暴挙だと感じました。
命令系統がシンプルな小隊が無事で、現場の声を無視して編成された大部隊が遭難するのも、象徴的でした。
知覧特攻平和会館を訪れた時にも感じましたが、ひとりの若者の後ろには、親もきょうだいも祖父母もいて、ひとりひとりがかけがえのない命です。
このミッションも、ひとりひとりの命が粗末に扱われているようで、憤りを感じました。
国民がいてこその国なのだと、気づいて欲しいです。
午前十時の映画祭は、主要顧客がシニアの方々です。
上映時間3時間は長く、トイレに立たれる方が数人おられました。
ちょうど後ろに座っていたご高齢のご夫妻が、ここは映画館ではなく自宅のリビングか!?と思うくらい映画へのリアクションを話していて困りました。
私は、2度「上映中は静かにして下さい」と伝えたのですが、それでも、旦那さんの方は完全に静かにならなかったです。
映画館という環境に応じた行動がしにくいのなら、自宅で観てくれーと思いました。
午前十時の映画祭を観る時、次からは、ギリギリに来場して、周囲に人がいない席を取ろうと決めました。
豪華俳優陣で雪山こわっ
全78件中、1~20件目を表示