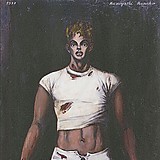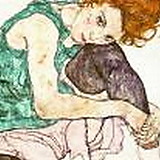秋刀魚の味(1962)のレビュー・感想・評価
全58件中、41~58件目を表示
なぜ小津は分離を描き続けたのか
小津ちゃんの遺作である本作を鑑賞した後、もしかしたら彼は自身の母との関係をずっと描いてきた人なのでは、という連想を抱きました。
生涯独身だった小津は、終生母親と暮らしていたそうです。そして本作は母親と死別後に撮った作品。トボけた味わいのあるユーモラスな雰囲気ながら、その影響はモロに出ていると感じました。
本作では、対象を喪失した悲しみよりも、強烈な孤独感が印象に残ります。「ついにひとりになってしまった!」という小津の内面に渦巻く動揺が伝わってくるようです。
主人公・智衆の恩師である東野英治郎演ずる老人ひょうたんと、杉村春子演じる中年娘との関係は、小津自身と母親が投影されているように思えました。
ある夜、ひどく酔ったため、智衆ら教え子に自宅まで送ってもらったひょうたん。ひょうたんは歳のいった娘と2人でラーメン屋を営んでいます。
送り届けた教え子たちが去った後、ぐでぐでのひょうたんと娘の2人だけになり、突如娘が涙を流すシーンは強烈です。ライトも陰鬱となり、異常なまでの暗さと惨めさが描かれていました。いずれひとりになり、じわじわと孤独と絶望を生きる運命からもう逃れられない。そしてその運命から脱するチャンスは過去にあったかもしれない。父親から離れて、自身の幸せを追うこともできたかもしれない。けれど掴めなかった。もう遅すぎる。そんな後悔の念まで感じられる、凄まじい場面でした。
ひょうたんの娘は2シーンくらいしか出てきません。役どころとしてはチョイ役ですが、ここに名人・杉村春子を配した意味があるのだと思います。
(東野英治郎と杉村春子の顔が超似てるというギャクの面もあると思われる)
小津のバイオグラフィでは、未婚であるよりも、終生母親と暮らしたことに違和感を覚えていました。そんな人が、娘の嫁入りや家族の死別等、喪失すなわち愛する対象との分離を描き続けたわけです。
(正確に言うと関係性全般がテーマですが、喪失・分離が特に目立つ印象です)
これまで、小津はなぜ分離を描き続けたのかよくわかりませんでした。しかし、本作を観て、小津自身が分離できない苦しさを抱えていたからなのでは、と思うようになりました。
表面は父と娘の物語ですが、それは分離できない母と子の翻訳なのかもしれません。
小津が体験したリアル喪失を彼がどのように乗り越えるのかは見ものですが、それが作品化されることはなく、小津は母の後を追って亡くなりました。本作が遺作になってしまったのは残念です。
演者について。岩下志麻はさすがの美しさですね。鋭い美貌。でも、歳食ってからの志麻の方が妖艶で魅力があるようにも感じます。
あと、智衆の友人の若い奥様がとても美しくて品があり、目を惹かれました。誰かと思いしらべたところ、環三千世というヅカ出身の方でした。若くして引退、しかも早逝された方のようで、wikiもないですが、小津の『小早川家の秋』にも出演されているとのことで、楽しみです。
小津作品
モノクロからカラーとなってもまだまだ続く嫁に行くのか行かぬのか問題...
間が引き立つ、日本の映画
古き良き時代の黄昏を感じてください。
ラストの「独りぼっちかぁ」が印象的。トリスバーでの元軍艦の乗組員が...
●古き良き昭和。
スーツ姿の笠智衆は初めてだ。
高度成長期突入段階の日本。
女性が普通にお茶汲みしてたり、冷蔵庫買おうか迷ったり。
ゴルフクラブやハンドバックに憧れたり。
一方で、戦争の会話も。
「なんで負けたんですかね」「負けてよかったんだろう」
東京物語でも、こういう1コマがあったな。
バーで軍艦マーチをかけてもらう。
ご機嫌に踊り出す。
曲に合わせて敬礼する。
教育ってのは怖いもんで、戦後世代はなんとなく軍歌に抵抗を感じる。
でも彼らにとっては、青春真っ只中の盛りの流行歌なんだろうと実感させられる。
別に軍歌そのものが悪いワケじゃない。
同じように、適齢期が来たら女性は結婚を、とか、
日本人みんながほとんど同じ価値観で生きていた時代。
そうやって見合いでスッパリ嫁に行ったり、
娘がいなくなったらなったで、男たちは生きて行く。
人間がその寿命の中で、それぞれのタイミングを理解して
自然の摂理に抗うことなく生きた時代。
時に窮屈さもあっただろうが、人はリミット決めないと
ダメだなあと感じさせられた。
秋日和と日をあけず観たせいか前半は笠智衆と佐分利信の設定が違うだけ...
軍艦マーチのシークエンス
元駆逐艦の艦長である笠智衆が、当時の乗組員だった加東大介とバーへ行くシークエンス。この部分は映画の本筋とは直接関係のない話であるのに、わざわざ挿入されたのはなぜだろう。
軍艦マーチに合わせて敬礼をする加東に応えて、笠とバーのマダムの岸田今日子が掌を顔にかざす。この時の岸田の表情のなんと可愛らしいことか。控えめに微笑みながら頭を左右に揺らす彼女からは、後年のおどろおどろしい役柄にぴたりとはまる女優を想像することはできない。
そして、敬礼をしながら行進を始める加東のコミカルな姿は、どこまでが冗談で、どれくらい真面目なのか見当がつかない。この人の芝居にどこまで本気で付き合えばいいのか分からない状況を観客はしばし楽しむことができる。こうした演技はこの人をおいて他に出来ないだろう。主役の笠ももちろんだが、加東もオンリー・ワンの俳優だ。
考えてみれば、他にも代替えのきかない俳優が何人も出ている。中村伸郎だって、あの冷めた毒舌と下ネタで友情を温め合う芝居など他にできるものがいるだろうか。杉村春子だって、あの行かず後家の品格を保ったやさぐれ感を他のどの女優が出せるというのか。
しかし、このシークエンスで重要なのは加東や岸田の魅力ではない。彼らの仕事の素晴らしい出来映えとは本来関係のないところにこのシークエンスの意味がある。
笠と加東が「もしも戦争に勝っていたら」という話をする。もし日本がアメリカとの戦争に勝っていたら、今頃はニュー・ヨークにいるかも知れないと夢想する加東に対して、負けてよかったのではないかと応じる笠の会話。
下らない連中が威張り散らすことがなくなっただけ、戦争に負けて良かったのではないか。
これがこの二人の結論であった。
戦争を経験してきた者たちのこれが感想なのだろう。家が焼けた、食べ物に不自由をした。そんなことよりも、バカが大威張りだったことのほうが嫌な思い出だったのである。
だからこそ、お道化て軍艦マーチのリズムに乗ることができるのだ。あれを偉そうに押し付けた者たちを茶化すことで、嫌な思い出を笑い飛ばしたいのだ。
遺作となった小津安二郎監督はどうしてこのような戦争への回顧を映画に差し挟んだのだろうか。きっと鉄筋コンクリートの団地で核家族という物語を始めた人々に、憶えておいてほしかったのだろう。
それにしても、ゴルフの練習をする佐多啓二のフォームはきれいだった。実生活でもかなりやり込んでいたんだろう。
ゆっくりと時は流れて
古き良き映画、でも自分好みではないかも
総合:60点
ストーリー: 65
キャスト: 65
演出: 55
ビジュアル: 65
音楽: 65
人々のありきたりの日常と彼らの抱えるささやかな問題を、しっかりと話としてまとめて映画化するという点において、本作は独自の位置を確保している。やたらと派手な出来事や目を引く映像がなければ映画化にならないことが多いであろう娯楽産業において、この位置づけは興味深い。その中で、恩師とその娘の人生の「失敗例」としての描き方はなんとも厳しい。
しかしこのころの映画の特徴なのか小津安二郎監督の特徴なのか知らないが、科白は互いに重なることもなく交互に順番で行儀よく喋られる。映画の中の会話というよりも舞台演劇の科白回しのようだ。しかも淡々と棒読みをするだけである。現代の映画を見慣れていると、それがいかにも演技という感じを受けてあまり自然な演出には思えない。セットもたいしたことはない。
この不自然な演出も含めて、なんとなく良さはわかりつつも、それほど好きな作品とも言い難い。やはり昔の映画だなと感じるし、のんびりしたなかなか進まない話にもちょっと退屈を覚えることもある。世間の評価も高いし古き良き映画なのだろうが、もしかすると自分の世代の好みではないのではないかと思う。いやでも若い世代もこの映画を支持しているようだから、ただ単に自分の趣味にぴったりとは合わなかったということか。
あっ、わかってる、わかってる、しっかりおやり。幸せにな
映画「秋刀魚の味」(小津安二郎監督)から。
今更、私がわざわざ書かなくても・・と思うくらい、
驚くほどの人たちが、この作品の感想をネット上に書いている。
そしてまた、全編を通して、一度も登場しないのに、
タイトルが「秋刀魚の味」だから、その推測も多くの人が・・。(笑)
一度、「秋刀魚の味」で検索して欲しい、本当にビックリするから。
さて、私は私の方法で・・とメモした台詞を振り返って眺めていたら、
ひとつ気付いたことがある。
1回の台詞が非常に短く、NGを出すような長い台詞は無いに等しい。
それが、ひとつのリズムとなって、画面の切り替えに繋がっている。
日常生活の家族の会話って、こんなもんだよなぁ、と感じた。
最近、1人の台詞が長くて、走り書きでメモをするのに苦労するが、
この作品は、そんなことは1度もなかった。
だから今回の「気になる一言」は、あえて長い台詞を選んでみた。
岩下志麻さん扮する娘が、結婚式を前に、父親役の笠智衆さんに、
お決まりの挨拶をするシーン。
「おとうさん・・」と口にした途端、その後の彼女の台詞を遮って
「あっ、わかってる、わかってる、しっかりおやり。幸せにな」。
これが、娘を嫁にやる父親の気持ちであり、
「長い間、お世話になりました」というフレーズは耳にしたくない、
父親の本音が伝わってきた。
ニュースになるようなことは何も起こらない、
どこにでもある日常生活なのに、こんな温かい胸を打つ作品になるのは
「魔法」を使っているとしか、言いようがない。
そう「オズの魔法使い」ではなく「小津は魔法使い」です。
全58件中、41~58件目を表示