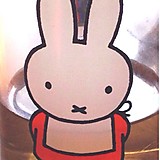黒部の太陽のレビュー・感想・評価
全37件中、21~37件目を表示
三船敏郎、石原裕次郎という豪華布陣
黒部に挑んだ男たちの男臭い記録。が、似たようなやつで言えば「海峡」のほうが私は好きだ。映画的にはこちらのほうが評価は高いだろうが、好みとしては海峡が好きだ。
だって青函トンネルって何十年とかけて掘ったんだぜ。死人は黒部のほうが多いが、プロジェクトとしては青函だね。
完全版を鑑賞。「休憩」の文字にびっくり。それくらい長い。それ故、超...
●先人達の結晶と、興行と。
2011年に気になっていた。
映画と現在から色々な思いが溢れ出た。
DVDを買おうか迷う作品。
土建業は色々、責められるが至難の連続の業界。
そして、末端の作業員が常に危険に曝されている。
機械化(大型シールドマシーン)、シールド工法が進歩してきたので最近、作業員の死亡を聞かなくなったような気がする。
2016.3.26(土)に北海道新幹線が開通。
貨物線と在来線の4本がそれぞれセパレートできれば
本当はよかったのかも。
貨物との共用だと安全上、340km/hが出せない。
新幹線の意味がない。海外のように貨物車両+普通車両で
走らせるといいのか?
また、震災から5年経つが、除染作業はほぼ50年掛かる。
私も見届けられる自信がない時間。
なぜか、トンネル作業と重なってしまう。
今、東海道リニアの作業(品川〜名古屋)が始まっている。
映画を見た限りでは有毒ガスが出なかった気がする。
新潟の十日町のトンネルでは有毒ガスが出て、作業員が亡くなっている。
水・地熱だけを考えれば、意外とトンネルは抜けるのかなと思った。
「黒部の風」を知るため、もう一度、鑑賞し、トンネル形状を
頭に入れたい。
複雑な人間関係も表現できてあり、感動した。
これまで、3度も黒部に行っているが、やっと映画を見た。
いま、見るからさらに感動が増すのかもしれないと勝手に
思った。
昭和の男達
田舎町の行事にてフィルムで観賞
これを観ちゃうと最近の日本映画ショボすぎる。
崩落を伝える恐怖の音
総合65点 ( ストーリー:65点|キャスト:70点|演出:65点|ビジュアル:75点|音楽:60点 )
掘りたてで不安定なトンネルを崩れないように支える支柱や板が、不気味な音を立てて曲がって割れ目から石が落ちてくる。家族にも会えない人里離れた狭くて暗いトンネルの中で、いつ崩落を始めそれに巻き込まれてしまうのかという恐怖感に襲われる。断層に湧水にと難工事が続き、上からは仕事の怠慢を疑われ、下からは厳しい仕事に不満が燻り逃げ出すものが続出する。世紀の大工事の現場には土木工事に男を賭ける心意気が見えた。「狂った果実」に出ていた若い頃は台詞棒読みで大根役者だった石原裕次郎も、年月を経てここではずっとまともな演技になっていた。
しかし建設計画からいきなりトンネル内部、そして貫通からダムまで場面場面が飛んでしまっていてどうも物語の繋がりが悪いし、その間に感動を作ろうとするわざとらしい人間劇が挟まれているのは余計に感じる。それにトンネル内部の危険性を表す描写はあっても、トンネル工事を進めて行く技術的な側面や掘削の描写が少なくて、工事自体の素晴らしさが伝わってこないし現場の臨場感を削いでいる。大勢が死んだのは知っているが、危険ばかりが強調されているのは不満。かなり金がかかっていそうだし良い部分もありつつも、あちらこちらに引っかかる部分もあった。
建設の醍醐味がわかる名作
映画史上は特筆されるだろうけど
ただただすごい
長らく幻の映画となっていた本作が映画館で上映されることになって、以前はスケジュールが合わずに断念したが、今回はなんとか観ることができた。
ただただすごい映画である。
トンネルの掘削現場の迫力もさることながら、人間ドラマも見応えがあった。
かつてトンネルの現場で息子を死なせた岩岡(辰巳柳太郎)と、兄を殺されたと思っている息子(石原裕次郎)の確執は、辰巳の粘着質の演技とあいまって胸にささるものがあった。
息子が父親を追いつめるシーンの裕次郎の芝居は、いままで観たことのないものであった。
裕次郎の映画を見直さなければならないかもしれない。
製作当時の状況を考えると、三船敏郎と石原裕次郎がイニシアチブをとっていたと思われる現場で、熊井啓監督は、ドラマ部分で力量を発揮している。
ただ関電北川(三船敏郎)の娘のエピソードは必要だったのか。
世紀の大工事を映画化した映画人の執念というものを感じた。
CGがない時代に描くスペクタクル。すべてのことをコントロールしていたとは思えない映画の現場。
想像を絶する苦労があっただろう。
それだけのものが映画には込められている。
スクリーンで観ることができて幸せである。
観ている自分にも自然と力が入ってしまう、見逃せない名作
あの幻の映画『黒部の太陽』を観られた事は私の映画人生にとっても新しい財産になった気がしています。
少々大袈裟と思われるかも知れませんが、敗戦の日本から脱出し、高度経済成長の時代へと日本が向かう中で、工業化をひたすら押し進め、日本の未来の発展は工業製品の製造に掛っていた時代で、その状況下では、益々重要の増える電気消費の為には、ダムを作り水の貯蔵は不可欠であった当時、どれ程の犠牲を強いても、戦後日本の立て直しには、ダムの建設を最優先しなければならないと考えた、当時の大手建設業界が一丸となって、国家の威信を掛けて取り組んでいた大事業、その過程をこの作品が再現する。
これはドキュメンタリータッチのドラマとしてあくまでも描かれている点が素晴らしい!
これを単なる記録映画とせずに、あえてドラマとして描く中で、巨匠熊井啓監督が当時の社会の在り方や、日本の将来を様々に考察し、撮影をされた事に大きな価値が有ると私は思うのだ。そして、そんな大作映画が生後のこの時期に制作されていた事実を観て、驚嘆した。
現在では昨年の東日本大震災が起きてしまい、原発の放射能汚染被害も起こり、不安の材料であり、諸悪の根源の様な存在として敵視されている原発であるけれど、この映画を観ていると一番に感じるのは、一人一人の人間の大きな犠牲の上に現在の日本の姿と言うものが存在していて、良い悪いと言う議論は不毛で、時代を長く経た未来でこそ、そのプロジェクトの真価が問われるのであり、その時代の只中にいる多くの人々は懸命に目の前に置かれている仕事が、未来に生きる人の為になるとひたすら信じて、励んで来られた、そんな名も無き大勢の犠牲者の見えない努力と犠牲の果てに、当たり前のように、日々変わらぬ快適な生活を享受している私達だけれども、過去の人々が創り上げた基盤が出来ている事は本当に有り難い限りだ。
この映画が制作されていたあの時代は5社協定などが厳しく存在しており、中々自分たちが作りたい映画が出来なかった時代であり、俳優の自由に好きな作品に出演する事が不可能だった時代に、三船敏郎と石原裕次郎が自ら制作に加わる事で実現した力作だ。
CG合成が出来ないあの時代で、この迫力ある作品は、やはりロケセットで、現実の現場で多数撮影が行われていたからこそ、描き出された迫力と言うものだ!
今月初めに亡くなられた我が国のバイプレイヤーの大御所である大滝秀治もまだ若くて良い芝居をしている!そして出演者の殆んどが、今では亡くなられてしまい、存命の俳優さんは極僅かであるけれど、出演者の皆様が、とても活き活きと見事に輝きを放ち役に取り組んでおられるのも、素敵な事だ。機会があれば、この様な過去の名作との出会いをたまには持って置きたいものだ!只只ありがとう!と感謝で胸が一杯になる!ラストの宇野重吉と北林谷栄のダムの上に立つ老夫婦の無言の芝居が脳裏に焼き付いた!
映画ファンなら、「見ておくべき」
遂に「黒部の太陽」を見た!
“裕次郎の夢〜全国縦断チャリティー”と題して、あの「黒部の太陽」が上映。
ご存知の通り「黒部の太陽」は、DVDどころかビデオ化もされておらず、石原裕次郎生誕○周年とか没後○周年でしか上映されない幻の作品。
映画ファンとしては見たくてもなかなか見れず、しかもノーカットで上映されるのだから、これは絶対見るしかない!と思い、電車に乗って隣町の映画館まで観に行って来た。
3時間強、ズッシリとした重量感と見応えの力作。
落盤シーンなどほとんどが生身で、撮影中死傷者も出たという。
この映画を作ろうとする姿勢が劇中の工事と被り、その記録映像のような本気度は凄まじく、「劇場の大画面で見て欲しい」という石原裕次郎の意志も納得。
冒頭、“戦争の焼け跡から復興した人々の記録”とのスーパーが出るが、それは東日本大震災から復興する現代人へ掛ける言葉に他ならない。
工事責任者として一人の父親として苦悩する姿を、三船敏郎が力演。
トンネル屋の父と確執・対立する図面屋の息子を石原裕次郎が熱演。
工事中基盤が軋み、まるで不気味な怪物の鳴き声のよう。それでも、難航する一大工事にたくましく挑む、多くの人々の群像劇でもある。
昔はこういう力作があった…とは言わない。
全国縦断上映なので、もし、住んでる町や近くの町で上映されるのなら、是非見て欲しい。
こんな機会は滅多に無いのだから!
(印象の“幸せ”は、見れて良かった!という意味で)
全37件中、21~37件目を表示