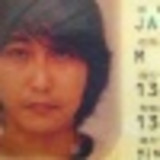狂った果実(1956)のレビュー・感想・評価
全18件を表示
時代を超えても若者の苦悩は変わらず!!
新人・石原裕次郎、津川雅彦の初主演作!!
石原裕次郎もさることながら津川雅彦の初々しさは中年の魅力を醸し出す円熟の演技とは別の一面が観られ必見!!
そして石原裕次郎は太陽族の体現者として大人の世界に反抗する若い世代のアイコンとしてこの作品の中でも怪しい魅力を振りまいている・・・・・・・
70年前の作品となるが、若者のモラルの喪失は時代の差こそあれ変わらないと実感させられます!!
昔の鎌倉駅
仲良し兄弟が人妻痴女にたぶらかされ仲違いする話。 どういう女?そら...
【高等遊民の様な奔放な兄と、真面目な弟が愛した若き人妻。そして、赦されざる三角関係が齎した衝撃のラスト。今作は邦画の概念を打ち破った日本のヌーベルバーグ的位置にある作品なのである。】
■夏の逗子海岸。
何不自由なくヨットやサーフィンで遊ぶ兄弟。
享楽的な兄の夏久(石原裕次郎)に対して、弟の春次(津川雅彦)はウブで純真だったが、海岸で出会った美女、恵梨(北原三枝)に引かれ、真剣に付き合うようになる。
だがある日、夏久は偶然に、恵梨に夫がいることを知ってしまう。
◆感想
・今作では、アンモラルな「太陽族」のような兄の夏久と、弟の春次の対比が巧く描かれている。
・又、夏久が夫がいる恵梨をそれ故に誘惑し、恵梨が大した抵抗もせずに二人が情交を結ぶシーンもアンモラルである。
この描き方は小津監督に代表される、それまでの邦画では考えられない。
■若き、石原裕次郎、北原三枝(ご存じの通り、今作品を切っ掛けに結婚。)津川雅彦も当たり前だが、魅力的である。
<ラスト、夏久が恵梨をヨットに乗せ、船内で情交し朝を迎えるシーンと、二人を追ってボートを血走った目で疾走させる春次が取った行動は衝撃的である。
そういった意味で、今作はそれまでの邦画の潮流を変えた、日本のヌーベルバーグ的位置にある作品なのである。>
兄弟愛
16歳の津川雅彦が黙って怒り、兄さんと初体験相手を殺ってしまう狂気
石原慎太郎原作、石原裕次郎に北原三枝、津川雅彦が主演。裕次郎の遊び人仲間として岡田真澄も登場。海に砂浜、ヨットにモーターボート、孤島で砂利の上で体を重ねる二人。懐かしい日活青春映画の匂い。
津川雅彦が見染めたお嬢さんは、実は外人の妻で、失われた時を戻すため津川雅彦と相引きを重ねる。それを知った兄裕次郎は、北原三枝に関係を迫り、夫の留守宅で関係を重ねる。外から二階へ窓から忍び込む裕次郎の姿がなかなか良い。
最後に兄達の関係を知った弟は夜中二人を追いかけて、そして。清くも正しくもないフランス映画の様なストーリーだが、武満徹と佐藤勝の音楽も相まって、かなり魅力的な映像であった。
中平康監督、あまり名前は残っていないが、他の監督作品も見てみたいと思った。
映倫はまだない
太陽族の裕次郎
世界最初のヌーベルバーグ映画なのかも知れない
1956年 本作と太陽の季節
1959年 大人は分かってくれない
1960年 勝手にしやがれ
本作と太陽の季節こそ世界最初のヌーベルバーグ映画なのかも知れない
撮ろうとしたこと、表現しようとしたこと
それは同じだ
もしかしたらなら直接的に影響を及ぼしていたのかも知れない
まるで絵画に於ける19世紀末のジャポニズムと同じように
エロチックさの微妙な表現は露骨なものより遥かに扇情的だ
60年以上経つのに古びていない
これよりずっと後の作品の方が古ぼけているものが多い
もっと国際的に高く評価されるべきだ
世界的に誇れる作品だと思う
石原裕次郎はもちろん、津川雅彦、北原三枝は現代でも通用する美形、スタイル、ヘアを持ちアイドル性がある
題名の狂った果実の意味は、戦争が終わり平和という果実をえたがそれは無軌道な狂ったような自由であった
そのような意味だと思う
岡田真澄はハーフ顔が多い現代でもこんな美形は未だに超える俳優はいない
「水の中のナイフ」を先取り
武満徹の音楽、波に揺れるヨット、泳ぐ美女、危険な匂いのする若者。ロマン・ポランスキーの「水の中のナイフ」を彷彿とさせる。
もちろん、この「狂った果実」のほうが先に作られた作品である。ポランスキーが「狂った果実」参考にしたかどうかは分からない。しかし、成瀬巳喜男の「流れる」と同年の作品とは思えないくらい、この「狂った果実」は現代的な視点を先取りしている。
東京・隅田川には滅びゆく花柳街がまだ残る一方で、横浜や湘南にはアメリカナイズされた若者たちの風俗が現れているのだ。
太陽族が岡田真澄の家にたむろし、大人たちを批判する言葉を続けていくシークエンスは、原作者・石原慎太郎の思想そのものを耳にねじ込まれるようだ。しかも、俳優たちの滑舌の悪さも手伝って、一刻も早く終わって欲しかった。
しかし、彼らの希望無き欲望を描くこの映画の側面を伝えるのに必要であることは理解できる。
戦争が終わって十年ほどしか経っていないが、物質的に豊かであり、なおかつ思想・行動が大人たちから自由な太陽族。湘南の海を舞台に繰り広げられる若者たちのこのような物語は、ここから現在に至るまで基本的に変わることなく繰り返されている。
例えば、石川慶監督「愚行録」においても、金持ちの子弟たちが海辺の別荘を舞台に奔放な行為を繰り返す。
そこで傷つくのは「狂った果実」の津川雅彦と同様の生真面目な人物である。彼らは、自らが連中に受容されたと束の間錯覚するが、結局はアウトサイダーでしかないことを思い知らされる。
そして、所詮その核心には触れることの出来ない者の彼らに対する酷い復讐もまた同様なのである。
ださカッコいい。
邦画というより昔のイタリアかフランス映画のよう
総合:75点
ストーリー: 75
キャスト: 65
演出: 65
ビジュアル: 65
音楽: 65
石原裕次郎の初主演作にして大人気に火が付いた作品だそうだ。だがそんな彼の気障な科白の棒読みぶりにまず驚いた。相手が喋り終えてから次の人が喋るという順番を必ず守る不自然な演出にもすぐに気が付く。正直演技が上手いとは思えなかった。
制作は1956年だそうで、当時の東京周辺の学生の殆どは風呂なし便所なしの部屋で食うや食わずの貧困生活を送っていたことだろう。それなのにここでは高級外車や船を乗り回し連日パーティをしながら女遊びをしつつ、誰かを批判し喧嘩を売り退屈しのぎをする。とても日本とは思えないような現実感がないその生活は、邦画というよりも昔のイタリア映画かフランス映画の、地中海で退廃生活を楽しむ貴族の生活を見ているようだった。調べてみるとむしろこの作品がフランス映画に影響を与えたということだそうで、もしそうならば随分と先端を走っていたことになる。
公開当時にこれを見た現実社会に生きる人々はどう思ったのだろうか。これが今でも語り継がれているということは、憧れをもって本作品を迎え入れたのかな。金持ちのドラ息子の豪華な生活はともかくとして、現代的な感覚から見ると個人的には暴走する若者のその刹那的な雰囲気が懐古的で逆に新鮮に映って面白かった。現実社会に根差した生活からは対局にある、自分たちが作り出した退廃した基準に染まってしまって暴走して自ら堕ちていく姿は儚くも衝撃的。自分は好きな話だった。
ポータブルDVDによる車内鑑賞レビュー
通勤時間を活用して、ポータブルDVDプレイヤーで地下鉄内鑑賞、モバイルPCで感想文を車内執筆をしております。
日本というこの貧しい国から、遠く数万マイルも離れて、
“生活”という無粋な言葉とは無縁の場所に位置する、
「湘南」 という 独立王国。
今作は、そんな別世界に住む、特権階級の方々の物語なのです。
しかし、中盤以降は 「道行き」 的な前近代的悲劇性を帯び、捉え方によっては、演歌的・浪花節的な様相を呈してしまうのです。
狂ってしまったのは、罪作りな人妻や裕次郎氏、そして暴走をする弟ばかりではなかったのです。
不格好きわまりないこの “アンバランス” を生み出してしまった、この映画のプロット自身こそが、
実は、
誰よりも狂っていたのです。
制限文字数では語り切れず 完成版はこちら、ネタバレ注意
↓
http(ダブルコロン)//ouiaojg8.blog56.fc2.com/blog-entry-5.html
全18件を表示