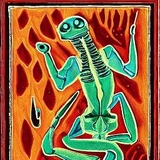関連ニュース
-

自主製作映画の収蔵から上映まで――「わらじ片っぽ」の軌跡【国立映画アーカイブコラム】
2024年3月10日 -

映画復元のスペシャリストたち【国立映画アーカイブコラム】
2022年5月18日
映画レビュー
すべての恐怖の源
百年前のアヴァンギャルド映画。百年はいいし、アヴァンギャルドもなんとなく、よい。だけど二つくっついたら、もう想像力が及ばない。
本来こういう映画は、崩壊まぎわの三階建ビルの地下にある名画座かなんかでやっているものじゃないか?扉をあけると、ガリガリにやせて血走った目をしたアートなお兄さんにギロッと睨まれる、とか。決して配信などでみるものじゃない、と、一応心してアマゾンで鑑賞させていただいた。
が、極上ホラーとして楽しめてしまった。もちろん名匠衣笠貞之助も文豪川端康成も恐怖映画を撮るつもりなどなかったはずだが、ぎっしり詰め込まれた当時の先端映画表現手法は後年ホラーの作り手にしっかり受け継がれていて、改めてみるとこれまで見た恐怖映画の映像が頭にあふれて、精神の安定を失いかけた。
さらにざらざらした白黒の映像は「貞子」や「ブレアウオッチプロジェクト」を思い起こさせて、怖い。作り物感がまったくないのである。予想していたのはまったく違った映画的快楽を味わえた。
ところでこのころ芥川龍之介は存命で、川端康成と交流があったというから、鑑賞する機会はあったのだろうか。想像するとちょっと恐ろしい。翌年彼は自殺し、同時に日本の暗い昭和が始まるのである。
どこまでが幻覚なのか?
日本映画史の中でも、これほど特異な作品はほとんど存在しないと思います。
衣笠貞之助監督による日本初のアヴァンギャルド映画であり、脚本は若き川端康成。さらに特撮に円谷英一が関わっており、1926年という時代にすでに多重露光などの実験的技法を駆使した、日本の映画表現の原点とも言える作品です。
物語は精神病院を舞台に、養務員として働く男と、その病院に入院している妻、そして結婚を控えた娘をめぐる幻想的な悲劇として展開します。男はかつて船乗りで、放蕩の果てに妻を捨て、贖罪のために病院で働いている。妻は過去に娘を池に落としてしまった罪の意識から心を病み、精神病院に閉じこめられています。娘は結婚の報告に母を訪ねますが、母が精神病院にいることを婚約者に知られまいと苦悩し、そこから現実と幻覚が入り混じる混沌へと物語は沈み込んでいきます。最後には病院がパニック状態に陥り、男が暴走する場面が描かれますが、それが現実なのか幻覚なのか、観客には判然としません。結末は、すべてが養務員の見た幻覚だったのではないか、とも解釈できるつくりになっています。
この映画の最大の特徴は、多重露光や重ね合わせによって「精神の内面」を可視化している点です。冒頭で登場する踊り子の少女は、実際に当時の前衛舞踊のダンサーであり、彼女の舞いは患者の幻想世界の象徴として描かれます。格子状の球体の前で踊るシーンは、精神の歪みや閉塞を表しており、ドイツ表現主義映画の影響を明確に感じます。檻や影といったモチーフが繰り返し登場し、精神の“折”=無意識の拘束を象徴しているようにも見えます。これは同時代に広まっていたフロイトの精神分析とも響き合うもので、衣笠と川端が「人間の無意識」を映像で表そうとした試みのように感じます。
特筆すべきは、この作品が「字幕をあえて廃した」点です。
もともとは字幕付きで制作されましたが、完成後に監督が「言葉による説明を排して、映像だけで精神を表現する」ことを決め、すべて削除したと言われています。その結果、観客は意味を掴もうとしても掴めず、映像の奔流に呑まれるような体験を味わうことになります。私自身、最初に見たときは音楽だけを聴きながら完全に理解不能で、途中で眠ってしまいました。それほどまでに、意味の手がかりを徹底して排除した映像です。けれど二度目に、脚本を解説してくれる人の動画と併せて見たとき、ようやく構造が見えてきました。それでも、これは「理解する映画」というより、「感じる映画」なのだと思います。
多重露光によって現れる重なり合う人物像、踊り子の回転する身体、森の光のちらつき――これらはすべて「狂気」そのものではなく、狂気を通して見える人間の内面を描いています。
つまり、夢オチ的な構成ではあっても、夢そのものを描いているのではなく、夢という構造そのものを映画化した作品なのです。
『狂った一頁』は、意味の消失の中にこそ美を見いだす、きわめて大胆な実験映画です。
日本映画が後に到達する「精神の映像化」――たとえば黒澤明の『どですかでん』や増村保造の心理的カメラワークなど――の原点を、すでにここで提示していたと感じました。
観る者を混乱させ、眠らせ、そして無意識の奥に連れ去っていく。そんな、1926年という時代にしか生まれ得なかった、まさに“狂った”一頁でした。
鑑賞方法: Youtube
評価: 80点
特撮の原点にして、邦画SF・アヴァンギャルドの起源
本作製作は大正末期1926年。まだ夢野久作小説『ドグラマグラ(1935)』やルイスブニュエル「アンダルシアの犬(1928)」公開前、チャップリンの「黄金狂時代(1925)」やセルゲイ・エイゼンシュテイン「戦艦ポチョムキン(1925)」、フリッツ・ラング「メトロポリス(1927)」が作られた頃。ドイツ表現主義の影響が色濃く反映されつつも、強烈なまでにオリジナリティを追求した革新的一作。
長い間、失われたと思われていた映像が1971年発見されるも、ビデオやDVD化されず観る機会が無く作品の名前は知っていたものの、そんなこんなで年月が経った。
先日なんとアマプラで配信されてるのを知り、早速、鑑賞。
まさしくアヴァンギャルド!
当時のキャメラは勿論モーターではないので、手回し、基本はフィックスなはずのに、その映像はとにかく“斬新”!。撮影は杉山公平とあるが、クレジット(アマプラ配信では無い)には円谷英一(後の円谷英二)の名が写されていた(撮影助手と言うよりはアドバイザー的な役割だったらしい)。
円谷英二曰く「初めて特撮を撮影したのは『稚児の剣法(1927)』」と語っているインタビュー記事を見ていたが、この作品でもアニメーションによる雷や多重露光、歪曲鏡による人物撮影、紗幕の様な薄いガーゼ越しに人物を霞ませる技法など当時としては画期的なトリック撮影が盛り沢山。そして何よりも本作で円谷英二が思いついたと証言している、パン棒を使った“パンつなぎ”は、今では当たり前のように使われているが、当時としては画期的な技術だ(当時のキャメラはフィックスで、左右上下に振る場合は右手でフィルムを回しながら、左手や助手がクランクで動かしてた)。
これら全てのアイデアが円谷英二のものか、衣笠貞之助のものかは定かでは無いものの、その後のゴジラなどの特撮作品のみならず、多くの映画作品に影響を与えた事は言うまでも無い。
ちなみに、本作にはふたつのverがあるらしい(正確には「染色版」を含めて3ver?」アマプラで見ることができたのは1971年のニュー・サウンド版(トーキー24fps59分)。オリジナルはインタータイトル(中間字幕)無しの無字幕、サイレント、16コマ?(衣笠貞之助監督曰く「18コマで回している、何故ならチャップリンがそうしていると聞いたから」と語っているが、当時のカメラマンはハンドル一回転8コマを2回転/秒が身体に染み付いているのでどう考えても16fpsと考えるのが自然)かと思うが、なにぶんオリジナル上映も無いので確認が出来ない。※:オリジナルは79分(サイレント版、18fps)とされている。
しかし、京都文化博物館で24fpsでも18fpsでも無く、16fpsで映写してみた記録には
「初めて上映された十六コマ版は、十八コマ・二十四コマ版ではバラバラに解体されていた物語が一気につながり、無理なくストーリーが理解出来る。“狂った一頁”と言う映画の姿を大きく変えた。上映後に、思ったより切ない話しだった。あの日その場にいた全員が確信したほどの衝撃的な体験だった」と言うのだが、未だ十六コマでの上映機会は無い。
想像してみたが、あの南栄子のダンスが2/3倍ゆっくり、滑らかに踊られているとしたら・・・。
この作品に対する印象が変わる事が容易に想像できると共に、よくよく考えると世に知れ評価されている「狂った一頁」の真の姿とはなんなのか、そして、インタータイトル無しのサイレント映画な訳で、活動弁士がこの前衛的な作品をどう伝えていたのか、そんな事も考えると尚更興味深い
1926年当時は編集機が存在していないので、監督もカメラの中に現像済みネガを入れ、杉山カメラマン本人に回してもらいながらレンズを覗きタイミングをはかってフィルムを切り貼りしていたという、撮った本人のスピードで再びカメラを回してるので、監督は十八コマと思っていた物が実は十六コマだったとしても齟齬は生じないし、ラッシュがある訳でも無いので衣笠監督本人も当時劇場では観ていない可能性は否定できない。
余談だが、スターウォーズのオリジナルが47年ぶりにロンドンで公開されるらしい。ディレクターズカットはそれとして、やはりオリジナルの衝撃ってその時その場でしか味わえない“歴史”も含まれるので、ディレクターズカット版と共にオリジナル作品も大切にして欲しいと改めて感じた。
難解
サイレントだから台詞わかんないし、あらすじと場面から推測することしか出来ないんでこの映画の本質とか真意をちゃんと汲み取れてるか自信ないです。
にしても後半の展開はよくわかんなかったな。
まず脱走を企てた理由。
家族で幸せに暮らしたい?
妻に娘の花嫁姿を見せたい?
とかならしっくりくる気がするけど、娘は精神病の母の存在を旦那に知られたくないわけだから普通は来て欲しくないよな?
そして脱走時の暴動とその後。
ここがマジでわかんなかった。
先生殺しちゃった?あれ?生きてる?
そしてあんなことした男が普通に働いてる?
結局どういうこと?
難解な映画だったけど、演者の迫真の演技は凄かったな。マジで。特に妻をはじめとした精神病患者の面々。



 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子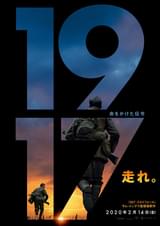 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令