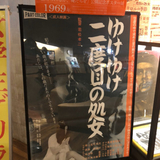獄門島(1977)のレビュー・感想・評価
全20件を表示
大原麗子は流石っす
日本映画史上最も美しい見立て殺人
横溝正史の代表作の一つで、金田一耕助シリーズでは本陣殺人事件に続いて2作目にあたる作品としても有名な小説の映画化。
原作と犯人が異なることでも有名で、監督の市川崑が横溝に承諾を得て九里子亭(くりすてい)という脚本家名で書き換えている。
個人的には劇場鑑賞はしていないが、テレビ、レンタルビデオ、配信ともう何回観たかわからない映画。
横溝お得意の田舎の因習に相続を絡めた本当に小さな世界で起こる凄惨な殺人事件を、市川崑がおどろおどろしい雰囲気を損なうことなく、豪華キャストと映像美にこだわって撮った佳作。
冒頭の金田一と傷痍軍人のコミカルなやり取りが楽しいが、皮肉にもこれが後にとんでもない悲劇を生むという非常に練られた構成には驚かされる。
アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」に出てくるマザーグースの童謡に見立てた殺人を参考に、松尾芭蕉と宝井其角の俳句に見立て派手な着物を着た若い女性を被害者にした描写は、日本映画史上最も美しくも恐ろしい見立て殺人の映像といっても良いと思う。
かなり昔VHSで鑑賞した時には佐分利信が何言ってるのかわからないほどセリフが聞きづらかったが、最近見た配信では補正されちゃんと聞き取れる様になった・・・ような気がするが真相はどうなんだろうか。
司葉子、大原麗子、坂口良子、浅野ゆう子(付けボクロをしてるけど)の美の共演も楽しく大好きな映画の一つ。
金田一が 島の駐在によって容疑者として留置場に入れられてしまうのが気の毒だった。 佐分利信の活舌のせいでセリフがわかりにくいのが難。 兄の葬儀にあでやかな着物で登場する3姉妹がいかれている。
動画配信で映画「獄門島(1977)」を見た。
1977年製作/141分/日本
配給:東宝
劇場公開日:1977年8月27日
市川崑監督
久里子亭脚本
横溝正史原作
石坂浩二(金田一耕助)
司葉子(勝野)
大原麗子(鬼頭早苗)
草笛光子(お小夜)
東野英治郎(鬼頭嘉右衛門)
内藤武敏(鬼頭与三松)
浅野ゆう子(鬼頭月代)
中村七枝子(鬼頭雪枝)
一ノ瀬康子(鬼頭花子)
佐分利信(了然和尚)
加藤武(等々力警部)
大滝秀治(分鬼頭儀兵衛)
上條恒彦(清水巡査)
松村達雄(漢方医幸庵)
太地喜和子(巴)
池畑慎之介(鵜飼章三)
三木のり平(床屋の清十郎)
坂口良子(お七)
市川崑監督・石坂浩二主演による金田一耕助シリーズの3作目。
いつも通り飄々と現れた金田一だが、
島の駐在によって容疑者として留置場に入れられてしまうのが気の毒だった。
佐分利信の活舌のせいでセリフがわかりにくいのが難。
兄の葬儀にあでやかな着物で登場する3姉妹がいかれている。
鬼頭嘉右衛門は島ではなんでもやりたい放題。
勝野も鬼頭嘉右衛門に手籠めにされてしまう。
鬼頭嘉右衛門の遺言のせいで数十年後に殺人事件が起こってしまう。
鵜飼章三は文字通り、巴の鵜飼いの鵜だった。
満足度は5点満点で4点☆☆☆☆です。
The 女優
0141 ワタシも犯人の名前を知りません
1977年公開
ターザンよろしく石坂金田一が飛ぶ。
時たまインパクトを与える市川演出は好き!
獄門島は金田一耕助長編デビュー作なので
原作は結構攻めた調子。
しかし本作は犬神、手毬唄からの発展を期待するので
先が見えてしまうところは致し方なし。
ちょいマンネリ気味でもあるがそこもまたよし。
大原麗子、司葉子は「犯人は女性です、それも美しい」
は行けると思うが大地喜和子はそそらんなあ。
吊り鐘の解読は個人的にビジュアルでうまく説明してもらい
面白かった。
80点
初鑑賞 1977年9月1日 梅田劇場
パンフ購入
錚々たる役者たち
70年代に流行った金田一映画は全部見た気になっていたが何度も見たのは「犬神家」だけで後は原作を読んでいただけだった(個々の内容はもう覚えてないです)。だからこの映画も初見で新鮮で面白かった。役者の豪勢さに目を奪われてうきうきしてしまったので名前を書かせて下さい!太地喜和子(この時34歳!大人の女ー!)、大原麗子、三木のり平、加藤武、大滝秀治、草笛光子(金歯に凄み)、三谷昇、松村達雄、佐分利信、東野英治郎、司葉子、坂口良子…。
映像、カメラワーク、編集、スピード感、でかい文字のフォントが市川崑だなあと思って楽しかった。冒頭のキノコ雲と復員兵の様子と昭和的ナレーション、一方でエレキギターだかウクレレがハワイムードを醸し出していた。ドラムも何度も聞こえた。
旅回りの役者の話も胸をくすぐられた。道成寺、狐忠信、葛の葉子別れ。最後の二つは親と子の悲しい話。親を慕う子、引き裂かれる思いで子から離れなければならない母親。上手い構成だなあ。古さを感じなかった。蝉の音、冷や麦、絽などの着物で夏を感じることができた。
【”獄門島には、本鬼頭先代の怨念がオンネン・・と呟き、二人は身を投げた。”禁断の結婚による、孤島での血塗られた人間関係を描く、市川崑監督、石坂浩二金田一耕助シリーズ第三弾。】
ー 且つて海賊の住処で、その後流刑地になった、獄門島には、”本鬼頭”と、”分鬼頭”の人々が住んでいる。
だが、両家に間には、隠された血縁関係が・・。
そもそも、島に暮らす人たちが、皆血が繋がっているのかもしれない。
故に、発狂者もしくは精神的に不安定な人たちが多いのかもしれない・・。ー
■感想
・キャスティングで、誰が犯人かが”何となく”分かってしまう、”安心感”。
ー 金田一映画シリーズの特長である。これは、第2作でも記載。
只、今作は大原さんかな?と思いながら、観ていた。ー
・屏風に書かれた俳句が殺人の見立てになる所。
ー これも、金田一シリーズの特長である事は、周知の事実。ー
・登場キャラクターの多さ及び、複雑に入り組んだ人間関係。
隠された血縁関係。
ー 今作では、凄ーくお若いピーターや、殺されちゃうけれど、浅野ゆう子さんも、出演。ー
・”そうか、分かった”が口癖の、全然分かっていない等々力警部(加藤武)も健在で・・・。
<獄門島という架空の島の、近親婚の重なりによる人間の精神性の脆さ、先代の本鬼頭当主の狂気性が惹き起こした事を、じわりじわりと序盤から描く市川崑監督の映画作りが良い。
そして、現在では物故者が多くなってしまったが、”昭和”の名役者さんたちの姿。
第1作、2作と比較すると、作品レベルはやや落ち気味だが、一定レベルの面白さはキープしている作品。
昭和50年代の映画って、残虐描写もナカナカ・・。
ジャパニーズホラーの萌芽時期だったのかな?>
懐かしいけど
惜しい一本。
犯人変更は興行的には成功していると言えても、映画としてはとても成功とは言い難い
市川崑監督、石坂浩二主演での金田一耕介シリーズの第3弾
横溝作品のなかでも人気の高い作品で、特に鐘を使ったトリックは有名
「きがちがうがしかたない」もまた有名
市川崑監督は第3弾も続くとは考えてもいなかったという
流石に新味がだせない
早い話がマンネリになってしまう
それを平然とやれる監督とそうではない監督がいるが、市川崑監督は後者だ
原作の発表順は、本陣殺人事件、獄門島、八つ墓村、犬神家の一族、女王蜂、(中略)、悪魔の手毬唄、病院坂の首縊りの家と続く
つまり第3作は原作の執筆順とは逆に映画化することになるわけだ
監督も東宝もシリーズになるとは考えてもいなかったのだ
執筆順に撮っておれば、各作品が単独であっても自然に展開が作品ごとに発展させてくいことができたはずだ
しかし遡っていく形になってしまった
だから、あの手この手で新味をだす工夫を考えなければならなくなった
その無理が本作の内容に作用した
ツケがわまったと言うべきか
あの手この手では足らなくなってしまった
それが犯人変更になってしまったということだ
原作と違う犯人というのは、確かに大変に話題を呼ぶやり方だ
しかし興行的には成功していると言えても、映画としてはとても成功とは言い難い
ピーターは素晴らしい存在感で原作にある淫靡さを示したのだが、竜頭蛇尾の出番に終わった
まだまだ足らない、もっともっと濃くても良かった
そこに本当の本作の成功の答えがあったのだと思う
それでも内容は濃く見応えたっぷり
原作のエキセントリックな殺人現場が忠実に映像になっているだけでも、ファンなら満足できるだろう
把握するのにめっちゃ時間がかかった。
『獄門島』鑑賞。
*主演*
石坂浩二
*感想*
金田一が千万太が亡くなったことを家族に知らせる為に獄門島へ向かい、そこで連続殺人事件が起こるお話。
前作の「悪魔の手毬唄」も観ましたが、やはり、今回も登場人物を把握するのに時間がかかったし、バックボーンも全体的によくわからなかった。犬神家や悪魔の手毬唄もややこしいって書いてありましたが、個人的には難しいです。(^^;
しかし、おどろおどろしい雰囲気が良かったですし、鐘のシーンはグロかったな~(^^;
犯人の動機がイマイチよくわからない。海賊と入り乱れて、解説見てもあまりよくわからなかったです。(笑)
キャスト陣が凄い豪華だった。石坂浩二さんを初め、大原麗子さん、浅野ゆう子さん、大滝秀治さん、、ん?大滝秀治さんといえば、前作にも出てたような、、、、?
金田一少年の事件簿の世代なので、僕は合わないのかな?(笑)
ははは・・・(^^;
雪月花という3人の妹。頭が悪そうだけど可愛い。浅野ゆう子、中村七枝子、一ノ瀬康子。
海賊と流人の子孫の島、獄門島。冒頭のナレーションが怖い。 そしてキ...
金田一・市川論
冒頭、プロローグ的に原爆のきのこ雲や復員列車のモノクロ映像が流れる。そして、金田一耕助が訪れる瀬戸内の小さな島では、戦争から戻ってくるはずの若者を待ちわびる者たちが、例によって陰惨な事件を引き起こすのだ。
市川崑は、一連の横溝正史シリーズだけではなく、他の作品でも、戦後の混乱を執拗に描く。彼によって描かれる戦後は、それ以前の習俗、生活習慣、社会階層の崩壊過程として描かれる。
名探偵・金田一耕助が訪れるのは、決まって岡山県のどこかの旧い封建的な因習の残る村である。
なぜいつも岡山県なのか。それは、いつもの早とちりな県警の警部・加藤武に「よし、分かった!」の名セリフを言わせるためだけではあるまい。岡山県は関西にも近く、そうした都会との交流が決して多くはないが、少なからず存在する。海と山の自然が豊かで、都会からもそう遠く離れてはいないことが、物語の舞台としての要件なのだ。
その舞台となる村には、たいてい金田一以外の他所者の存在があり、そのことが村人の旧来の価値観にゆさぶりをかけている。しかし、その他所者が恐ろしい殺人を行うことはない。むしろ、殺人の首謀者は旧制度によって最も守られている人間であり、しかも、その犯人が守ろうとするのは自分自身ではなく、その最愛の者の利益である。
犯人が連続して顔見知りの人間を殺さねばならないきっかけは、戦争へ行った者の帰還もしくは帰還しないことであることが多い。こうした戦争が人の心の中に落とす暗い影は市川崑の映画の通奏低音ともいえる。
殺人の被害者たちは、おそらく戦後の社会変動ののちには生きて行くことが最も難しい人々である。それは、村の有力な家の娘たちで、彼女たちの生活と人生は、その家の経済力と村人からの畏敬によって保証されている。旧来の制度が失われたのち、彼女たちの居場所はない。多くの横溝作品で、若い娘が次々と殺されるのだが、仮に殺人が行われなかったとしても戦後社会に彼女たちの生きて行く場所が存在しないのである。
闖入者である金田一耕助によって、たまたま事件は解決されるが、そのために犯人が守ろうとした旧い家族制度が崩壊していく悲劇。
しかし、戦争が終わった後の大きな社会の変化の中では、遅かれ早かれ彼らの守ろうとしたものは失くなっていく運命だった。そうした、戦後史の視点でみるとこの殺人事件は喜劇的なものになる。
全20件を表示