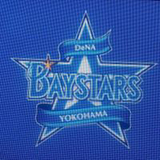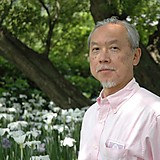男はつらいよのレビュー・感想・評価
全45件中、21~40件目を表示
トリックスターがやってくる。 喜劇役者・渥美氏の真骨頂。 みんな、若い(笑)。
寅さん(渥美さん)の流れるような名セリフの数々。
さくら(倍賞さん)の様々な表情。キラキラ輝く。博との結婚はあんな風に決まったんだね。決めるときは決めなきゃ幸せにはなれないね。
博と寅さん、恋愛指南が笑った。あのそばにいたママは渡辺えりさん?
結婚式では、寅さんの言葉に、一番に御前様の娘が拍手し、二番手に御前様が拍手、そして皆に広がっていく。その時の御前様の表情。
ストーリーとしては特にどうってことない。
でも、あの寅さんの口上・言い回しを中心とする、おいちゃん、おばちゃん、さくら、博、タコ社長、御前様、登のアンサンブルに、いつの間にか最後まで観てしまう。
役に立ちたいと、ほめられたいと行動するんだけど、かえって迷惑をかけてしまうどうしようもない主人公。
それに振り回される団子屋とご近所の面々。
おいちゃんが「バカだねえ」と言い、
御前様が「困った、困った」を連発する。
そんな寅さんを兄と慕う博と登。
そんな男どもをさりげなくフォローしているおばちゃんとさくら。
殴り合い、罵倒しあうけれども、相手を大切に思い、相手のためになろうとする気持ちが根底にある。
懲りない人々の繰り返し(笑)。
寅さんはトリックスター。
いつもの変わらぬ日常が、トリックスターによってかき回されて非日常となり、また定番の世界に戻る。退屈な日常が、トリックスターによってちょっと冒険的・破壊的になり創造されなおして事が収まり、いつもの日常に感謝する。
その繰り返し。
ギネス記録を打ち立てた映画の記念すべき第1作。
すでにドラマとして評判で、その終了に伴って作成された映画だという。
だからある程度の世界観はすでに出来上がっていた。
とはいえ、TV版とは違う役者が演じている役もある。
TV版を見ていないので、違いは語れないが、世界観を引き継ぎつつ、新風を吹き込む。
言葉だけを抜き出せば、ひどい言葉の応酬。今ならNG。
とはいえ、こんな風に腹の内をさらけ出して大喧嘩して、それでも相手の存在を否定することなく受け入れ、いつの間にか元のさやに納まる。
こんな喧嘩、いつの間にできなくなってしまったのだろうか。
我慢に我慢を重ねて、修復できなくなる関係。
だからちょっとしたきっかけで、決定的に破城する。
だから、仲直りできない。
だから、地雷を踏まないように、武装する。
そんな人間関係に疲れた身には、どんなにトリックスターが暴れようと、壊れない帝釈天の人々にほっとする。お茶に団子が身に染みる。
数年前に訪れた、帝釈天や矢切の渡し・江戸川の土手が懐かしく...。草団子が食べたくなってしまった。
第一作にしてフォーマット完成
20年ぶりに柴又に帰ってきた寅さん(渥美清)、優しいさくら(倍賞千恵子)、おいちゃん(森川信)、おばちゃん(三崎千恵子)、タコ社長(太宰久雄)、御前様(笠智衆)を笑わせ、悩ませる。
さくらは博さん(前田吟)と結婚、式には博の父(志村喬)も出席する。
片思いのお相手は御前様の娘(光本幸子)で、相手にもされない。
デジタルのおかげで、これまでで一番美しい映像だった。
全作観るぞと誓える第1作目
超有名と万人受けした寅さん。
関西人の自分としては、テンポのある口上と下町言葉が乱れるこのシリーズは完全に食わず嫌いで避けていた。
耳障りなのだ。また、
「どこがおもしろいんだ?」と。
ここに辿り着くには流れがあった。
単身赴任を始めて6年。
週末に時間がたっぷりある。
もともと好きだった映画やドラマを見出す。
好きなジャンルが分かってきた。
50歳に差し掛かり人情に心打たれる気持ちよさに気付く。
釣りバカ日誌全作鑑賞。
NHKの少年寅次郎を観てえらく感動。
岡田惠和作品にめっぽう弱い😭
興味が湧いた。
それなら寅さんだろ。
Huluに加入したのでチャンスだ。
こんな古い映画観てもなぁとやっぱりどこかで斜に構えていたが、名作には名作たる所以がそこにあった!
テッパンのストーリー展開が既に確立。
笑いのポイント。なるほど笑える🤣
今で言うフリーターが好き放題やらかすドタバタ劇に、今の時代は全く受け入れられないだろうなぁと感心しきり。
そこがおもしろい。
奇しくも自分の生まれた年にこの作品も産声を上げた。
この作品の歴史とともに自分もあるのかと思いを馳せて全作鑑賞したいと思いました。
次回作からはちゃんとレビュー書きます😅
語りの量の丁度良さに毎回泣く。
記念すべき第1作目
日本映画史上に残る名作
改めて見た。年を重ね、少しは目も肥えて見ると、全49作の中で最も完成度が高い名作であることに気づく。最近の日本映画にもいい作品はたくさんあるが、必ずと言ってよいほど、どこかにスキがある。それは、一瞬のリアリティ失速だったり、脚本のほころびだったり、演技の凡庸さだったり、演出の瑕疵だったり、平凡なカメラだったり、いろいろだ。しかし、「男はつらいよ」第1作は完璧だ。
演技では、倍賞千恵子が光る。さくらの恋愛がテーマになっていることもあるが、第2作以降とは存在感が違う。もう一人の主役と言っても過言でない。当時の倍賞は二十代半ば、竜造・つね夫婦に対しては娘らしく、寅次郎に対しては妹らしく、まだ子供っぽさが残るさくらの可愛さ、いじらしさをよく演じている。クライマックスでは、大切に育ててきた博との恋をめぐって、不安、怒り、強い意志が、とても二十代半ばの女優の演技とは思えない。
主役級だけでなく、脇役の細かい演技にまで、隙がない。たとえば、マドンナ冬子の来訪を受けたとらやで、竜造がたばこをくわえ、マッチを擦って火が軸にしっかり燃え移るのを待ちながら冬子と話すうちに、思いがけず寅が帰ってくる。あっけに取られる一同に寅が二、三つっこんだあと、竜造に向かって「ほら、燃えてるよ」と指摘し、竜造が「あっちっち」と慌てて笑いになるシーンがある。マッチを擦る前から続く長いワンカット。マッチの燃える時間を伸ばしたり縮めたりできないから、芝居の呼吸が秒単位で合わないと「あっちっち」の笑いにならない。こんな一見何げないシーンまで、緻密に計算されている。
高羽哲夫のカメラがまたすばらしい。高羽哲夫は第2作以降も撮影していて、どれもすばらしいが、第1作は特にすばらしい。特筆すべきは、クライマックス、京成柴又駅のシーン、さくらに振られたと誤解した博が柴又駅で電車に乗ろうとするところに、さくらが追いつき、とっさに一緒に電車に乗り込んだ直後のカットだ。カメラは、上下ホームをつなぐ踏切から、二人が乗った最後尾車両正面を下からアップで撮っている。これは、下から見上げることを除けば比較的一般的な日の丸構図に近い。ところが、電車が発車すると、上り電車だからカメラから遠ざかるわけだが、遠ざかるにつれ、電車は画面右下の消失点に向かって小さくなっていくのだ。停車中は大きく平凡に写っていた電車が、発車とともに、夜の闇の中、画面右下の消失点に向かって小さくなっていくようすを、切れ目なくワンカットで撮っている。最終的には、1/3か1/4構図になる。クライマックスにふさわしい美しさだ。
娯楽作品ながら、日本映画史上に残る名作と言ってよいと思う。
寅さんが生きられた時代
こんにちはフーテンの寅さん
拝啓
こんにちは寅さん。
ここに来て寅さんの映画を人生初めて拝見しました。
もちろん子供の頃から存じ上げておりましたが、子供ながらに古臭い映画は毛嫌いしており○○洋画劇場などで放映されても敬遠し、今日に至るまで腰を据えて観たことはなかったと思います。
しかし、なんと素晴らしい映画ではないでしょうか。
古臭いどころか見るもの全てが新鮮で、そこらの8Kテレビのサンプル動画なんかより、どれも煌びやかなシーンばかり。
昭和の生き生きとした世界がこの90分間に満ち満ちていて、あっという間に引き込まれた自分がおり、映像の細部まで食い入るように観てしまいました。いやぁいい時代だなぁ。
ただそれだけではなく人物から建物、風景、空気感までここまで観ていて心安らぐ映画を観たのも久しぶりのような気がします。実際にこの時代を生きていなかったとはいえ、やはり私は日本人なのだとしみじみ実感。
無鉄砲で口も悪く、器用なようで不器用な寅さんの人間臭さがとても親しみやすく、生前の渥美清さんの記憶といえば、お体を悪くしているときに舞台挨拶に出られているニュース映像を拝見したのは覚えておりますが、作中の寅さんと言えば、それはそれは縦横無尽に全力投球している演技を観て感動しました。今観ても本当に笑えます笑
いよいよ私も全力で寅さんを観られるような歳となって参りました…笑
古き良き…と言いたいところではありますが、そんなことは全く感じないこの素敵な映画。遅ればせながら、これから細々と寅さんの旅の続きでも観させていただきたいと存じます。
敬具
世界遺産
もう寅さんの映画の中でしか、人と地元とのつながりを見れなくなってしまった
やっぱり盆暮れには観たくなりますよね
寅さんみたいにたまには懐かしい地元に帰って、親兄弟、幼なじみ、近所の人々の顔みたくなるのと同じなんでしょう
都会で独り暮らしも長くなると、もうフーテンの寅さんみたいなもんで、地元のみんなからはどこで何やってるんだかみたいなもんです
高度成長期を駆け上り、みな忙しく働いている昭和の中で、自分の代わりに地元に帰って旧交を温めてつながりを確かめてくれる寅さんの映画はそんな役割を果たしてくれていたのだと思います
だから、バブル崩壊とともに寅さんシリーズもまた終了したのは当然なのかもしれません
失われた20年だかは、もう地元とのつながりも失せ、その地元も少子高齢化で消滅危機自治体だったり、都会でもシャッター商店街になってしまい
柴又のような昭和と変わらないところは珍しい存在になってしまっています
だから未だに寅さんを盆暮れに観たくなるのだと思います
というか、寅さんの映画の中でしか、人と地元とのつながりをもう見れなくなってしまったからなのです
全国どこでも同じ郊外のショッピングモールに行ってもそんなつながりは無いのです
さくらのお見合いのホテルは、紀尾井町の超一流ホテルのニューオータニですね
そりゃあ寅さん無理です
奈良は二月堂かと思われます
バター(笑)の記念写真は奈良公園の中にある鷺池の浮御堂です
御前様と冬子さんを寅さんがタクシーで送り届けたホテルは、格式高い名門、奈良ホテルです
西の迎賓館と呼ばれ国賓や皇族の方々がお泊まりになるようなところです
寅さんの冬子さん宛てのハガキのシーンのあと、寺男が境内を掃くその前景の冬子さんの部屋だったところに、奈良で寅さんがかったピンク色をした鹿のビニール人形がしおれてそのまま放置されていて、にくい演出です
ラストシーンは日本三景の一つ、天橋立です
駅裏のケーブルカーで登った山の上から見下ろしています
見下ろした天橋立の付け根の左手の甍が沢山みえる寺が知恵の神様・文殊菩薩を祀ってある知恩寺で、そこの7月にある文殊堂出船祭のお祭りで、テキ屋の商売をしているようです
知恵の神様のお寺をラストシーンに持ってくるのは洒落が効いていますよね
お馴染みの寅さん、知っているつもりできちんと全作は観ていなかった。...
お馴染みの寅さん、知っているつもりできちんと全作は観ていなかった。第1作目の寅さんは当然のことながら若々しく張りがあり小気味良い。人情味溢れるその人間像はまさに日本人の心の故郷、記憶の通り愛すべきキャラクターだった。これから歳を重ねていく寅さんを楽しみに見ていきたい。
台詞回しが小気味いい。
台詞回しが小気味いい。流れるように歌うように寅さんの台詞回しがあって、それを聞くだけでも面白い。
コメディとしてのテンポの良さもあって、寅さんのハラハラしながら、とんでもないことをしでかす面白さがこの映画の魅力ですね。
今でも笑えるし、桜の結婚式では泣けます。やはり、長期シリーズになるだけはある第1作目ですね。
さくら役の倍賞千恵子さんがすごい可愛いですね。歳をとってからしか知らないので、若い頃は初めて見ました。劇中では、さくら、という名前が当時は人名としては珍しい、という話でしたけど、現在では普通ですよね。この映画の影響なんでしょうか。綺麗な名前ですよね。
おじさん役の森川信さんも素晴らしく、この映画に味わい深さを与えてますね。
寅さん役の渥美清さん。寅さん以外の何者でもないですね。愛すべきバカというか、空回りしながらも、逞しさがあるというか。でも基本嫌なやつですね。現実にいると嫌なやつだと思う。
設定をあまり知らずに生きてきたけど、寅さんヤクザなんですね。まあ、今ほどヤクザはアンダーグラウンドではなかったからかな。
さすがの映画
寅さんってかなり破天荒
寅さんという人間はありなのか
全45件中、21~40件目を表示