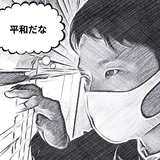ファイト・クラブのレビュー・感想・評価
全270件中、121~140件目を表示
人によっては覚醒剤の映画
凄い映画ですよ。
我々は誰しも法に従って誰にも迷惑をかけないように生きている。
そんな価値観をぶっ壊す映画です。
大体人を殺したり傷つけたりするのは駄目だなんて所詮は人が決めたことだし限られた人生で自分のやりたい様に生きるのが一番良いという理性を放ったらかしに人間という動物の欲望に塗れた作品です。
人の心を動かす映画なのである意味感動します笑
タイトルなし(ネタバレ)
映画『ファイト・クラブ』観る。
「父性」という観点からこの映画を観ると深くて面白かった。
『ファイト・クラブ』
◆あらすじ
主人公は仕事は真面目にこなすし、上司の言う事もきちんと聞く、会社の不正も仕事の為だと目を瞑ってこなす。プライベートでは贅沢な家具を取り揃えるのが趣味で人生は全てうまくいっているように見えるが不眠症という悩みを抱えています。
不眠症改善の為に最初は病気友の会に行くけれど劇的には改善しません。ある日飛行機内で隣の席になった男(ブラッドピット)と世間話をするうちに友人となる。この男と酒の酔いに任せて地下の喧嘩場、ファイトクラブを設立する。
◆登場人物の描写
主人公とブラピは対照的な描かれ方をしています。主人公は痩せ型で真面目なサラリーマン、ブラピは筋骨隆々、デカいサングラスと赤い革ジャンでアナーキーな生き方をしています。主人公は自分にはない何かを持っているブラピに惹かれていきます。
◆肥大化するファイトクラブ
ファイトクラブは世に不満を抱えた男たちがストレスを発散するのにうってつけのようで会員数が増え続けます。元々ブラピはいたずら癖が酷く最初は子供のいたずら程度が徐々にエスカレートしていきます。やがてファイト・クラブはブラピの私兵団と化し、ビル爆破などの度を越えたテロ行為にまで発展していくように。主人公はブラピの女癖の悪さや度を越えた犯罪行為に次第に嫌気がさし、ビル爆破計画に至っては阻止しようとします。
最初は惹かれていたのに嫌悪する、このグラデーションが絶妙で非常に面白かった。主人公には父親がいない、法律や一般常識に囚われない生き方をするブラピに最初は惹かれ憧れていた、これは自由、自律した大人への憧れと言えます。主人公はそんなブラピに自分にはない父性を感じていたのです。
しかし、物語が進むにつれて段々嫌悪するようになる。まるで思春期の子供が父親を嫌うように。そして最後に父親殺し(父を乗り越える)試練(ビル爆破計画の阻止)に立ち向かいます。序盤友好的で温かさすら感じていた平和な映画が中盤から一変してスリリングな内容に転がっていく所も非常に面白かった!そしてブラピかっけぇ!ちょっとワルイ男に惹かれる感じ!
◆感想
人は父親と母親から良影響か悪影響を受けて育ちます。父親がいない主人公は問題を抱えて成人します。ブラピに父性を見出し、そしてブラピを嫌う感情のグラデーションが繊細に描かれていてとても良かったです!前半ちょっとだけ展開が遅く眠たいもののそれも伏線となっていたので耐えて観て良かったです。
話題だったファイトクラブを再度視聴
二度目の視聴。前回は前知識なくまあ普通に楽しんだだけだったが、その後、①ファイトクラブ問題(特定グループにおいて、古参である自分を差し置いて昔の自分が親しんだグループが自分が居ないうちに全くの別物(多くは陽キャのワイワイサークル的な)になっていて自分の居場所がなくなる事)というようなこの映画の名前を用いた面白い活用の仕方をとあるポッドキャスト番組で聞いて気になっていた②とある陰謀論サイトにて、911事件にからめてこの作品の予言性が強く語られていた・・・ということがあり、この作品には自分として強い因縁を感じており、二度目の視聴は②を軽く確認する意味で見ることに至った(事前に断って置くとそういう自分は陰謀論に詳しくない)。
結論として、予言ではなく、予告という言葉は甘く、儀式に近いと思う(思うという表現理由は、自分は論理的な結論づけをしているわけではなく、テキトーな自分内部での帰結であるからだ)ということだ。つまり、用意周到な予言の益は、大多数の人間が見るフィクションで皆が共有してある指向性をもった事象のシンボルを見ることによって、それが現実化することを促進する目的があるのではないかということだ。実益が無いとなんぼ自意識過剰で大愚を馬鹿にしたいからといって犯罪予告をするバカではないだろうからだ。
911事件に関わるとして、この映画で気になった点をあげていく。冒頭においてground zeroという言葉を使い、20:26において、発音が近いdrops to zero(人生の残り時間はやがてゼロになる)という言葉を用いている。21:41に飛行機が飛行機に突っ込む描写がある。序盤で主人公の一室(高層ビルの8~10Fほど)が爆破される。ラストに米国の金融関係の複数のビルに同時爆破テロをしてエンドとなる。「お前は廃墟となった'ロックフェラーセンター'の大峡谷でヘラジカを追う。」という言葉。物語中、頻発される「タワー」という言葉。「飛行機が墜落する」という主人公の言葉(01:52)。スフィアの一石二鳥作戦(玉はチェス盤をもしたテーブル席✖2に向かって転がる)。気になった具体例は以上となる。それとともに、タイラーによるインパクトある「お前は物に支配されている」等の主張が視聴者に与える影響性はもちろん大衆に悪影響を与える意味があると考えたのが一つ。もう一つは、無意味で面白げあるサブリミナル表現(ところどころのタイラー?の画像の挿入、ラスト02:16の男性裸体の下半身画像の挿入)は、大衆にこの作品の儀式性を確信されるのを防ぐためのブラフ(面白おかしく馬鹿げて下品で妄想なのだよという見せかけ)を目的としているのだろうなとテキトーな仮説をたてた。
上記に関わらないこととして、この作品はとても楽しめた。不眠症を抱えながらも悲壮感よりはコメデイチックに飄々と自分の病気と向き合って行く主人公。自分のスタンスを強烈に掲げ資本主義を憎悪し主人公を面白い世界に連れて行ってくれるタイラー。主人公の鏡面役(同じ性質)と思いきや、主人公を現実から見つめるリアル側の目撃者となった、マーラの存在。そしてファイトクラブという社会のはぐれものが鬱憤を晴らす組織から人肉を用いた石鹸工場、社会へのテロ組織と変遷していった組織。共感を誘われたし憧れもする内容だ。
謎な点もあるが名作でした
なんか最初はブラピカッケーな!ぐらいにしか感じず、ナレーションも多く途中で見るのをやめようかと思ってました。
途中まではなぜ評価の高い映画なのか不思議だったけど後半からのストーリーの展開に一気に集中力高まりました。
店主がタイラーを殴っているシーンがあるがあれは誰を殴ってるんだ?僕はそれを見てたじゃないか!とかちょっと謎なシーンはあるが最後のどんでん返しは衝撃的でした。
もう少し前半に伏線を入れてくれると集中して見れた気はします。
たまたま最近パーフェクブルーってアニメを見たからだけど少しストーリーかぶるなぁと思いました
殴り合え!スカッとするぜ!
【極力ネタバレしない様にレビューしてみました】
冴えない会社員のジャックは不眠症に悩まされていた。そこに破天荒な男タイラーが現れ、ある日飲みに行き仲良くなる。その帰りにどういう訳か、殴り合いをすることになる。お互いボコボコに殴り合うが、これでジャックはストレス発散できた。毎晩のようにジャックとタイラーは殴り合った。それを見ていた見物人達が、自分たちも殴り合いたいとなり、ファイトクラブが結成される。
本編はこの後、様々な展開を迎え、タイラーの犯罪行為などもあるが、観ている方はスカッとしてしまう。そして衝撃的なラストを迎える。
私も仕事のストレスで不眠症気味になり、運動不足解消のために総合格闘技を始めた。似たような境遇で、心に刺さるものがあった。でもこの感情は私だけでなく、この映画の見物人や、この映画を好きな多くの人に共通する感覚なのだろう。
オスの本能、生きている実感、殴り合うことでそれが満たされる。自分たちは知的な生き物のふりをしながら、獰猛な動物に戻りたがっているのかもしれない。
何か自分を変える、イマイチな人生を変えるヒントがあるような気がした。
最後にこの映画の結論としてはブラピがかっこ良い!
ブラッドピット全開!
若者だからこそ
各所に散りばめられた巧妙な伏線の数々とは裏腹に、映画の展開はかなり破茶滅茶で、そこがウケるかウケないかでこの映画の評価は分かれると思います。
しかし、消費社会の奴隷となる人々への批判と、内なる自分の解放を見事に表現したデビッド・フィンチャー監督の手腕は素晴らしいとしか言いようがありません。
また、この映画が公開された90年代末ごろは日本で「ゆとり世代」などと若者が批判に曝されたのと同様に、アメリカでも若者は「スラッカー(怠け者)」と呼ばれていたようです。主演のエドワード・ノートンはそういった若者が抱える虚無感や無力感を理解した上で演じていたようなので、この映画にも説得力が生まれたのだと思います。
90年代以上に社会の結びつきが弱まり、人々の関心が自らの内面に向かっている現在において、この映画は若者にこそ刺さるのかもしれません。
殴り合いてえぜ
まさかのオチ。衝撃的というか男ならアツくなる部分があったが、まさか同一人物とは。。友達が勧めていたの確かに、という感じ。昔兄弟と身体を通じた殴り合い。痛みこそが生きている証拠を得られたような感覚があったことを思い出した。この社会はクソだってパンクも最後に流して血とセックスを感じる。興奮した。。。「我々は消費者だ。ライフスタイルの奴隷。」「職場といえばガソリンスタンドかレストラン、しがないサラリーマン。宣伝文句に煽られて要りもしない車や服を買わされてる。」「歴史のはざまで生きる目標が何もない。」「テレビは言う。明日は君も億万長者かスーパースター。大嘘だ。その現実を知って俺たちはむかついている」
ブラピのかっこよさで成立してる映画だけどそれだけで傑作
あれだね。疲れた時に見るのは良くないね。
「ファイトクラブ」という題名を目にし、ボクシング映画かと勘違いして鑑賞。
もうやだ。僕のライフはゼロだよ。でも最っ高に面白いです。
やっぱりこの映画の凄いところはラストですよね。ずっと中盤までは難解で家で見るには辛いかもしれませんがラストの大どんでん返しと伏線回収は見ものなのでそこまで見て欲しいですね。もっと語りたいんだけどね。全部が伏線みたいなものなので語れないんですよね。気になったら本当に見て欲しいです。
そしてブラッドピットの演技も良かったです。クズい演技がリアリティがあり本当に恐ろしいです。アメリカがすごく怖くなりました。
劇場で見たかったですね。そうすればもっと集中して自分で考察できたのだろうけど....
是非見ていただきたい傑作映画です。考察できる要素も沢山あるのでそういうのを考えるのが好きな人も楽しめると思います。
あ、見終わった後はちゃんと精神安定させる物を用意してくださいね。私は「ご注文はうさぎですか?」を用意しておきました。
見終わってすぐ他のレビューを見ました
この映画は脚本が途中でうまくいかなかったに違いない。
まあまあいい線いってたのに、途中で
二重人格⁈ そんなことで決着つけないでほしかった。
わかった時点で「ストーップ!」です。
ブラピとE•ノートン良かった、それだけ。
BS12字幕版鑑賞。 「現在の放送基準に合わせて内容の一部を修正し...
精神病患者の妄想
決して口外するな
家庭の中のモノは何でも爆薬になるとか、フィルム映画のつなぎ目は「シガレット・バーンズ」などと言うとかのウンチクだらけ。ファイトクラブを設立するまでは、病気でもないのにマーラ(ヘレナ・ボナム・カーター)とともに患者の会に参加するというエピソードが面白い。「睾丸がんの会」のネタがストーリーの後半には伏線として生かされてることも絶妙だった。
20年近く経って見直してみたが、どっちがどっちだったか忘れてしまってた。知り合ったタイラー(ブラピ)と廃屋で生活するようになってからも、自分の内臓を一人称にするヘンテコな小説を見つけ、ジャックの延髄などという一人称をたまに吐くのも面白い。とにかくネタが豊富な作品であることは間違いない。
鬱屈した昼間の生活から自分を解放したい奴が続々と集まってくる。日常ではアザだらけ血だらけになって日常に戻る会員たち。ルールのあるファイト・クラブでは自己変革を求めながらも社会生活に順応していたはずだった。徐々に放火や度の過ぎた“宿題”のおかげで彼らは反社会活動家となってしまい、死者も出てしまうことに・・・それが睾丸がんの会のボブだったことが主人公(エドワード・ノートン)にショックを与え、不眠症もいつしか治ってしまう。
徐々に反社行動になっていき、リーダーさえも止められない。騒乱(mayhem)計画なるものも作られ、隠れ家の地下室にはニトログリセリンだらけに。ある意味、テロリストというよりファシズムさえ感じられる展開。こうなったら自分がいなくても次から次へとテロリスト、ファシストは生まれてくる。抑鬱の解放という裏のテーマが静かに身をひそめているのだ。まるでサブリミナル効果のように・・・
初見では単純に二重人格だったというオチを楽しむのもいいだろう。しかし、タイラーに喋らせている台詞は奥が深いので鑑賞2回目以降なら彼らの台詞を楽しむしかない。資本主義の揶揄、しかし非暴力ではない。ガンジーと殴り合いたいなどと言ったのが正解とされるのだから相当なものだろう。しかし、公開されたのが1999年であることも考えると、物質文明を破壊するという世紀末思想も絡んでいるに違いない。全てを“0”に・・・爆弾を仕掛けたのもクレジット会社ばかりというのも頷けるのです。そうして、何かとこの後の9.11を思い出されるため、自分の心の中でも映画の中身を封印してしまっていたかもしれません・・・
ネタバレは
全270件中、121~140件目を表示