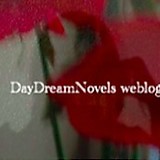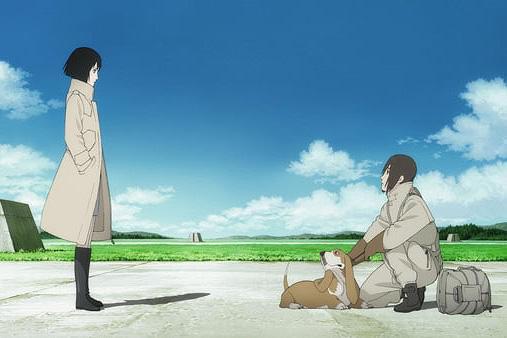スカイ・クロラ The Sky Crawlersのレビュー・感想・評価
全38件中、1~20件目を表示
その世界、ときどき攻殻機動隊
背景に素材感はあるのに
人物と衣装にはそれが無い。
発する声は静かで激しく
そこよりも少し遠くにあった。
感じるのは
"その世界の向こうの世界"
"強く愛した人が居た"
…それを強く感じた。
平和な時代の悲しい瞳
引き込まれる世界
好きだと感じた。
※
傑作。押井作品で一番好き。
押井監督の作品は『ビューティフル・ドリーマー』や『天使のたまご』から観てましたが、映像はすごいし、面白いけど、理屈っぽいセリフでけむに巻かれて結局よくわからない、という印象でした。
「押井守の映画50年50本」を読んでも、とり上げられている映画は戦争、SF、バイオレンスものばかりで、この人が興味があるのは結局はテクノロジーと暴力なのかと、鑑賞者として少し距離をとっていました。
でも『スカイ・クロラ』は、人間についての映画でした。押井監督はインタビューで「年を取ったことで逆に人間的なもの、人間くさいものに興味が出てき」たと話していますが、確かにそう感じます。人間がストーリーの飾りや駒ではなく、草薙や函南の悲しみや迷いがものすごく繊細にアニメで描かれていたと思います。
また、彼らの永遠の待機時間を表現できるかが勝負、とも監督は語っていますが、押井監督はその勝負に勝ったと思います。出撃を待つ、仲間の帰還を待つ、穏やかだけど、ぼんやりとして何となくさびしい、アニメでこんな時間の流れ方を描いたものはほとんど観た覚えがありません。
私自身は、この作品は押井監督の最高傑作だと思います。脚本と音響もすばらしい。
日テレ開局55周年記念作品とのことですが、押井監督で、しかもヒット作のセオリーを逸脱したこの作品を記念作品とした日テレの懐の深さにも感心しました。
「これが、大人のやり方かぁー!」 と言う、これが噂のスカイ・クロラ...
公開当時劇場鑑賞以来のサブスク再見
この作品の持つ特殊性は押井と言う作家の特殊性とシンクロしている。この作品の中にあるものは「関係」のみで「設定」も「キャラ」も「情景」もなく、全てこの「関係」から紡ぎ出されたもののみで構成されている。全てが記号的でありながら生々しくもぬるぬると不完全でいてこれ以上ない完成度を示す。色も線も動きも構図も見た事のない作品として成立すこの完成度の高いアニメーションは近年では井上雄彦の🎦スラムダンクくらいしか知らない。この唯一無二の世界観の中で人とは言えない存在の存在そのものに向き合うテーマは重く重要である。何層にも読み取りの可能な、もはや神話と言っていいレベルのこのアニメ作品は見る者をいつも途方に暮れる状態に放り出さす。
原作のテーマは尊重して欲しい
原作未読ですが、シリーズの最初の作品であるが、最終章にあたる作品だということと、映画とは結末が違っている事は確認しています
つまり、原作はこの作品を世に出してから、過去を創作して行ったという事です
最初からの構想か、評判が良かったからそうしたのかは知りません
攻殻機動隊の押井守がこのSFを映画化作品として選び、結末を変えたのも興味深い
キルドレとは新薬の実験で偶然誕生した生命体で思春期を過ぎると成長が止まり永遠に生き続ける存在
肉体的には通常の人間でセックスも出来るし、子供も作れる
人間とのハーフが不死なのかは知らされていません
彼らの存在は、本来なら、世間に知られてはいけない
なぜなら、既存の人間の妬みを買いますからね
情報が漏洩したんでしょうか
彼らへの処遇は、彼らの不死を奪う事だったんでしょう
殺し合いをさせる事で不死を奪った
恐ろしい話です
今なら反対する人も出てくるだろうけれど、人間の思考も今とは違うんだろう
人の思考の変遷は、最近、特に痛感する
ドラマを観るのに、倍速で観て情報だけを取得する若者達
彼らは情緒などと言うものは無くなっていくんだろう
なんて、自分の居なくなった未来に背筋がゾッとしたり
まあ、死んでんだからどうでもいいけど
押井守は、この作品で
「今を生きる若者たちに、声高に叫ぶ空虚な正義や、紋切り型の励ましではなく、静かだけど確かな真実の希望を伝えたいのです.」
だそうです
そのために、原作をいじったんですね
なんか、原作の意図を蔑ろにしているような気がします
読んでないから、わからないけれど
2008年の作品です
ちょうど”崖の上のポニョ”が公開され頃
絵本好きな大人が増えたせいで、ポニョのず一人勝ちだったようですが
色々考えさせられる作品です
それは原作の力だと思うので、読んでみたくもあります
その原作は2001年と古い
時代を先読みしたすごいSF小説ですね
映画だけで、そう思います
作者は森 博嗣という理系の人で
”すべてがFになる”の作者です
ドラマ化されていましたね
「とある世界」観という認識の明確さが欲しい
「キルドレ」とは特異変異した遺伝
子供のまま永遠に生きることができる。
これを商品化したロストック社
戦争で死なない限り生き続ける「商品」としてパイロットにさせられる。
子供が乗る戦闘機
請負戦争をするロストック社とラウテル社
とある世界の物語
「人類は戦争がなければ平和を考えることができない」
当初あった国同士の戦争から、戦争そのものだけをピックアップすることで余計な犠牲を減らしつつも、会社同士が請負戦争のために「戦争」をゲーム化した世界。
戦争のビジネス化
もう長く戦争に関わってきたクサナギは、キルドレという性質上子供の体をしながらその目は全くの空虚であり無表情だ。
彼女は機械のような思考を決め込んでいるかのように動いている。
しかしそれは「絶望」の中の立ち居振る舞いだったのかなと思った。
前のエースパイロットのクリタジンロー
おそらくクサナギの娘の父
クサナギがジンローを射殺したという噂がある。
クサナギは、戦闘で死なない限りパイロットとして生き続けなければならない彼女たち「キルドレ」の運命を呪い、愛した男を安らかにしたいと願ったのだろう。
ところがエースパイロットだったジンローの操縦技術を「新しい」キルドレに組み込むために再利用されてしまう。
そうして新しく配属さたのが「カンナミユウイチ」だった。
さて、
この作品は、人類史上決して終わらそうとしない戦争に焦点を合わせている。
その戦争と、実際戦地で戦っている人々は何の関係もない。
一部の特権階級が勝手に決め、それは合法だと吠え、国家事業として戦地で戦闘をしなければならない。
そしてこの物語ではそれは、永遠に子供のまま生き続けてしまう遺伝子操作によって作られた子供たちにその役を担わせているのだ。
この世界の仕組みがよくわかってしまったクサナギにとって、この世界で生きることの意味を何も見いだせなくなってしまった。
少しでも好きになった人を「死」という安住の場に送ってあげることが最善の幸せだと信じている。
それがジンローを射殺した理由。
そして、自分自身も射殺してほしいと願う。
ある日、
ジンローの感覚を移植されたカンナミが基地にやってきた。
それの事実は既知の事実としてロストック社の機密文書か何かの中で記されていたのだろう。
司令官という立場でそれを見ることができるクサナギには、それは恐ろしい絶望を感じたに違いない。
ティーチャー クロヒョウ
大人のパイロット 元ロストック社の社員でクサナギの上司だった人物
彼の心理がわからない。
彼の目的がわからない。
ティーチャーはいつか死ぬ普通の人間の大人である。
彼が敢えてパイロットとなっているのは、刹那的な心理状態だからかもしれない。
彼は自分が教えてきた戦略と戦術を学んだ部下たちを殲滅する方が、戦争を早く終わらせることができると読んだのかもしれない。
さて、
これらの事実が明らかになった後、カンナミはクサナギに言う。
「君は、生きろ。何かを変えられるまで」
カンナミに抱きしめられたクサナギは、人間としての実感を覚えたのだろう。
初めて人間らしく涙を流す。
やがてまた戦闘指令が発令され、皆出撃する。
ティーチャーを見つけたカンナミはたった一人で立ち向かうものの、あえなく撃墜される。
帰還者たちが待ってもカンナミは戻ってこない。
ここでエンドロールとなるが、最後に新しいパイロットが配属される。
「ヒイラギ」
彼の立ち居振る舞いはカンナミそっくりだ。
つまり彼はカンナミの感覚を遺伝に組み込まれているキルドレだ。
クサナギはヒイラギに対し「待っていました」と意味深なセリフを言う。
クサナギの眼光は明確な目的意識がある。
それはおそらく、「この世界の何かを変え」ようとする大きな意思の表れだ。
『この狂った世界を変えたい』
このことこそが永遠に生き続ける者の使命
クサナギはそう考えたのだろう。
そしてこのことこそが、この作品が伝えたかったことだと思った。
テーマが明確で素晴らしい。
ただ、
ティーチャーの心理描写が欲しかった。
複製されるように登場するキルドレ
彼らも人間として普通に意志と意識を持っている。
同じ戦争に巻き込まれている普通の大人ティーチャー
彼の心理はこの作品に必要だったような気がしてならない。
なぜなら、
片方だけの言い分ほどあてにならないものはないからだ。
そして、
「部長に会わせていただきます」
この部長なる階級は一般会社
彼らの目的をもっと明確にしてほしかった。
そして、
日本語と英語の存在
とある世界の物語のはずだが、この言葉の使い分ける意味が皆目解らなかった。
読売新聞とデイリー読売が登場していることで、2か国語が存在しているのはわかるが、その理由がわからなかった。
戦争をしていることはわかるが、パイロット等が大人なのか子供なのかが見た目でわからないことと、物語の問題がしばらく何かわからないことが作品を見飽きてしまう。
とある世界の世界観をもっと先に明確化してほしかった。
とはいえ、
2008年の作品
邦画はこの先飛躍的に面白くなるが、この作品の不明快な部分がブラッシュアップされるのだろう。
奥行きが深くなることで面白さとリアリティが大幅にアップされるのを期待したい。
哲学的戦争解釈(マ王の戦争と平和観)
コレはマ王の持論であり万人に対しての訴えでは無いので何の賛同も求めてません🤚
ただし、本作を初めて観た時の率直な感想は何度観直しても大きな変化は無く、マ王の考え方の骨みたいな部分に響いているんだな、と感じたりしてます😊
自分を再確認する時に「スカイ・クロラ」を頼る場合があります😐
で「スカイ・クロラ」は観る人によって解釈が様々になりがちな映画だと思うのよね💦
キルドレか戦争か人間のどれに注目して観るかで感じ方が変わるのが本作だと考えるのよ🤔
またどの視点にもドラマがあるから今作は面白い✨
ただし、映画としては難解な部類だとマ王は感じる😐
そもそも戦争と平和なんて言葉があるから皆が混乱するのさ🥸
戦争の対義語は泰平(らしい)だし平和の対義語は暴力なのよね✨
だから戦争が無くなったとしても必ずしも平和になるとは断言出来ない。
万人が幸せに暮らすユートピアなんて存在せず転じてデストピア地味た空間になるのは目に見えている。
「悪」を擁護する話ではない。
人間は善人にはなれないという話だ。
実に単純な事で全世界の人間の求める幸福が一致するなんて奇跡は無いからだ。
それとも地球総人口が80億人に届きそうな現代、皆が一二の三で聖人君主にでもなるのかね。
それが出来ないから戦争は終わらないし暴力も絶えない。
こんな話もある。
国の人口の単位を「人」から「円」に変えると政治家の考え方が見えてくる、と。
例えば日本の総人口は2022年で約1億2千5百万人。
コレを人から円に変えると125,000,000円になる。
で、貴方がこの金額を所持してると思って考えてほしい。
東日本大震災の犠牲者って何人だったか覚えてる?
少なくとも万人単位では上の桁は小揺るぎもしない。
そこでこの話が世界規模ならどうなる?
国のトップは「人」でなく「円」で(お金で)考えてると思うと納得しないか?
「スカイ・クロラ」でも戦争をショー化する事で広範囲の被害の縮小には成功しているが、その裏で何が犠牲になってるかが暗黙の了解になっていて、ソコに無言ではあるがキルドレとの差別が存在している。
人間が人間である為に争いは絶える事は無い。
なのに声高に平和を訴える連中とソレを事業として生きる人間達の浅ましさに、マ王は吐き気がします🤢
世にある武器を製造する国や会社もアカンけど、実現不可能な事象で食ってるヤツも詐欺師と同じやぞ😡
こんなん別に今更言う話でも無く自分自身を振り返ればどんな人でも疚しい事の一つや二つは出てくるモンで、そういう自分を受け入れないウチは「暴力反対」「平和云々」とか言わない方がいい。
ガチの自分を受け入れて尚且つそういう自分に打ち勝ってから漸く、身の回りの小さな平和を維持出来るのがやっとで人生なんだし、ソレを幸福と感じないのなら無理をしない方が良い。
まぁ恐らくではあるが、そんな努力が出来ないからこそ人間てのが存在してんだろうけどね😑
ちなみにマ王はそういう人間が嫌いではないです✨
もっと評価されるべき映画
学生の頃に鑑賞した。辛い時期だったが、この作品は支えになってくれた。
そしてそんな人は私だけではないと思う。
本作は有り触れた「日常」をひたすら描いているため、その秀逸さを理解する事が非常に難しい。だが繰り返し繰り返し観るとその美しさが分かってくる。
幻想的で切なく悲しい。でもその中に希望がある。
繊細に、自然に人間を描いた、稀有な日本映画だと思う。
何とも不思議な世界観の作品だ。 国家間ではなく、会社同士で戦争をし...
終わりなき日常の絶望をどう生きるかに取り組んだ傑作
押井守がビューティフル・ドリーマーで描いた永遠に続く文化祭前の一日は、とてもハイな永遠なる日常だった。それは日常がもたらす"倦怠"の打破が課題だったと言える。
本作は戦争ドラマだが、実はあの学園ドラマの裏バージョンで、ここには夢邪鬼ならぬ人類が仕掛けた、ダウンな永遠なる日常が描かれている。今度の日常がもたらすのは"絶望"である。
かつて永遠なる日常でラムやあたる達と遊び、軽やかに転覆させて自己の青春を総括した押井は、今度はそれに悪戦苦闘している。
輝かしい未来も華やかな過去もなく、ぼんやりした現在を麻痺した感覚で生き、感動もなく死んでいき、翌日には似た奴が隣にいるキルドレ達の世界。
「お前という人間は、いつでも誰とでも交換可能だ。自分がいついなくなっても、明日には代替品が自分の席に座っていて誰も何も困らない。自分などいなくても構わない。自分は無価値で、誰かを愛することにも何の意味もないし、そもそも愛などと言うコミュニケーションさえ自分たちには生まれない…」
三ッ矢が語るのは、永遠なる日常の絶望がもたらす無意味、無価値、無感動の世界への抗議である。
かつて政治的な閉塞感をもたらした東西冷戦は終焉したが、その後に到来した格差社会は、経済的文化的な閉塞感を若者に生み出し、新たな終わりなき日常の絶望を強いている。それに対して押井は、何らかの倫理を提示しようと試みる。
それが「君は生きろ。何かを変えられるまで」という主人公の言葉だ。日常に踏み止まれ、と。そしてその直後に、主人公は日常を転覆する企図に生を擲っていく。これはかつての学生運動時代に流行した、サルトルら実存主義哲学による自己投企の再提起かもしれない。
いずれにしろ転覆を図らなければならないほど絶望的な日常と、その空気を写し取ったのが本作であり、能天気でバカげた恋愛ドラマばかりが量産される日本では、とても現実的な映画と言えるのではないだろうか。
原作は未読だが、その原型は恐らくSF作家サミュエル・R・ディレーニのリリカルな短編「然り、そしてゴモラ」だと思われる。
宇宙空間で労働するために16歳でサイボーグ化され、性を失うとともに欲望も希薄化して、人間の抜け殻になったような航宙士と、無性状態の若者に群がる地上の性倒錯者たちとの絶望的な関係は、本作の終わりなき日常の絶望感に通じているようだ。
個人評価:3.5 薄暗く陰鬱な押井守の世界観。無機質なキャラクター...
もう一度,生まれてきたいと思う?
空中戦が楽しい
物語よりも
まず、最大のマイナス点が、草薙役の菊池凛子が声優に不向きだってこと!!
女優としては全然嫌いじゃないし、パシフィックリムの時とか良かったんですが、声優はやっちゃいかんかった。
草薙が喋るたびに耳障りが悪すぎて不快感。完全に物語を損なってました。残念。
ストーリーとしては、斬新だったし面白かったです。
出てくる登場人物がみんな暗いので、土岐野(谷原章介)に癒されました。作中で一番強いのは、土岐野なのではないかなと、思ったり。
あんな過酷な環境の中で、面倒見がよくて明るく振る舞えるなんてすごいなって思います。
ずっと思春期のまま戦い続けるキルドレ。
想像しただけでいやーな気分になりますが、このいやーなもやもやした感じが押井監督の、作品だなって思う。
押井監督の作品が好きなら見て損はないかなと思いますが、万人受けはしないかな。
雰囲気に価値がある
不思議な空気感。
全38件中、1~20件目を表示