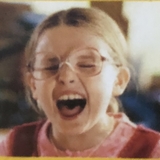海の上のピアニストのレビュー・感想・評価
全29件中、1~20件目を表示
籠の中の鳥は、籠の外では生きられない。
戸籍の無い男の一代記であるとともに、その男とコーン吹きの友情の物語。
それを、この世の物とは思えない音楽で綴る。
音楽に酔いしれる上映時間は至福の気分に浸れます。
でも、でも、でも…。
私には、1900が、
飼育されてしまって、野生に戻れなくなった動物のように見えて…。
『ショーシャンクの空』のブルックスを思い出させられて…。
大家族の中で大切に養育されたものの、家族以外との接触がなく、社会化する機会を逸して、引きこもりになっている子どもと重なって…。
万能感に浸った少年が、現実を前に、足がすくんで動けなくなった姿に見えて…。
本来の保護者からは捨てられた1900。
でも、養い親ダニーは愛情深く、周りの船員からもかわいがられて育つ1900。
船長でさえも、下船させることや、当局に届けさせることなく、船で育つ。後1年で20世紀が始まる頃、今よりも戸籍の観念が緩く、彼らにとっては当然のことであったのだろうか。
27歳になっても、悪戯小僧。前思春期・ギャングエイジのような1900。
嵐の夜のピアノ演奏は、見ている分にはとても魅かれるシーンだが、現実的に、あんなに装飾が見事なガラスを割るのは、現実的ではない(壁や周りの家具にぶつかるであろうことは、大人なら予測がつくことだ)。
船からの悪戯電話。彼の境遇を考えれば、涙を誘う場面だが、やってよいことと、いけないことの判断がついていない。
女性の寝室に忍び込んで、寝ている女性の許可なくキス。今なら性犯罪で訴えられる。
すべて、賠償金付きの懲戒免職になってもおかしくない事案だ。
だが、映画の中では、その音楽の才能もあって、「我らが至宝」と称えられる。
1900のピアノを聞くためだけに乗船する客が多かったから、経営陣は1900の悪戯に目を瞑っていたのか?
戸籍の無い不遇な”子”として、甘やかされていたのか?
今の時代より、コンプライアンスが緩い時代だったのか?
映画は、完全に”寓話”として、1900の特異性を、それを称える人々・エピソードを、耳心地のよい音楽と共に紡ぎだす。
そして、彼の才能を大金に変えようとする人々。
単に、彼の素晴らしい音楽を多くの人に届けたいという思いからきているのだが、誘う言葉は「大金持ちになれる」。アメリカンドリームの夢を抱き、食い詰めた人々が、USAに移民に出る不景気の中では、当然の思いであろうが。
そんな欲に見向きもしない1900。
モートンとの対決も、初めは音楽で”対決”という意味が解らず、ただただ、モートンの演奏に感動するだけ。煽られて、最後は打ち負かすような演奏はするものの。
監督は世俗にまみれない純粋さを描きたかったのか?
金持ちの客にも、移民する人々にも、そして演奏シーンはなかったが、たぶん病院船の中でも、そこに音楽を愛でる人々がいれば、演奏していた1900。
「海の声」それを聞けば、自分が何をすべきかが判るという。
音楽を奏でることは息をするようなもので、その上で自分探しをしていた1900。自我の目覚め。
そんな葛藤と、1900が出した生き様を描きたかったのか。
ロス氏の演技が、そんなサヴァン症候群?と思いたくなるような、夢想した表情、いたずらっ子な表情、それでいて、思いつめた時の思慮深い様、達観した時の表情と様々な様子を見せて、魅了してくれる。
そんな1900を大切に思い、ごく一般的な幸せを願うコーン吹きの眼差しが温かい気持ちにさせてくれる。
コーン吹きの温かい眼差し、至極の音楽に酔い、素晴らしい映画を観た気になるのだが、
今一つ、映画のストーリーには乗れなかった。
足止めしてしまう1900の気持ちは判る。
でも、同じような人が側にいたら、何らかの手立てを講じられるだろうと思ってしまうのだ。
今も、親の結婚事情とその主義による無国籍児が日本にもいる。
様々な事情で、今の場所に囚われて、踏み出せない人々がいる。
最終的に、どこでどのように生きるかは、その人自身が決めるものだが、一人で悩んで一人で決めるものではないだろうと思うのだ。
養い親は、1900が8歳の時に亡くなってしまったから仕方がないとして(彼が生きていたら、1900を自立できるように育てていたはずだ)。
船員たちは、可愛がりはするものの、誰も1900の成長に責任を持たない。
コーン吹きは、なんとか1900を船の外に連れ出そうとするものの、一人で行かせてしまう。30歳の男としては、一人でできるだろうと、27歳の男との自立度を図りかねるのは仕方がないとして、実際は、援助が必要だった。だって、1900の中身は自立前の10代の少年なのだから。
そんな自立に失敗した男が自分ができることとして選択した生き様に思えてしまうから、この映画に素直に感動できない。
でも、監督はそんなことを描こうとしたのではなく、もっと芸術よりの純粋性を描きたかったのではないかとも思う。
なので乗れない。私にとっては、音楽を楽しむ映画かな。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
”芸術”という点では、
誰に、何を届けようとするのかということもテーマなのかとも思う。
ダンスホール、今ならライブハウス?1900は「2,000人」と言っていたから、コンサートホール規模までか。
オーディエンスの反応を見ながら(感じながら)、奏でられる音楽。
1900が奏でるのはそういう音楽。
だが、マス相手になれば、そうもいかない。
コロナ禍で、無観客ライブ配信もあったが、誰に、何を届けていいのか、わからなくなる。方向性が見えなくなる。
1900はそれはできないという。
この映画も、短いファイン・ライン版と、45分も長いイタリア完全版がある。
この監督の有名映画『ニュー・シネマ・パラダイス』に至っては、インターナショナル版と、映画の趣が変わってしまう3時間完全オリジナル版がある。
映画もマス相手。オーディエンスの反応を見ながら、演技や演出を変えることはできない。
その辺のジレンマが、1900に投影されているのか。
他の監督のように、第三者の編集者や制作の手が入ったもので、良しとせずに、ご自身が納得するものと、世俗受けするものを作っている監督だから、ついそんな妄想を抱いてしまった。
イタリア完全版未見。いろいろな評を拝読すると、音楽シーンが丁寧に描かれていて、ファイン・ライン版で不明な点が了解できるという。また、印象ががらりと変わるのだろうか?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
≪以下、ネタバレあり≫
レコード?
病院船にあったピアノに隠されていたという。
1900ほどの演奏者が、自身がひくピアノに、通常無い物が入っていたら気が付かないのか。
ピアノはちゃんと調律していないと、音が変わると聞いている。何か入っていたら、響きが違ってくるから、1900は気が付くのではないか。
気が付いたけれど、コーン吹きの思いを想って、自身の青春の思い出として、そのままにしていたのだろうか?
コーン吹きとの再会。
あれ?この状況で、タキシード?汚れていない…。1900もやつれていない?髪・髭ぼうぼうでもない…。
病院船で生き延びていたとはいえ、病院船が廃止されてから、どう過ごしていたのか。爆破のために、主なものはすでに運び出されているというのに。鼠のように、床に転がっていたものを食べて生き延びたのか?水道管が壊れ、流れ出た水で、洗顔し、洋服を洗っていたのか。ものすごい数のタキシードを持っていたのか???
一瞬、幽霊が現れたのかと思った。それならば、華やかな頃の格好は了解できる。
地縛霊だから船を降りられないのでは?
レコードとコーン吹きにつられて姿を現したのでは。
なんてことも考えてしまう。
ラストにはどうしても納得できない
ピアニストの生い立ちは、まるでおとぎ話のように、神話のように独り歩きをして、大げさに語られていったのかもしれない。
それにしても、魅力たっぷりに、船の中の人間関係を描き出し、ピアノ対決なんかは、まるで音に優劣があるかのように、鍵盤から出てくる音が、相手を打ちのめし、拳のように叩きのめす。
ラストだけ。本当にラストだけが、「そりゃないわ」ということでした。仮にあったとして、あの爆発はもう少し何とかならなかったものか。色を消すとか、音を消すとか、スローモーションにするとか。直接的な表現を避けるとか。
とにかく、ラストシーンにがっかりした。
なぜか幸せな気持ちに
1900,1908,1927,8,1933,1933+α、
が映し出されている。
1908と1928と1930年代は客のドレスの
デザインの変遷が見れる。
🎼🎺エンニオ•モリコーネの音楽も満載♪🎹
皆がアメリカ🇺🇸だ!と叫んでいる時、一人の
女性が「音楽!」と日本語で叫んだ❗️
1900が8才で初めてピアノを弾いた時見に来た
観客の一人の女性、白塗りオバケ⁉️
と時折何かわからないけれど、何かある。
マックスと初対面で揺れる船🚢にあわせての
演奏しながらのピアノスケート滑り
お気に入り❣️
ジャズ対決の時、ジャズの発明者だかが、
2曲目終わってバーに行き、バーテンダーが
出してくれたドリンクにタバコを入れるとは?!
マナーが悪い⁉️
だから、結果も見えていると思った。
対決の時の1900、ラストに本領発揮❗️
あの心惹かれた女性の船室に忍び込み
キスするとは⁉️
1930年代だからこそだろう。
ぶら下がっていたのは?ストッキング❗️
決心して船🚢を降りる、と。
様々な手続きしてマックスに貰ったコート着て
皆に手を振って別れの挨拶したのに、
なぜ引き返したか。
本人は後にマックスに陸の生活が未知数で
怖くて自分には無理だ、と言うが、
船🚢を見捨てられなかったのだと思う。
あの女性よりも大事なんだ。
1900はこの船🚢を自身の生まれ故郷そのものと
考えていたのだと。
例として適切かどうか、
生まれ育った村がダム湖としてして沈んでしまい
運命を共にする(してはいけない)というのに
近いのでは?
船🚢をひとりぼっちで死なせるのは
忍びない、と考えたのだろう‼️
マックス、よくレコードを拾っておいてくれた。
感謝❣️
とにかく、本作数年前に初めて観た時から、
鑑賞後幸せな気持ち💕になるのです🌸
一年前から心待ちにしていた企画。
やはり映画館で観るのがいいですね💕
記:午前十時の映画祭企画
2024/3/13 ユナイテッドシネマ橿原
2024/3/28 大阪ステーションシティシネマ
過去TV視聴
限定された時間空間での満足した生涯
孤児を偶然拾った男性が育てるという話はありがちであるが、船内で育ち、無戸籍のまま一生を過ごし、才能は如何なく披露し、名人の鼻っ柱をへし折る痛快な勝負も乗り切っていくが、恋に迷い、破廉恥な行動にも踏み出し、陸に上がって常人の仲間入りをするかと思ったら、踵を返してそれまで通りの船内に限られたままの人生を全うし、命が奪われることを心配した親友の勧告も聴き入れることはなかった。本人はきわめて満足した生涯ということだったのだろう。冒頭のアメリカを発見することと女性との巡り会いの話が、だんだんと回収されていく。
人生は壮大!肝心なのは、そこに飛び込むかどうか。
私は、時を戻したいとは今まで思ったことはない。
けれど、今作を観て、若かりし頃に戻れるなら、何か楽器を演奏できるようになりたいと心底思った。
荒れ狂う海に翻弄される大型客船内で、気持ちよくピアノを演奏する主人公は、楽しげでサイコー。
余すところなく、音楽の魅力を体感した。
農夫は、海を初めて見た時に。
主人公は、初めて恋に落ちた時に(ここ、ヒロインがめちゃ魅力的!)。
雷に撃たれたような衝撃とともに、人生の壮大さに気づく。
2人の違いは、農夫は冒険に飛び込み、主人公はとどまったところ。
最後の爆破前のシーンで、初めて主人公の変化に対する恐れを聴く。
勇気を出して新しい世界に飛び込んで欲しかったけれど、足がすくむ気持ちも分かる。
それでも。
友人とともに船を降り、人生に飛び込んで行って欲しかったな。
主人公は、親には恵まれなかったけれど、音楽の才能、職場、友人、そして恋に恵まれた。
主人公の長い人生を一緒に伴走した気分。
さて、それでは、私は。
どんな人生がいいのか、自由な発想で真剣に考えてみよう。
いつ雷に撃たれてもいいように。
その対象の世界に、飛び込めるように。
名作だが、古さを感じない。
最後の最後まで、素晴らしい演出。
すべてにブラボー!
有限の世界と無限の世界
リバイバル上映ということで鑑賞。
このような人物が実在したのかどうかは分かりませんが、ようやく船から降りてみようとタラップを途中まで降り、やはり止めようと船に戻った理由が秀逸でした。
鍵盤は88で、きちんと終わりがある。だからこの有限の世界の中でならメロディーが無限に表現出来るし、有限だからこそ生きていける。
でもタラップを降りた陸は無限に広がっていてとても手に負えない。無限の世界では「誰を愛するのか」「どこに住むのか」「どの道を選ぶのか」を、どうやって決めたらいいのか分からない。だからとてもじゃないが陸では生きていけない。。
情報過多の現代を風刺するようでもあり、
なかなか心に刺さる言葉でした。
船が爆破されることになって営業停止になった時点で船への食糧の供給は無くなるから、船からどうしても降りないのであれば運航しなくなる時点で彼の運命は決まっているのですが。。
彼をなんとか生かしたいトランペッターの友人の想いも伝わるだけに最期は切なかったです。
船で生まれ船で育った主人公は、どんな荒波の航海でも決して船酔いすることがない。
船の揺れに耐性のある主人公が果てしなくファンタジックで、ピアノの技巧も含め魅力的な主人公でした。
名作中の名作
また見たい。無料で借りたのが申し訳ないくらいおもしろかった。名作と言われているだけある。すごく良かった。是非たくさんの人に見てほしい。世界はとてもとても大きく限りないんだな。すごい世界で生きているんですねわたしたちは。ピアノが本当に楽しかった。また見たい。13.12.14
大人の寓話
美しくて悲しい映画でした。
芸術に秀でる事は感性が敏感過ぎて、良いことばかりない様です。
だいぶ違いますが、私も42年間在籍していた会社を退職するときは、無職という新しい世界に戸惑いがありました。
1900が想いを寄せる少女役のメラニー・テイリーの舷窓越しの姿が、風に吹かれている一枚の絵の様で、とても美しかったです。
タイトルなし(ネタバレ)
ストーリーの完成度が高すぎて非の打ち所がない。ラストシーンの感動は忘れることができない。海の上で生涯を過ごすというのは全く想像もつかないからこそ難しいテーマだと思うが、見事にまとめきっている。
ピアノの上に置き去りにされていたのはもうその運命だったとしか思えない。自分の才能に胡座をかくこともなく、ひたすら音楽を楽しむ姿勢には学ぶことも多くあり、ジャズの創始者とのピアノ決闘ではまるで連弾しているかのような表現と表情を交互に映し出すこと、さらにその音楽に圧倒された。
最後は船が家の1900にとって、一緒に人生を降りる覚悟はずっと決めていたことのようにも見えた。本人にはそんな気なくても伝説的な人物。
自由について
最後のマックスに胸が詰まりました。
自分だったらどうするか考えたり...。
最初の船酔いから助ける場面大好きです。
"何かいい物語があって語る相手がいる限り、人生捨てたもんじゃない"
"問題は目に映ったものではなく、映らなかったものだ"
伝説のピアニスト
音楽・映像・ストーリーどれもが素晴らしいです。
音楽はどの場面のものも好きです。曲の種類もジャズやワルツやバラード、壮大なオーケストラ風のものまで幅広く、そのどれもがそれぞれの場面にぴったり合っていて心に残っています。特に好きなのが、ナインティーンハンドレット(以降1900)とマックスが嵐の夜に2人で波に揺れながらピアノにのる場面のワルツです。(サントラに入ってなかったのがとても残念です。) 船上で会った少女を想いながら弾く曲も心に染みます。
映像も幻想的でとても美しいです。豪華客船の煌めきとか、そこから眺める海の白波とか一場面一場面をこだわって作られているのが伝わってきます。
主人公の1900自身も魅力的です。見た目は大人だけど、中身は純粋な少年のようであり、それでいて人智を超え、誰もが魅了する音楽を紡ぎ出す。つかみ所の無い不思議なオーラを持った1900を見事に演じきったティムロスの演技も素晴らしいです。
原作も読んだのですが、私にはいまいちピンときませんでした。ですが、その原作からこの映画を創り上げたトルナトーレ監督のイマジネーションと創造力には脱帽です。
好きな場面は色々ありますが、ジャズ対決シーンは圧巻です。音楽ももちろん素晴らしいのですが、「煙草」で両者の心境が表現されているのが面白いです。対決を申し込んだジェリーロールモートンは初めは余裕綽々であり、煙草の灰が全く落ちないという所からもその心境が窺えます。しかし、最後の曲で自身の敗北が明らかになると、煙草の灰がホロリと落ちてピカピカに磨かれた靴に降りかかる。ジェリーロールモートンの渾身の最後の一曲に対する1900の煙草返し(?)の演出は笑えたし、スカッとしました。
初めてこの映画を観た頃はラストが悲しくてモヤモヤしました。しかし、20年以上経った今観ると、これ以外のラストは考えられないなと思っています。上手く言葉で表現できませんが、1900がマックスと一緒に陸で楽しくピアノを弾くラストってなんとなく違うなという気がします。
「陸(=無限に続く鍵盤)のピアノは自分には弾けない。ピアノの鍵盤は88と決まっていて、そこ(=海の上)から生み出される音楽は無限だ、そこが好きだ。」という1900の言葉は好きですが、それが彼が死を選ぶ理由になるのかは今もわかりません。が、マックスが辛い決断をしたのは、1900の気持ちを真に理解したからこそなのだという事はわかるような気がします。
切なさの残る作品・・・全編を通して楽曲が美しい
当時のニューヨークへ向かう人々の熱気が印象的に描かれていました。
主人公とトランペット奏者マックスとの出会い( 揺れる豪華客船のホールで、グランドピアノを演奏するシーンは、かなりインパクトがありました 。 )と友情、才能溢れる即興演奏、ある日淡い恋心を抱く女性が現れますが・・・。
豪華客船と運命を共にした主人公の生き様が切なかった。
エンドロールで流れた弦楽器の旋律がいい。
映画館での鑑賞
現実的であり、ファンタジー的でもある
通常スクリーンで鑑賞(4Kデジタル修復版,字幕)。
監督、ジュゼッペ・トルナトーレ。作曲、エンニオ・モリコーネ。「ニュー・シネマ・パラダイス」のコンビが組むと何故こんなに美しい作品が生まれるのでしょうか?
流麗な映像と素晴らしい物語に魅惑的な音楽が合わさって、唯一無二の魅力が醸し出される。思わずうっとりとして、否応無しに感動のスイッチがONになってしまいます。
現実的でありながら、ファンタジー的でもある、不思議な作風だと思いました。1900の存在を知るのはマックスしかいない。しかしマックスは常に目が泳いでいて話の信憑性が薄れてしまう。これはどう捉えたらいいんだろうか?
船上で育ったからこそ、陸を知っている人間とは違う視点で物事を見つめ、感じることが出来たのだろうと思いました。
だからこそ、誰も聴いたことの無い楽曲を奏でられたのだろうし、切ないけれど、最後の決断に繋がっていったのかも。
※リライト(2020/09/01)
※修正(2024/03/23)
「曲名は?」「知らない」
このやりとりがたまらない!正しくjazz improvisation ですね。ドキドキさせるほどのインプロビゼーションには唸らされます。全く音楽教育を受けてない(想像)にも関わらず天才的な旋律を奏でるのは、音楽家の湧き出るまでの心を感じさせます。JAZZ対決もスリル満点でした。でも、どうやって判定してるのかはわかりません。対決の最後に速いクロマチックのスケールライクな演奏は、聴衆の心に訴えるというよりテクニックと勢いだけという感じでしたけど、タバコに火が点くほど熱い運指でした。
魚屋の娘に対する恋心と一度セッションした父親への思い。1900の葛藤と陸に降り立とうとする気持ちが絶妙で、その後の彼の言う「神の領域」が唐突ではあるけど、まさしく無限に広がるという神の言葉でした。88鍵がよこにすると∞になる瞬間だ・・・
結局、船を降りることが出来ない1900なのですが、気持ちは伝わりますし、実際に地上に立ってしまったら普通の人に成り下がるような気もします。それでも一緒にバンドを組もうと言うトランペッター・マックスの友情に乾杯!
もし陸に降り立ち、少女の元へと行ったのなら、無限が無限でなくなり、平凡なピアニストになったかもしれません。色んな想像ができてしまう味わい深い作品でした。それにしてもマックスの眼球が泳ぎすぎ、ホラ話と言われても違和感がないほどでした。
不思議な、おとぎ話のような映画
こういう映画には高評価を付けるものなんだろうなと思いつつも、自分の気持ちに正直に、他の方のレビューを読む前に、星の数を決めました。早い段階で、リアリティは無いと思ったので、あるトランペット吹きが体験した夢のような話、として観る事にしました。
豪華客船が入港後、船内に、レモンの木箱に入れて置き去りにされた赤ん坊。1900年にちなんで”1900”(ナインティーンハンドレッド)と名付けられました。最初のうち隠されたのはしょうがないとして、養父が死んだ時やピアノの才能が知られた時に、なぜ、戸籍をどうにかしようと誰も思わないのか。
不思議な映画としてそこは曖昧にしておくのもアリなのですが、「彼は存在していないも同然」「生まれたことにさえなっていない」と繰り返し強調したのが気になりました。戦争で国を追われた人々を象徴しているのでしょうか。”1900”には実は天才ピアニストの才能があったのですが、開花する環境にあったとは言えなので、かなりの奇跡です。バンドのピアニストとして採用されると、音楽の教育を受けていない彼は即興で美しい旋律を次々と生み出していき、それが大評判となります。音楽の神様に愛されていたわけですが、彼にはたぶんそういう概念は無く、一応キリスト教徒でしたが信仰心もあったのかどうか。
ある時彼はトランペット吹きのマックスと知り合い、生涯の友を得ます。マックスの目には音楽を心から楽しんでいるように見えた彼ですが、一人の少女と出会って心を奪われます。とうとう船を降りようと決心しますが、いざその時になると目の前の街を見て、降りるのを止めてしまいます。その真意は・・・
彼が愛したのは少女なのか、音楽なのか、故郷とも言える船なのか、それとも何も愛してなどいなかったのか、私には理解するのが難しいです。(そういえば、「陸の人間は答えを求めすぎる」と彼は言っていたような・・・)そもそも戸籍が無いから上陸出来るのかもわかりません。そこでファンタジーとして考えるには、船の爆破シーンはリアル過ぎました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
9月6日、完全版を観ました。1つ訂正、「陸の人間は理由を求めすぎる」でした。映画に対する印象も少し変わりました。不思議な話という印象自体は変わりませんが、幾つかモヤモヤした件について、完全版ではもっと時間が割かれていて、腑に落ちました。
170分の完全版の方をぜひ見てください。
とても複雑な気持ちです
自分の想像力の貧相さに自己嫌悪することになってしまいました。
なぜかというと、このピアニストがニューヨークの社交界で、俗物たちをギャフンといわせて、最後はあの少女ともめでたく…。そして、なんだかんだと街(世間)に染まることはなく、又別の形で海の上に帰っていく。
そんなクロコダイル・ダンディー的な展開を期待してしまったからです。
あー、情けない。
確かに街並みや道路の広がりは、88個の鍵盤に比べたら無限だけど、陸のピアノだって鍵盤の数は一緒なので、やっていけるはずなのになぁ、とか思ってる時点で、私の感性は1オクターブ分にも満たないのかもと落ち込んでます。
陸に降りても〝ピアノが弾けることの喜び〟が、自分の生まれ育った船というゆりかごを離れる不安に勝ることができなかったことが、私には残念に思えました。
でも、音楽シーンはどれも圧巻で大満足です。
どんな場所であれ、生まれた場所は愛する故郷
4K修復上映にて初めて鑑賞。事前にある程度作品内容、背景を収集していた為実話でないことは知った上で観賞したが、まるで実話でありそうなファンタジー作品。
20年前の作品を物凄く見ているわけではない為この時代に作られた他の作品をはじめとした流行だったり時代背景というのはあまりわからないけど、この作品は戦争背景なんかも揶揄してるのかなと勝手に思いながら観賞していたりもした。
1900は船で生まれ育ち、陸に上がることなく最後は船と共に自らの人生に終止符を打つ。
陸で育った僕からしたら命を自ら落とすことに抵抗を覚えるが、彼にとって船は愛する故郷である。
その愛する故郷とも共に命を落とすことを望むのは自然の事なのだろう。
この辺りがなんか戦争地域、その地域の人々と重ね合わせたりもしてしまった。
名前もなく、船を離れれば名前はおろか存在すらも忘れられてしまう1900。これが幸せなのか不幸なのか…中々簡単にはどちらだということはできないが、一瞬一瞬の人との出会いだったり、喜びを与え与えられる事もた人との繋がりとして大切なのだろう。
あまり過去の作品とマッチする事がない未熟な僕だがそんな僕でもまずまず楽しめた。
セッションという映画を思い出した
ニューシネマパラダイス好きの私としてはジュゼッペ・トルナトーレ監督のこの作品観ないわけにはいかない!
舞台はずっと船。主人公は船で生まれて船で働く労働者に育てられる。
なぜピアノが上手くなったのか?なぜ戦争中船で生活して食べ物に洗濯に困らなかったのか?謎。
女性を見つめながら作った音楽は悲しげで泣きそうになるくらいジーンと来る。
きっと彼の境遇を知ってしまったから余計に。
船での生活しか知らず、船での生活に満足していた彼には大陸へ降りてからの目的が見出せなかったのだろう。
運命的出会いの彼女を追いかけ訪ねて行って欲しかった。
彼は悩み結局船を降りなかったけれど、現実的にはパスポートもないしきっと手続き面倒になるだろうなんてそんな事考えながらタラップのシーンを観ていたからこの映画にどっぷりのめり込めなかったのだと思う。
主人公の決断と友人の諦めの良さが納得いかなかった。
ついでにヒロイン役のメラニー ティエリーが美しくないと言うか好みではない。
モリコーネの音楽は非常に良かった。
全29件中、1~20件目を表示