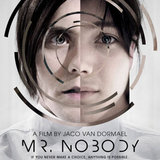メメントのレビュー・感想・評価
全261件中、61~80件目を表示
かなりの低予算、だけど10年に1本、稀有な雰囲気を持つ映画
主人公の心の中にグサグサ入ってゆく!!
「観ている人も思い出しながら進む」
そう思えばいい。
ただ真正面から取り組んだら、、、
ごく普通の映画、物語になっている。
見せるタランティーノ
感じさせるノーラン
これは面白い。
※
難解ではなくて、覚えてられないだけ・・・
クリストファー・ノーラン監督の実質上の長編劇映画デビュー作、20年以上前にこのプロットを作り込んでいる事に感服します
時系列が崩され、ラスト→始め→ラストのちょっと前→始めからちょっと進んだ所→・・・というストーリー展開が理解できればストーリー自体は全然難しい内容ではないのですが、いかんせんその時系列で起こることを順列で整理しながら覚えていられないので、結果“難解”と言われるんだと思います
先日のアカデミー賞受賞式にて「オッペンハイマー」で監督賞を受賞したノーラン監督ですが、これまでの監督作品「インセプション」「インターステラー」「テネット」といづれも“時間”をテーマにした傑作群、その原点がこの作品というのが、元来おそろしい感性の持ち主だなあとあらためて感心しました
何にしても、一回観たら直ぐにもう一回観たくなる中毒性のある作品だと思います
いやこれ思ってたのと違う・・・
タイトルなし(ネタバレ)
惹きつけるものがある。集中してみる映画。
時系列で進まない、ちょっとずつ戻る仕掛けが効いてる。
最初のポラロイド写真が、ちゃんと写ってたのがだんだん消えていっておかしいなと気づくと、時間が戻るのだとわかる。
巻き戻しで銃に弾が戻り、銃声がして、この場面にどうやって向かうのか集中して見た。
この映画を昔見たことがあって、所々覚えてるけどほぼ忘れてて、主人公の擬似体験をする作りだけど、実際に体験してる気がした。
また忘れて、ワクワクして見たい。
認知症もこんな感じかなと思った。
アンソニー・ホプキンスの「ファーザー」は認知症体験映画だった。
うーん…ノーランぽい感じではあった。
ノーラン作品って最初何も分かんなくて、主人公も何も分かってないから、主人公の混乱と視聴者の混乱がシンクロする面白さがあると思うんですよ。
本作品も、何も分からない混乱と、結末がどうなるか分からないワクワクは序盤確かにあった。
でもなんとなく「主人公が犯人パターン」「全部主人公の妄想パターン」はありきたりで萎えるし、流石にそこは外してくるだろって最初から思ってたから、結末の答え合わせでガッカリしちゃった。
物語の結末として面白くないのに、「人間ってこうだよね」「深い!」みたいに絶賛するのももはや食傷気味だ。
なんか、「記憶を失う男」の視点を視聴者にも共有させて、最後巻き戻す見せ方も、
TENETとか最近のノーラン作品を観てると「ああ、そういう感じね」と変に斜に構えて観てしまった。
そんなこんなで、過程も結果もそこまで楽しめなかったかな。
記憶と取捨選択と意思
クリストファー・ノーラン監督の映画は、『インセプション』『インターステラー』『TENET』は見たことあったが今のところはこの『メメント』がダントツで難しかったように感じた。
展開の構造的には『TENET』と似ていて(制作順で考えると『TENET』が『メメント』に似ているというのが正しい)、カラーの場面が時系列的には未来から描いており、モノクロの場面が過去から描いていた。そして物語終盤で二つの時間が交差してエンディングに差し掛かるという形だった。
序盤に物語の答えだけを知り、次第に事件が起こった原因が分かっていくという形で描かれていて、謎を解いても新たな謎が出てくるため鼬ごっこをしている気分になる。そのため最初のほうの場面は忘れていて、観客である私たちもメモを書きながら鑑賞したいという気分になる。
このように観客にレナードの体験を追体験させることが、この難解な展開の目的だったのだろう。
物語のテーマは記憶はどこに内在するのか、どう保持するのかという問題であり、記憶は記録ではないというセリフが印象的であった。そのためレナードは出来事をメモに書き起こし、記録として頼っていたが、書き起こされる出来事は取捨選択されるため、その記録も信用することが出来ない。
では人は何を信用すればいいのだろうか。
ただ一つ言えるのは、記憶なんかに惑わされない自分の信念のようなものを頼りに行動するべきなのではないかと感じた。実際、良い悪いかは置いといて、作中のレナードは「復讐」という信念のもとに行動を続け記憶を改ざんしていた。
ノーラン作品の原点...のちの作品の構成要素が凝縮
自宅に忍び込んだ強盗によって妻をレイプされた男
殴られたことによって脳に障害を追い、「前向性健忘」を患ってしまう
これは「事故前の記憶はあるが、事故後の記憶は10分間すると忘れてしまう」というもの
何か新しいことを見聞きしても、10分間しか覚えていられないのだ
彼は妻をレイプした犯人を探し出し、復讐を遂げる
ところが障害によって、復讐を遂げたことすらも忘れてしまった主人公
妻を襲われた記憶と、復讐心だけが残り、「妻を殺した犯人を探し出しては殺害する」復讐鬼と化してしまう
実は妻はレイプされた後、命に別状はなかった
しかし記憶を保持できない主人公が、彼女の持病である糖尿病の症状を抑えるインスリン注射を何度もしたことによって妻は亡くなってしまう
主人公の記憶が保持できないことを信じられず、彼を試すために、彼の記憶を呼び覚すために、妻は何度も注射を頼んだのだ...
・主人公はすでに復讐を遂げており、記憶を保持できないために何度も殺人を犯す
・実はレイプ後に妻は生きており、彼女を殺したのは主人公自身
という二重のネタバレ。
妻を殺した罪悪感に苛まれてか、主人公は「サミー」という別人の話にすり替えて、記憶を失った男と、彼によって殺された妻の物語を何度もするようになる
※主人公は記憶を保持できないのに、無意識裡あるいは潜在意識・深層心理のどこかで妻を殺した罪悪感を抱えているということだろうか...?それとも設定上の粗か?
・・・・・・
妻を殺された主人公は、犯人探しのために警察の伝手を頼るのだが、記憶を保持できないが故にだんだんと利用されるようになる。
本物のレイプ犯を殺したあと、麻薬捜査官に騙されて売人を殺すのだが、その売人の彼女もまた主人公を利用し、麻薬捜査官を殺すように彼を仕向ける。
愛した女が実は自分を利用しており、胡散臭いがそれなりに無実な男を相手に罪を犯す。
ノワール調で開始する物語だけれども、「情報の錯綜」によってシェイクスピアばりの悲喜劇が繰り広げられていたことがわかる
・・・・
こういったネタバレは、物語の内容を整理したうえで執筆されたものであり、実際の映画は「時間を逆行させる」ことによって構成されている。
1本の映画を撮影したあとで、フィルムを分割し、順番を並び替えて未来から過去へと遡るように上映することを想像するといい。
より正確には、逆行から成るカラーパートと、順行によってなるモノクロパートの「2軸」によって映画は構成されている。
この「カラーパート」と「モノクロパート」は接続点を持っているので、映画全体はあたかも「U字構造」を持っており、『メメント』こそが『TENET/テネット』の原点となっていることがわかる。
・・・・
さて、「逆行」パート(カラーパート)においては、事件が発生した順序を入れ替えることによって因果関係が逆転する。つまり、物事の「結果」が先に提示されたあとで、「原因」が後から明かされるという構造をとるのだ。
このような細かいネタバレの連続は、『プレステージ』へと継承され、(時間の逆行は伴わないもののネタバレの連続という意味で)『ダークナイト』で結実する。
『ダークナイト』がハラハラする展開の連続となっているのは、『メメント』で養われた手法に基づいているのだとわかる。
・・・・・・・
物語の冒頭、主人公が男を殺害したのは、彼を殺すように主人公自身が仕向けたものだと終盤で明かされる。
主人公は記憶をなくし、メモだけを事実・真実だと信じる。
けれども彼は、自分に都合のいいことだけを記録に残し、都合の悪い内容は破棄する。都合のいい書き方でメモを残すし、都合のいいようにメモを解釈もする。
主人公のこの間抜けさの理由には、もちろん物語の書き手の意思もあるのだけれども、女を信じて胡散臭い警官を信じない描写などには、人間の心理に関する洞察に基づいているし、観客の期待に沿いながら後々で裏切る=どんでん返しをするために利用していることでもある。
・・・・・
このように、主人公が自分自身に対してついた嘘によって映画は始まり、嘘に嘘を重ねることによって物語は結末を迎える。
この物語は嘘をつくことによって始まったものであり、本来、嘘がなければ存在しなかったものであるとも言える。
そして主人公自身が物語を作り上げているとも言える。
その背景には、「映画自体が広義で『嘘』なのだ」というノーランの視点が反映されているように思う。
映画とは、現実ではない仮定を置くことによって始まるストーリーだ。
最初の仮定にどんどん新たな仮定を重ねていくことによって物語が展開していく。
「もしもXがAだったとしたら?」「YはBだろう」というように
仮定のはしごを空に掛けるようにして高みへ登っていくのが映画だ。
このように、映画を作る人物たちを投影するようにして、主人公は自らに嘘をつく、自分自身を騙すことによって物語を作っていく。
それは自分自身にとって都合がいいからで、のちのノーラン映画で「嘘が暴かれる」という要素が何度も登場するのも、『メメント』という原点があるからだとわかる。
・・・・・
映画制作という行為は一般に作品の外部に置かれがちであるが、『メメント』では主人公自身が嘘によって物語を作るという形で、作品の内部に埋め込まれている。
例えば『インターステラー』では、主人公たちを宇宙へと誘うワームホールを設置したのが未来の人類であり、主人公がしばしば目にするいくつかの異常現象も、その正体が主人公自身であったと明かされる。
ここには「物語を発生させるのが自分自身だ」という映画の作り手自身の意識が反映されているように思える。
映画を作るためになくてはならない作為性。その作為性を発生させるのが映画の作り手自身であり、映画は作り手による自作自演なのだ...という意識の投影として。
『インセプション』のラスボスが主人公の心の中に潜んでいるのも、『TENET』の黒幕が主人公自身だと判明するのも、映画を駆動する「神」たる映画製作者の存在が、「物語を作る主人公」という形に投影されているのではないだろうか。
監督の才能に敬意を払うしかない
クリストファー・ノーラン監督の出世作にして、それはもう“記憶障害の疑似体験”。
進んでは戻りの繰り返しで結末から少しずつ時間を逆上っていく事により、物語の本当の道筋が見えてくる。
最後に待つ衝撃の事実に脳内は困惑必至。
これは是非DVDもしくはBlu-rayで見て頂いて、内容を知った上で特典の「もう一つのメメント」を見てもらいたい。
時の流れを正したストーリーを見る事で、より深く理解できて新たな発見と更なる驚愕に陥るはず。
合わせて4時間かかるけど、その価値はある1作で2度おいしい衝撃作でした。
非常によく出来た作品ですが、その後どうなったんだ!?と少し疑問が残った部分と、常に頭を使って見るので好き嫌いが分かれるだろうなという印象も。
ストーリーが繋がっていく気持ちよさ
なぜ今まで観ていなかったのか、自分。
「メメント観たことある?」と聞かれたが観ておらず一緒に鑑賞。クリストファー・ノーランという固有名詞が脳に定着する前に知った作品だったため本作もクリストファー・ノーランだとは知らなかった。
さすがクリストファー・ノーラン、冒頭の時間が逆戻しになるシーンも良作であることも難解であることも如何にもクリストファー・ノーランという感じがして良き。
鑑賞後レビューを書いてない作品が何作かあるがこちらを優先的に書かなければレニーのように記憶を無くして後から書けなくなると思い、真っ先に書くことにする。
「妻を亡くして記憶を維持できない主人公」という情報をまず得ておかないと物語が理解ができなかっただろう。実際に時間が戻っているということもすぐには理解できなかった。
私は伏線回収映画は大好きで好んで観ているが、時間を少しずつ戻して自分も主人公と同じ「分からない」を作り上げる手法が素晴らしい。
上記に優先的に書かなければ…と書いたが、実際のところ書きたいことは多くあるが上手くまとめることができない。
とりあえず、「クリストファー・ノーランは凄い」と言っておく。
※人と一緒に観ることをオススメします。一人だと分からないまま先に進んでしまい混乱するので。
10分前、俺はなにをした?
数分で短期記憶を失ってしまう男
妻を亡くす以前の記憶はあるが、それ以外はメモを頼りに犯人を探す生活をしている
描写が独特でカラーの時は時間が逆行、モノクロのシーンは順行する
テディが撃たれるところから映画が始まる
話が進むにつれて友人を名乗るテディや親しそうなナタリーなど怪しさが増してくる
周りの何人かはレニーの症状を理解して利用している
一番長い付き合いのテディは本物の犯人を探す協力をしたのちは、割り切って自分の利益のためにレニーを利用する
レニーは復習という目標を作ることで妻を殺してしまった事実から逃れ続ける
自分の症状を利用してあたかも妻が生きているかのように錯覚させるような行動からも現実逃避の気が見て取れる
自分の体にのこしたメモは10分後の自分への新たなヒント
目を瞑っていても世界は続いている
記憶を失い続ける男か、記憶を改竄し続ける男か
このセリフを発するのには皮肉が効いている
記憶のない間も世界は続いているし、それを理解しつつも最も目を逸らしているのはレニー自身
逆回転で謎を解明していくストーリーが斬新で、見応えがある映画です。
映画史上、おそらく初のストーリー展開です。
すべてが「逆回転」でのストーリーになっています。
つまり、「結末」から始まって、「なぜこのような結末になっているのか?」と謎を解き明かしていく構成になっています。
主人公は、ある障害により直前の「10分間」しか記憶が残らないようです。
そのため、ありとあらゆる方法で、メモを残し、そのメモから記憶を辿り、謎を解明していきます。
謎めいた映画ですが、観る人に親切な工夫もあります。
現在の(逆回転、つまり現在から過去に遡る)場面はカラーで描かれ、記憶を辿る(過去から現在の)場面はモノクロで描かれています。
そして、ラストシーンは、びっくり、衝撃です。
理解を深めるために、
おそらく、大半の方は、もう一度、最初から観ると思います。
何度も見返したくなる
10分しか記憶を保てない男が妻殺しの犯人を追うというストーリー。 ...
10分しか記憶を保てない男の話。なんとも面白そげ。段々と過去に遡り...
全261件中、61~80件目を表示