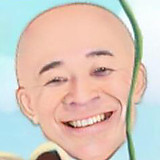グッバイ、レーニン!のレビュー・感想・評価
全42件中、21~40件目を表示
ドイツが越えた時代の大変動
どう考えてもあり得ない話なんだけれど、ドイツの越えた時代の激流をうまくコメディタッチに変換して描いている。
わずか数年前の生活を変えないようにすることがここまで難しいか、と思わせておいて、
全体を見終えると、東西統一による生活の変化がいかに大変動だったか、しみじみと感じさせるのである。
イデオロギーが一気に逆転したとき、その急激な時代の流れに人々の心の切り替えが追いついていなかった現実を炙り出しているかのようだ。本作は、先行して流れていった時代の波と人間の感情の橋渡しをしているように感じた。
オスタルギー
時代の厳しさとそれに対する反抗心
母にショックを与えないように嘘をついてるが、その嘘の生活にアレックス自身も救われているという設定が面白い。
ドイツの急激な変化は、自由で華やかで一見良いものに見えて、アレックスや母のように地道に働いてきた労働者にとっては生きにくい世界を作り出してしまった。
当時のドイツの時代の流れは急激で、色々な新しいものに抗いたい気持ちを多くの人が持っていたのだろう。
アレックスの家族内でも、妹と婿は新しいことに順応しているけど、アレックスと母は昔の方が良かったと思っていて、気持ちの分裂があった。
アレックスは母への愛と自分のプライドで母に真実を明かさなかった。母のためだけじゃないってところが良い。
赤ちゃんがとにかく可愛かった。なんでそんなに演技が上手なの!?笑
「エーミールと探偵たち」(2001年に製作されたドイツの映画) の...
「エーミールと探偵たち」(2001年に製作されたドイツの映画)
のラストシーンと合わせて見てみると面白い。
全くバラバラのように見えていた子供たちが突然群れになって
行動しだす。
その時になって初めて自分が追われていたことに気がつく悪役の男。
それはフィクションでもパラノイアでもなんでもなく、
国民の90人に一人が秘密警察の関係者で、
通りを歩いている人や自分の友人さえもそうかもしれないと思いながら生きてきた東ドイツの人にとっては、
たいして異常なことでもない。
秘密警察には
各国民個人の行動習慣や人間関係、ビン詰めにされた体臭サンプルまで保管されており、
そうしたデーターベースや心理テクニックを基に、
ある個人がある個人に対して特定の行動をするように仕向けることも可能だった。
この「グッバイ・レーニン」は、
国家が個人の視聴覚の外延と呼べるものを事実上全てハイ・ジャックすること可能だった時代から、
NGOや企業、テロ組織などがそうした能力を引き継ぐ時代へと移行していく、
まさにその瞬間の様子が克明に表されていると思う。
東ドイツの秘密警察(STASI)は解体されたが、
その手法を引き継いだ組織は北朝鮮と
日本(にある朝鮮総連)に現在存在している。
主人公に共感できず!!
10年位前に観て面白かった気がするのでまた観てみましたが、母を亡くした事もあり、終始お母さんを騙し続ける内容が酷いと思いました。お母さんが社会の一員としてのモチベーションが高いので、東ドイツ体制の良かった部分を感じました。主人公のドヤ顔と無駄に可愛いガールフレンドも何だかなあという感じでした。
単につまらなかった
2時間ほどの映画ですが、1時間ちょいでつまらなくて視聴を辞めた。
コメディーを期待してたけど、個人的には笑えなかったのでヒューマンドラマに思えた。
主人公による母親に対する嘘が喜劇部分の主軸として展開しますが、母親が気の毒に思えて笑えなかった。作中のヒロインも「母親に嘘をつき、ぬか喜びさせるのは気の毒」という内容で主人公を非難してたけど、ヒロインの意見に全く同感で、全く笑えない。ヒロインにこういう台詞を言わせるところから察して、作者も人を選ぶ映画と分かりながら作ってるように思う。
また、母親を気遣っての嘘だとも思いますが、個人的には人に気遣いされるのが好きじゃないので、それも笑えなかった理由。もし自分があの母親の立場なら、気遣いされるのが嫌なために、第一に鬱陶しく、心暖まるなんてことはない。
評価がそこそこ良いので、おそらく良い感じで終わるのだろうけども、つまらなさすぎて最後まで見れなかったのは残念。
逆に、他人に気を遣われるのが好きな人や、嘘をつかれる母親を気の毒に思わない人は楽しめそう。人は選ぶ映画。
コメディ
そこに生きる人々
暖かくも残酷、優しくも滑稽
●母への優しさ。
舞台は旧東ドイツ。厳格な母親が心臓発作で昏睡状態に。寝てる間にベルリンの壁が崩壊してしまう。意識が回復するも、息子のアレックスは崩壊を言い出せない。母親を刺激せぬよう、以前と同じ生活を送る。はたしてバレずに済むか。
崩壊後、資本主義の波が容赦なく襲う。スーパーの商品はあっという間に西側製に。それでも古いビンを見つけ出しピクルスを詰めたり、TV番組まで製作して平穏を維持する。西側への憧れとの葛藤。母親への愛情。西に渡ってしまった元夫。
クライマッックスは、母親が一人で外出するシーン。程度は違えど、こうした急変に直面したときにどうやって人はそれを受け入れるのか、なんてことを考えた。ある程度、自分の都合のいいように解釈して、少しずつ現実を受け入れるのだろう。それが早いか遅いか。
母親は息子のおかげで救われた。ラストはなんかいい終わり方だった。
自由とは何なのだろうか?
最後のほうで家族みんなでドライブに出かける。その車のデザインの先進的なこと。まるで21世紀の水素自動車やハイブリッド車を思わせるデザインではないか!
多くの人々が自由を待ち望んだのだろう。決して少なくなくはない数の人が共産党政権下で思想や身体の自由を奪われていたことだろう。
しかし、西側が自由だったのかと言えば、そうとは言えない。
市場原理によって、登場人物たちが慣れした親しんだピクルスすら消え去るのが「自由で豊かな」消費社会なのである。そこでは、東側の生産効率に代わって販売効率が幅を利かせる。販路を得た西側の製品が東の市場を席巻するのにほんの少しの時間も必要なかったのだ。
自由に商品を選びとっているのと同じように、主人公の父親は自分の人生も自由に選び取ったはずだった。だがしかし、それは彼の自由を勝ち取ったわけでなく、別の抑圧が始まる物語だったのだ。
優しさに満ち溢れ
母のため、息子は奮闘する。
観てから数日たつのであまり覚えてないがベルリンの壁が壊された時のあ...
消え行く祖国にさよならを
総合60点 ( ストーリー:65点|キャスト:70点|演出:70点|ビジュアル:70点|音楽:65点 )
今までの社会が崩壊して価値観が全く変わってしまった混乱の中で、母親のために努力をする息子を軽快に描く。
ずっと西側世界に生きていると、さっさと古い体制は葬り去って姉のように切り替えちゃえばいいのにとしか思わないのだが、実際にこのようなことに直面するとそう簡単にもいかないのだろう。信じていたものが消え去って今までの自分の価値観が否定された中で、果たして祖国に対してどう接していいかわからない主人公が、母親のためといいつつも結局は自分の価値観や愛国心をもがきながら探す行動になっている。これは彼が悪戦苦闘しながら、母親に対して、同時に祖国にさよならを言う心の準備を整えるまでの儀式なのだ。
悪くはないけれど、こじんまりとした話だし引き込まれたわけではなかった。しかし自分がそれを間近に体験したドイツ人だったらまた違った意識をもっただろう。例えば、鬼畜米英・天皇万歳と教えられた日本人が、突然戦争後に反対のことを言われたら混乱するものだ。そんなときは自分で考えて自分なりの答えを見つける必要がある。そんな彼の葛藤を暖かく見つめている。
これは観るべきの映画。
誠実だけどおかしくて、抱きしめたくなる
もっと描きたした方が分かりやすいのに・・・と思う部分が少しあったけど、まあこの映画はあくまでも“アレックス”という人物を描こうとしていたから、必要ないと言えば必要ないか。
誠実だけれど滑稽で、まっすぐだけれどそれはどこか歪曲している。そんなアレックスという人物像を、東西ドイツ統一という出来事への彼のかかわり方を通して、見る者に捉えさせる。最後に、彼は自分がそれまで救ってきたと思っていた人に救われる。このラストも、良い。
全42件中、21~40件目を表示