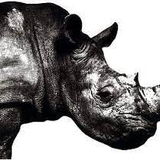四月物語のレビュー・感想・評価
全32件中、1~20件目を表示
初々しい
Love Letterや花とアリスを観て岩井俊二監督が好きになった方ならきっと気に入って頂けると思います
四月物語
1998年公開
正に四月物語
大学入学で北海道から上京してきた女性の四月の日々をスケッチした映画です
ストーリーはあるような無いようなものです
Love Letterや花とアリスを観て岩井俊二監督が好きになった方ならきっと気に入って頂けると思います
主人公はもちろん、当時21歳の松たか子が演じる女子大生です
でも本当の主役は四月でした
四月の温かく柔らかな陽光
涼やかに吹く薫風、ほんの少しの湿気や日陰の冷たさ
雨の温かさ
そういった空気が映像の中に閉じ込められてあります
新年度、新しい学校、職場、環境、土地、部屋、人間関係
不安と期待と精一杯の背伸びと緊張もまた
遠い遠い昔のことになったのに昨日のことのように思い出させてくれるように、フィルムに写し撮られているのです
撮影監督はLove Letterと同じ篠田昇さん
2004年にお亡くなりになられていたことを知りました
大変に残念なことです
そして今さらながら、気づいたことがありました
本作に写されていた主人公始め新入生は2002年卒業であったはずということに
2002年は、就職氷河期の中でも特に就職状況が悪く、就職率が55.1%と最も低かった年です
全員が就職氷河期世代だったという事に気付いたのです
こんなに暖かな日差しが降り注いでいたのに、4年後、彼等、彼女達は氷河期の氷に閉じ込められて氷雪に遭難する運命だということに気付いてしまったのです
それから一世代分の年月が過ぎ去り、それからどうなったかを私達はすべて知っているのです
主人公やその憧れの先輩のその後の人生がどうなったであろうかもだいたいのところまで推測できてしまうのです
遠い、遠いところに来てしまったという胸の張り裂けるような思いと深い感慨に浸ってしまいました
そうして、また夏が過ぎ去り秋が来て冬が終われば、来年も四月が訪れるのです
30年近く経とうとも、おなじような四月物語がまたあるのでしょう
折れた傘を返しに行く物語も
訳の分からない大昔の映画を背伸びして観る物語も
〝Give thanks for unknown blessings already on their way.〟
走り出した電車のなかの卯月の指先が緊張を伝える
たくさんの不安と小さなよろこびをのせた新しい季節の始まり
観る側の立場によって
我が子や、兄妹、昔やいまの自分に
投影しながら
二度とない宝箱のような時間をそっと見守る
淡い色の物語
きらきらと舞い続ける彼女の心が
この両手にあふれるようだった
〝Give thanks for unknown blessings already on their way.〟
〝すでにこちらに向かっている幸運に、今から、ありがとう、を。〟
このレビューを書いていたら、ちょうどのタイミングで大好きな方が素敵な言葉をSNSにのせて教えてくれました。
ぴったりかも。
久々の今日の早起きにも感謝^^
修正済み
オープニング、電車に乗るシーンでは松本幸四郎一家集結。
これも岩井監督らしい作風の一本
大学進学は、多くの場合、生まれて初めて独り暮らしを始めるきっかけ-。
当然のこととして、引越しも初めてなら、部屋に納まる荷物の量に見当がつけられないことも、言ってしまえば、ままあること。
所属するサークルを初めて決めるのも、半分どぎまぎ、半分ワクワク。
貧乏学生にはマイカーという訳にもいかないので、自転車を買って行動半径を広げる。
時間はたっぷりあるので、アルバイトで稼ぎまくるのでもなければ、行きつけの古書店を決めて、古本で読書三昧(もちろん、読み終わった本は、またその古書店に持っていって、買い取ってもらう)。
大学も三年次・四年次ともなると、いかに苦労せずに卒業するために必要な単位を揃えるかにだけ腐心するようになってしまい、往時の「フレッシュさ」は欠片(かけら)もなくなってしまったことは、今では思い出です。
高校までは「生徒」という立場で、教員から見れば「まだ子供」という位置付け。
(実際、高校の教員も、自分の担任クラスの生徒を、うちのクラスの「子供たち」という言い方をしたりもする)
しかし、高校三年生と同じ年齢だったとしても、いったん大学に入ってしまえば、その立ち位置は「学生」で、教員たちも、子供という目線では見なくなる-。
そんな境界線に立ったばかりの卯月を、少女・若い女性を描かせたら右に出る者はないともいえる岩井俊二監督ならではの筆致で瑞々しく画き切った一本ともいえそうです。
本作は。
いかにも、ようやく「大人の女性」になりつつあるかのような、はんなりとした色香・雰囲気を湛(たた)えた松たか子さんを主役に据えたことも、キャスティンクとして、最適だったと言えるでしょう。
これも、佳作と評するべきだと思います。
評論子には。
(追記)
当時の評論子ともいえば、半日授業だった土曜日の午後は、そのまま街で過ごして、新宿・歌舞伎町にまだ何軒かはあった映画館を梯子するのが常でしたけれども。
(評論子の人生の中では「第一次」映画ブームともいうべき時期でした。)
名画座で時代劇を鑑賞する卯月の姿に、往時の自分を重ね合わせた評論子でもありました。
ちなみに、卯月が観ていた『生きていた信長』は、DVDの特典映像によると「岩井俊二郎」監督の手になる作品で、本作の作中で使うための撮り下ろしの超短編のようです。
短い映画
...............................................................................................................................................
松たか子が東京の大学に合格して上京、一人暮らしを始める。
内気で付き合い下手で、お付き合いで入った釣りサークルも面倒に。
実は高校の先輩に憧れてこの大学を受験したのだった。
偶然その先輩がバイトする本屋を見つけ、少し仲良くなれた。
...............................................................................................................................................
オープニングで松の実の父と兄がいたので、
もしかしたらこの映画の主人公は松なのかと思ったらその通りだった。
気付く順番が逆ってか?(場)
おれも大学の頃、特に般教の頃は友人がおらんかったし、
付き合いで入ったバレーサークルも面倒で1年で辞めたし、よく似てた。
友達が欲しくて、おとなしそうな隣人を食事に誘って断られたり、
今度は隣人が訪ねて来たがかみ合わなかったり、何となくわかる(場)
地上波放送80分、正味60分の映画。
【”愛の奇跡”岩井俊二監督の作品って、何でこんなに透明感に溢れているんだろう。松たか子さんも不老の人だなあ。劇中に流れる曲も品がある、初々しい青春映画である。】
■東京の大学に通うため、北海道から上京した卯月(松たか子)は、小さなアパートで初めての一人暮らしを始める。
個性的なアパートの隣人、大学のフィッシングサークル仲間らと触れ合ううちに東京での生活にも慣れていくが、そんなある日、卯月は高校時代に憧れていた山崎(田辺誠一)と再会する。
◆感想
・大袈裟なストーリー展開がある訳ではないが、好きだった山崎先輩を追って、武蔵野大学に頑張って合格した卯月を演じる松たか子さんの、今と変わらない初々しさが良い。
・卯月が北海道から上京するシーンでは、”本当のお父さん”が、お父さんを演じているのも、何だか良いなあ。
・卯月が映画館で観ている「生きていた信長」もアクセントとして、効果的である。
ー 良く見たら、信長を江口洋介が演じている。「生きていた信長」も映画にしたら面白そうだなあ・・。>
<自分が、大学に入学したころのドキドキ感を思い出してしまった作品である。私が卒業した小学校にも、”武蔵野”と言う名前が付いていたなあ‥。(遠い目)>
上京のやわらかい頃
進学を契機に上京したときの、そこはかとない万能感を孕んだ始まりの予感。自転車を買う気持ちってすごいわかる。なんか簡単に征服できそうな気がするんだよなあ。東京って。狭いし。起伏ないし。でも実際はそんなこと全然なくて、武蔵野からだったらせいぜい八王子くらいが限界だと思う。東京は普通に広い。
大学に入って一番最初の自己紹介、嫌だったな。自分は高校では◯◯をしてて◯◯が趣味で受験方式は◯◯で…みたいな。こっちは◯◯にとりあえず代入する何かを考えるので精一杯なのに、東京慣れしてる人たちは歌でも歌うみたいに朗々と。そいつらだけでアレは良いとかコレは悪いとか独自の世界ができあがってて、こっちには北海道って寒いの?みたいな定型的な質問がたまにお情けで向けられるだけ。
東京って怖いな、みたいな素朴な恐怖がこのへんで生まれる。一人暮らしなんかしてるとこの恐怖が際限なく大きくなってくから、読書とか電話とか隣人とか、そういうノイズで誤魔化すしかない。万能感なんかとっくに消えてる。
宙ぶらりんのままフラフラしてテキトーなサークルに無理やり入れられるのもわかる。釣りサークルって絶妙ですよね。公園でルアーの素振りって何の意味があるんだろ。ていうかたいていの大学のサークルには何の意味もない。でもその意味のなさが居心地の良さの正体だったりする。少なくともそこにいる間は何者にもならなくていいから。
1ヶ月もすると自分の周りに起きる良いことと悪いことが同じくらいの比率になってきて、東京の特別さも薄れていく。自分が特別だと感じていた出来事が、実は東京においては普通の出来事に過ぎなかったことを知っていく。東京が生活になっていく。
何も起きない映画、という指摘はとても正しい。本当にその通りだし。この映画が捉えていたのは主人公の心の変化だ。主人公のやわらかい心が、多種多様の些細な出来事を通じて、平坦な生活の重力に耐えられるよう錬磨されていく様子が描かれている。
描き方が少しあざとすぎるんじゃないかという箇所も多いけど、むしろ巧いレトリックだと思う。本当にそのくらいやわらかいんですよ、上京者の四月っていうのは。
初々しい!かわいい〜!
劇中劇が長い〜!ここで観るのやめようかと思った!
不満はその点くらいで、何も起こらないのに眺めていられます。30代半ば以上限定ですが笑
90年代のリアルさがまんまで、そこが素晴らしいなと思いました。登場する大学生がすごく大学生で、たまらなくよかったです。
今の映画は大学生を20代後半が演じるようになったからでしょうか?大学生が大学生らしくない!
これは初々しい感じが全面に出ていて、こんな感じだったなと懐かしくなりました。
ラストはここで終わりなのー?!という感じでしたが、よかったねぇぇー!とおばちゃん嬉しくなりました。
憧れをパワーに出来るのって素晴らしいですね。私にもそんな才能欲しかったな。
しかし、うまくいったのは卯月がかわいいからだと思わずにはいられませんが、不器用な上京したての大学生が自分なりに奮闘してやっていく姿は心が暖まり応援したくなりました。
90年代いいな、あの時代よかったなと思える映画でした。
松たか子のプロモーションビデオ
全32件中、1~20件目を表示