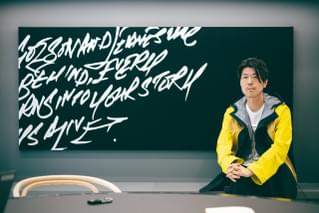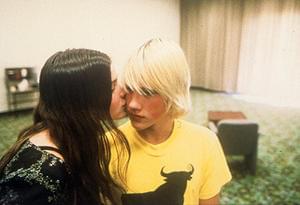ネタバレ! クリックして本文を読む
22年前の2003年公開作。カンヌで作品賞パルムドールと監督賞を受賞とのこと。それほどの作品なのに、まったく知らなかった。
かなり変わった構造・構成の映画だ。主人公がいつまで経っても特定されない。というか主人公はいないのだ。そういう映画なのだと気づくまで、主人公探しをしてしまった。
そうした映画だから、物語を見る推進力にもなる、何かの事件的なことも最後まで起きないし、主人公のなんらかの解決すべき課題や動機も描かれない。
ただ、神様の視点――いや、自分が幽霊になってアメリカの地方の普通の高校を漂い、平凡な一日の高校生たちを観察しているような感覚を味わえる。
長回しで生徒の背中を追いかける映像は、誰の視点にも同一化せず、ただそこを漂う。
今回は、コロンバイン高校の事件をモデルにした映画ということだけ頭に入れていた。だから、何事もない高校の一日のように見えるが、この先何が起こるかは知っている。
一人、または2〜3人のグループの高校生をしばらく追いかけて観察しては、また別の高校生に観察の対象を移す。おそらく誰かが犯人のはずだが、みんな普通である。
ただ普通の高校生活というのは、仲間づきあいにしても、恋愛にしても、あるいはちょっとした陰口など、かなりしんどいものだなあということも伝わってくる。確かにもうずいぶん昔のことだが、学生時代はしんどかったことを思い出した。
そして唐突に凄惨な事件が始まる。
幽霊となって観察した身としては、いくら自由に飛び回って現場を監視していても、誰が対処すべき問題を抱えているのかはわからないし、事件の原因はなんなのかなど、見ていても事件を語ることはできないものだということを実感させられる。そして、現実というのはそういうものだろうということも、教えられた思いがした。
この展開から、タイトルの「エレファント」とは「群盲象を撫でる」ではないかと思った。会場に貼ってあった監督紹介で、そうであることが確認できた。パーツパーツをいくら観察しても、真の姿は見えてこないという諺だが、それを見事に表現している。
同時に、同名の1989年作『Elephant』(アラン・クラーク監督)を参照しており、“暴力は理解不能である”というメタファーが二重に込められているのだそうだ。
危機的状況においては、それが危機であるとは認識できない。まずは「大丈夫だろう」と考えて終わり。正常化バイアスだ。
でもなんかおかしいと疑いが芽生えたら、「何があったの?」と説明を求め、情報収集したくなる。
いずれも、それが本当に危機なら無駄で愚かな行動だ。野生の反応を発揮して「逃げるか、戦うか」そのいずれかを直ちにするべきなのだ。
しかし、現代人はもはや“逃げるか戦うか”という原始的反応を忘れてしまった。いや、必要な時に発揮できなくなったのだ。「にげるか、戦うか」反応で人間関係を壊したり、ビジネスなどで失敗することはビジネス書などで嫌というほど解説されている。
コロンバイン高校の事件についてはかなり研究も進んだようだが、現在でも全てが公開されたわけではなく、不明な点も残っているようだ。
ソシオパス的な犯人のメンタリティが明らかになったようだが、同級生にも教師にもその予感はまったくなかったという。
人の心の本当のところのわからなさ、そして今日自分が無事に一日を終えられるのかのわからなさ、そうした“わからなさ”を体感させてくれる不思議な傑作だった。
この事件は、アメリカ人にとってはトラウマ的な大事件だ。
この事件の後、学校には校内警察が導入され、カウンセリングも大々的に導入された。また、生徒の言動やSNSから問題の予兆を探る試みもされているようだ。
そうした取り組みにもかかわらず、模倣犯を思わせる同様の乱射事件はその後数十件も起きている。
どう見ても再発防止には銃規制しかないように見えるのだが、そこはアメリカにとっての聖域であり、現在も規制法案が成立する見込みは立っていない。



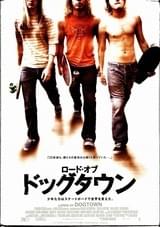 ロード・オブ・ドッグタウン
ロード・オブ・ドッグタウン グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち 追憶の森
追憶の森 マイ・プライベート・アイダホ
マイ・プライベート・アイダホ 永遠の僕たち
永遠の僕たち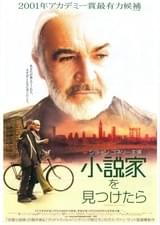 小説家を見つけたら
小説家を見つけたら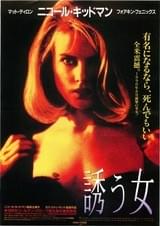 誘う女
誘う女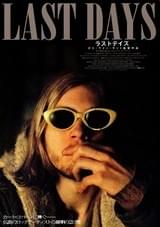 ラストデイズ
ラストデイズ ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド