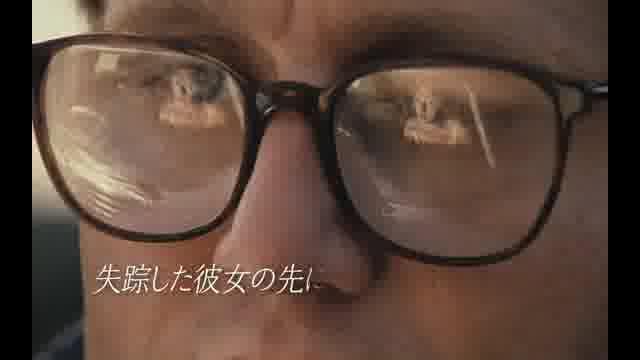ザ・バニシング 消失のレビュー・感想・評価
全18件を表示
真実を知りたい!知りたい!!知りたい!!!の先に待つもの。
映画「セブン」を超えるラストシーン。とか、宣伝されてしまうと、
フィンチャー好きの私としては、行かざるを得ない。
単館上映されるとのことで、行ってみました。
-------
没入感の演出が非常にうまく、彼女に何がおきたのか、知りたくて、知りたくて、たまらなくなります。
この先、どうなるんだ!! そんな気持ちが、どんどん大きくなるように作られています。
ラストに向かって、あれこれ、想像するものの、全部否定されてしまい、
この人、実は良い人なのか!?と錯覚すらしていきます。
作中の主人公と、観てる人の心境がシンクロした状態での、あのラスト・・・。
良くできてる。本当に良くできている。
-----
行った映画館では、売店に、ブランデー入りの珈琲を売ってました。
珍しいので買ってみたんですが、わざわざ、水筒から珈琲を注ぐので、何だろう?と思ってましたが、
まさか、そういうことだったとは。映画館も、なかなか洒落がきいてます。
80年代にこんなサスペンススリラーがあったなんて、伝説の作品といわれるのも良くわかる。
しばらく、暗いところで寝れない・・・。
こんな面白い映画あるの?
こんな面白い映画あるの?って久々思った
常に面白い。スリルがあるし画面のルックも常に最高。
話も良い。終わりも良い。(最悪で)
映る全てに意味がある丁寧な作り。
普通のカップルがぬるりと、闇に滑っていくような恐怖と、犯罪者側の心理や思考のプロセスと、自ら望む結果を得る為の細かいトライアンドエラーのプロセスまで見せるのに、映画としてものすごく綺麗にまとまっている。
ほんとにすごい。
終わり方も、めちゃくちゃ嫌な終わり方で最高。
ほんとうの悪は、こうなんだよな。ってゆう恐怖の終わり方。
この神経質な殺人鬼はジョジョの吉良吉影を思わせるから、元ネタの1つなのかなとも思った。
サスキアがほんとうに、太陽の様な魅力を持った人
だったから、レックスと一緒に真相迫っていく中で
生きててくれないかな、と願ってしまっていたので
あの結末はすごく悲しくもある。
黄色の使い方とか色の印象も強く残ってる。
レックスとゆう男性の喪失と執着の話でもあるので、真実を知りたいとゆう人間の欲求も描かれてて
ほんとにすごい映画だ。めちゃくちゃ面白かった。
これが長らく日本未公開だったなんて信じられない。
配信で鑑賞
花柄ポット! パトリシア・ハイスミスの濃厚な影響を感じさせる「失踪ミステリ」の秀作。
ナナフシで始まり、カマキリで終わる。
『ザ・バニシング』は「捕食者」に関して考察する映画だ。
面白くないわけではないし、評価されるべき映画だとも思うが、実像以上に「面白そう」に語り伝える宣伝回りのテクニックが実に巧みで、ちょっと嫉妬してしまうくらい(笑)。
いわく――、
●サイコ・サスペンス映画史上No.1の傑作、ついに解禁――。
●ラストへの戦慄が『サイコ』(60)、『羊たちの沈黙』(91)、『セブン』(95)、『ゴーン・ガール』(14)を超える!
●巨匠スタンリー・キューブリックが3回鑑賞し「これまで観たすべての映画の中で最も恐ろしい映画だ」と絶賛!
●ただじっとりと流れる暗黙の時間に身を委ね、無情にも訪れる史上最悪のクライマックスを待つしかない。
ここまで言われたら、観るしかないじゃないか(笑)。
あと、シネマート新宿限定で販売されたコラボドリンク「バニシングコーヒー」(花柄のポットから供される)は500杯の売上を記録、ってのもネタとしてふるってる。
(以下、はっきりネタバレはしていない気もしますが、展開自体を伏せておいたほうが初見者にはよさそうな映画なので、いちおうネタバレ設定としておきます。)
で、初めて観ての感想。
これって、……まんま、パトリシア・ハイスミスじゃないか!!
オランダ出身の頭のおかしな監督というと、まずはポール・バーホーベンとディック・マースと相場が決まっているが、本作のジョルジュ・シュルイツァーはフランス生まれ。原作のティム・クラッべのほうはオランダ人だ。
国境を接している以上、仏蘭両国には比較的ひんぱんに人的交流もあるのだろうし、本作でも「国境」「オランダ語とフランス語」「自転車と車」など、「気軽にフランスを訪れたオランダ人観光客の巻き込まれ型サスペンス」という設定をうまく使っている。
にしても、このパトリシア・ハイスミス・フォロワー感はただごとではない。
パトリシア・ハイスミスというのはアメリカの女流ミステリ作家で、1950年代に『見知らぬ乗客』(のちにヒッチコックが映画化)でデビューして、90年代まで活躍した大家である。代表作は『太陽がいっぱい』(のちにルネ・クレマンが映画化)あたりか。
ほかに『水の墓碑銘』『愛しすぎた男』『ふくろうの叫び』『ガラスの独房』『ヴェネチアで消えた男』あたりも面白い。
個人的には、現代の「サイコ・サスペンス」の土台を作った作家だと思っている。
別名義で『キャロル』というレズビアン小説の嚆矢となる作品を書いたことでも知られている。ついこのあいだ、『パトリシア・ハイスミスに恋して』というドキュメンタリーが日本でも公開されたので僕も観てきたが、その映画の主題は、彼女の同性愛者としての性指向についてだった。
60年代からはフランスで暮らし、ちょうどこの映画が撮られた80年代はスイスに移住していたはずだ。だから、どちらかというとアメリカ以上にヨーロッパでの人気が高く、リスペクトされていた作家である。
たぶん、TVでたまたまこの映画をやっていたとして、タイトルも履歴もわからない状態で観たとすれば、僕は十中八九「パトリシア・ハイスミスの未読作が原作」の映画だと判断したと思う。それくらい、テイストが「パトリシア・ハイスミス」してる。
ひとりの女をめぐっての、男ふたりの知的闘争。
やがていつのまにやら女そっちのけで、
男同士のねちっこい執着合戦がお互いを縛り合う。
このホモソーシャルな「相手への粘着、執着、執念、付きまとい」をとめられない感覚、むしろそれに「淫していく」感覚が、実にパトリシア・ハイスミスっぽい。
「悪」の側にいる人間に、通常の意味での道徳観や相手を慮る道義心がきれいさっぱり欠落しているのも、実にパトリシア・ハイスミスっぽい(本作の登場人物は、自らを「ソシオパス」だと自己紹介する)。
そこかしこに「くすり」と笑わせるようなコミカルな描写をはさみながら、それを鬼畜のような所業や悪夢のような結末と平然と並置する。
そのことで起こるケミカルな「違和」の反作用が、作品の魅力になっているところがまた、パトリシア・ハイスミスっぽい。
パトリシア・ハイスミスの特徴であるところの、
●犯罪者と被害者が特定のインティメットな関係(どこか同性愛的)に陥り、「狩るものと狩られるもののゲーム」にのめりこんでゆく。
●犯罪者側には罪悪感や道徳心が決定的に欠如していて、自分でもコントロールできないほどの執着と好奇心に食いつぶされている。
●被害者側にも何かしらの問題があって、似たような執着の傾向とマゾヒズム的性向を示して、結果的に犯人と「共依存」的な関係に陥る。
●これらの歪んだ関係性や狂った行動が、あまり説明もないまま淡々と描出されていくので、作品全体に異様な不条理感が漂う。
●その際、たくみな比喩と切れのいいレトリックを用いて、ある種の「笑い」の要素を挿入してくることも多く、逆に全体の不気味さを増幅させる。
といった要素が、『ザ・バニシング』にはすべて驚くほどの再現性で「踏襲」されているのだ。
犯人側は、ごく当たり前の幸せな日常生活を家族と送りながら、単純に「究極の悪を成す」という実験精神のために(要するに何かしらの利得を求めてではなく、悪であること自体を目的として)誘拐計画をねちねちと練り続けているのが、とにかく気持ち悪い。
それも、自分でクロロホルムの効き具合を試したり、いつ捕まってもおかしくないような危なっかしい「狩り」を続けたりと、綿密に計画している割には、やたら「わざわざリスクを背負った」犯罪計画にまい進している。
このあたり、まだ幼いころに「飛んでみなければわからない」とバルコニーから実際に飛び降りてみたり、パパになってから、水路で溺れる赤の他人の少女を助けるために一瞬の判断で飛び込んでみたりと、後先を考えない自暴自棄な「勇気」を発揮しているのと密接に連動している。
要するに、この男は生来的な「デスウィッシュ」であり、
そもそもが「自傷的」な人間なのだ。
何かしら、危険を前にしたら、それを実行せずにはいられない人間。
そのなかでこそ、生きている実感を得られる人間。
もとい、そのなかでしか、生きている実感を得られない人間。
そのせいで自らが破滅しようが、そんなことは二の次の人間。
いっぽうで、愛するフィアンセを「奪われた」側の男の行動も、たいがいに粘着質だ。
女性が失踪してから3年。
彼はまったく衰えない熱意と執着をもって、旅先の街で姿を消した女を探しつづける。
その異様なのめりこみようと、ぎらぎらとした飽くことなき追求精神は、やがて、もうひとりの飽くことなき「悪」の精神を引き寄せることになる。
この物語の「狩るもの」と「狩られるもの」は、同じコインの裏表のようなものだ。
同じ臭気を嗅ぎ取ったからこそ、誘拐犯は、もうひとりの男に異様な執着を示す。
「似たもの同士」だからこそ、ふたりは呼応し、引き合い、必然的に邂逅を果たす。
「似たもの同士」だからこそ、あの結末へと転がり込んでゆく。
考えてみればいい。
「ああしなければいけない理由」なんて、
じつは「なにもない」のだ。
本当は、いくらだってやりようがあったはずだ。
官憲を呼んだら終わりというのは、
犯人側の暗示による単なる「思い込み」にすぎないし、
むしろ捕らえて永遠に終わらない拷問にかけてもよかったし、
あれだけ「マヌケ」な犯罪者なんだから「飲んだふり」だってできただろう。
ふたりの思考回路が「似すぎている」から、被害者は暗示にはまってしまったわけで、結局のところ、この物語は「噛み合ってしまった」犯罪者と被害者の「猫と鼠のゲーム」なのだ。
で、こういうところが本当にパトリシア・ハイスミスっぽい、というわけだ。
ちなみにあの『セブン』を超えると宣伝されている「ラスト」なのだが、実は観ながら「こう終わる可能性」をちょっと考えていた。
というのも、この犯人のノリだとか話の組み立てとかが、パトリシア・ハイスミスっぽいのと同時に、どこか「エドガー・アラン・ポー」を思わせるところがあったからだ。
あと、そう昔ではないころにラーシュ・ケプレルの『砂男』という上下巻を読んでいて、あれには「似たような」犯罪を恒常的に繰り返しているサイコパス殺人鬼が登場する。
なので、なんとなく、こういうオチもあるかなあと思いながら観ていた感じだった。
なんにせよ、映画の出来自体はそこまで最高傑作だとも思わないのだが(とくに音楽が超絶ダサすぎる)、とにかく個人的にパトリシア・ハイスミスは大好きなので、その作風に影響を受けているとおぼしき本作もまた、拾いものというか、愛着のもてる作品だったという感じ。
あえてヒロインのその後を描かない手法とか、時系列のシャッフルをきかせたナラティヴとか、終盤に出てくるコーヒーポットの演出とかは、とてもいい感じだったかと。「二つの金の卵」の予知夢や「二枚の埋められたコイン」のメタファーが、そのままラストで並んで●●される「運命」を暗示(明示?)しているのも、実に気が利いている。
パンフで高橋諭治さんが、ヒロインがトンネルでパニックになるところや、犯人が「閉所恐怖症でシートベルトができない」というあたりと、ラストシーンの関連性について指摘してられて、なるほどなあ、と。
ただ、あんだけド田舎の駅前とかサーヴィスエリアで、見知らぬ女性に声をかけまくってて、挙句、知り合いにまで気づかずに声かけたりしてて、現実だったらこの犯人、絶対失踪事件の捜査過程で捕まってる(もしくは犯行以前に通報されてる)と思うけどね(笑)。
まあ、この犯罪計画の細かいようでいて抜けまくった「ずさんさ」や、男の醸し出すケント・デリカットのような「愛嬌」と、行う犯罪の残忍さ、非情、狂気の深さの「ギャップ」こそが本作の魅力の一端でもあるので、これはこれでよかったのかな?
なんにしても、こちらがチェックできていなかった秀作を、最終上映としてしっかりリマインドして流してくれた映画館と配給会社に感謝。
キューブリックが
3回も鑑賞し「これまで観たすべての映画の中で最も恐ろしい映画だ」とまで言わしめた作品らしいね
不気味さや派手なサイコさはないけど、
それが本当に日常の中にありそうな現実味のある雰囲気だとも思う
先が想像出来る好奇心に耐えられないシーンは心の準備が出来てるのにゾッとしたな
愛する人の死様を恋人に追体験させるって思考をする犯人が次はどんな殺人を重ねたのか気になる
異常は見た目ではわからない
いわゆるサイコパスの犯人だが、始めは事前練習をしたり、少しコミカルにも見え親しみさえ覚える。
ただラスト付近で車の運転中にシートベルトをし、持病である閉所恐怖症である事がわかったうえで、ラストの罪は、自分の最も苦手な状況を、激しい恨みが有るわけでもない相手に行なうとは、殺人者のなかでも異常です…
ストーリーはどんでん返しみたいなものがなく、ストレートに進んだイメージ
愛と悪は無限大
何がどう凄いのか分からないけれど、これは観なくてはと思っていた作品。(リメイク版も未観賞)
百聞は一見にしかず。
大方想像がついたとしても、見てみたい、体験してみたいという欲望。
凡作と知りながら度々貴重な時間を浪費させる好奇心を抑えられない自分と、3年間恋人Saskiaを捜し続け、絶望的な真実に身を投じてしまうRexが重なりました…。
「結局Saskiaはどうなったのか」
その一点だけに引っ張られ、引っ張られ…
…え〜ぇ!!… ∑(゚Д゚)… 。
もう一回観て、細かい所まで作り込まれていることに感心。
とにかく凄いのは、Rexが真相に執着する心理と、ソシオパスRaymondの心理が丹念に描かれている所です。
トンネルでのハプニングがなければ、恋人達が愛を一層深めることもなかったし、Saskiaを独りにしたことにRexが罪悪感を抱くこともなかった。捜索時に妻と呼んでいたのは、コインの誓い?で結婚を密かに決意したからではないでしょうか。
一方のRaymond。女性を誘拐するため、入念に予行練習をし、何度も撃沈する犯罪者予備軍の姿は滑稽にすら映ります。
アブナイことは、想像だけで実行しないのが当然なのか?
そこで行動に移す自分は異常だと「発見」した16歳のRaymond。
その26年後、彼が思い付いた新たな「実験」とは?
川で溺れていた少女を助けたことで娘からヒーロー視されるが、「手放しの称賛」より、もっと嬉しいことに気付く。
溺れていた少女は、川に落ちた人形を拾おうとして、自身も川に落ちたか飛び込んだのでしょう。自分の危険は顧みない所と人形をビデュルと名付けて呼んでいることから、余程大事にしているのだと分かります。
少女は助かるも、彼女にとっては親友ビデュルを永遠に失ってしまったという後悔と喪失感が心に刻まれたことを知り、彼女からむしろ「恨まれる」ことにRaymondは快感を覚えているのです。
「殺人は最もひどいとは言えない」
ならばRaymondが辿り着いた、最もひどい悪事とは…。
大切な人から永遠に引き離すこと。
その大切な人が苦患の末に壮絶な最期を迎えること。
これこそただの殺人より残酷なことだ。
だから身寄りのない貧しい娼婦を更に不幸にしても面白くない。
生き生きと、幸せに暮らしている女性が良い。
恋人や夫に愛されて、生活に満足していそうな女が良い。
愛する人と突然離れ離れになり、それまで想像したこともなかった冷たい土の中、孤独と絶望で発狂するがいい。
何の落ち度もない人を、満たされた人生から、一気に地獄へ突き落とす。
Raymondは化学教師。
最大の悪事を働くという実験成功のためには、綿密な準備が欠かせないのです。
別に棺桶でなくても良いのでしょうが、Raymond自身が閉所恐怖症のため、彼の思い付く一番の恐怖が閉じ込められることなのかなと。
Saskiaの最期はRaymondのみぞ知る訳ですが…、結構彼は正直に話しているのではないかと思いました。Rexの好奇心に賭ける。全ての真実を手に入れない限り、きっとRexは自分を殺さないだろう。ギリギリまで引き付けて封じ込める。派手な捜索活動によって二度と心が乱されないように…。
劇中繰り返される様々なサイン。
◇2
夢で現れる金の卵。
金の卵のように光る車のヘッドライト。
2台の自転車(二輪車)。
2つのコイン。
コインの誓いでSaskiaが立てる2本指。
ボールやフリスビーで遊ぶ2人組の子供達。
子供のRaymondがバルコニーから見下ろす2つのマンホール。
Raymondの2人の娘。(はっきり言って1人でもいい。)
Rexがコーヒーを飲む前に、2本の木の周りを走る。
Raymondの別邸の2本の植木。
Saskiaの夢や会話では、最初金の卵と木はそれぞれ1つ。
◯8
Saskiaの好きなナンバー。
Infinity ∞ の暗示。
RexとLienekeの交際も8ヶ月で終了。
もしくは8も⚪︎2つの意味?
◯主要人物達はほぼ常に1対1。
SaskiaとRex。
SaskiaとRaymond。
RexとLieneke。
RexとRaymond。
RexにRaymondが近付くとLienekeは去る。
なぜ ”pair” にこだわるのか…。
恋愛やスポーツなど、相手が居ないと出来ない事柄だけでなく、善悪、明暗、上下、勝敗といった対義的存在も含めて、片方がいなくなることで成立しない関係の象徴なのかなと思いました。
◇青いトラック
RexとSaskiaが離れ離れになるサイン。
ガス欠の時と誘拐時に現れる。
◇バラ
Saskiaの好きな花。
Raymondの妻が別邸の庭で水をやっている植木は白いバラ??
◇昆虫
ナナフシ?は、RexとSaskiaのドライブシーン直前に登場。
クモとカマキリはRaymondの別邸で。
クモやカマキリはナナフシを食べる。
Saskiaの笑顔は、まるでNorma Jeanのように愛くるしいのですが、Rexの思考能力の欠如が著しくて、もはやSaskiaの呪いのように思えてきます(^_^;)。Raymondはごく普通に見えるソシオパスですが、Rexは異常な執着心が瞳にも行動にも現れ、ちょっと普通に見えない普通の人。両者とも「イカれている」と言えるかも?
…もう独りにはしないで。決して私から離れないで。
コインの誓い、恐るべし。
せっかく犯人と待ち合わせ場所にいるのになぜもっと策を練らないのかとか、コーヒー飲むフリくらい思いつけよとか、教師はそんなに暇なのだろうかとか、ツッコミたくなる点も幾つかあります。
君は知りたいことを知らないままにできるかね?
本作も、観客の好奇心にかなり賭けてます(^^)。
キューブリックの評価は観賞後に知りました。そのキャッチコピーだけに釣られて観ると、かえって期待値が上がってしまうのかなという気もします。
しかし地味にすごい、隠れた良作です。
***
「忘れるのに必要な時間は、一緒にいた時間の半分」
この台詞、SATCでもそっくり出て来ました。“It takes a half the total time you went out with someone to get over them.”
本作を参考にしたのかな。
「入念な計画もたったひとつの偶然で変わる。」
『パラサイト』でも類似の概念が出て来ましたね!
それが彼女に起きた真実とは限らない
飛び降りる事を「想像」する。
誰が飛び降りないと決めた?
飛び降りてみなければ分からない。
普通はしないであろう事を想像する。
何故、それは「普通しない事」なのか?
「それをしない」のは「危険」だから。
「危険」か否かは、してみなければ解らない。
だから「する」。
普通は人を殺さない。
何故か?
人を殺せば我が身にも不利益が及ぶリスクがあるから。だから普通は殺さない。誰が決めた?殺してみなければ分からない。だから殺した。
レイモンに倫理は通用しない。まず、16歳のレイモンは、本当に自らの意思でベランダから跳んだのかさえ疑ってしまう。全てがレックスを「嵌めるための詭弁」で無い保証は?全てがフェイクかも知れないとは思わないのか?劇中、レイモンの表情を見ていると脳裏に浮かぶ疑問が怖い。
永遠に私を一人にしない事。浅く埋めた2枚のコイン。山荘の土中、プレゼントされたライターで酸素を浪費するレックス。これじゃ、まるで呪いじゃないか。
いずれにしてもレイモンのサイコパス振りが忌まわしい。考える力を自らの感情で流し去ってしまったレックスが惨め。真実を知った、その先の事など、何も考えていなかったのですか?真実を知った時、そこで自分自身にどんな感情が生まれるのか、考えなかったのですか?
リメイク版含めて初見。キューブリックは名作と評したそうですが、マジか?
胸糞悪い心理劇は、1988年の作品。レックス達が乗ってたプジョー、古過ぎるよ。ってのは置いといて。なんか、マジ胸糞悪い。何が胸糞かって言うと、レックスの自己陶酔型思考 without 知性が。これは何かの暗喩ですか?
俺ならコーヒー飲まない。警察へも行かない。時間を掛けてレイモンを研究し、復讐します。
純正サイコパス映画とはこうういうもの
オランダから自動車でフランスに来たレックス(ジーン・ベルヴォーツ)とサスキア(ヨハンナ・テア・ステーゲ)のカップル。
道中、多少のいざこざはあったもののフランスのサービスエリアまでやって来た。
これまでの運転の労をねぎらおうとサスキアは売店に飲み物を買いに出るが、ぷっつりと行方がわからなくなってしまう・・・
というところから始まる物語で、行方不明の彼女は、フランス人男性レイモン(ベルナール・ピエール・ドナデュー)に拉致されたことが早々にわかるが、勧善懲悪からは程遠く、そんなものの彼岸に達してしまう映画である。
とにかく、スリラーサスペンス映画という枠組みの定石のようにはじまるにも関わらず、ほっとするとか、ああ良かった・・・というようなカタルシスは皆無。
評するのが難しく、恋人の行方不明になった男に共感する間もなく、その女性を拉致する犯人の描写になり、かつ、犯人の過去や拉致を成功させるためのリハーサルまで丹念に魅せられる。
ま、捕まらないようにと、念には念を入れて、という領域を超え、なんだかバランス感覚が著しく欠如しているようにもみえる。
けれど、終盤、犯人側に立ってみると、なるほどとも思う。
が、思うのは実際的にはよろしくない。
多分に、この映画、娯楽映画から無意識に純文学的映画にシフトしていると思うのだが、シフトしたあとの描写に、観客側がとまどってしまうからかもしれない。
「純文学は特別なひとが遭遇する普通の物語を描くが、わたしが書くようなエンタテインメントは、普通のひとが遭遇する特殊な物語だ」とは敬愛するスティーヴン・キングの言だが、最終的には、特別なひとに落ち着ていしまうとしても、特別でないような感じがして、すこぶる居心地が悪い映画でした。
なお、監督自らが本作をハリウッドでセルフリメイク(『失踪』)しているが、こんな絶望的な結末ではなかったと記憶しています。
キューブリックが傑作というほどではないと思った
うーん、最も恐ろしい映画というほどではない。
というか、じわじわと苦しめられ命の危険を感じるような分かりやすい〈怖さ〉は全く無かった。
80年代の映画の割にはカメラワークも映像の質感もチープだし、全体的な雰囲気が昼ドラ。
最初から犯人視点で物語が展開されるというのも怖さが半減した要因。殺人鬼の犯行の手順が余りに稚拙過ぎて、途中からただのコメディかと思った(笑)
ただ、「謎」について「知りたい」という人間の欲求、またはそれにより生じる苦しみを改めて考えさせられた映画ではあった。
また、一見社会的に成功した人物がサイコパスであった場合、それをどうやって人に知らしめればいいのか?という疑問もわく。
以前、監禁された少女の事件を思い出す。10代の女性が犯人のいない隙に外に出て公園にいる女性に助けを求めたら、「力になれない」と言われ、絶望してどこに行けばいいかわからなくて、結局また部屋に戻ってしまったという(再び意を決して逃げ出したが)。
助けを求められたほうは、少女を「頭のおかしい子」だと思ったのだろうか。
例えばレックスが車中から沿道の人に「こいつは殺人鬼なんだ!」と訴えても、変な目で見られるだけだろう。
そういった意味での〈怖さ〉は感じた。
とはいえ、レックスは早々に、サスキアも自分も生きて帰されることは無いと悟り、車を降りて警察に「犯人だと名乗る者が接触してきた」と通報すればよかったのに。殺人鬼の横で睡眠薬を飲むなんて、手の内で転がされるにも程がある。
ラストは、閉所恐怖症だと話していた犯人が、あえて自分が恐怖する行為を獲物に与えたというところだろうか。
近年なら『ゴーン・ガール』『アメリカン・サイコ』など、いくらでも傑作はある。わざわざこの映画を見に行く必要はない。
古い映画でも、ヒッチコックや『何がジェーンに起こったか』など名作はいくらでもある。
自分の気づかない視点があるかもしれないので、墓から叩き起こしてキューブリックに「どこが怖かったのか」と問うてみたい気持ちになった。
あ、犯人が「サスキアをレイプしたのか?」と聞かれて馬鹿にするな!と逆ギレしたときはこいつやばいな、とは思ったけどね。
今見るには手垢が付いてしまった印象
サイコパスの異常性の描写。
恐怖のラスト。
公開当時に見たら、ホント衝撃的だったと思います。
でも、30年の間にさんざん使われてしまったので、今みたところで特に目新しい衝撃はなく、そうかそうか、まんまとなあ…という感想になってしまう。
何とも後味の悪いサスペンスでした。
犯行シーンと犯人の家族との団欒シーンを交互に描くことで、犯人の中で人を殺したい願望と良き家庭人としての人格が矛盾することなく共存していることが強調され、思わずゾッとします。だから、被害者が車の中で犯人と家族の写真を見て信用してしまう展開には、絶望感に打ちのめされます。
ストーリー展開のキレが悪い所やゆるい点もあるんだけど、犯行シーンはおろか死体すら見せずに、悪夢のようなエンディングまで繋げる監督さんの手腕は凄いです。
最後どうにかならんのかい
彼女が行方不明になってその行方を探す男と、その彼女を誘拐した男の話。
.
この犯人、普通に家族がいて娘も2人いる。なのに女の人を誘拐しようとして色々準備してるのが気持ち悪いんだよね。
.
サイコパスってこの映画みたいに普通に生活してるんだろうと思うと怖いな。誘拐された子が油断した理由も家族の写真を見たからだし。やっぱ男の人は誰であろうと信頼しないでおこう、うん(笑).
.
最終的に2人は会うんだけど、睡眠薬入のコーヒーを飲めば彼女と同じ目に合うから真相がわかると言われて飲むんだよ、主人公。バカか?.
.
とりあえず会うなら相手殺せるだけの武器持ってけよ~絶対彼女死んでるし、そいつに殺されてるの99パーだろ~.
.
心理面を重視したサイコパス・クライム・ムービー
とても面白い映画だ。ヨーロッパの映画だけに内面の描き方が上手い。家族を愛し愛され、ホワイトカラーの仕事もこなし、家計も豊かなハイクラスの一見まともな人物の歪んだ精神。汚点のない背景を持つことでサイコパスが際立つ。ここに描かれた恐怖はトラウマの如く記憶に残る。エンディングも絶妙。ここまで救いのない映画も、なかなかお目にかかることはない。
一人にしないで
SASKIA SASKIA SASKIA SASKIA SASKIA SASKIASASKIASASKIA SASKIASASKIA SASKIA SASKIA SASKIASASKIASASKIASASKIA SASKIA...
置いて行かないで、一人にしないで。
ガス欠の際のサスキアのセリフが最後に効いてくる。
二枚のコインの隠喩が悲しい。
美しく素敵でいつも優しいサスキアとずっと一緒にいるって約束したじゃない。
死んでいてもいいから、ただ一人ポッカリと消えないで。何があったか教えて。
何もわからないまま愛する人を失って3年。
新しい道を選ぼうとしても囚われから逃れられない。
いくら時があり過ぎようと未だにあのパーキングに閉じ込められたレックスの決死の覚悟に感動と恐れを抱いた。
すぐ側に居た恐怖と真っ向から対面しなければならないストレス。
目の前に犯人がいるのに殺すことができない弱み。
尋常じゃない緊張感で体がびりびりしながら観ていた。
犯人の描写が多く、厭なことに私はその魅力に強く惹かれてしまった。
これがサイコパスというものか!とひしひしと感じる。
自らの目的のために入念に計画と練習とテストを重ねる姿がなんだか可愛らしい。
ハンカチ重ねて置くの大好き。
常に微笑をたたえた表情が気持ち悪いのになぜだかとてもチャーミングで素敵な人に見えてしまうのはなぜだろう。
彼の家族が心から愛し合っている様子も納得がいく。
悲鳴のシーンがめちゃくちゃ好き。もうこの家族が愛しくてたまらない。
プレゼントのシーンも暖かくて素敵だし、余計にレイモンの隠れた異常さが引き立っている気がする。
この調子だとたぶん私も車に乗ってしまうコースだな…気をつけないと。
飛び降りないのが”当然”だなんて誰が決めた?
飲まないのが”当然”だなんて誰が決めた?
逃れるためには、知るためには、やるしかない。
呆気ない結果も望んだこと。
生き埋めだなんて本当に嫌だ。
性欲だとか拷問だとか、そういう分かりやすい欲望ではなくただただ厳しい最期を突然与えるだけの殺人ってなんなんだろう。
ライターで箱を燃やしたって自分にも火がついてしまうし、逃げ場ゼロ。考えるだけで息が止まる。
思うのが、この映画の結末は結果的に見ればバッドエンドだけど精神的に考えればハッピーエンドととらえることもできるんじゃないかということ。
夢の話や喧嘩のとき、イチャイチャの途中でしきりに言っていた「一人にしないで」という言葉通り、サスキアの許にレックスはやってきてくれた。
一人で膨大な恐怖と苦しみに襲われ寂しく死にゆきずっと一人地中に沈んでいたサスキアの許に、やっとレックスがやってきてくれた。
木の下に埋められた二枚のコインのように二人は寄り添って埋まっているんだなと思うと、ものすごく悲しいのに少し救いがある気がする。
死後の世界がもしあるなら、サスキアはちょっと嬉しいんじゃないかな。
自分本位で考えるなら、遺された恋人の新しい幸せよりも自分を選んでくれたことが嬉しいんじゃないか。なんて思ってしまう。
粋というか悪趣味というか、あの水筒から注がれたコーヒーを劇場で売っていたので私も飲んだ。真実を知るために。
レックスと同じタイミングでがぶっと飲めたのがとてもうれしい。
コーヒーが苦手だから頭痛くなったし美味しくもなかったけど、すごく良い映画体験ができたと思う。
アイリッシュコーヒーだったので少しウイスキーが入っていて、ほんのりホロ酔いになれて素敵だった。
怖い
映画で完全犯罪をし、その死体の上で家族とピクニックをする。
狂っている。
主人公は狂った彼であり振り回される馬鹿な男が適度で面白い。
冷静なカット割りも心地よく
映画としてはこれはいいのかと思ったが。
視聴者を試すようでいいのだろう。
瓦
フランス旅行中のオランダ人カップルの女性がドライブインで買い物に出掛けたまま行方不明になる話。
後にハリウッドリメイクされた「失踪 妄想は究極の凶器」は随分前だけど鑑賞済み。
窓ガラスが割れちゃったり、リアクションがおかしかったりと違和感がかなりあった中でみていたこともあるけれど、1988年の映画ってこんなにショボかったっけ?ダイハードと同じ年だよね…。
確かに何もないからこそサイコであり、わかっているのにのっかって行くところに面白さがあるのはわかるが、穴だらけで怖さよりも主人公のボンクラさばかりが気になった。
先にリメイク版をみていてそれと比べるのはナンセンスだけど、オチもリメイク版の方が好み。
怖さの正体は、たぶんジンワリと伝わってくる実感にある
誰もが経験したことのあるようなささやかなことや後になって考えれば迂闊だったな、というようなことの積み重ねで構成されています。
その効果なのだと思いますが、実はすぐそこにある邪悪は(それはサイコパスかもしれないしテロかもしれない)、いつでもどこでも襲いかかってくるし、一度襲われたら誰も逃げられないのではないか、という怖さがじわじわと迫ってきます、鑑賞後もじんわりと。
『ビリーブ』を観た時に、説得力というのは訴える側だけでなく、説得される側の度量や知識にもよるというようなことを書きましたが、この作品では、何となく信頼できそうな雰囲気の話し方で、追い詰められている相手が一番欲しいものを出すと、外から見てる我々からするとなんでそんなことを⁈という行動を当事者の立場の者は説得するまでもなく、ついついしてしまうのだろう、ということも実感として伝わってきます。
全18件を表示