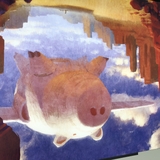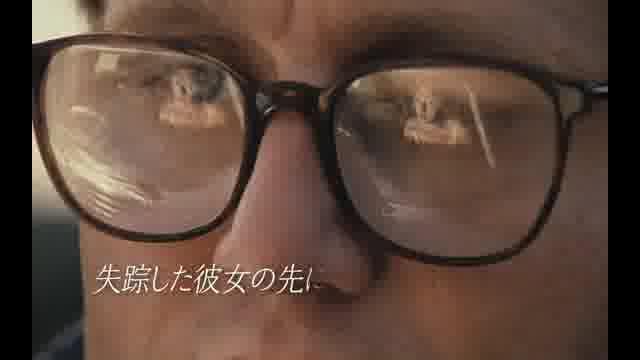ザ・バニシング 消失のレビュー・感想・評価
全52件中、1~20件目を表示
迫り来る飄々とした恐怖。真相を知らずにいられなくなる心理的作用に震撼。
この映画の噂はずっと前から聞いていたが、なかなか見る勇気がなかった。なにしろあのキューブリックが絶賛するほどなので、うっかり足を踏み入れると、何か邪悪なものが心の中に入り込まれそうな気がしていたからだ。が、公開から30年もの月日が流れ、ようやく意を決して観た本作は、私の予想を大きく覆すものだった。バイオレンス場面は皆無だし、表立って恐ろしいことが起こるわけではない。
むしろ「忽然と恋人が消えた」という心の穴を突きつけられ、そこに「何らかの事情を知る男」のコミカルにさえ思えるほどの飄々とした日常と思考を対比していくことで、本作は実に不気味な手触りと陰影を生み出していく。冒頭のトンネル内の映像は実に象徴的だ。
気付かぬうちに徐々に引き込まれていく流れ、真相を知らずにいられなる心理的作用に、唸らせられる。もしかすると『セブン』などの後続のサスペンス作はこの影響を多少なりとも受けているのかも。
U-NEXT を検索していてびっくり
真実を知りたい!知りたい!!知りたい!!!の先に待つもの。
映画「セブン」を超えるラストシーン。とか、宣伝されてしまうと、
フィンチャー好きの私としては、行かざるを得ない。
単館上映されるとのことで、行ってみました。
-------
没入感の演出が非常にうまく、彼女に何がおきたのか、知りたくて、知りたくて、たまらなくなります。
この先、どうなるんだ!! そんな気持ちが、どんどん大きくなるように作られています。
ラストに向かって、あれこれ、想像するものの、全部否定されてしまい、
この人、実は良い人なのか!?と錯覚すらしていきます。
作中の主人公と、観てる人の心境がシンクロした状態での、あのラスト・・・。
良くできてる。本当に良くできている。
-----
行った映画館では、売店に、ブランデー入りの珈琲を売ってました。
珍しいので買ってみたんですが、わざわざ、水筒から珈琲を注ぐので、何だろう?と思ってましたが、
まさか、そういうことだったとは。映画館も、なかなか洒落がきいてます。
80年代にこんなサスペンススリラーがあったなんて、伝説の作品といわれるのも良くわかる。
しばらく、暗いところで寝れない・・・。
こんな面白い映画あるの?
こんな面白い映画あるの?って久々思った
常に面白い。スリルがあるし画面のルックも常に最高。
話も良い。終わりも良い。(最悪で)
映る全てに意味がある丁寧な作り。
普通のカップルがぬるりと、闇に滑っていくような恐怖と、犯罪者側の心理や思考のプロセスと、自ら望む結果を得る為の細かいトライアンドエラーのプロセスまで見せるのに、映画としてものすごく綺麗にまとまっている。
ほんとにすごい。
終わり方も、めちゃくちゃ嫌な終わり方で最高。
ほんとうの悪は、こうなんだよな。ってゆう恐怖の終わり方。
この神経質な殺人鬼はジョジョの吉良吉影を思わせるから、元ネタの1つなのかなとも思った。
サスキアがほんとうに、太陽の様な魅力を持った人
だったから、レックスと一緒に真相迫っていく中で
生きててくれないかな、と願ってしまっていたので
あの結末はすごく悲しくもある。
黄色の使い方とか色の印象も強く残ってる。
レックスとゆう男性の喪失と執着の話でもあるので、真実を知りたいとゆう人間の欲求も描かれてて
ほんとにすごい映画だ。めちゃくちゃ面白かった。
これが長らく日本未公開だったなんて信じられない。
配信で鑑賞
花柄ポット! パトリシア・ハイスミスの濃厚な影響を感じさせる「失踪ミステリ」の秀作。
ナナフシで始まり、カマキリで終わる。
『ザ・バニシング』は「捕食者」に関して考察する映画だ。
面白くないわけではないし、評価されるべき映画だとも思うが、実像以上に「面白そう」に語り伝える宣伝回りのテクニックが実に巧みで、ちょっと嫉妬してしまうくらい(笑)。
いわく――、
●サイコ・サスペンス映画史上No.1の傑作、ついに解禁――。
●ラストへの戦慄が『サイコ』(60)、『羊たちの沈黙』(91)、『セブン』(95)、『ゴーン・ガール』(14)を超える!
●巨匠スタンリー・キューブリックが3回鑑賞し「これまで観たすべての映画の中で最も恐ろしい映画だ」と絶賛!
●ただじっとりと流れる暗黙の時間に身を委ね、無情にも訪れる史上最悪のクライマックスを待つしかない。
ここまで言われたら、観るしかないじゃないか(笑)。
あと、シネマート新宿限定で販売されたコラボドリンク「バニシングコーヒー」(花柄のポットから供される)は500杯の売上を記録、ってのもネタとしてふるってる。
(以下、はっきりネタバレはしていない気もしますが、展開自体を伏せておいたほうが初見者にはよさそうな映画なので、いちおうネタバレ設定としておきます。)
で、初めて観ての感想。
これって、……まんま、パトリシア・ハイスミスじゃないか!!
オランダ出身の頭のおかしな監督というと、まずはポール・バーホーベンとディック・マースと相場が決まっているが、本作のジョルジュ・シュルイツァーはフランス生まれ。原作のティム・クラッべのほうはオランダ人だ。
国境を接している以上、仏蘭両国には比較的ひんぱんに人的交流もあるのだろうし、本作でも「国境」「オランダ語とフランス語」「自転車と車」など、「気軽にフランスを訪れたオランダ人観光客の巻き込まれ型サスペンス」という設定をうまく使っている。
にしても、このパトリシア・ハイスミス・フォロワー感はただごとではない。
パトリシア・ハイスミスというのはアメリカの女流ミステリ作家で、1950年代に『見知らぬ乗客』(のちにヒッチコックが映画化)でデビューして、90年代まで活躍した大家である。代表作は『太陽がいっぱい』(のちにルネ・クレマンが映画化)あたりか。
ほかに『水の墓碑銘』『愛しすぎた男』『ふくろうの叫び』『ガラスの独房』『ヴェネチアで消えた男』あたりも面白い。
個人的には、現代の「サイコ・サスペンス」の土台を作った作家だと思っている。
別名義で『キャロル』というレズビアン小説の嚆矢となる作品を書いたことでも知られている。ついこのあいだ、『パトリシア・ハイスミスに恋して』というドキュメンタリーが日本でも公開されたので僕も観てきたが、その映画の主題は、彼女の同性愛者としての性指向についてだった。
60年代からはフランスで暮らし、ちょうどこの映画が撮られた80年代はスイスに移住していたはずだ。だから、どちらかというとアメリカ以上にヨーロッパでの人気が高く、リスペクトされていた作家である。
たぶん、TVでたまたまこの映画をやっていたとして、タイトルも履歴もわからない状態で観たとすれば、僕は十中八九「パトリシア・ハイスミスの未読作が原作」の映画だと判断したと思う。それくらい、テイストが「パトリシア・ハイスミス」してる。
ひとりの女をめぐっての、男ふたりの知的闘争。
やがていつのまにやら女そっちのけで、
男同士のねちっこい執着合戦がお互いを縛り合う。
このホモソーシャルな「相手への粘着、執着、執念、付きまとい」をとめられない感覚、むしろそれに「淫していく」感覚が、実にパトリシア・ハイスミスっぽい。
「悪」の側にいる人間に、通常の意味での道徳観や相手を慮る道義心がきれいさっぱり欠落しているのも、実にパトリシア・ハイスミスっぽい(本作の登場人物は、自らを「ソシオパス」だと自己紹介する)。
そこかしこに「くすり」と笑わせるようなコミカルな描写をはさみながら、それを鬼畜のような所業や悪夢のような結末と平然と並置する。
そのことで起こるケミカルな「違和」の反作用が、作品の魅力になっているところがまた、パトリシア・ハイスミスっぽい。
パトリシア・ハイスミスの特徴であるところの、
●犯罪者と被害者が特定のインティメットな関係(どこか同性愛的)に陥り、「狩るものと狩られるもののゲーム」にのめりこんでゆく。
●犯罪者側には罪悪感や道徳心が決定的に欠如していて、自分でもコントロールできないほどの執着と好奇心に食いつぶされている。
●被害者側にも何かしらの問題があって、似たような執着の傾向とマゾヒズム的性向を示して、結果的に犯人と「共依存」的な関係に陥る。
●これらの歪んだ関係性や狂った行動が、あまり説明もないまま淡々と描出されていくので、作品全体に異様な不条理感が漂う。
●その際、たくみな比喩と切れのいいレトリックを用いて、ある種の「笑い」の要素を挿入してくることも多く、逆に全体の不気味さを増幅させる。
といった要素が、『ザ・バニシング』にはすべて驚くほどの再現性で「踏襲」されているのだ。
犯人側は、ごく当たり前の幸せな日常生活を家族と送りながら、単純に「究極の悪を成す」という実験精神のために(要するに何かしらの利得を求めてではなく、悪であること自体を目的として)誘拐計画をねちねちと練り続けているのが、とにかく気持ち悪い。
それも、自分でクロロホルムの効き具合を試したり、いつ捕まってもおかしくないような危なっかしい「狩り」を続けたりと、綿密に計画している割には、やたら「わざわざリスクを背負った」犯罪計画にまい進している。
このあたり、まだ幼いころに「飛んでみなければわからない」とバルコニーから実際に飛び降りてみたり、パパになってから、水路で溺れる赤の他人の少女を助けるために一瞬の判断で飛び込んでみたりと、後先を考えない自暴自棄な「勇気」を発揮しているのと密接に連動している。
要するに、この男は生来的な「デスウィッシュ」であり、
そもそもが「自傷的」な人間なのだ。
何かしら、危険を前にしたら、それを実行せずにはいられない人間。
そのなかでこそ、生きている実感を得られる人間。
もとい、そのなかでしか、生きている実感を得られない人間。
そのせいで自らが破滅しようが、そんなことは二の次の人間。
いっぽうで、愛するフィアンセを「奪われた」側の男の行動も、たいがいに粘着質だ。
女性が失踪してから3年。
彼はまったく衰えない熱意と執着をもって、旅先の街で姿を消した女を探しつづける。
その異様なのめりこみようと、ぎらぎらとした飽くことなき追求精神は、やがて、もうひとりの飽くことなき「悪」の精神を引き寄せることになる。
この物語の「狩るもの」と「狩られるもの」は、同じコインの裏表のようなものだ。
同じ臭気を嗅ぎ取ったからこそ、誘拐犯は、もうひとりの男に異様な執着を示す。
「似たもの同士」だからこそ、ふたりは呼応し、引き合い、必然的に邂逅を果たす。
「似たもの同士」だからこそ、あの結末へと転がり込んでゆく。
考えてみればいい。
「ああしなければいけない理由」なんて、
じつは「なにもない」のだ。
本当は、いくらだってやりようがあったはずだ。
官憲を呼んだら終わりというのは、
犯人側の暗示による単なる「思い込み」にすぎないし、
むしろ捕らえて永遠に終わらない拷問にかけてもよかったし、
あれだけ「マヌケ」な犯罪者なんだから「飲んだふり」だってできただろう。
ふたりの思考回路が「似すぎている」から、被害者は暗示にはまってしまったわけで、結局のところ、この物語は「噛み合ってしまった」犯罪者と被害者の「猫と鼠のゲーム」なのだ。
で、こういうところが本当にパトリシア・ハイスミスっぽい、というわけだ。
ちなみにあの『セブン』を超えると宣伝されている「ラスト」なのだが、実は観ながら「こう終わる可能性」をちょっと考えていた。
というのも、この犯人のノリだとか話の組み立てとかが、パトリシア・ハイスミスっぽいのと同時に、どこか「エドガー・アラン・ポー」を思わせるところがあったからだ。
あと、そう昔ではないころにラーシュ・ケプレルの『砂男』という上下巻を読んでいて、あれには「似たような」犯罪を恒常的に繰り返しているサイコパス殺人鬼が登場する。
なので、なんとなく、こういうオチもあるかなあと思いながら観ていた感じだった。
なんにせよ、映画の出来自体はそこまで最高傑作だとも思わないのだが(とくに音楽が超絶ダサすぎる)、とにかく個人的にパトリシア・ハイスミスは大好きなので、その作風に影響を受けているとおぼしき本作もまた、拾いものというか、愛着のもてる作品だったという感じ。
あえてヒロインのその後を描かない手法とか、時系列のシャッフルをきかせたナラティヴとか、終盤に出てくるコーヒーポットの演出とかは、とてもいい感じだったかと。「二つの金の卵」の予知夢や「二枚の埋められたコイン」のメタファーが、そのままラストで並んで●●される「運命」を暗示(明示?)しているのも、実に気が利いている。
パンフで高橋諭治さんが、ヒロインがトンネルでパニックになるところや、犯人が「閉所恐怖症でシートベルトができない」というあたりと、ラストシーンの関連性について指摘してられて、なるほどなあ、と。
ただ、あんだけド田舎の駅前とかサーヴィスエリアで、見知らぬ女性に声をかけまくってて、挙句、知り合いにまで気づかずに声かけたりしてて、現実だったらこの犯人、絶対失踪事件の捜査過程で捕まってる(もしくは犯行以前に通報されてる)と思うけどね(笑)。
まあ、この犯罪計画の細かいようでいて抜けまくった「ずさんさ」や、男の醸し出すケント・デリカットのような「愛嬌」と、行う犯罪の残忍さ、非情、狂気の深さの「ギャップ」こそが本作の魅力の一端でもあるので、これはこれでよかったのかな?
なんにしても、こちらがチェックできていなかった秀作を、最終上映としてしっかりリマインドして流してくれた映画館と配給会社に感謝。
キューブリックが絶賛に惹かれて
願望
サスキア‼︎
88年のオランダ、フランスの合作映画。
監督はジョルジュ・シュルイツァー。
オランダからフランスへドライブ旅行に来たレックスとサスキア。しかし途中で立ち寄ったドライブインでサスキアは忽然と姿を消した。
そして3年の月日が流れるが、レックスは新しい恋人がいてもサスキアを忘れられず捜し続けていた。やがてそれも限界に達し半狂乱に陥るレックス。ついにテレビ番組にて見えない相手に「真実が知りたい」と問いかける。結局新しい恋人はレックスの元を去るのだが、同時にサスキアの消息を知っていると語るレイモンという男が現れた。
知りたければフランスまで一緒に来いとの誘いにレックスは仕方なく乗り、レイモンに同行する。
道中、レイモンはある動機を語り始める。
26年前に思いついた実験。
悪事を働くには悪の心が必要ではない、という証拠であるということ。
殺人には「殺したい」という感情が働いているが、生き埋めにするならば「穴掘り」と「埋める」という単純作業で事足りる。つまり感情は必要なく、そうする事でレイモン自身に悪は存在せず、それが自身の正しさを証明する証拠にもなる、という理論。
レックスは「狂ってる」というしかなかった。
そして、レイモンはレックスに一杯のコーヒーを差し出し「これを飲めば真実が分かる」と告げる。
あまりにも怪しすぎる展開。
眠らされると分かっていて睡眠薬入りのコーヒーを飲むなんて愚の骨頂としか言いようがない。
真相を知らずに死ぬか。
真相を知ってから死ぬか。
いつしかレックスの人生はこの二者択一にのみの思考にしか従えなくなっていた。
ある意味、レックスもサスキアの末路に取り憑かれた結果、レイモンと同様の反社会性パーソナリティ障害に陥っていたのかも知れない。
目が覚めたレックス。
言うまでもないが暗闇の中。
かろうじてライターを照らすと狭い箱の中らしい。
いくら叫んでもどこにも届かない。
結局サスキアの最後がどうなったのかが描かれることはなかったが、レックスの末路を見れば一目瞭然と言わざるを得ない。
ラストカットはレイモンの無表情な顔、そして新聞に載ったレックスとサスキアの顔写真と行方不明の文字だった…。
スタンリー・キューブリックが大絶賛した本作。
近年まで日本未公開だったが2019年に満を辞して日本での劇場公開に至る。
サイコサスペンスの金字塔とも言うべき数々のキャッチコピーがつけられる名作であるが、あくまでも88年の作品でありハリウッドのような派手な演出は一切ない。
ソファに寝っ転がって観たが、途中で寝落ちしなかった。何か惹きつけられるものがあったんだとは思うが、一体なんだったのだろう。
そして、それ以上に不思議だったのは、予約録画をセットした記憶は一切ないのに、この映画が突然録画されていたことだ。
何故だろう?
キューブリックが
3回も鑑賞し「これまで観たすべての映画の中で最も恐ろしい映画だ」とまで言わしめた作品らしいね
不気味さや派手なサイコさはないけど、
それが本当に日常の中にありそうな現実味のある雰囲気だとも思う
先が想像出来る好奇心に耐えられないシーンは心の準備が出来てるのにゾッとしたな
愛する人の死様を恋人に追体験させるって思考をする犯人が次はどんな殺人を重ねたのか気になる
既視感ありと思ったら「失踪」のオリジナル版だったんだ。 最初のトン...
主人公は「ラスコーリニコフ」か?
行方不明になった恋人を探し求める主人公と、その犯人の心理を描く物語。
異色のサスペンス・・・というよりは、人間の酷さをを描いた人間ドラマのように感じられます。
特に、犯人の描き方が不気味で秀逸です。
良き夫、良き父を演じながら犯行の衝動を抑えられず、冷徹に実行に移す犯人。
人間の不気味さと残酷さを際立たせる存在でした。
ただ、映画全体としてみれば捉えどころがなく、高い評価は難しい作品でもありました。
不親切さが心地好い。
異常は見た目ではわからない
いわゆるサイコパスの犯人だが、始めは事前練習をしたり、少しコミカルにも見え親しみさえ覚える。
ただラスト付近で車の運転中にシートベルトをし、持病である閉所恐怖症である事がわかったうえで、ラストの罪は、自分の最も苦手な状況を、激しい恨みが有るわけでもない相手に行なうとは、殺人者のなかでも異常です…
ストーリーはどんでん返しみたいなものがなく、ストレートに進んだイメージ
犯行の一部始終
変態男が女を連れ去る事件をリアルに描いている。
カップルの女が連れ去られ男が3年にも渡って探し出し、ついに犯人を特定し、真相を探ろうとする。
真相を探る過程で犯人の回想による犯行の一部始終がリアルに描かれる。
間違って知り合いの女に声をかけて気まずい思いをしたり、声をかけた女の男に難癖をつけられたり、やっと車に乗せることができたかと思えば、くしゃみをして台無しになったりと成功するまでの紆余曲折をリアルに描いている。
そんな経緯をえてついには成功する訳だが、数々の失敗の描写があるゆえに成功したときのリアルさがより一層強化されている。
犯行の回想のシーンは徹頭徹尾犯人の主観で描かれていて思わず感情移入してしまう。
「予感」のコントロール
全52件中、1~20件目を表示