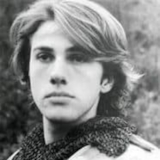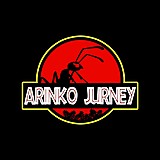ドッグヴィルのレビュー・感想・評価
全45件中、21~40件目を表示
美人は結局大事にされる、ってそりゃそうだ。
初見時は愚民の心底の闇とは?と見たが、
再見時は美人が居たらどうなるか?だけに見えた。
裏切られ疎んじられる程に、異様に美しく輝く美人女優を見る悦び。
それだけが残る文学風味の珍作。
美人は疎んじられた先で結局大事にされるのよ、ってそりゃそうだ。
だが好きだ。
三部作のはじまり
まるで舞台劇のようなセット。背景もなく壁もない白線を引いただけの村。他の家で何をやっているのか全てわかるようになっている。奇抜な発想のため集中力なくしては観れない映画なのかもしれない。
プロローグと9章からなる3時間のこのストーリー。途中、かなり眠気を誘うのだが、後半村人の変貌に度肝を抜かされ、スクリーンに釘付けとなってしまうのだ。舞台は多分20世紀初頭で失業と貧困層の社会問題があるころに思われる。貧困が生んだ荒んだ心と閉鎖的な村でのエゴイズム。その犠牲者がグレース(キッドマン)となる。
少年ジェイソンまでもがSM気たっぷりで、まともな人間はいなくなる。そう、彼らはまさしく犬なのである。本能だけで生活し、権力にしつけられることもない。その狂気の沙汰をまざまざと見せつけられる痛い映画だったのだ。こうなってくるとラストも予想できるのだが、エンドロールの背景写真に見られるように単なるギャング映画に終ってないところがすごかった。
【2004年6月映画館にて】
自己分析の心理テスト
人の善意に頼ることがいかに危ういか、善とは悪の仮面であり偽善の一面に過ぎないという性悪説もしくは閉鎖的な部落に起こりがちな悲劇なのでしょうか、朗読劇、百歩譲って舞台劇としても、舞台自体が心眼で見ることを前提としたような囲いを排した奇異な設定である。
人類の歴史を観れば性善説を唱える立場でもなく、かといって世の中悪人ばかりではないことは自明だろう、無理を通すためには閉鎖的なドッグビルという仮想の村が必要だったのだろう。
制作者の意図を善意に解釈するとすれば反面教師として心清き人よ用心あれと言いたいのだろうか、それとも観る人の混乱する様を楽しみたい悪戯なのか。
状況説明のナレーションですら煩わしいが心理描写まで文字を読み上げる手法はかって無声芸術として誕生した映画文化の対極でもあり映画への挑戦あるいは冒涜とも受け取られかねない。既存の価値観、様式の否定からしか自己表現できない人がいても不思議はないがシュールであることイコール高尚な芸術表現と称える気にはなれません。賞賛、許容、困惑、否定と受け取り方次第が自己分析の心理テストのような映画でした。それ以前に診察台に乗った心境で178分という長さに耐えられないかもしれませんね。
顔に道徳的な平手打ちをくらったかの様な衝撃
顔に道徳的な平手打ちをくらったかの様な、衝撃的な映画体験をした作品の1つ。
ラース・フォン・トリアーの作品なのに、ラストシーンでカタルシスを感じられて気持ちがいい!と思える人が少し羨ましい。
村人たちの行動原理はエゴや弱さが丸出しだけれど、そこまで突拍子のないものでもなく、理解できる範疇にある。村人と一見いい人そうに感じるトムも実際の我々の側面であって、グレースは理想の人。
私はグレースの、全てを許容し慈悲深く、村人に寛容な姿に共感。しかし、最後に全てを覆す裁きを下したこと(母親の前で子供を殺して…など故意ありの裁き)にカタルシスを感じつつも、グレースも村人たちと同じ人間なんだなぁ…と悲しくもあり、自分も同じことするだろうなぁとも思うので、共感していた自分に嫌悪感すら感じる。まさに寛容の自己満足というやつでしょうか。
ラース・フォン・トリアーの作品を観ると人間嫌いなんだなと感じるけれど、他人よりも自分のことが嫌いでしょうがないんじゃないかと感じています。
アメリカ、鬱
恩寵
ドッグヴィル=犬の街 つまり人間は存在するがそこに理性はなくただ本能だけが存在する街ということ。
ドッグヴィルの人々はグレースを異分子として自分たちの都合のいいように奴隷として扱う。首輪をつけられたグレースはまさしくその姿だ。
トムはグレースに対し「愛している」や「助ける」と言っているが、いざ人々から自分が責められそうになると全てをグレースのせいにする偽善者である。
グレースはもし自分が人々と同じ立場だったら自分もそうなってしまうかもしれない。だから人々を許すのだと。
しかし、それは傲慢だと父親に言われる。
自己を犠牲にして相手を許したからといって相手は何も変わっていない。時がたち再び同じ過ちが繰り返されるだけである。ならば悪事を働いたものたちにはその責任をとってもらわなければならない。
衝撃が強すぎて忘れられない映画
言葉を失う圧倒的な感動と重さ
実験的で前衛的でありながら、これ程の言葉を失う圧倒的な感動を与えられるとは!傑作中の傑作だ
エンディングにあのような明るい曲を持って来なければ誰も見終わった後に席に座りこんだまま動けなくなってしまうだろう
本作の重さはそれほどの感動の重さだ
まず、セットに驚かされる
建物の壁もドアもない、黒い床に引かれた白線が建物の輪廓を示し誰の家か明示されてあるのみ、最小限の家具だけが置かれているのみなのだ
風景もまた無い、美しいと台詞で語られる山や谷は昼は白く夜は黒いのみだ
俳優達はなにもない白線の内側の家の中でそれぞれの行動を演技する
なにもないドアををノックして開き出入りするのだ
しかし効果音はあり確かに建物は存在していることをしめしている
何故見えないのか?
一体何の為にこのような舞台を用意しているのだろうか?
パントマイムのような前衛舞台の真似事?
とんでもない、これは神の視点なのだ
神の目からは何も隠し通すことはできない
それを映画として表現しているのだ
それを監督はチャックがグレースを初めてレイプしたシーンで私達に気付けるように、それまでの図面のような上からでなく、横からの町全体のショットで明らかにする
神の視点で有ることを理解できたならば、あとは全てがつながり恐るべき結末までもが起こるようにして起こる
グレースはキリストであり神であった
トムはユダであり、町の人々は私達人間の全ての暗喩だったのだ
キリストはユダに裏切られてもなお人間の罪をみな許し、その罪を背負い昇天する
しかしキリストをローマ人に売ったユダヤ人には神の怒りの鉄槌が振り下ろされるのだ
主の怒りと罰は神が操るローマ人の手によって下されたのだ
衝撃のラストシーン
やはりそうであったかと、これから起こることに戦慄を覚えながら、実際にその凄惨な殺戮シーンが始まったときに我々の胸中に去来するカタルシス!
それに驚かされてしまうのだ
このカタルシスは一体何だろうか?!
口だけで正義や道徳、平和や平等や人権を語る偽善、自らへの欺瞞
それを神が裁き完膚なきまでに叩きこわしてしまわれた
主の怒りが裁きが行われ、人間が正しく導かれ罪を償った
そのカタルシスだ
田舎だから?育った環境の問題?貧しさがそうさせたのか?
充分な教育が与えられなかったから?
人間の弱さ、不完全さからのこと?
だから許す?
そんなことは神が判断なさることだ
神の権限であり、人間がそれを語り許し赦されるなどと考えること、それこそ恐るべき傲慢な考え方なのだ
罪は罪だ、罰されなければならない
つまりグレースの父が語る言葉こそが本作のテーマであったのだ
悪を正す勇気のなさによって、自らの良心を偽善によって騙すことによって、人間が人間を許した
その傲慢さがこのドックヴィルをこの様にしてしまった根本的な原因なのだ
それこそが人間の弱さだ
このような結末にならないように私達は自らを常に律して、自らに厳しく、間違っていたことは直視して自らを罰しなければならない
そして罪を犯した他者は正しく罰するべきだったのだ
その勇気をもたなければならなかったのだ
良心を偽善でだましてはいけなかったのだ
さもなければ、人間という弱い被造物はこのドッグビルの住人にたちまちなってしまうのだ
愛、正義、平和、平等、差別、博愛、偏見、人権・・・
そのような美しいご立派な言葉を口にするとき
自分は今、犬畜生の町の住人になっていないか
それを私達は自らに問わなければならないのだ
それは自分の良心への欺瞞ではないのか?
間違っていることを正す勇気がないだけではないのかと?
神は全てを見通しておられるのだ
そして必ず罪を裁かれるのだ
2度と観たくないけど大好き
最初に観たので最後。あれから1度も観てない。レイプシーンがつらすぎる。
でも、とても大切で、とても好きな作品。
人の偽善、悪意、醜さ、憎悪がどんどん出てきて、子どもまで悪。でもそういう醜悪さって、見て見ないフリすると善意が殺されていく。自分がされたら絶対我慢できないことを、なんで他人にやってしまうんだろうこの人達という疑問が、観ている間ずっとつきまとう。特殊な人達じゃない、狭い社会の人間関係の中で、当たり前に生きている人達の姿が描かれている。
全編スタジオで、しかも特殊なセットで撮られているのが視覚的には非常にインパクトがある。余計な物を全部そぎ落として、頭がっちり掴まれて瞬きさえも許さない、みたいな雰囲気で、ものすごくシビアなシーンが展開されていく。
精神状態の良い日に観たって、観終わったあとはしばらく口を開けないかもしれない。とにかく重い。でも、傑作。
自分の中の悪意
理由もわからず逃げてきた女(ニコールキッドマン)をかくまい、徐々に人間の本性を表しはじめる村の人々に対し、嫌悪感しか感じられず、こんな奴ら全員死ねばいいのにって思った。
するとギャングの親玉がやって来て、ニコールキッドマンの判断で皆殺しになってしまったのを見て胸がスッキリしている自分に気付かされた。
数日前に「スリービルボード」を見て、怒りの被せあいはよくないって思ったばかりなのに、真逆の感情が自分の中に表れて嫌な気分にさせられた。
この作品を傑作とまでは思わないが、会社や部活、相撲のかわいがり、内ゲバなど閉鎖された組織の中でのあるあるを巧みにあぶり出した作品だと思う。
強い憤りを感じる作品
密室劇/復讐劇
舞台を観ている感覚で広い空間での密室での遣り取りにオチは皆殺し。
過酷な状況を耐えての失踪に最終的には村人を全滅と暴挙に出る我が儘キッドマン。
酷い扱いの連続に観ているコッチは嫌なストレスが溜まるがラストは気分爽快にスカッ!として笑える。
恐ろしい女に卑劣な手を下した村人たちの無様な顛末にコメディ要素も!?
暗いスタジオ、チョークの白線。
絶望 さらなる深い絶望
かくも弱き人々
ドッグヴィルという小さな村が、「人類の持つ暴力性」の象徴になっていて、人間の持つダークな部分が普遍的にも極端に描かれた傑作です。
村人の言うことを何でも受け入れる主人公グレースは、慈愛の象徴になっていますが、その慈愛に甘んじて村人達は徐々にその牙をグレースに向け始めます。お願いごとだけから始まったことが次第に虐待にまでエスカレートしていく残虐性は、閉鎖的な人間の集団の中ではもはや止めることはできません。
そして、村人が人間の残酷性の象徴だとしたら、トムは観念的な偽善の象徴でしょう。
どんなに綺麗ごとを言っても、本能の前ではそれは無力である。だからこそ、首輪をはめ時にはムチを与えるしかない。慈愛だけでは、自分の行動に責任をとる機会が与えられず人類は犬(本能)のままである。現代では首輪やムチの代替物が、宗教や法律や倫理に変わっただけなのかもしれません。
個人的には、犬になる様な社会を作りだしたらいかん!と思います。人間である以上、犬になる前に何らかの策が出せる可能性があると信じているからです。しかしトリアーには、こんな綺麗ごとは通じません。私もトムと同じ偽善者なのか?こういう人間でありたいという夢もただの寝言でしかないのか?
トリアー!!!!!
なんてこったい。
かくも弱き人々となった村人達に与えられたムチに快感を覚えた私も、グレースを虐待した村人と全く同じ人種だということに気づかされる人間の性を的確に暴いた恐ろしい作品でした。
この監督は、恐ろしい
Trier監督、恐るべし。アメリカ三部作という位置づけながら、ひたすら悪行に耐え続けるGraceには「ダンサー・イン・ザ・ダーク」に近いものを感じ、黄金の心三部作に近い印象を受けた。しかしあれからは主人公の心の美しさを感じたものの、こちらからはものすごい不気味さを感じた。
一見アメリカにある排他的な田舎の社会と見えたドッグヴィルは、その牙を美女Graceへ向けてゆく。しかし誰もそこに違和感を覚えない。Graceすらもが、全てを受け入れてゆく。それを観る私たちは、彼女の代わりに怒りを募らせてゆく。これは「ダンサー」にも言えるかもしれないが、Selmaが息子という人質を取られていたのに対し、Graceはいくらでも怒りを表現することができるはずだった。我々はここに違和感しか覚えないのだ。しかし、これは監督の思うつぼなのかもしれない。人間の善意とは、悪意とはなんなのか。怖い、怖い作品だった。しかし、長い、長い作品だった。
そういうとこHeneke監督の「ファニーゲーム」に似てるかも。
全45件中、21~40件目を表示