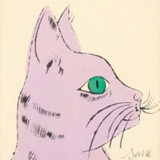めぐりあう時間たちのレビュー・感想・評価
全49件中、1~20件目を表示
【82.2】めぐりあう時間たち 映画レビュー
スティーヴン・ダルドリーの手による二〇〇二年の映画「めぐりあう時間たち」は、二十世紀文学の深淵に触れたヴァージニア・ウルフの精神を、三つの時代の重層構造へと転生させた野心的な文芸映画である。本作は、映画という媒体が持ち得る洗練された工芸品としての性格を極限まで突き詰めており、十九世紀的演劇性と現代的編集技術が高度な次元で融合した稀有な一作である。
作品の完成度を考察する。本作の白眉は、ピーター・ボイルの編集が「日常の反復」という視覚的リズムによって、異なる時間をひとつの意識体へと昇華させた点にある。洗面、卵を割る音、花を飾る動作といったモチーフが、時代を超えて共鳴するシームレスな転換は、時間芸術としての映画の優位性を存分に発揮している。しかし、この洗練は同時に、映画が本来持ち得る「生の無秩序さ」を去勢し、すべてが運命論的に収束していく箱庭的な調和をもたらした。構成は完璧であり、観客の情動を一定の方向に導く設計図は極めて精緻だが、その整合性の高さゆえに、既存の映画技法の集大成という枠組みを脱するまでには至っていない。脚本のデヴィッド・ヘアは、ウルフの思想を普遍的な「生の問い」へと整理したが、文学的な台詞回しが俳優の身体性を規定し、映像言語が語るべき沈黙を言葉で埋めてしまった点は、文芸映画の宿命的な限界を露呈している。
役者の演技において、本作は三人の主演女優による競演が核心を成す。
ヴァージニア・ウルフを演じたニコール・キッドマンは、特殊メイクによる外見的変化以上に、精神の均衡を欠いた人間の「焦点の合わない視線」を克明に演じ、アカデミー主演女優賞を獲得した。彼女の演技は、常に死の磁界に引き寄せられる作家の孤独を、冷徹なまでの様式美で表現している。その表現は高度に計算されたテクニックの産物であり、理知的なアプローチによって、神経症的な作家像に圧倒的な説得力を与えた。
ローラ・ブラウン役のジュリアン・ムーアは、戦後アメリカの幸福という神話の中で窒息していく主婦の絶望を、抑制された静止の演技で描き出した。彼女の瞳に宿る空虚は、言葉による説明を排してなお、観客にその深淵を見せつける。本作において最も純粋な映画的表現を担っているのは彼女であり、静かなる崩壊を体現したその手腕は、見る者の肺腑を突く。
クラリッサ・ヴォーン役のメリル・ストリープは、現代のニューヨークを舞台に、過去の亡霊と闘う女性の焦燥を多層的に演じた。彼女の演技は、日常的な動作の中に深い愛情と諦念を滲ませる卓越したものであるが、その老練さは時としてキャラクターの切実さを上回り、技巧の高さが際立つ結果となっている。
リチャード・ブラウン役のエド・ハリスは、病に蝕まれた肉体と、崩壊していく精神の極致を見せた。彼の窓際での最期は、本作における悲劇の絶頂であり、その凄絶なリアリティは助演の枠を超え、作品の倫理的支柱として機能している。
晩年のローラを演じたトニ・コレットは、クレジットの最後を締め括るに相応しい重厚な存在感を放つ。過去に下した非情な決断と、その結果としての「生き延びた者」の矜持を、彼女はわずかな出演時間で完璧に定着させた。
映像と美術に関しても、一九二三年の沈鬱な褐色、一九五一年の偽飾的なパステル、二〇〇一年の冷涼なブルーという色彩設計は、それぞれの時代の閉塞感を補完し、物語を美学的に統一している。フィリップ・グラスによるミニマル・ミュージックは、反復する日常の虚無と、逃れられない運命の足音を旋律化した。特定の主題歌を持たず、通奏低音のように流れ続けるこの音楽は、映画全体をひとつの巨大な意識体へと昇華させている。
総じて「めぐりあう時間たち」は、二十一世紀初頭のハリウッドが、文学という高尚な素材を、最高の技術と人材で料理した至高の成果物である。その美しさは、完成された墓標のような静謐さを伴っている。良質な文芸映画というジャンルの完成型として記憶されるべきだが、その足取りはあまりに典雅であり、既存の美意識に忠実な、極めて保守的な傑作である。
作品[The Hours]
主演
評価対象: ニコール・キッドマン、ジュリアン・ムーア、メリル・ストリープ
適用評価点: A9
助演
評価対象: エド・ハリス、トニ・コレット
適用評価点: B8
脚本・ストーリー
評価対象: デヴィッド・ヘア
適用評価点: B+7.5
撮影・映像
評価対象: セイマス・マクガーヴェイ
適用評価点: B8
美術・衣装
評価対象: マリア・ジャーコヴィク、アン・ロス
適用評価点: A9
音楽
評価対象: フィリップ・グラス
適用評価点: A9
編集(加点減点)
評価対象: ピーター・ボイル
適用評価点: +2
監督(最終評価)
評価対象: スティーヴン・ダルドリー
総合スコア:[82.2]
凄い映画
語彙がなくて凄いしか言えないのがもどかしい。
メリル・ストリープも、ニコール・キッドマンも、ジュリアン・ムーアも、みんな凄かった。
病気の妻のために生活と人生を捨ててまで田舎に移り住んだのに、あんなに大声で自己主張したあと、間髪入れずに「じゃあロンドンに帰ろう」と言ってくれた夫がいて、ヴァージニア・ウルフがうらやましい。
病気のせいなのか?あんなに偏屈であんな面倒くさそうな女を愛し、そばに居続けてくれる夫がいるなんて、どんな僥倖…
愛してくれる夫と子がいて、世間的に満たされてると思われるのに、辛くて逃げたいローラ・ブラウン
あんなに幼くても母の言動に敏感で、自殺をやめて戻った母に「I love you 」と言える子に育ったリチャードが、
若くして出会えた、共に人生最良のときを過ごせた愛する女を「ダロウェイ夫人」と呼んで閉じ込め、彼女の人生を圧迫し続けることになる皮肉というか…
そんなクラリッサは、苦しみながらもリチャードに寄り添い続け、彼の作品を肯定して、生活も支えている。
傷付けても愛される人たち、ヴァージニアウルフ、リチャード
苦しんでもがいても生きる人たち、ヴァージニアの夫、クラリッサ
己の業に正直に生き、報いを受けたまま生きるローラブラウン
リチャードは、両親が不仲だったわけでもなく、おそらく虐待なども受けていないだろうが、幼いころ彼の存在を丸ごと受けとめ愛してくれる人に恵まれなかったと思う。父は母に盲目で、母は自分で精一杯で。
リチャード自身に何も落ち度はないのに、愛されなかった弊害は、リチャードに降りかかる。
毒親を持った子が背負わされる理不尽。
でも彼はクラリッサに大切にされた。
人工受精で授かったクラリッサの娘は、聡明で優しい。彼女が愛する人と幸せに生きられますように。
色々考えさせられて、まとまらない。
とても深くて、凄い物語。
2002年公開らしいが、そのとき母と観に行った記憶がある。母のチョイスだろう。
そのときはむずかしい映画だなと思った(それ以外に感じ取ることができなかった)記憶がある。
母は何を思ってこの映画を観たいと思ったのだろう。
それしかなかった
あらすじは読まずに鑑賞。ポスターだけみると、違う時代の女性たちが強く逞しく生きていく話なのかと思いきや…
女性=強いというイメージがあるけれどここに出てくる女性たちは何かに対して苦しんでおり、自分の人生を歩めていない人たちである。観終わった今は、死に方の話なのかなと思った。
特に印象に残ったのはジュリアンムーア演じるローラ。かわいい子ども、妻思いの優しい夫、立派なお家…なにもかも手に入れている現代女子の憧れともいえる存在やと思うけど、心の奥底に秘めた思いがふとした瞬間溢れ出し自殺を決意する。結局、自殺はしなかったがローラは「家族」からにげなければ近い将来自ら命を絶っていただろう。結果的に子どもや夫を不幸にしたが、ローラが生きていくためにはあの選択肢しかなかったんやと思う。裏切った人たちの十字架を背負うことを覚悟しながら自由を選んだローズは果たしてどちらがよかったのか…
ニコールキッドマン演じたウルフも苦しみを抱えた女性。最初、ニコールキッドマンだと分からず…メイクすごいな。この人は最初から理想の死に方を探しているのだと思った。この時代では生きていけないと悟ってたんやろうなあ。メリル・ストリープ演じるクラリッサにしても、リチャードが心の支えであり、人生のストッパーにもなっていたのかもしれない。あんな形で最期を迎えるとは想像していなかっただろう。
心から大切に思ってくれている人がいるにも関わらず死を選ぶ者たち。その選択がどれだけ残された人の心に傷を残すのか。残されたものの気持ちを思うと…なんともやりきれない。
すっかり魅了されました 【バラの映画】
1923年、小説『ダロウェイ夫人』を書く女バージニア、1951年『ダロウェイ夫人』を読む女ローラ、2001年『ダロウェイ夫人』と呼ばれる女クラリッサ。
それぞれの場所でパーティーを開く女達の「その日」が、絡み合うように描かれます。
死の気配がまとわり付く女達の苛立ちや悲しみ、決断の行方を、大女優達のしっかりした演技で観せてくれました。
良い妻・母を演じ続けるローラが特に痛々しく、心に残りました。
それなりに歳を重ねた今、出会えたことを感謝したい作品です。
とっつき難そうで、長年ちょっと忘れた振りしてました。
そういう訳で、観終わってから激しくも美しいバージニア・ウルフを誰が演じているのか知って、もうね、ビックリ。
凄いものです。アカデミー賞でしたね、忘れすぎ、失礼しました。
❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿
〜バラポイント(加筆)〜
死の気配の傍らには、これでもかとバラの花が。
香りにむせ返るようです。
【バラの映画】
2015年、広島県福山市の市政100年の際、映画館を中心に集まった有志で、市花に因み小冊子〚バラの映画100選〛を編みました。
皆でバラに注目して観まくり、探しました。楽しい時間でした。
若い方から「ゴジラ対ビオランテ」が紹介され大拍手!
2025年、世界バラ会議に因んで、私選のバラ映画10を紹介します(一部レビュー加筆)。
アフリカの女王/アンタッチャブル/エド・ウッド/ゴーン・ガール/素晴らしき哉、人生!/ダ・ヴィンチ・コード/Dolls/プリティ・ウーマン/めぐりあう時間たち/めまい
時間軸が何十年も前後する巧みな構成。交差しない一日。3人の女性の生きざま。
原題は、「THE HOUSRS 」
“複数の時間たち“か、めぐり会わない物語。
(邦題はなかなか考えた技アリの題名)
3人の女性たちは、繋がりはあるけれど、一度の会わない。
3人を繋ぐのが、ヴァージニア・ウルフ作の小説、
「ダロウェイ夫人」という手法です。
原作は、マイケル・カニンガムのピュリッツァー賞を受賞した
1999年に発表された同名小説で、カニンガム氏は、ゲイとの事です。
映画は、イギリスを代表する女性作家のヴァージニア・ウルフの
「ダロウェイ夫人」を中心に置き、ヴァージニア・ウルフの
実生活とともに描く・・・といったいった手の込んだ作品です。
(非常に知的でスリリング、ミステリー的です)
2001年のニューヨーク、
ダロウェイ夫人(クラリッサ)の、
メリル・ストリープのPart。
1951年のロサンゼルス。
詩人の母親であるローラ(ジュリアン・ムーア)のPart。
そして冒頭の、
1941年のイギリスのサセックス。
病気療養していたヴァージニア・ウルフは、
遂に59歳で、力尽きて入水自殺をします。
演技力に定評のある3女優の競演で見応えあるのですが、
クラリッサにダロウェイ夫人とあだ名を付けた、
エイズに侵された初恋の男性・リチャード(エド・ハリス)が、
栄えある文学賞の受賞をお祝いするクラリッサの目の前で、
窓枠から飛び降り自殺してしまうのです。
そしてその夜、お通夜のようなクラリッサの家を訪れたのは、
リチャードが「母親は自分が幼い日に自殺した・・・」
そう言っていた母親でした。
小説でも殺していた母親のローラが姿を現すのです。
彼女は幼いリチャードと、その妹を置き去りして出奔していたのです。
それで息子はその存在を抹殺してしまったのですが、
心の傷と欠落は、言いようもない寂しさだったのでしょう。
原作が素晴らしく、映画も多くの賞に輝いたのも頷ける
知的なアンサンブル映画の傑作でした。
ヴァージニア・ウルフを演じたニコール・キッドマンがつけ鼻を付けた
特殊メイクで終始しかめっ面。
本人の面影が全くなくて驚きでした。
良き母、良き妻では、女は幸せになれない、
そんなメッセージを感じましたが、
そこはちょっと疑問でした。
良いご主人でしたのにね。
ゲイやレズビアンといった価値観が色濃く滲んでいます。
【3人の世代を超えた『ダロウェイ婦人』の生と死の香り漂う一日を描いた作品。名匠スティーブン・ダルドリーによる見事な作品構成、且つ脚本が絶妙に上手い、格調高き哀しき作品でもある。】
ー ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ婦人』を書架の奥から引っ張り出して来て、色々と確認しながら、観賞。-
■1941年、英国サセックス。作家のヴァージニア・ウルフ(特殊メイクをしたニコール・キッドマン)は、夫に感謝の言葉を綴った遺書を残しポケットに石を入れ、川に入って行く。
■1923年、英国リッチモンド。ヴァージニア・ウルフは浮かない顔で、『ダロウェイ婦人』の粗筋を考えている。精神を且つて病んでいた彼女は、少しその症状が出つつあるのか、憂鬱そうな顔をしているが、姉のヴァネッサ・ベル(ミランダ・リチャードソン)には秘めたる想いを持っていて、彼女がロンドンへ帰る際にキスをする。
■1951年、米国ロサンゼルス。ローラ・ブラウン(ジュリアン・ムーア)は、何処か満たされない思いを抱きながら、夫ダン・ブラウン(ジョン・C・ライリー)の誕生日ケーキを息子リチャードの手伝って貰いながら作るが、上手く行かずにそのケーキを捨ててしまう。
友人のキティ(トニ・コレット)が訪れるが、彼女は子宮筋腫である事を告げ、ローラは彼女に涙を流しながらキスをする。
そして、彼女はリチャードが”お母さん、行かないで‼”と叫ぶ中、車をあるホテルに向けて飛ばす。部屋に入ると彼女は愛読書『ダロウェイ婦人』をベッドの上に置き、更に数種類の薬の入った瓶を置き、横になるが水に呑み込まれる夢を見て我に返り、家に戻る。だが、この出来事はリチャードの心に傷を残してしまう。
■2001年、米国ニューヨーク。クラリッサ(メリル・ストリープ)は、HIVに犯された友人リチャード(エド・ハリス)の受賞パーティーの準備をしているが、リチャードは若き時にクラリッサと若き時に暮らした想い出に浸って、厭世観漂う表情をしている。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・今作は、ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ婦人』の内容と、ヴァージニア・ウルフが終生苦しんだ精神病及びレズビアンの性癖を、1951年のローラ・ブラウン、2001年のクラリッサの一日と連関させて描いている。
・クラリッサと言う名は、『ダロウェイ婦人』の名前であり、ローラ・ブラウンの息子リチャードは2001年のクラリッサの若き時の恋人である。
又、リチャードと言う名は、ダロウェイ婦人の夫の名でもある。
そして、リチャードは母の行為から受けた心の傷などもあり、クラリッサに”感謝の言葉を述べて”窓から身を投げるのである。
そこに駆け付けた、老いたローラ・ブラウンは”誰も私を許さないでしょうが、私は死よりも生きる事を選んだの。”とクラリッサに告げるのである。
<今作は、3人の世代を超えたヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ婦人』の、生と死の香り漂う一日を描いた作品なのである。
名匠スティーブン・ダルドリーによる見事な作品構成、且つ脚本が絶妙に上手い、格調高き、哀しき作品でもある。>
タイトルなし(ネタバレ)
劇場で観て以来15年ぶり?2度目。
一度目はどっぷり感情に浸ってしまってわからなかったところが2度目だといろいろ見えた気がする。
と言うか勝手に解釈した。
ローラ・ブラウンとクラリッサ・ヴォーンの一日はヴァージニア・ウルフの小説なのではないか。
実際ヴァージニア・ウルフの小説にそんな内容のものはないのだけれど、初めて観た時ヴァージニア・ウルフだけ時間軸が絡まないことが妙に気になっていた。
そう考えると私の中ですっきり通る。
そんな解釈をしているレビューは見たことがないのだけれど。
また観てみよう。
新たな発見があるかもしれない。
ダロウェイ夫人とは?
文学的なかほりがする。「オーランドー」だけは読んだことがあるのだが、ヴァージニア・ウルフのことは、あまり知らない。wikiってみたら、実際に入水自殺していたらしい。姉のヴァネッサとは仲が良かったようで、今作でも引用されている「ダロウェイ夫人」の次作「灯台へ」を出版する際は、姉が装幀を手掛けたそうだ。ちなみに、ヴァネッサの生き様もなかなか激しい。この映画では良妻賢母のような雰囲気だったが。
ヴァージニア・ウルフから、ローラ、クラリッサへ、時を越えて受け継がれる「ダロウェイ夫人」とは、どのような女なのだろう。すごく知りたくなってきた。どうも観念的で読みにくそうな気がするが、チャレンジしてみるかな。
オープニングでキャストの名前を見ていたはずなのに、ヴァージニア・ウルフがニコール・キッドマンだと、最後まで気づかなかった。ジュリアン・ムーアも老けメイクで、二人には女優魂を見た。
いくら心を病んでるとはいえ、長年親しくしていて、自分の面倒までみてくれている人の前で、飛び降り自殺するのはひどい。その人がどれだけ傷つくか、思いやれないものかな。そんなことを考えられないくらい、追い詰められていたのだろうか。負の遺産が続くようで、やり切れない気持ちになった。あと、真っ青なケーキは怖いわー。
BS松竹東急の放送を録画で鑑賞。
ヴァージニア・ウルフや原作へのリスペクトに溢れる死と生を対置したドラマ
1 ヴァージニア・ウルフとは何者か
1882年生まれ1941年没の英国の女性文学者。ジェイムズ・ジョイスらとともに、「意識の流れ」のモダニズム手法により小説の在り方に変革をもたらした。
ロンドン・ブルームズベリーの自宅に、姉や兄とともに文化人社交サークル、ブルームズベリー・グループを形成し、新しい文化・思想の発信地の役割を担う。
グループの中心は兄であるケンブリッジ学生トービーや、画家の姉ヴァネッサとヴァージニアで、メンバーには「4月は最も残酷な月」で知られる詩人T.S.エリオットや、有効需要の原理で経済学に革命を起こしたジョン・メイナード・ケインズがいた。
私生活ではレナードと結婚したが、男性との性生活が営めず、ヴィタ・ウエストら複数の女性と恋愛関係を結び、晩年には「戦争は男性が引き起こすもので、女性が国家に影響力を持っていれば戦争はなくなる」というバカげた戦争論『3ギニー』を発表。
また、父母の死後、精神病に悩まされ、22歳、32歳の時に自殺未遂事件を起こし、最後には1941年に59歳で入水自殺する。
以上の履歴から彼女は今、「前衛芸術家、フェミニスト、レズビアン、リベラル知識人の文化的アイコン」となっている。
2 『ダロウェイ夫人』の内容
1925年に発表されたウルフの代表作である。ジョイス『ユリシーズ』と同じく、意識の流れを人間の現実と捉えて、英国上流階級の女性がパーティを開く一日の感覚、感情、記憶等を辿るとともに、これと第一次大戦で心に傷を負った男の狂気と死を対置させることにより、生への肯定的な志向と否定的志向という人間存在の振幅の大きさを描く。
当初、表題は「時間」と予定され、ウルフは「この本で私は生と死、正気と狂気を描きたい」と日記に記している。
狂気を代表するのは当初、ダロウェイ夫人本人と構想されていたが、やがて第一次大戦でシェルショック、今でいうPTSDにより精神を病んだセプティマス・ウォレン・スミスとされた。
セプティマスは「雀たちがギリシャ語でさえずっている」と妄想し、死に追い詰められていくのに対し、ダロウェイ夫人は俗物だが、「もう恐れるな、灼熱の太陽を、激しい冬の嵐を」と念じつつ、「パーティとは人生への捧げものだ」と人生を肯定する。
ウルフの狙いは両者を対置させて描くことであり、いずれかを勝たせいずれかを退けるものではなかった。
3 小説『めぐりあう時間たち』について
米国の作家マイケル・カニンガムが1998年に発表。原題が「時間」というのを見てもわかるが、『ダロウェイ夫人』の「本歌取り」的作品である。つまり、ウルフの小説を換骨奪胎して、類似の設定で類似のキャラクターを登場させ、別の内容を語ろうとしている。
本作の訳者高橋和久は「1980、1990年代の小説には、文学史上の『古典』に『寄生』し、その続編もしくは前史という体裁をとった作品がずいぶんと発表され、それがポストモダン小説のひとつの潮流となっていた」といい、本作もウルフの設定、人物ばかりでなく、文体まで模倣するなどしており、その一つであると指摘する。
確かに、ダロウェイ夫人がロンドンのバッキンガム宮殿周辺を歩き回れば、本作では「ダロウェイ夫人」というニックネームの女性がニューヨークの中心街ソーホーやグリニッチ・ヴィレッジを歩き、花を買い求めると、二人ともその途中でバカのような知人(ヒュー・ウィットブレッドとウォルター・ハーディ)に出会う。以後、ウルフ作品と類似の出来事が頻出するのである。
小説はこの「ミセス・ダロウェイ」のほか、「ミセス・ウルフ」「ミセス・ブラウン」を登場させる。
ミセス・ダロウェイはエイズと精神を病むかつての恋人、詩人リチャードの面倒をみるほか、何年も会っていなかった昔の友人ルイスに会う。彼らはウルフの小説のセプティマスとピーターに相当する。
ミセス・ウルフはヴァージニア・ウルフ本人で、狂気に陥るのを恐れるとともに、使用人に威圧されながら小説『ダロウェイ夫人』を執筆する。
ただ一人、1950年前後の米国の理想的家庭の主婦ミセス・ブラウンは、小説『ダロウェイ夫人』を読んでいる心を病んだ女性だが、彼女を登場させる必然性がよくわからない。子供リッチーの意味もまたしかり。
ところが詩人リチャードが自殺した後、本作はそのフルネームが「リチャード・ワージントン・ブラウン」であることをさりげなく示す。この瞬間に影の薄かったブラウン夫人とその子リッチーがいっきょに主役に浮上し、本作の独創性が際立ってくるのである。
「失われた母親であり、挫折した自殺願望者であり、一切を置き去りにして立ち去った女」ミセス・ブラウンの息子リッチー=リチャードは、心を病んだ挙句、ミセス・ダロウェイに向かって「でもやっぱり時間はやってくるだろう。一時間、また一時間と。それを何とかやり過ごす。するとなんてことだ、次の時間がやってくるじゃないか。吐き気がしそうだよ」と言い残して、ビルの5階から飛び降りていく。ああ、あの子が数十年後にこうなったのかと読者は驚愕し、沈黙せざるを得ないのである。
彼の通夜に訪れたミセス・ブラウンを迎えたミセス・ダロウェイがどうしたか。
「怒りと悲しみに満ちた女性。悲哀に満ちた、目眩めく魅力に満ちた女性。死に恋した女性」を前に、彼女は夜食を用意して、「こちらへどうぞ。準備万端整いました」ともてなし、小説は終わる。ウルフ作品とは異なる「パーティ」の主催者として、人生への捧げものを提供するのだ。見事だと思う。
4 映画作品について
ヴァージニア・ウルフという作家とその代表作の本歌取りをして、素晴らしいドラマを構築した原作は、いかんせん複雑すぎる。ましてやその映画化である本作にいたっては、ヴァージニア・ウルフの伝記や『ダロウェイ夫人』、さらにカニンガムの原作を読んでいなければ、そのあらすじさえ理解できないに違いない。
映画を見ているだけでは理解できないのでは、作品として評価しようがない。普通ならそうだろう。
ただ、本作にはウルフやその作品に対するリスペクトがあり、死と生を対置したドラマがある。その志をよしとしたい。
難し過ぎ
................................................................................................
女性小説家がうつ病で病んで自殺未遂、夫と共に田舎へ。
そこで紆余曲折あって、結局自殺。
................................................................................................
心の世界、おれの割と好きなテーマなのに、難しくて分からんかった。
現実世界と、小説の中の世界(ニコール領域、メリル領域)が並行して進み、
どれが何で何がどれなんかさっぱり分からんかったわ。
その主な理由がオバちゃん達が多数出過ぎなこと。しかもみんなそっくり。
だから誰が誰なんかもよう分からんままについてけんくなった。
また見る機会があれば高得点つけれるかも知れんが、今は☆2つで。
時間の不思議
「長い一日」ってあるものだ。何気なくすごした一日はあっさり過ぎてしまうんだけど、自分にとってとても意味のあった日、大事なことがあった日っていうのは、とても長かったって、感じる。
この映画の中にでてくる時間は、3人それぞれの「長い1日」だ。
「運命のいたずら」という言葉がある。この作品では、ウルフに「あの人を殺さなかったから代わりにあの人に死んでもらう」といわせていたが、何かがこうでなければ・・・という可能性はいくらでもある。誰かの気がちょっと変わっただけで、他の誰かの運命が大きく変わることもある。信じられない奇跡的な時のめぐりあいを経て、私たちは今自分の周りにいる人たちと一緒にいるといえるかも。
それにしても~今回は3人の女優、配置が絶妙!
ニコールは’20年代の英国、J・ムーア、フィフティーズのLA、そして現代のNYはやはりM・ストリープ。ぴったりでしたね~
時間と記憶を巡る複雑にして稀有な作品
とても複雑な構成。冒頭で描かれるのはダロウェイ夫人を書いた作家のヴァージニア・ウルフが死を選ぶシーン、そして彼女の遺書。そして詩人のリチャードが父母と過ごす場面、母のローラはダロウェイ夫人を読んでいる。そしてリチャードと以前つきあっていたクラリッサは、その名からダロウェイ夫人とからかわれ、彼女は編集者としてリチャードとつながりを持っている。リチャードは病み、希死念慮を抱きつつ生きている状態…。時間も場所もさまざまな彼らは、希死念慮という共通点をもつといってもいいだろう、クラリッサはそれを抱くリチャードと向き合いつつ、その状況にもう耐えられないと感じている。
ローラは、夫にこの暮らしが幸せの理想形だと強調されますます苦しみに囚われる。違う、これじゃないと感じつつそこに居続けるもどかしさ、自由がないと感じる息苦しさ、そして本当に欲しい愛はこれじゃないという疑念、そこから彼女が何を選択するか。詩人リチャードは母やクラリッサを自分の本にどう描いたか、また彼には何が見えていたのか、何が彼を苦しめ、そして支え、どの瞬間が彼にとっての最愛の貴重な時間だったのか。現代を生きるクラリッサにとっても同様に。時間と記憶を巡るストーリーはかなりぶっ刺さるので、思い入れが強くなる。
現代を生きるメリル・ストリープが演じるクラリッサの周囲の人物は、恋人のサリーに元恋人のリチャードと、ダロウェイ夫人をなぞらえているかのよう。でもリチャードというよりピーターでは?と思うので、あえてなのかな、なぞらえすぎないように。彼はピーターでもありセプティマスでもあるわけだし。
ヴァージニア・ウルフの遺書は世界一美しい遺書と言われているけど、彼女の遺書には愛の言葉はない。幸せだったことと優しさへの感謝とはあるけれど。クラリッサはサリーと暮らすがそこに愛はあるのだろうか、傷を舐め合い時間を共有しても、愛は過去にしかないのかもしれない。そこを突き詰めナーバスに捉えることには苦しみもあるけれど、鈍感が正しいとも思わない。
観客を選ぶ映画だ。好きな人にはたまらないだろう。
METで上演された同名オペラの口(目?)直しに、DVDを借りてきて鑑賞した。やはり、名作だ。
作家ヴァージニア・ウルフやその代表作「ダロウェイ夫人」が好きな方にとってはたまらない作品だろう。また、予備知識なしにこの映画を鑑賞しても何を言おうとしているか分からないと思う。私も元ネタの「ダロウェイ夫人」を読んでいるとき、よくわからなかった。人間の心の動き(メンタル疾患を含む)を味わう映画で、根底には死への誘惑と生の渇望がある。おまけにバイセクシュアルも絡んでくるからややこしい。改めてみて、挿入される音楽が素晴らしい。現代音楽作曲家のフィリップ・グラスが担当している。R・シュトラウス辞世の歌が使われ効果的だった。やはり、原作者の原作本「めぐり合う時間たち」を読んでみなければと感じた。
ダロウェイ夫人〜心の渇き
ニコール・キッドマン演じる女流作家ヴァージニア・ウルフの心が、不安定に揺れ苦悩し続ける姿から目が離せなかった。その美しい瞳とスレンダーな肢体のみニコール・キッドマンでした。
精神が不安定な母( ジュリアン・ムーア )の顔色ばかり伺う幼い少年リチャード( ジャック・ロヴェロ )。大好きな美しい母を見つめるその瞳が切ない。
ジュリアン・ムーア、メリル・ストリープ、エド・ハリスの競演の見応えある作品。
ー凍てつくような疎外感
ー後悔すら出来ないものよ…他に道がないと
ー選んだの…生きることを
BS松竹東急を録画にて鑑賞 (吹替版)
自分で解釈したい人向き
大正のLON、終戦後のLA、現代のNY、三つの時代の無関係な三人の女性の生活が同時進行で進みます。
三人にどういうつながりがあるのか、関係がありそうにもなさそうにも思えますし、様々な設定が何故必要なのか?どこにどう話としてつながるのか?知恵袋に質問多く、回答も様々です。
つまり、それぞれ独立した三つの話の関係性や、何のためかよくわからない設定なんかに、理屈つければ説明できるかも?というタイプの作品なので、「自分で想像するのが好き派」の人は自分なりに解釈して面白いと感じるんでしょう。一方、「はっきりしてくれよ派」の人は、「その解釈こじつけじゃねえ?」ってなります。
換言すれば、よくも悪くも普通の人には「何いいたいのかよくわからないの」作品なので、好き嫌いがハッキリ別れます。評論家なんかにはウケるんでしょうが、一般受けはしません。
話の展開が早いのでそこそこ面白いですけどね。
全49件中、1~20件目を表示