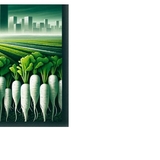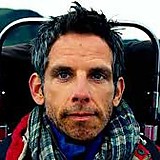ペイ・フォワード 可能の王国のレビュー・感想・評価
全33件中、1~20件目を表示
自分には刺さらなかった
自分が受けた親切を他の3人にするペイ・フォワードの運動から、どうストーリーを展開していくのかを特に気にしながら観てみた。ストーリーの主軸は恋愛で、恋愛要素とペイ・フォワードの運動を上手くリンクさせているところはよくできていると感じた。
感動的な内容だが、自分には刺さらなかった。一番引っかかるのが、ペイ・フォワードの運動がどのようにして全米に広がっていったのか、その過程がいまいち分からないこと。テーマがテーマだから難しいとは思うけど、いつの間にか上手いこと広まっていて、皆がトレヴァーを持ち上げて、都合が良すぎるように思えてならなかった。
悲劇的な結末なのも、ペイ・フォワードの運動を印象付けるために入れた要素にしか思えない。あからさまに感動的な展開を狙う感じも、あまり好きではなかった。
見たい物語を見ることが出来た満足感
受けた好意を他人に贈る“ペイ・フォワード”というテーマから、予想どおりの展開と結論の物語でした。描いて欲しいように話しが進み、役者の演技には嫌味がありません。
これまで何となく気後れして鑑賞することを躊躇していましたが、NHKBSプレミアムシネマの放送を切っ掛けにして本作を鑑賞できて幸いでした。
顛末に不満を言うレビューもありますが、エンドタイトル前のシーンには静かな余韻を感じ、癒しになります。遠くに救援部隊や応援が近付く兆しを残してエンドタイトルが出る、ようなエンディングを、いつも求めて映画を鑑賞しています。
2001年公開の本作ですが、この映画が切っ掛けになって舞台であるカリフォルニア州などで安直な改革ムーブメントが強まったのではないことを本作のために祈ります。本作から、改革は文字どおり(肉体的にも精神的にも)生命を掛けた厳しいものと教えられました。
なお、ツイスター以来、ヘレン・ハントは好きな女優の一人です。顔立ちに惹かれています。
幸せのねずみ講
情けは人の為ならず。巡り巡って自分の元に…。
でも、それまで待てないヒトは言う。情けをかけると、かけられた人の為にならないから、情けは不要。自己責任で完結すべし。…本来の意味が失われて、久しいですね。
ヒトには、将来のことを考えて今を我慢しようと思う抑制サイクルと、今だけを考えて我慢しない刹那サイクルが、あるそうです。これを偽善と露悪のサイクルと云うらしいです。
偽善と露悪。天使と悪魔。悟りと煩悩。いずれもヒトを構成する要素ですし、ヒトは逆立ちしても、神様にはならないので、あって然るべきですけど、どこにウェイトを置くかで、ヒトの生き様は変えられるような…
露悪の巨塊が合衆国を牛耳るこのタイミングで、某国営局がこの映画を放送するのは、どんな意図があるのかしらと、勘繰りたくなる今日この頃です。そしてこの映画は、他ならぬ、その合衆国で、かつて創られたものです。
この映画のラストを、どう受け止めるかは、かなり割れるでしょう。昔、刹那さを殺せないって、唄ってた方もいましたけど、やらぬ善よりする偽善に、ヒトの可能性を見出だしたい私です。
最近、他人様にいいことしました?。
何もしてない私ですけど。
嗚呼、刹那さを殺せないなぁ。
皆様なら、何に先払いします?。
皆様の情けは、誰が為にあります?。
以上、四半世紀前に観た記憶で、レビューしてみました。地味な映画ですが、未だに印象が残っているのは、この映画に何かがあるからでしょう。その何かに、多くの方が触れることを願います。
人に与える大切さ。
『ペイ・フォワード 可能の王国』は、善意が人々の生活を変える力を持つというメッセージを描いた感動的な映画です。物語は、少年トレバーが「ペイ・フォワード(恩送り)」というアイデアを通して他者への善意を広げ、次々と人々の心を動かす様子を中心に展開されます。この映画は、一人の小さな行動がいかに多くの人々に影響を与え、社会を変える力を持つかを感動的に示しています。
1. 少年の純粋な視点がもたらす力
映画の主人公であるトレバーは、心の純粋さと行動力を持ち、善意の連鎖を生む「ペイ・フォワード」を自ら実践します。この発想は子供らしい素朴な思いやりに基づいているため、見ている側にとっても非常に強く響きます。大人たちが見過ごしてしまう善意の力を、トレバーは無垢な目で捉え、真剣に行動に移すのです。彼の無邪気さと純粋さが周りの人々の心を打ち、善意の輪が広がっていく様子は感動的で、「自分も何かできるのではないか」と考えさせられます。
2. 逆境の中で生まれる善意
この映画は、トレバー自身もまた困難な環境に生きていることを描いています。アルコール依存症の母親と暮らし、親子ともに苦しみながらも、その中で善意を実践し続ける姿が、物語に一層の深みを与えています。逆境にある彼が、自分だけでなく他者をも助けようと行動する姿には心を打たれると同時に、「本当に困難にあるときこそ、誰かを助ける意義がある」と教えてくれます。
また、トレバーの行動が、彼の周りの人々、特に母親や恩師にも影響を与え、彼らの心にも変化が起こる様子が描かれています。自分もまた逆境にあるにもかかわらず、周囲の人に手を差し伸べる姿に「真の強さ」を感じさせられます。
3. 善意の連鎖が人々の心を動かす
映画の中で描かれる「ペイ・フォワード」という善意の連鎖は、観客に強いメッセージを投げかけます。善意は、それを受け取った人の心を変えるだけでなく、その人が次に他の人へと善意を広げるという連鎖を生むのです。トレバーの小さな親切が、思いがけない形で多くの人々に波及していく様子は、映画のハイライトとも言えます。
この善意の連鎖の中で、観客は「善行には自分が思う以上の影響力がある」ことに気づかされます。人はつい「自分一人の行動で何かが変わるのか」と考えがちですが、この映画は、たった一つの行動が予想を超える結果をもたらす可能性を教えてくれます。この点が、『ペイ・フォワード』の持つ魅力と説得力の源泉であり、人々の行動を変える力となっています。
4. 親子や人間関係の成長
映画を通じて描かれるのは、単に善意の広がりだけではありません。トレバーと母親の関係や、トレバーを取り巻く大人たちの心の成長も、物語の重要なテーマです。特に、困難な状況にある母親が息子から刺激を受け、次第に自分を見つめ直す姿には共感が湧きます。
このように、家族や周囲の人間関係が善意によって成長し、深まっていく姿が丁寧に描かれており、家族や友人、同僚といった日常の関係を見直すきっかけにもなります。トレバーの善意が家族や友人にまで浸透し、彼らを変えていくプロセスに心を動かされ、温かい気持ちになれます。
5. 善意を行う難しさと真の勇気
映画では、トレバーの純粋な善意がいつも簡単に広がるわけではなく、その実行が困難であることもリアルに描かれています。特に、人間関係の中でのトラブルやトレバー自身が直面する困難が物語にリアリティを与えています。善意を行動に移すことは美しい理想ですが、それがいかに難しいかをこの映画は教えてくれます。
トレバーが行う「ペイ・フォワード」は勇気を必要とする行為であり、善意の実行に伴うリスクや代償も現実の一部として描かれています。しかし、この困難を乗り越えていく彼の姿には、真の勇気を感じさせられます。この映画は、善意を実行するための「勇気の価値」を観客に示し、逆境にあっても前向きに生きる力を感じさせます。
6. 映画がもたらす心の変化
『ペイ・フォワード』を見た後には、「自分も善意の連鎖に貢献したい」という気持ちが湧き上がります。トレバーが行動する姿を見ていると、自分もまた、他人を思いやる心や、困難に立ち向かう勇気を持ちたいと感じさせられるのです。この映画の本質は、観客の中に「行動を変える動機」を与える力にあります。物語を通じて、「他者に優しさを分け与える」ことが、どれほど大きな意味を持つかを感じることができるでしょう。
善意の連鎖が少しずつ広がり、他者の心を動かしながら、さらに次の人へと続いていく。映画を通じてこの善意の連鎖に触れることで、「自分も何かを変えたい」という意欲が沸き上がり、私たちの行動や考え方に小さな変化を促してくれます。
結論
『ペイ・フォワード 可能の王国』は、善意の力がいかに広がり、他者に影響を与えるかを感動的に描いた映画です。トレバーという少年の純粋な行動が大人たちの心を動かし、困難にある人々を救い、善意の連鎖を生んでいく姿に、観客もまた心を揺さぶられます。善意を行動に移す難しさと、それを乗り越える勇気の大切さを教えてくれるこの映画は、私たちの日常にも応用できるヒントを与えてくれる一作です。
善意の連鎖は、一つ一つが小さな行動であっても、それが集まることで大きな変化を生む可能性を持っています。この映画を通して感じたことを心に留め、私たちも日々の生活の中で他者に手を差し伸べる姿勢を持ち続けることで、世界が少しずつでも温かくなるかもしれません。『ペイ・フォワード』は、善意とその力を信じる気持ちを新たにさせてくれる感動作と言えるでしょう。
あのラストはショックすぎる
前情報全くなしで鑑賞
ケビン・スペイシーが出てきたから、また胡散臭い嫌なやつと思っていたら、クセはあるけどとっても良い人で、ケビン・スペイシーの良い人って初めてかもです
子役の子が素晴らしい演技、ジム・カヴィーゼル、デヴィッド・ラムゼイと嬉しい出演でした
トレバーのインタビューに感動の涙、なのにそこからまた違う涙を流させられる事になるとは
感動の涙のままだったら☆5だったのに
☆4にしましたが、あのラストだったので☆1にしようかと思ったくらいです
でもラストまでは本当に良かったんですよねー
親切の連鎖が本当にステキで心が暖かくなりまくりでした
日本では「恩返し」だけど、今作では「恩を渡す」、そういう表現の仕方ってとっても良いなぁと思いました
明日から私も毎日「恩を渡す」をしようと思ったし、この作品を観て同じように思った人も多いように思います
世界中で「pay it forward」が広がってほしいです
恩を返すのではなく次の3人へ渡す
諦めたらそこで試合終了だよ。
コロナ禍で再び話題になった作品!
流行病によって会社や学校に行けない人が増え、飲食店やイベントなどの自粛が起こりました。
そして、社会的資本が失われていく中で、助け合いを望む声が溢れたそうです。
先生は「もし世界を変えたいと思ったら何をするか」という課題を生徒たちに与え、
子供らしいアイディアが飛び交う中でトレバーは、自分が受けた善意や思いやりをその相手ではなく、別の3人に返すという「ペイ・フォワード」を提案しました。
それを実践しますがなかなか結果にならず、失敗だったのではないかとトレバーは思い始めます。
しかし、トレバーの知らない所で「ペイ・フォワード」は続いていました。
というあらすじとなっています!
私は今までキャリアを上げていく中でいろな人と出会い、その出会いを大切にしてきました!
トレバー達が努力し続ければ結果になることを伝えてくれたように、私自身も努力を惜しまず、これからも人とのご縁を大事にしていこうと思いました!
世界が変わるのを見たい
物語の本質は人として大切な事
ネバダ州の荒野!
人の感情や思想はその風土を抜きにしては語れない、とこの映画を観てつくづく思う。ラスベガスの町はあまりに人工的で嘘臭く、その周りに広がるのは果てしない荒野。映画のストーリー自体よりもその風景にばかり心が捕らわれていた。このような場所でまともに生活していくのは、想像する以上に難しい気がする。明日への不安を酒で紛らわすか、自分の立てた予定通りにきっちりと一日を過ごすか、人を虐めて自分を慰めるか…(異常な宗教に没入して現実を忘れるという方法もあるかもしれない)。
生活の参照とすべき伝統もなければ助け合う共同体もない世の中で、それでも正常を保とうとするならば、自分が変わり周りを変えるしか方法がないと考えるのは当然といえる。ゲンコツを与えるか慰撫を与えるか。その実践の困難さを描くのがこの映画。フォレスト・ガンプのように無心の行為が世界を変えるのとは違い、実践は誠に難しい。世界はクソだから。そんなクソの世の中でも、続ければ一輪くらいの花は咲くんじゃないかというのが主題。みんなクソまみれになりますけど。
カタルシスはない。大成功、万々歳な終わりかたではない。しかし、主役の男の子がメディアの注目を浴びた後クズ人間になる可能性もないので、そこは安心できたかなと思う。
気になっていた映画なので、消化できてよかったというのが正直な感想。可もなく不可もない。
人はまっすぐな良心に共感し、集う
NetFlixのおすすめに出てきて、引き込まれるように観た。
先生の板書からストーリーは始まる。「幸せを連鎖せよ」と。
少年は真正直な心でそれに答えようとする。
そしてその感動の波が広がって、お母さんとおばあさん、そして先生とお母さんが結ばれた直後。。悲劇が訪れる。
しかし皮肉にも「Pay Forward」のストーリーは感動の波を呼び、その悲劇を弔う人でラスベガスの片田舎の家の前は一杯になる。
正直言って感動のストーリー展開から、「あのラストは無いだろう」と私も思った。脚本家や監督に直接聞いてみたいと思ったぐらいだ。
でも最後のシーンで、まるで「フィールドオブドリームズ」のように「良心」というハートランドに集まる人々の姿を見て、「人は自分の捨ててでも人の役に立ちたい人に心を寄せる」ということが素直に心に入ってきて、「なぜだ」と思いながら、何とか受け入れることができた。
「パラサイト 半地下の家族」を観た後のような、複雑な感情が入り混じった気持ちだ。しかし。。理解したい、きっと意味があると。
あのラストは必要だったか?
3人に良い行いをし、連鎖させることがテーマ。
期待しすぎた。
思ったよりもストーリーの起伏がなく、
中盤で繋がりがわかっても大きな感動もなかった。
・読める大筋
・惹かれ合う描写のない急な恋愛
・不自然なほどに大人びて、大人の仲を取り持つ子ども
・不要なラスト展開
始まりは主題の規模の大きさを感じさせる展開だったので
わらしべ長者的に小さなことが大きくなっていく、
広がっていくことを期待していたが
終始主人公の周りの小さなことがメイン。
離れた場所での広がりは本当に前段に過ぎず
ガッカリ。
そしてラストは急に起伏を持たせたかったのか?
ああである必要は全くなかった。
なんと悲劇的な…と思わせたかったのだろうが、
全く感情は動かなかった。
途中から早送りで観るくらいだったので
2度は観ないな。
現実に起きて欲しい
自力作善は当然破綻する
例えば「歎異抄」の親鸞の言葉にはこうある。
「慈悲に聖道浄土のかわりめあり。聖道の慈悲というはものをあわれみかなしみはぐくむなり。しかれども思うがごとく助けとぐること極めてありがたし」
人間が、自分の力で何かを助けようとしてもそれが理想的な形でかなうことはまずないし、ましてや助け続けることなどほとんど不可能だ、という意味である。
現代のアメリカ人の知恵は、800年前の日本人の智慧に遠く及ばない。
伝統を知り、ある程度の教養がある真っ当な日本人がこれを観れば、この映画は「世に無数にある、幼稚な自己中の偽善が、単に失敗しただけのさま」以上の評価はできないのではないか。
終幕もお粗末。
死をもって美化するのがアメリカ映画の王道とはいえ、あんなので感動するとか…ないな。
時間の無駄でした。
Pay it Forward
全33件中、1~20件目を表示