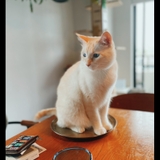星と月は天の穴のレビュー・感想・評価
全88件中、1~20件目を表示
衰えゆく文芸映画の残り火
原作は吉行淳之介が1966年に発表した小説、時代設定は1969年(昭和44年)、主人公は恋愛小説を執筆している作家、映像はモノクロ基調(口紅や糸など赤系の色が要所でパートカラーになる)とくれば、昭和レトロな文芸映画の薫りが自然と漂う。主人公・矢添(綾野剛)の執筆シーンでは、原稿用紙に文字を綴る姿に合わせて文章を音読する綾野の声が流れ、さらに白文字の縦書きテロップを映像に重ねる念の入れよう。3人の女性たちとの関りから、作家が何を思考し、それをどう創作物に転換していくのか、その内面の動きが物語の軸の一つになる。
吉行淳之介作品の愛読者や、かつて文芸映画が人気の一ジャンルだった時代を知るシニアの映画好きなら、本作を懐かしさとともに楽しめるだろうか。ただまあ、このジャンルが衰退傾向にあるのも確かで、キャストの顔ぶれや映像の作りからも予算の少なさが伝わるのが切ない。ヌードで濡れ場を演じるのはメインの女優3人のうち比較的マイナーな2人。モノクロ映像も、フルカラーで60年代を再現することに比べて製作費の節約につながったはずだ。
振り返ると、テレビの普及に押されつつも映画がまだ娯楽の王様とみなされていた頃、文芸大作がそれなりに作られ、メジャーな女優がヌードで情愛の場面を熱演して話題になることもあった。例を挙げるなら、五社英雄監督作「鬼龍院花子の生涯」(1982)の夏目雅子、吉田喜重監督作「嵐が丘」 (1988)の田中裕子、森田芳光監督作「失楽園」(1997)の黒木瞳など。
文学的に描写された男女の情愛を映像化する際、必然性があればヌードも辞さないという女優は、従来から欧米に比べ日本では少なかった。さらに言えば、成人向けコンテンツも多様化している昨今、エロティックなものも含めた好奇心の対象を劇場公開映画に求める層は確実に減っているはず。文芸映画に限らないが、邦画界においてヌードはキャリアのある女優にとってメリットよりもリスク、配給元や製作委員会にとっても客層を限定する点でやはりリスクととらえる傾向がさらに強まっているのだろう。
「火口のふたり」「花腐し」などでも監督・脚本を務めた荒井晴彦は、情愛を描く文芸映画のそうした衰退傾向に抗い、火を絶やさぬよう奮闘しているようにも思える。
黒と赤のモノクロと赤のパートカラー
1.はじめに:荒井晴彦監督との相性
❶1947年東京生まれの荒井晴彦は、早稲田大学第一文学部除籍後、脚本家の田中陽造に師事し、若松孝二作品の脚本を出口出(でぐち・いずる)名義で、足立正生他と共同で執筆した。(Wikipedia)
❷脚本家としての単独デビューは30歳の『新宿乱れ街 いくまで待って(1977)』。以降、ピンク映画や日活ロマンポルノなどの脚本を多数執筆したのを始め、『Wの悲劇』(84・澤井信一郎監督)、『リボルバー』(88・藤田敏八監督)、『ヴァイブレータ』(2003・廣木隆一監督)、『大鹿村騒動記』(11・阪本順治監督)、『共喰い』(13・青山真治監督)の5作品で、キネマ旬報脚本賞を受賞し、日本を代表する脚本家となった。(Wikipedia)
❸監督デビューは、50歳の『身も心も(1997)』。以降、本作を含め5本の監督作品が公開されているが総て脚本兼任である。内、①を除く全作をリアルタイムで観ている。全体の相性は中~上。
①1997年『身も心も』 監督/脚本、1997年公開:未鑑賞。
②2015年『この国の空』 監督/脚本、2015年公開・鑑賞:85点。
③2019年『火口のふたり』 監督/脚本、2019年公開・鑑賞:60点。
④2023年『花腐し(はなくたし)』 監督/脚本、2023年公開・鑑賞:80点。
⑤2025年『星と月は天の穴』 監督/脚本、本作、70点。
2.マイレビュー◆◆◆ネタバレ注意
❶相性:中。
❷時代:1969年。
この年は、ニュース映像に登場した「東大の安田講堂事件」や「アポロ11号の月面着陸」や「ウッドストック・フェスティバル」等大きな出来事があった時代。
❸舞台:東京
❹主な登場人物
①矢添(やぞえ)克二〔綾野剛、42歳〕:主人公の小説家。43歳。13年前結婚したが、1年で妻に逃げられて以来独身。若くして総入れ歯であるというコンプレックスがある。女性とは精神的な結びつきを忌避して、肉体的関係のみ。娼婦・千枝子と体を交え、過去を引きずりながらやり過ごしていた。そして自身が執筆する恋愛小説の主人公Aに自分自身を投影することで「精神的な愛の可能性」を自問するように探求するのが日課だった。ところがある日、画廊で偶然出会った大学生の紀子との奇妙な情事へと至り、矢添の日常と心が揺れ始める。その過程で自分の弱さと向き合い、それを受け入れるようになる。愛車は左ハンドルのBMW。
★日本に輸入されているBMW他の外車は、右ハンドルに改造されているものが大半だが、ウインカーとワーパーのレバーが国産車とは逆になっている。その理由は国際規格ISOで、ハンドル位置に関わらず「ウインカーは左(ワイパーは右)」と定められているため。
②千枝子〔田中麗奈、44歳〕:矢添の馴染みの娼婦。矢添の一番の理解者で、愛をこじらせている矢添に寄り添う。矢添が総入れ歯であることを指摘する。
★田中麗奈の黒の下着姿がセクシー。
③瀬川紀子(のりこ)〔咲耶(さくや)、24歳〕:矢添が画廊で偶然出会う大学生。矢添とのセックスを通じて女性としての欲望に目覚め、矢添の人生に影響を与える。セックスで興奮すると盲腸手術の痕だけが赤くなる。
★吹越満と広田レオナの一人娘である咲耶がフルヌードを披露。
④矢添の大学時代の同級生〔柄本佑、38歳〕:21歳の娘がいる。
⑤娼館「乗馬倶楽部」の女主人〔宮下順子、75歳〕:恋愛の酸いも甘いも噛み分け、矢添の迷いや千枝子の焦りにスパイスを加える。
⑥娼館「乗馬俱楽部」の新人の女〔MINAMO、24歳〕;俳優の養成所に通っている。矢添は小説の中のB子に彼女を重ねていく。
⑥小説の中の主人公A〔綾野剛、42歳〕:結婚に失敗した小説家。43歳。矢添自身を投影している。
⑦小説の中のB子・女子大生〔岬あかり、25歳〕:20代。
❺考察:
①作品は、「黒のモノクロ」をメインとし、矢添と紀子のセックスシーン等の一部が薄い「赤のモノクロ」と、サーモンの切り身や口紅を塗った唇等が赤のパートカラーになっている。荒井晴彦監督インタビューによれば、その理由は以下の通り。
ⓐ今の日本は外国と違い昔を再現するのは不可能に近い。道路の白線や信号のLED等。だからモノクロを選んだ。
ⓑ原作に、興奮すると盲腸の傷跡が赤くなるというのがあり、まずはそこを赤くした。他に、主人公が見て感情が動くようなものを赤にした。
★画面を幾種類も色を変えたモノクロにしたり、カラフルな彩色にする手法は、日本では鈴木清順が知られている。又、黒のモノクロの中の一部をカラーにする手法は、黒澤明が『天国と地獄(1963)』で、煙突の煙だけをピンクにして強烈な印象を残している。このような例は内外で古くから行われている。
②原作は1966が舞台だが、本作は1969年が舞台になっている。その理由も監督インタビューで明かされている。
ⓐ1969年は、「東大の安田講堂事件」や「アポロ11号の月面着陸」や「ウッドストック・フェスティバル」等大きな出来事があり、いろんな始まりと終わりが一気に押し寄せた年だった。当時21歳の荒井晴彦が、失恋や大学抹籍等で、人生が変わった時代が1969年だったのだ。
ⓑ本作の最後に「1969年の思い出に」というテロップが入るのはこの理由による(荒井晴彦監督単独インタビュー 2025/12/19)。
③本作には、荒井晴彦お得意のセックスシーンが何度も登場するが、違和感なく受け入れられる。原作の持つ文学性と官能性を、脚本と演技と映像で表現していると思う。上映館である伏見ミリオン座のパンフに荒井晴彦のメッセージが記載されている:「配信だとボカシが入ります。ボカシのないこの映画を階段式のこの素敵な映画館で味わってください。」
④本作では、矢添と千枝子と紀子等の「現実の世界」と、AとB子の「小説の世界」が並行して描かれている。そして、「小説の世界」では、セリフ以外は無音になってる。
⑤主人公の矢添は、原作者吉行淳之介が投影され、劇中小説の人公Aは、矢添が投影され、更に、矢添とAには荒井晴彦の思いが投影されている。上手い構成である。
⑥本作には、最初と最後に橋とブランコが登場する。
ⓐ幕開きは、橋の上で、矢添が大学時代の同級生と偶然再会するシーン。ラストは、矢添えと紀子が並んで橋の上を歩くシーン。
ⓑもう一つのブランコは、最初が無人で、多分矢添の元妻が好きだったものだろう。半ばでは、矢添、千枝子、紀子が乗っている。そしてエンドロールに重なるのは、紀子がブランコを漕いでいるシーン。
ⓒこれ等は、最初と最後で矢添や紀子が変わったことを示していると思われる。
⑦タイトルの意味:
紀子が夜空を見上げて、「星があんなに輝いているのに、どうして私はこんな年上の男とこんなことをしてるんだろう」と嘆く。それに対して矢添は、「あんなのは空の穴ボコだよ。星は小さな穴ボコで、月は大きな穴ボコに過ぎないんだ」と言う。つまり、「星と月」というきらびやかな対象を、物理的な穴(空洞)として捉えることで、ロマンチックな情景に潜む不気味さや虚無感、そして中年作家の孤独や性、愛の迷い等を表現していると思われる。
❻まとめ
①「現実の世界」と「小説の世界」を並行して描いて、更に原作者を投影した主人公に、監督・脚本家の思いを投影して多重構造にした脚本は上出来である。
②モノクロ画面とパートカラーの技法も成功している。
③主人公以下主なキャラの行動も理解出来た。
④一番の収穫は、女性と本気で向き合えないバツイチの40男が、女性と付き合うことで、自分の弱さに向き合い、それを受け入れるようになったこと。それを克服しようとする真摯な努力が、未来に繋がることが示されたことが何よりもうれしい。
⑤唯一の難点は、主人公の生き方に理解は出来るが、共感出来なかったこと。
綾野剛さんのために星三つ
この映画の美学がわかりませんでした。
結局入れ歯のことなんだ…
うーん、男の夢、の映画ですかね。
最近昔の設定の映画が多いですね。
退屈してしまいました。
エロくて文学的
1969年。妻に逃げられた40代の独身小説家・矢添克二は、心に空いた穴を埋めるように娼婦の千枝子を抱き、妻に逃げられた過去を引きずりながら日々を過ごしていた。そして、知られたくない自分の秘密にコンプレックスを抱えてたことも、彼が次の恋愛に尻込みする一因となっていた。そんな矢添は、執筆中の恋愛小説の主人公に自分自身を投影し、愛を探求することを日課にしていた。そんなある日、画廊で出会った大学生・瀬川紀子とお茶をした事をきっかけに情事へと至り、矢添の日常と心は・・・そんな話。
EXPO70大阪万博前年の昭和をモノクロで時々赤の差し色が入る絵で撮っていて、昭和を感じた。1969年頃にあんな娼婦宿が有ったのかと知れた。
矢添役の綾野剛はさすがの演技だった。
大学生の紀子役の咲耶は大胆な濡れ場を演じてて良かった。娼婦の千枝子を田中麗奈が演じていたが、胸も出さずイマイチだった。
愛とは、文学的に考えさせられた。
わたし、情けないです
荒井監督はやはり脚本家としての作品群が素晴らしく、数え切れないくらいの感動をもらってます。
監督作品では一つ前の「花腐し」が大好きで、前作もそうでしたが、既に化石となりつつあるピンク映画とそこにしがみつくような作家たち、そして今回は文芸作品の周辺を、郷愁という言葉がいいのでしょうか、レトロ感タップリに魅せてくれました。ただ、「花腐し」の方が好きです。
ピンク映画独特のセックスシーンや大事なところの隠し方。わたしの年齢には懐かしです。
予習なしで観たからかもですが、B子さんと紀子さんが一人二役かと最後まで思ってました。何を観てたんだわたしは!本当に情けないです。荒井監督と2人の女優の方に本当に申し訳ない気持ちです。
前戯しろっ!!ゴム付けろっ!!(゙ `-´)/
インテリエロ
令和の時代に 「体当たり演技」
オープニング、日本語の発音が新鮮
昭和30年代〜40年代初頭の日本映画に出てくる
あの感じだ。
モノクロームの画面/一部着色は
「あ、こーゆー表現法方ね」とさほど驚きはしなかったが
かなり予算カツカツで製作されたのが 随所に感じられ
ボロ隠しの白黒だとわかってしまう
また1969年の 衣装の時代考証が酷かった
ブラジャー&ショーツは今の時代のデザインで
男性の下着も昭和の時代とは思えない
ちょうどミニスカートの流行から
パンストが普及するかしないかの時代か?
田中麗奈は左右別々のストッキングスだけど
ガーターベルトの描写は無し
男性の衣装も 今風のオーバーサイズ。
たぶんモデルとなった小説家だと その時代は
オーダーメイドだったはず。
※昨年公開で同じ1960年代を舞台にした
「ブルーボーイ裁判」、
文筆業を生業とする一人暮らしの男性
主人公、モノクローム作品の「敵」
の衣食住のリアリティと比べてしまうと
なんとも おそまつ。
宮下順子が、キャスティングされていた
女を客体化して性的に消費していた時代への
オマージュなのか、リアルでそれをしたいのか?
#MeToo を経た今の時代に見ると
かなり 違和感があって面白い。
ベッドシーンのリアクションが日活ロマンポルノ。
今の時代に見ると 不自然だが、逆に「喘ぎ声」等 かなり研究したと思われる
監督のインタビューの中に
「こんな映画もあるんだよ」という言葉があったが
「濡れ場」が多い割に体位のバリエーション・表情の捉え方が
あまりにも平坦。
今は無き ポルノ映画だ。
監督は自分の一番良かった時代に帰りたいのか?
違うことを考えてしまった退屈な映画
なぜ、いま吉行淳之介?
原作も読んでいたので、とても楽しみにしていました。
荒井監督がインタビューで語っていた、吉行淳之介の言葉を思い出しました。
「精神という花が咲いている。それを引っこ抜くと、その根っこには『性』がぶら下がっている。」
いくら高尚な理屈をこねても、女性と向き合えば逃げられない肉体のコンプレックス(入れ歯)に対峙せざるを得なくなる。
「終わりも始まりもあるわけない」と現実から逃れ、穴(虚無)を見つめる矢添(綾野剛)のどうしょうもない男の狡さがうまく表現されいて、でも、男としてその気持ちもよくわかるなあと感じました。
一方、失禁までして男を誘い、M化していく紀子(咲耶)の性へのあくなき好奇心、冒険心は、これとはまた対照的で欲望に忠実、奔放でとても魅力的でした。
綾野剛さんと咲耶さんに身長差や年齢差のギャップがあったのもよかったです。
また、娼婦の千枝子(田中麗奈)がデートに誘われて子供のように歓ぶ千枝子の姿は(性ではなく、愛の対象として見てもらえた)とても切なかったです。
人間の根源的なエネルギーや孤独は「性」に現れるんだなあと奥深さをあらためて感じました。
同じ監督に同じ綾野剛の主演なため、花腐しと非常にイメージが近い。女...
ATGか日活ロマンポルノか
時代背景が昭和30年代ということもあり、懐かしく鑑賞しました。昭和36年生まれの私にとって、映画好きな青春を過ごしたATGや日活ロマンポルノを彷彿とさせる雰囲気がありました。それもそのはず、原作が吉行淳之介だったのですね。私小説を代表とする時代の寵児。18歳規制がかかっていましたが、匂うような演技ではありませんでした。「不適切にもほどがある」ような昭和を生きた人々のお話でした。
小説と映画の違いなのかな
吉行淳之介さんの小説を読んだこともないけど、なんとなく映画のイメージと違っていた。
想像していたのは昭和の日本の学生紛争とかが盛んな時代に、戦争を体験してなんとなくやりきれない思いを抱えた中年男の心情の変化とかが描かれていて、馴染の娼婦とのすれ違いかなと・・・。
モノクロの中で赤が際立ち、ホテル(つれこみ旅館?)や矢添の家の感じは昭和レトロで好きな感じ。
監督・脚本家の特徴がすごく出ていて、以前の作品にも共通して「やって、やって、やりまくる」的な部分が多く、「文学的な映像を求めて」とか「綾野剛さんが素敵♪」と思って観に行くとげんなりするかも。
観たことのない女優さん達の割り切った全裸のシーンもあるけどいやらしさはない。どういう映画に仕上げたかったのか、喘ぎ声がAVみたいで耳障り。
「不感症なんだな」ってセリフがよく出てくるところが、ザ・昭和。
「お前がヘタなんや」って今なら突っ込まれるかも。
矢添自身のリアルな生活ではハイライトを吸っていて、小説の中の人物で登場するときはLARKを吸っていることになっている?
娼婦の下着があの時代っぽくない気もした。
映画館が悪かったのか、行った日が悪かったのか両隣が70代ぐらいのおじいさんで、股間に上着を被せて上映中はいびきをかいて爆睡。
女優のわざとらしい喘ぎ声が聞こえるとムクッと起きていびきがとまり笑わせてくれた。
コンプレックスあったとしても
たしかに40代で総入れ歯、そりゃ外した顔見せたくないよね 外した入れ歯見られたくない気持ちもわかる。綾野さん演じる作家さんがどこかアンニュイで優しさもあり、関係性がいい感じと思えたとしてもなぜか近さを感じさせない、掴みきれないこの距離感、逆に引き寄せられるかもしれない。次々と関係を持つのも作家さん、芸術家の性(さが)故かな。大学生から見たら魅力的だよね、女性はかなり開発されてしまったからね。身体の相性もよかったのかも、と想像した。自分の意見、堂々と伝えられる娘だったね。自分なら嫌われるのこわいから自分の意見ってあまり言えないかも。それにしても綾野さん、眼鏡かけるとエロさ倍増、ヌードな後ろ姿、カッコいい。黒スーツ夜の繁華街、以外の役、新鮮でした。観てよかったです。アンニュイ、セクシーサンキューです♡
「恋愛の最終段階は性愛にいたる」
皆さんは数の多さは別にして、恋愛をしている、恋愛をしていたと思います。きっかけは何ですか。相手が可愛い、恰好いいという人もいれば、お互いの話が、波長が合うという人もいるでしょう。そして付合いを経て最終的に「性愛」にたどりつくのではないでしょうか。お互いが愛しくなると抱きしめたいという気持ちは「本能」だと思います。
恋愛を経験した人、していない人はこの映画を見てどのように思うのか興味深いです。映画の半分くらいは「性愛」の行為が描写されます。それが自然の成り行きと思うか単なるエロ映画と見るか、どちらかではないでしょうか。
脚本・監督は荒井晴彦です。「火口のふたり」や「花腐し」でもかなりきわどい「性愛」を描いていました。「火口のふたり」は従妹という血のつながりが気持ちも肉体もフィットする映画でした。「花腐し」はお互いを好きになった女性と男性が「性愛」につながる映画でした。
今回の映画は面白い構成になっています。作家の矢添は小説の主人公Aを「精神的に愛する男」というベースで書いていきます。作家自身の矢添は「女を見るとやりたくなる」男です。小説と自分自身がまったく乖離していますが、年齢はともに43歳というのも肝です。
矢添は小説家ですが妻に逃げられてからずっと一人でいます。彼の心には妻に逃げられたことがショックでどこか女を信じられないというコンプレックスを持っているのです。それゆえ女への不信感から「女を見るとやりたくなる」という、女を「物」としか見られなくなっているのです。
小説のAはバーでアルバイトしている大学生B子に好意を抱きますが、あくまで紳士的にふるまいます。一方、矢添が朝食をとるときに赤い鮭を見て欲情すると、すぐ売春宿に電話してなじみの娼婦・千栄子を抱きます。この鮮明な赤色はのちに3度出てきます。娼婦・千栄子は彼にとって「物」です。彼女が矢添へ好意を持っていてモーションをかけますが矢添はまったく無視します。
矢添はふらっと入った画廊で大学生の紀子と出会います。彼女を車に乗せて家まで送るときあることがおき、二人は連れ込み旅館に入ります。裸にして「性愛」をしようとしても欲情しません。ただ部屋の隅に数えきれない男と女の毛を見た瞬間欲情するのです。それ以降何度も何度も矢添と紀子は「性愛」をかさねます。
あるとき矢添と紀子が「性愛」にいたったとき、紀子の体に赤い傷が鮮明に映し出されます。赤い傷。紀子の「性愛」に対する欲情です。体は正直なのです。矢添がいつもの売春宿から電話を受けて16歳の子がいると聞き、そそくさと出かけます。裸になったその子の唇に真っ赤な口紅がひかれている。この赤い口紅は後のB子につながるのです。
AはB子に紳士的でしたが、あるとき突然部屋へ行こうと言い「性愛」に及びます。なぜか。B子がつけていた真っ赤な口紅がB子らしくなかったからです。Aは純情そうに見えていたB子に悪意を持つ、そして強引に「性愛」におよんだのです。
紀子と二人車に乗っているとき事故を起こします。レントゲンを撮るふたり。そこで矢添の秘密が明らかになったのに、紀子の一言によって矢添は紀子を以前より愛おしくなっていくのです。ここにおいて女を「物」としてしか見てこなかった矢添は紀子に陥落するのです。そしてB子と紀子、Aと矢添がだんだんとリンクしていき、彼の小説は完成します。
恋愛というものは、「お互いがありのままの自分を愛してくれる人を愛する」に尽きるのではないでしょうか。娼婦・千栄子は矢添にとっては恋愛の対象ではなく、女という「物」でしかなかった。彼女が遠くを見る目つきで諦めたようにブランコをこぐ姿に「性行為」だけではどうしようもないことがあることを見事に描写していました。
滑稽で切なさがつのりますが、この映画はまさにラブストーリーです。愛する者同士の世界は面白い。お互いが高齢になったとき「性愛」がなくなっても愛は残るからです。
昭和はエロスが溢れていた
1969年。昭和で言うと44年は、ブルーボーイ事件の判決、連続射殺事件の永山則夫逮捕、アポロ11号月面着陸、ウッドストック開催、ビートルズ最後の制作アルバム「アビーロード」の発売、世界各地の紛争と日本の学生運動の高まりも含め、映画やドキュメンタリーの題材が溢れるほど起こった激動の年である。吉行淳之介原作の小説は1966年に上梓したのでこれらの出来事は後に起こったことであるが、月と星をアポロと絡めたかったのだろう、。
荒井晴彦監督作品は「火口のふたり」「花腐し」で男と女の性の営みを沢山見せつけていたので既に免疫はできていたが今回の綾野剛と咲耶の絡みは又別の種類のエロスを感じさせてくれた。
助監督時代からピンク映画で鍛えられ商業映画に進出し有名になった監督は沢山いらっしゃいますが皆さん随分とお年となってきました。荒井監督のこのような作風を継承する方がいるのかどうかわかりませんが、令和になっても日本には必要な映画のジャンルではないのか?と勝手に思っています。しかし、邦画も大作映画が上映するスクリーンの大半を制するような時代になってきたので、性愛をメインに据えるような作品は(今日、私が観た映画館では観客は3人のみだったし)興行的には厳しいのではないかと少し心配してしまいます、。
是非、この映画も高い評価を得て有名になってもらいたいです。
全88件中、1~20件目を表示