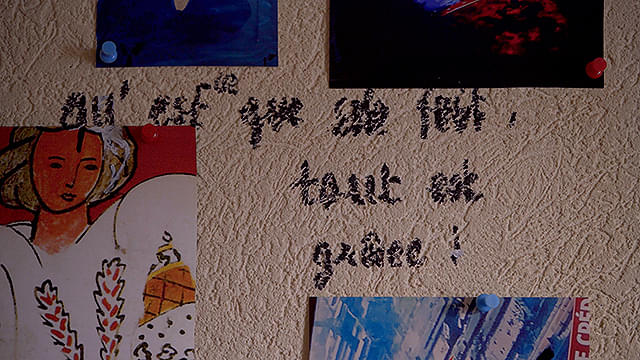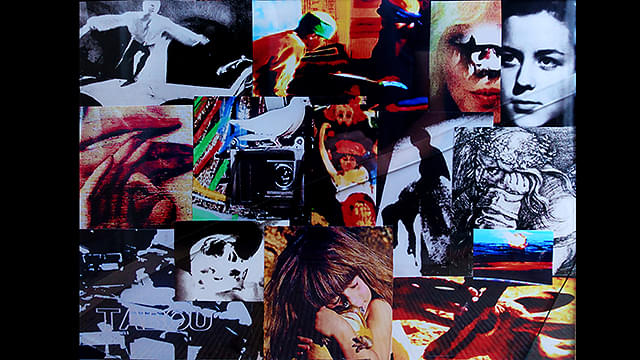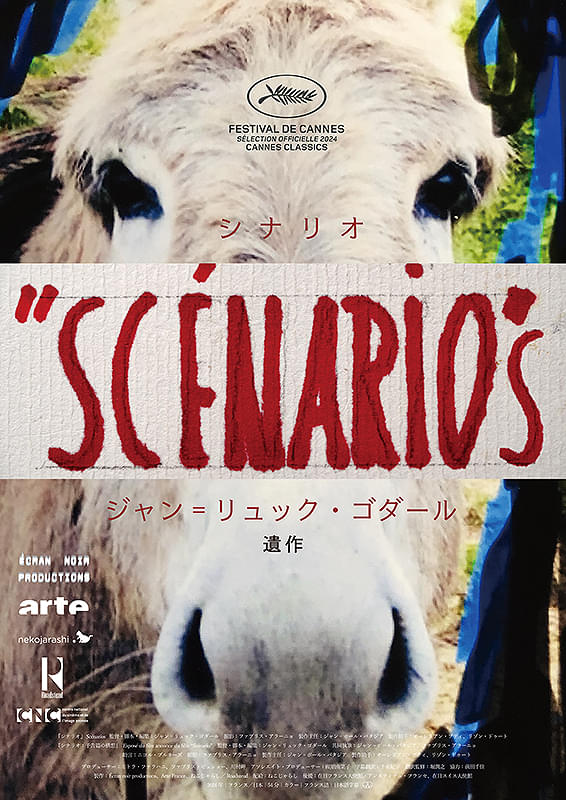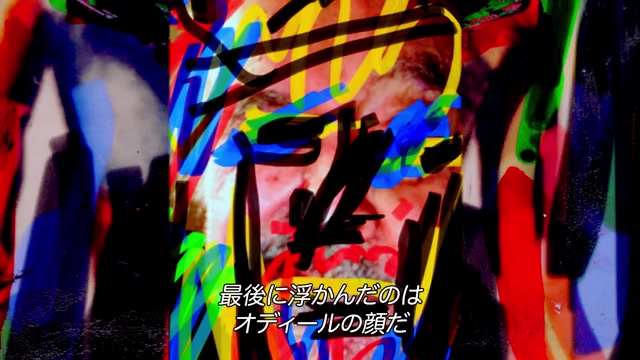シナリオ
劇場公開日:2025年9月5日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR

解説・あらすじ
フランスの巨匠ジャン=リュック・ゴダールが、2022年に居住していたスイスで安楽死する前日に撮影した遺作。
2022年9月13日、ゴダールは自身が書いたシナリオに従い自発的な死を遂げた。彼はその2年前から「シナリオ」と題した最後の長編映画企画に取り組んでおり、モンタージュの構想を記した手帳やノートを何冊も作成していた。しかし、ゴダールは死の数日前になってこの企画を仕切り直し、2部構成の映画として仕上げるよう指示を出す。それに従って制作されたのが本作「シナリオ」で、コラージュ技法による18分間の映像を収め、死の前日のゴダールの姿も映し出す。
ゴダール自身が本作の制作ビジョンを語ったドキュメンタリー「シナリオ 予告篇の構想」も制作され、2本でひとつの作品として構成される。2024年・第77回カンヌ国際映画祭クラシック部門でワールドプレミア上映された後、第49回トロント国際映画祭、第37回東京国際映画祭でも上映された。
2024年製作/18分/G/フランス・日本合作
原題または英題:Scénarios
配給:ねこじゃらし
劇場公開日:2025年9月5日
スタッフ・キャスト
- 監督
- ジャン=リュック・ゴダール
- 製作主任
- ジャン=ポール・バタジア
- 脚本
- ジャン=リュック・ゴダール
- 撮影
- ファブリス・アラーニョ
- 編集
- ジャン=リュック・ゴダール
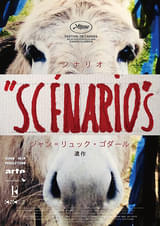
 気狂いピエロ
気狂いピエロ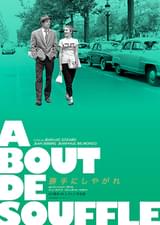 勝手にしやがれ
勝手にしやがれ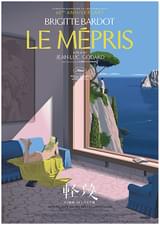 軽蔑
軽蔑 はなればなれに
はなればなれに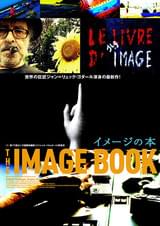 イメージの本
イメージの本 さらば、愛の言葉よ
さらば、愛の言葉よ 女は女である
女は女である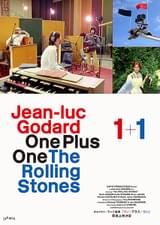 ワン・プラス・ワン
ワン・プラス・ワン 女と男のいる舗道
女と男のいる舗道 アルファヴィル
アルファヴィル