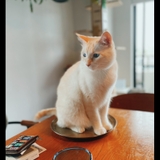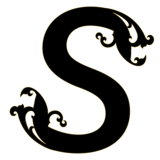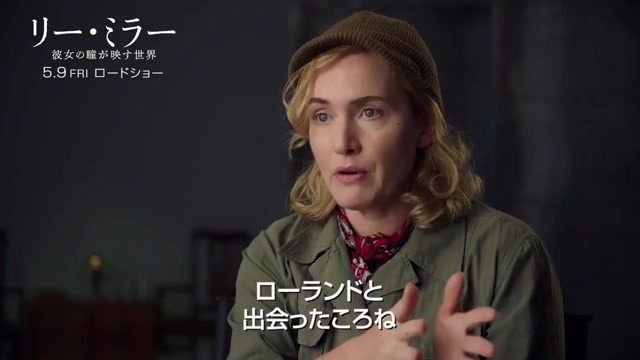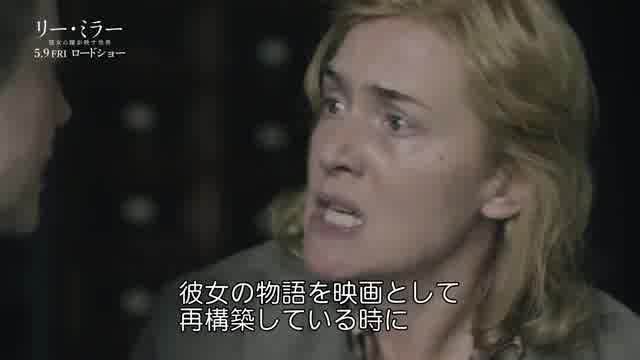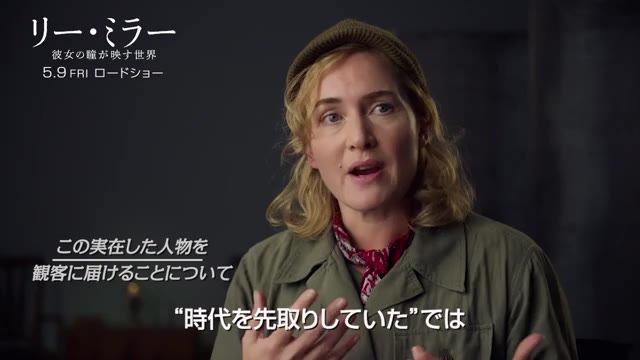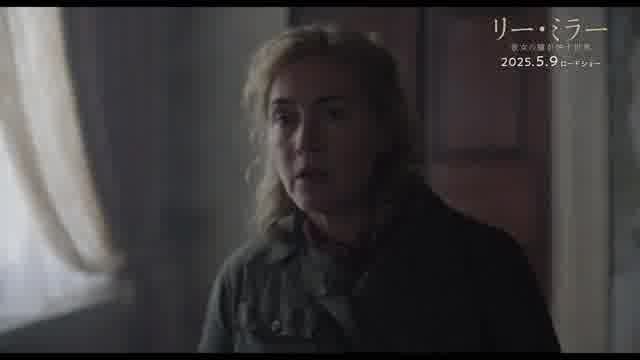リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界のレビュー・感想・評価
全126件中、21~40件目を表示
ケイト・ウィンスレット49歳入魂の烈女伝
リー・ミラーは、戦前の実在する元トップモデルにして写真家。
Wikipediaで調べてみたら、あのマン・レイの弟子にして愛人、とあるw
「好きなものは酒とセックスと写真」と豪語し、パリで詩人夫妻や有閑階級の御婦人がたと遊び暮らしていたが、やがて第2次世界対戦の開戦とともにロンドンに移り、ヴォーグUKの写真家となる。そして戦争の前線にやむにやまれず惹き付けられていく。
イギリスでは女性の従軍記者が認められないことに憤慨するが、自身がアメリカ国籍であることを逆手に取って記者証を入手し、ライフ誌カメラマンの盟友ディビィとともにドイツ占領下のフランス前線に潜り込む・・・
あの『タイタニック』のヒロイン、ローズ役の時は24歳?のウィンスレットも49歳か。面構えが半端ない。
実際のミラーは1907年生まれだから、前線で取材しているときは37歳という勘定になる。
のべつ幕なしにタバコを吸い、スキットルでぐいぐいウィスキーを煽りながら仕事に没頭。ちょっと理不尽な仕事上の扱いには容赦なくブチギれ、男装して米軍前線の作戦ブリーフィングに潜り込む。街の暗がりでフランス人女性に乱暴しようとする米GIを突き飛ばし、ジャックナイフをチラつかせて追い払う(そのナイフを女性に護身用にと渡してしまうのがかっこいい)。
そしてドイツ降伏後、取り憑かれたようにディビィとともにジープで荒れ果てたドイツ深部へ。ヒトラー邸宅と、最後に強制収容所に足を踏み入れる・・・
あー、なんてはちゃめちゃで婆娑羅な女性だ。
同じ女性を描くにも、『サブスタンス』みたいな下品な仕上げじゃなくて、こういう道を採って欲しかったな → デミ・ムーア。
素晴らしかった
インタビュー形式で進むかのように見える
リー・ミラーの半生。
モデル引退後に悠々自適に暮らしていたかのような生活が、
ある時を境に一変する。
そこまではさらっと、芯を残したまま描きつつ、
人物間の関係性は上手く見せている。
デイヴィッドとのフレンドシップ。
これも後になって、効いてくる。
マリオン・コティヤールとの再会、
「守れない約束はしないで」、この言葉が彼女を突き動かす。
(ああいう短い場面でもキメてくる流石のマリオンコティアール)
そして、ノエミ・メルランと再会する。
人々が消えていき、戻ってこない。
隠れていた人々の恐怖を、まだパリの人たちは知らない。
ここで、アレクサンダー・スカルスガルド演じるローランドとの再会があり、愛を確かめ合う。そして、帰宅を決めたかのように見えたリーが、戦場の最奥地に行くと決めた瞬間、デイヴィッドと同様に胸が熱くなった。
今までの映画だったら、家に帰ってたもん。
本当にリーのこういう姿を見せてくれるのがこの映画の良い所。
そして、収容所の厳しい現実を知る。
かの有名な浴槽での写真を撮る。
デイヴィッドの感情が溢れ出し、二人は友情により労わり合う。
戻って来たリーは、ヴォーグ誌に自らの写真が載らないことで、会社に駆け込み写真を切り刻む。世に出ないのなら、取っておいても仕方がないのだと。
こういう瞬間に、過去と現在が繋がるんだと思うんだよね。
本当に、世に出ない事実は、無かった事にされてしまうから。
そして、それを最も知っていたのは、リー本人だった。
幼い頃に性暴力に遭った経験をオードリーに話す。
どうしても、写真を残さないといけない理由。
それは、迫害に遭った彼らの為でもあり、自分の為でもあった。
自分の後悔を拭い去りたい、彼/女らの気持ちに共鳴したい。
その気持ちが、リーが戦場に出た根拠だったのだ。
ただ、その根拠というものを幼い頃の性被害と照らし合わせていいものだろうか、と少し逡巡した。本当は、写真を残すことに根拠なんて要らないのではないだろうか。リー本人がそう語ったのか、分からないが、同じような経験をしたことがある人しか突き動かされないのであれば、その動機はいつか無になってしまうのではないか。誰も居なくなったときどうなるのか。
ストーリーに戻ると、アンドレア・ライズボロー演じるオードリーが本当に良くて、リーはあの人に当たってしまったけど(それも当然のように思う)、でもオードリーと一緒にあの雑誌をパリに届けていたんだし、彼女自身、リーの写真がどれだけ重要なものかを分かっているから。写真を破壊してはいけない、とリーにそれを伝えるから。ちゃんと知っている人がいるから、リーの支えに見えて、本当にいい関係性だった。
インタビューはいつの間にか終わり、
(この辺がちょっとわかりにくい)
しかし、鑑賞後にあのジョシュ・オコナ―の台詞を思い返すと、非常に胸に迫るものがあって、泣けた。
「自分のせいで母親が不幸になったと思ってたんだ」
「何で言ってくれなかったんだ」
史実として、リーが息子に死ぬまで戦場での仕事を伝えなかった事実がある。それを描く際の選択として、最も正しい描き方をしていたのではないかと思った。
伝えなかったリー。知らなかった息子。
リーに、何故ヴォーグに写真を載せなかったのかと聞かれたオードリーが、「まだこの写真を見るのに恐怖や不安を感じる人がいる」と。一つの真理だと思った。確かに、どこかで自分と同じような誰かが地獄のような日々を送っていたと考えるのは、辛いし苦しい。ましてや写真を見てしまっては、精神的に不安定にもなる。
しかし、それでも載せるべきだったのだと、暗に語っていたのは息子だった。
「何で言ってくれなかったんだ」
(想像上ではあるが)あの悲惨な戦場での話を聞いて、写真も実際に見た。
その後に、母の人生を思って彼が告げた台詞が、言って欲しかったという事、知りたかった、という事なのである。どれだけ自分が傷ついたとしても、見たくなかったものを見る事になるとしても、言って欲しかったのだ。
そうすれば、その傷は少し癒えたのかもしれないから。
その苦痛は少し和らいだのかもしれないから。完全に消えなくとも、少しの間忘れられたのかもしれないから。残し続ける人が現れ、事実は無くならずに済むかもしれないから。痛みを知っている人がいれば、また同じ事が起こらずに済むかもしれないから。
これが、オードリーの反論に対する答えだと思う。
そして、この映画を観た我々に託された希望なのだと思う。
そして、エンドロール。
事実は残り続けると言うかのように、リー・ミラーの写真たちが流れる。
ここで止まっていてはいけない。
隠していてはいけない、表に出していかなかればいけない。
事実を無かったことにしてはいけない。語っていかなければいけない。
そんな重要なことを教えてくれる一作だった。
本当に久々に、まさに映画らしい映画を観た。
これよくアカデミー賞スルーされたな…。
改めて「関心領域」って何だったの?ってなるな本当に。
直視することなく描くって、まさに今生きる自分たちがしそうになっている事じゃん。それを映画にして、再演したって何の意味があるの?
重要なのは、自分を満足させることじゃなくて、何を見せるために映画があるか、じゃないの?
決して忘れてはならない負の遺産
❶相性:上。
❷時代(登場する文書やテロップや会話等の日付から):
1977→1938~1945→1977。
❸舞台:イギリス:イースト・サセックス、ロンドン。フランス:パリ、サン・マロ。ドイツ:ブーヘンヴァルト、ダッハウ、ミュンヘン。
❹主な登場人物
★以下の7人は全員が実在、実名。
①リー・ミラー〔実在:1907-1977〕(✹ケイト・ウィンスレット、47歳):主人公。アメリカの先駆的な従軍記者兼写真家。かつては『VOGUE』の表紙を飾るモデルだったが、30代で写真家に転じ、ダッハウ強制収容所を始め、ヨーロッパ各地で衝撃的で恐ろしい光景をフィルムに収めた。彼女の写真は、WWⅡにおいて最も意義深く、歴史的にも重要なものとして残り続けている。一方、凄惨なものを見たこと、そしてその物語を伝えることに多大な労力を費やしたことにより、精神的に大きな犠牲を払うことになる。
②デイヴィッド・シャーマン〔実在:1900-1984〕(✹アレクサンダー・スカルスガルド、46歳)
アメリカ「LIFE」のフォトジャーナリスト兼編集者。取材中リー・ミラーと出会い、チームを組み、数々の仕事をした。二人は生涯の友人となる。
③ローランド・ペンローズ〔実在:1916-1997〕(アンディ・サムバーグ、44歳)
イギリス人の芸術家、歴史学者、詩人、伝記作者。WWⅡ勃発の2年前にリー・ミラーと出会い、恋に落ちる。リーが従軍記者になることを応援しており、リーの人生における大きな転機には必ず彼女を支えた。
④オードリー・ウィザーズ〔実在:1905-2001〕(アンドレア・ライズボロー、41歳)
イギリス人ジャーナリスト。イギリス版『VOGUE』の編集者。リーの写真を評価する一方、社会的制約や雑誌方針との板挟みになる。
⑤ソランジュ・ダヤン〔実在:1898-1976〕(✹マリオン・コティヤール、47歳)
リー・ミラーの芸術家仲間。フランス版『VOGUE』の編集者。レジスタンスのメンバーだった夫のアヤン公爵は1942年にゲシュタポに逮捕され、幾つもの強制収容所を経てベルゲン・ベルゼン強制収容所に移送されたが、収容所が解放される前日に死去。ソランジュも強制収容所に送られていたが、パリ解放後リーと再会する。
⑥ヌーシュ・エリュアール〔実在:1906-1946〕(ノエミ・メルラン、34歳)
リー・ミラーの芸術家仲間。フランス人パフォーマー、モデル、シュルレアリストの芸術家。夫は詩人のポール・エリュアール。ナチス占領下のフランスでレジタンスのために働く。1946年にパリで病死。
⑦ジャーナリスト(実はリーとローランドの息子アントニー・ペンローズ)〔実在:1947-〕(ジョシュ・オコナー、32歳)
1977年、イギリスの自宅で、70歳のリー・ミラーに当時の様子を取材する若手ジャーナリスト。
★最後に、彼がリーとローランドの息子アントニー・ペンローズであることが示される⇒❺⑮★参照。
❺要旨と考察
①1977年。イギリスはイースト・サセックスのファーリー・ファーム(Farley Farm)の自宅で、70歳のリー・ミラー(ケイト・ウィンスレット)が、若いジャーナリスト(ジョシュ・オコナー)からインタビューを受け、写真家として活躍したWWⅡ時代について語り始める。
②1938年南フランス。31歳のリー(ケイト・ウィンスレット)は、芸術家や詩人の仲間たち──ソランジュ・ダヤン(マリオン・コティヤール)やヌーシュ・エリュアール(ノエミ・メルラン)らと休暇を過ごしていた。
③そこでりーは、イギリス人の芸術家ローランド・ペンローズ(アレクサンダー・スカルスガルド)と出会い恋に落ち同棲する。2人は1947年に正式結婚。
④同じころ、ドイツでjは48歳のアドルフ・ヒトラー(1889-1945/4)が政権を掌握し、WWⅡ(1939-1945)の脅威が迫っていた。
⑤1939年、りーとローランドはロンドンへ移住。仲間達はレジスタンスに参加する等して離れ離れとなってしまう。
⑥1940年、リーはかつてモデルとして活躍した『VOGUE』の英国編集部に、写真家としての仕事を求め、女性編集者のオードリー・ウィザーズ(アンドレア・ライズボロー)と出会った事で仕事を得る。
⑦写真家として活動する中で、リーは米国従軍記者のデイヴィッド・シャーマン(アンディ・サムバーグ)と出会い、チームを組む。
⑧1942年、リーは戦場を希望するが、英国軍の規定により女性の戦地への参加は認められない。アメリカ国籍のリーは、デイヴィッドの機転により、アメリカ軍の従軍記者となる事で戦場へ赴く。
⑨1944年。リー達はアメリカ軍が解放したパリを訪れ、やつれて変わり果てたソランジュと再会する。そこでリーは強制収容所の存在と、ユダヤ人をはじめナチスに抵抗する人々が姿を消している現実にを知る。
⑩真実を明らかにしなければならないとの使命感に駆られたリーとデイヴィッドは、先に待ち受ける“この世の地獄”を目指すことを決意する。
⑪1944年、仏サン・マロの戦いを乗り越え、史上初めてのナパーム弾が使用された瞬間をスクープする。
⑫1945年、独 ブーヘンヴァルト強制収容所とダッハウ強制収容所が解放されたその⽇に、現場に初めて⾜を踏み⼊れ、何万人もの行方不明者の死体を記録。
⑬1945年4月30日、ヒトラーが自殺した日、ミュンヘンにあるヒトラーのアパートの浴室を記録。
⑭戦争は終わるが、リーが目撃した光景は、PTSDとなり長きに渡り彼女を苦しめることとなる。
⑮時が流れて1977年のイギリス。イースト・サセックスのファーリー・ファームの自宅で70歳のリー・ミラーが、若いジャーナリストからインタビューを受けている冒頭のシーンに戻る。
★ジャーナリストはリーとローランドの息子アントニー・ペンローズだった。この時点で、リーは既に亡くなっていて、相続人のアントニーが、屋根裏部屋で発見したリーの遺産(写真と文書)から、リーの業績を振り返る仕掛けになっている。リーとの対話はアントニーの想像だったのだ。仕事一筋だったリーは、息子との時間が取れず、加えてPTSDにより、母と息子は不仲のままで終わっていた。最後に母の後悔の心を理解した息子に気持ちが強く伝わった。
★でも、この設定をよく吟味すると大いなる疑問があることに気付く。本作で描かれた、1938年~1945年のリーに関わる出来事は、アントニーの眼を介したものになっている。しかし、生前のリーと息子のアントニーは不仲で、相手の気持ちが理解出来ていなかった筈である。とすれば、そんなアントニーが、母の気持ちを代弁することは出来ないのではないか?
★このことから、リーに関わることは本人から語る設定にした方が良かったと思うのである。
❻まとめ
①圧倒的な男性社会の中で、女性の主人公が20世紀を代表する写真家の一人となった経緯がよく理解出来た。
②ヒトラーのアパートのバスタブでのリーの入浴シーン等、よく理解出来なかったシーンもあるが、容認出来る。
③一番の問題は、要となっている1938年~1945年のリーに関わる出来事を、アントニーの眼を介した設定にしたことだと思う。
④強制収容所とホロコーストに関しては、下記❼参照。
❼参考1:今は博物館になっているナチスの強制収容所
①1年前公開された『関心領域(2023米・英・ポーランド)』のラスト直前で、画面が突然現在の「アウシュビッツ・ビルケナウ国立博物館」に飛ぶ。そこでは清掃員たちが開館前の清掃を行っている。大きな窓の向こうには、亡くなったユダヤ人たちの遺品(靴や杖や写真等)が山積みになっている。つまり、80年以上前のホロコーストの悲劇が、現在でも学ぶことが出来るようになっているのだ。
②ナチス・ドイツは、ユダヤ人、反ナチ分子等々の該当者を収容するために、ドイツ本国及び併合・占領したヨーロッパの各地に強制収容所を設置した。
③最も悪名高い「アウシュビィッツ=ビルケナウ強制収容所(現在のポーランド)」を始め、最初に作られ後続の強制収容所のモデルとなった「ダッハウ強制収容所(ミュンヘン近郊)」等、2万ヵ所もあったという。
④現在では、多くの元収容所が整備されて博物館や付属施設となっている。忘れてしまいたい負の歴史を保存・継承し学習して、同じ過ちを繰り返さないようにするためである。ドイツのみならず、ヨーロッパ各国の学生や社会人が訪問して、体験学習出来るようになっている。
⑤私は、本作に登場した「ダッハウ強制収容所」を2011年に見学している。収容房、バラック、ガス室等の現物や、写真、展示物等過去の残虐な行為を自分の目で見て大きな衝撃を受けた。他国の出来事とは思えなかった。こんな悲劇は二度と起こしてはいけないと痛感した。他の見学者も基本的には同様だと思う。たとえ観光コースであっても、悲劇の遺跡を自分自身で体験することは、風化を防ぎ、未来へ継承するために、大きな意義があると確信する。
❽参考2:リー・ミラー(Lee Miller)とリー・スミス(Lee Smith)
『シビル・ウォー アメリカ最後の日(2023米)』でキルステン・ダンストが演じる報道写真家の名前リー・スミスは、本作のリー・ミラーから採られている。
ママはママなりの夢と挫折があったはずだが、私はお母さんの生き様を知らない。
行動し、挑発し、傷を引き受けた人生
VOGUE誌の表紙を飾ったモデルから第二次世界大戦の戦場カメラマンに転身したリー・ミラー。その存在を知るだけで意味のある映画だった。演じるケイト・ウィンスレットも本人が乗り移ったかのような力の入った演技で、代表作タイタニックを今から見てみたくなった。
冒頭、セレブ達がフランスの海岸で優雅にバーベキュー、主役のリー・ミラーはいきなり上半身裸で、胸をあらわにしながら煙草をスパスパ。その場を訪れたイギリス人アーティストと、数時間で恋に落ちる。
こういう肉食系の女性でありつつも、戦争が始まればいてもたってもいられずカメラマンとして戦場に乗り込む。ナチスが占領中のフランスを連合国が奪回する、ノルマンディー上陸作戦だ。
豊満な肉体と、戦争の状況を読み取る知性、戦場における男女の境界を突破しようとする執念や行動力。全部の方向へ100%エネルギーを注ぐ、今までにないような人物像に引き込まれた。
過酷な戦場でミラーの視線が向かうのは、何重にも傷つけられる女性の存在だ。フランスではナチスに協力したとして街頭で丸刈りにされる若い女性、ドイツでは男性の影に隠れてパンを分け合う、ホロコーストの生き残りのユダヤ人少女。
彼女たちの警戒心を解くため、ミラーは英語からフランス語に言葉を切り替えたり、「男装」して帽子の中に隠した長い髪をほどいたりする。
クライマックスはミュンヘンのヒトラーの私邸に忍び込み、浴室で自分を被写体にフォトセッションを敢行。これをナチスに向けた芸術的な挑発だと理解した。モデル、カメラマン、演出家としての役割を兼ねるミラーの真骨頂だろう。
女性が背負う見えない傷という現代的テーマもひしひしと感じる。何かに突き動かされるように悲惨な戦場を直視するミラー。しかし「見てしまった」ことによる傷、見たものを共有しようとしない友人への不信感という傷も背負うことになった。
ミラーが戦後、自分のキャリアについて語らなかったのもそれらの傷のためだろうか。晩年のミラーを描く場面はやや単調で、沈黙への答えを得る難しさを想像させられた。
マン・レイ登場せず
リー・ミラーと聞いて思い出すのは
マン・レイの反転写真。
ところが その後戦争写真家と
なって例のヒトラーのバスタブの
セルフポートレイトを撮った人物だったとは!!
とにかく いろいろ興味深い内容
マン・レイ含めて モデル時代の
歴史的な著名人とのエピソードには
ほとんど触れず。
VOGUE のカメラマンから、映画は始まる
当時は手持ちで二眼レフを使って
マグネシウムを焚いての撮影だったのか?
カメラケースは革製…
重くて 機動力の無い機材環境だったと
改めて 思い知る。
そう。
アナログ時代は ガラス面の反射を消す
オブジェクト消去なんて無いから
ヒトラーの写真額はガラスを外して
画面に納めるんだよな~
歴史上の人物のある数年間を
ギュッと詰めて描写する映画術
これはこれで私は嫌いじゃない。
また、主役の
ケイト・ウィンスレット!
役作りのための
ボディメイクも見応えがある
性的客体を完全に降りた
戦地を走り被写体と対峙する
一個の写真家の女性。
それを体現する 肉体に改造したのは
見事だ
たぶん食事を含めた 凄腕のトレーナーチームが組まれたのだろう。
先日のサブスタンスの
デミ・ムーアもしかり。
アカデミー賞にヘアメイクや衣装デザインもあるなら、ボディメイク部門もあっても面白いとおもう。
※全体的に 面白かったが
一部物足りなかったことが。
同じ写真家をモデルにした
マーク・ギル監督の「レイブンズ」のような
その時代の写真のテクニカルな
オタクが喜ぶ描写が、もっと欲しかった。
ケイト・ウィンスレット、その意気や良し。ただ…。
シビル・ウォーの記憶が鮮烈で、キルステン・ダンストのイメージがどうしても離れなかったせいもあるが、ケイト・ウィンスレットのリー・ミラーはやっぱり辛かった。
本当は大好きな女優の一人なんだけど…。
まず、申し訳ないが太り過ぎ。次に、これは致し方ないとしてもやっぱり歳を取り過ぎ。
実際のリーが第二次大戦の戦場を駆け回った頃の写真を見ると、痩せている訳ではないが、逞しさと精悍さがみなぎっていて、まさに戦場カメラマンのそれだけれども、ケイトの場合は、長年の怠惰がたたってどうしようもなく太っている風で、動作も同年代の標準よりずっとモッサリした感じ。これでリアリティを感じろと言われても難しい。
また、リーが大戦下のヨーロッパを駆け回った時期は、彼女がまだ三十代だった頃なのに、劇中のケイトはとてもそんな年には見えない。どうみても実年齢と同じ五十近くのおばはんだ。
こんな様子でどうやって感情移入すればいいというのか…。私には無理だった。
勿論、実際のリーに似ていなければダメだという訳ではないが、ここまで違うと、そもそも女性で行軍を許されたいきさつも、ロマンスも、ストーリーの骨格部分についての説得力が無くなってしまう。
脚本は中々だし、大事なメッセージを持った映画だと思うだけに、残念。
観終わってすぐに考えたことは、主演女優が誰だったらよかったか、ということだった。
本当は星三つがせいぜいかと思ったけれど、ケイトが製作まだ買って出た熱意や、晩年のリーが〇〇に向かって語るという設定の意外さで少し加点しました。
それにしても、そこまで意気込んで主役を張るんだったら、ケイトさん、もうちょっとアプローチしてほしかったなぁ。
でもまあ、そこがケイト・ウィンスレットの良いところかもしれないけど。
悪いことはみんな女の身に降りかかる。 (二回目鑑賞)
戦場カメラマンの、しかも女性の視点で描かれたあの時代と戦争。
プロデューサーも兼ねたケイト・ウィンスレットの本気、凄味。回想シーンへと移っていく前の眼差し。戦場での息づかい。女であるが故の差別への怒り、苛立ち。
戦地と遠く離れたロンドンとの意識の違い。
長く続いた戦争がようやく終わり、戦勝ムードに湧く中で犠牲者の写真を掲載しなかったのも理解できる。今でこそ、ホロコースト・何が行われていたのかが知られているが、あの時点では何も分からなかったのだから。(ただ、連れ去られ消えていく) 逆に掲載したアメリカ版の方が勇断だったろう。
リー・ミラーをはじめとする戦場カメラマンたちの功績は大きい。命をかけて、その後の人生をもかけて残してくれたものから、我々は何も学んでいないのではないか。
重く苦しい内容だけに、アンドレア・ライズポロウの美貌と軽み、アンディ・サムバーグの軽みが良いアクセントに。
最後の、、。
もう一度はじめから観直したくなる。
(二回目鑑賞)
最後の仕掛けで、もう一度見直したくなり2度目の鑑賞。
初回は、リー・ミラーについて解説以上の知識がなかったが、2度目にあたり少し調べて(検索すると、モデル時代の写真から、撮る側になってからの作品、この映画にも使われている写真をはじめ経歴等いろいろ知ることができる)鑑賞。
リー・ミラーについて知識を入れてから観ると、インタビューのところだけでなく、演出も編集も撮影も脚本も音楽も演技も、すべてが実にうまく作られていると思う。
リーが女性兵士?に、「あなたの写真が世の中のことを教えてくれる」と言われるシーンがあるが、この映画はたくさんの知るべきことを教えてくれた。
ケイト・ウィンスレットが、今までリー・ミラーの映画が作られていないのが不思議だ、みたいなことを語っているが、ケイト・ウィンスレットによって作られるのを待っていたんだと思う。
時代は、戦場は、女性を必要としていなかった
彼女の進んだ道、見たもの、心折れたもの、伝えたかったもの、本当の戦場カメラマンの、ジャーナリストの職責が心に滲みた。同時に、ケイト・ウィンスレットの存在が全てに重なっていた。
あの頃の有名な女性カメラマンはゲルダ・タローと数人しか知らなかった。映画を通じてリー・ミラーの事を少し知ったわけだが、カメラレンズを向ける感はゲルダよりも、アイディアに満ちソフトなのかな?と感じた。きっとファッション業界に居たことと、知り合った仲間たちとの文化的な関係があったからと想像する。
無関心でいれたはずなのに
リー自身が興味を持ち進んだ道は
女性が一段低く見られていた時代
夢中になった伝えるべきこと
時代が彼女を無の存在にしたのか
それとも自ら無の存在にしたのか
映画ははっきりと語らないが
脚色を混ぜながら事実を伝えた。
真実は”写真”のなかにある。
※
This movie must be made based on the idea and understanding of Kate Winslet.
This is the story of Lee Miller as a war photographer, as captured by Kate Winslet, who must have been busy making the film. It was made in the form of a conversation between the young interviewer and Lee, but from her particularly cold tone, we find out who the interviewer is halfway through.
She used a medium-sized Rolleiflex, which we have come to call a twin-lens reflex. On the other hand, David Sherman, a photographer, and editor at Life magazine, used a small camera that seems to be a Leica. However, there is never any mention of developing the photos. How on earth did they develop them on the battlefield?
After entering Normandy, France, she worked as a war photographer, but the problem is the passage of time. They traveled alone in a jeep that seems to have been loaned from the US military in Paris, but when they entered Germany, a couple who committed suicide with potassium cyanide is found, reminiscent of Goebbels and his wife. However, later, on April 30th, 1945, the day Hitler died in Berlin, she entered Hitler's former headquarters in Munich and took photos. Goebbels and his wife died the day after Hitler's suicide. Furthermore, she visited the concentration camps, Buchenwald and Dachau consequently, but the US military entered the former camp on April 11th, and Lee visited the latter concentration camp, known for its railroad siding, just before Munich. I wonder if the film was made based on these historical facts to some extent.
What did Lee Miller herself really want to do? She would like to express something particular by herself. She started taking photographs with Man Ray during her time in Paris (1930s), and she was also the subject of a photo shoot at Hitler's house. In wartime London, she managed to get into Vogue magazine as a photographer, where she had once been a famous model, and then made a fuss when the photos she brought in were not published.
Even though it was wartime, she showed no consideration for the subjects she photographed. The limited rights of women were mentioned many times in this film, but if she was an artist, it is not difficult to imagine how much the rights of her subjects must have tormented her in the latter half of her life.
I wish they had been a little more conscious of the historical facts surrounding the war when making the film. What a shame.
豪華な女優陣!
どこまでも個別的な、エゴイスティックな目的達成の行動原理
1938年フランス、リー・ミラー(ケイト・ウィンスレット)は、芸術家や詩人の親友たち──ソランジュ・ダヤン(マリオン・コティヤール)やヌーシュ・エリュアール(ノエミ・メルラン)らと休暇を過ごしている時に芸術家でアートディーラーのローランド・ペンローズ(アレクサンダー・スカルスガルド)と出会い、瞬く間に恋に落ちる。だが、ほどなく第二次世界大戦の脅威が迫り、一夜にして日常生活のすべてが一変する。写真家としての仕事を得たリーは、アメリカ「LIFE」誌のフォトジャーナリスト兼編集者のデイヴィッド・シャーマン(アンディ・サムバーグ)と出会い、チームを組む。1945年従軍記者兼写真家としてブーヘンヴァルト強制収容所やダッハウ強制収容所など次々とスクープを掴み、ヒトラーが自死した日、ミュンヘンにあるヒトラーのアパートの浴室で戦争の終わりを伝える。だが、それらの光景は、リー自身の心にも深く焼きつき、戦後も長きに渡り彼女を苦しめることとなる(公式サイトより)。
主人公のリー・ミラーは、女性差別が常態化する世の中への怒りや、戦争への憂い、平和への希求といった社会正義を行動原理しているわけではなさそうである。少なくとも序盤では、女性性を上手に利用しながら、その時に感じた、やや刹那的というか、退廃的というか、露悪的というか、自由な衝動を大切に生きているように見える。つまり、彼女の女性差別や戦争との格闘は、女性差別や戦争そのものへの反骨ではなく、あくまで彼女自身の自由な衝動の阻害要因だから、という理由に拠るところが大きい。
女性差別や戦争はそれ自体が巨悪なので、わたしたちは普通、巨悪の消失を目的化するが、リー・ミラーは例えば、自身の「自由な衝動」、子どもたちの「未来」、女性の「純粋な恋心」といった、極めて個人的な目的のために、巨悪の消失を手段にする。二酸化炭素の排出抑制という巨大な目的のためにはがんばれないが、大好きな海水浴ができなくなるかもしれないという個人的な目的のためならがんばれる、のような手段と目的の関係である。
こうした、どこまでも個別的な、ある意味でエゴイスティックな目的達成の行動原理が、彼女の作品に力を与える。だから、日の目を見ない写真など、だれかの個別的な目的達成に貢献しない写真に価値はなく、たとえ、そこにどれだけ史料的な価値が認められようと、破り捨てるだけなのである。
一方で、エゴイスティックな行動原理の代償は大きい。もともと「約束はしない主義」のリーだが、被写体としてフィルムに収めるということは、その人の個別的な目的を達成をリーが預かるということを意味する。
ある男性とのインタビューを通じて回想するという構造が、晩年に戦場でのPTSDが原因でうつやアルコール依存症でカメラを置いたリーの苦しみを、あえてドラマチックではなく極めて仄かに表現している。悪臭漂う部屋に無造作に捨て置かれた大量の遺体の写真を前にしたリーが、瞳孔から瞬時に光を失い、言葉が一切出てこなくなった場面はとてもアイコニックだ。
現代的な示唆。
シンプルなストーリーながら大きな示唆を与える作品だと思いました。主人公の女性写真家は己の自然な感情に忠実に行動するため、混迷する社会の中で自由の保障の大切さがよく訴求されています。日本人は先の大戦でナチスと同盟を結んで連合国に対して闘った訳ですが、やはりこの種の映画にどこまで真実味があるのか、またオカルト伝説ではヒトラー生存説というのがあり、ひいてはグローバル事象における報道写真の意義とは等の批判があるとは思います。この写真家はうまく大戦シナリオに乗っかった活動家と観る事も可能なわけです。しかしそれらの諸点を考慮しても、自然な自由への抑圧には断固たる反対が必要だと云う目的意識の点は非常に現代的な意義を捕えていると思います。民主化の目的とは何か、それは生きる意味の再確認・再獲得のプロセスに他ならず、当時ではなく現代群像に目を向れば何もできない・何も撮れない私たちこそ現代政治の主役たらねばならない、そんな情趣も思わせる映画です。
ケイト・ウィンスレットの演技が素晴らしかった。
存じ上げなかった実在の人物「リー・ミラー」
モデルからフォトグラファーに転身し
米国陸軍の従軍記者として
第二次世界大戦の数々の報道写真を残した
彼女の伝記的映画。
酒もたばこも男まさりで気性も激しい彼女が
残した写真は、戦場の凄惨さを女性特有の目線と
芸術性の高いものだったけれど
英ヴォーグは掲載を認めなかったけれど
その理由はその理由としてわからなくもない。
ただ、彼女の無念に思う心の叫びが痛い。
そんな彼女を陰ながら支えた
英ヴォーグ編集長オードリーと
同僚カメラマン、デイヴィ・シャーマンの存在が
とても羨ましく感じた。
ディヴィのリーに対する感情が垣間見れるシーンでは
切なくもある。
こんな仕事仲間、本当に羨ましいかぎり。
傷とは、見えないところにこそ深く負う。
外傷は時が来れば治って行くけど
心に深く負った傷は、
薬や酒に頼らなくてはいけなくなるほどで
本作ではその傷を彼女の苦悩として
隠さずしっかり描ききっている。
在り来りな感想ではあるけれど
人間の恐ろしさ、戦争の愚かさをまざまざと
見せつけられた本作は、
リーの残した写真のようでもある。
タバコと酒とセックスと写真
1938年、南フランスで仲間たちと休暇を過ごしていたリー・ミラーは、芸術家ローランド・ペンローズと出会い恋に落ちた。まもなく第2次世界大戦が始まり、すべてが一変した。写真家の仕事を得たリーは、フォトジャーナリスト兼編集者デイヴィッド・シャーマンとチームを組み戦場での写真を撮影した。1945年、従軍記者兼写真家として悲惨な戦場の様子をカメラに納め、ヒトラーが自死した当日、ミュンヘンのヒトラーの別荘の浴室で自らのポートレイトを撮影し、戦争が終わった事を伝えた。戦場での光景はリーの心に深く傷として残り、戦後も長きにわたり彼女を苦しめた、そんな彼女の半生を息子に語る様な構成で紹介した話。
まーとにかく、ひっきりなしにタバコを吸い、酒を飲み、セックスし、モデルとして峠を越えたら写真家となり、人が撮らない様な写真を撮り、真実を伝えようとした、超変人(有る意味褒めてます)のリー・ミラー。
ミュンヘンのバスタブ写真が有名らしいが、その事を知っただけでも観た甲斐があった。
ナチスの蛮行はこれまでもいろんな作品で観てきたから特別どうこうは無いが、どうしても戦勝国サイドからの作品は一方的過ぎるんじゃないかと思ってしまう。
リー役のケイト・ウィンスレットの体当たりの演技は素晴らしかったし、報道写真家としての実在の女性リー・ミラーはこんな人だったのだろうと思える素晴らしい演技だった。
あのタイタニックのローズから30年弱。時が経つのは早いなぁ、という感じ。
写真に込めた想い
こんな映画が見たかった。
彼女の世界?現実の世界?
まさに『その時代』を生きてきた人⋯⋯女かな?
あまり多くを語らない自由に誰にも縛られなく言いたい事も言い感性の赴くまま進んできた人。
なんだろうけど写真から見えた光や影には彼女自身そのものを捉えていたのかもしれない。
やはりまだ女というだけで虐げられた時代に翻弄されて納得行かないアメリカ人。
同じ所には長くいれば切れ味が鈍るナイフかの様に男や文化、そして時代に立ち向かって行った彼女。
別に好き好んで前線に飛び込んだ訳ではなく、自身に起きた過去から逃げて立ち向かい乗り越えようとした彼女の一部を写真にしたのかも。
そして戦争の終結時に霧の中に迷い込んだかの様に彷徨い行き着いた地獄の淵⋯⋯。
知って欲しかった今起きている世界を戦争を傷ついた人々を、そして女性たちを。自分自身を。
バスタブでの1枚はヒトラーの邸宅(戦争、暴君、権力、そして男たちの世界の象徴)ですべての不安を脱ぎ去り、温かい湯の中で安息をつき汚れを流してさらなる世界に準備をするかの様にも思える。
しかし誰も見ようとはしなかった。
戦争の真実や女性、そして彼女を。
彼女が現代にいたら何を見ているのだろう?
いや自分たちは目を逸らさず真実を捉え立ち向い後世に残し伝える。
過ちは誰でも起こしうる事。だけど過去から学ぶ事は出来るはず。
誰もが安心して温かい湯に身を浸す幸せな時間を得る事を祈りつつ。
全126件中、21~40件目を表示