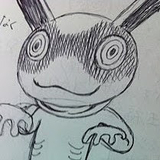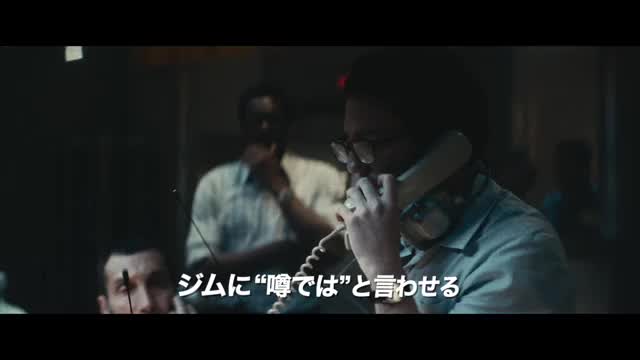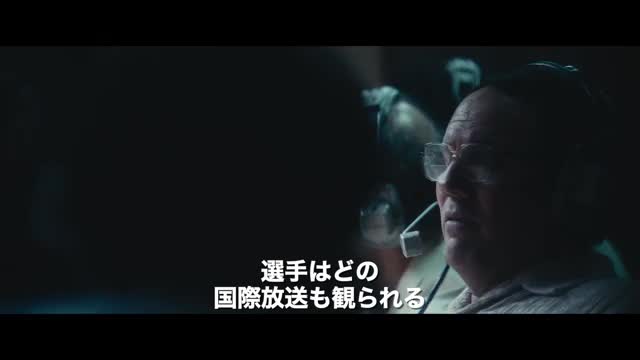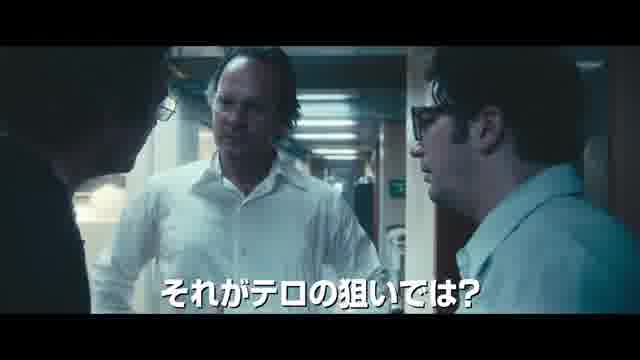セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全33件中、21~33件目を表示
実際に起こった哀しい事件であるが、捉え方と描写がもひとつに感じた。
今作「セプテンバー5」は1972年9月5日発生した実際の事件、ミュンヘンオリンピック開催中にパレスチナ武装組織”黒い九月”によるイスラエル選手団の選手村襲撃事件の事をメディア報道視点で描いており 初めてテロを世界に向けて実況生中継したとされている。
しかし中継したことで警察の作戦行動がTVを通して晒され作戦変更を余儀なくされた事、後の空港への犯人ヘリ移送と銃撃戦との流れに繋がる。
何にせよ、無実なイスラエル選手団11人と警察官1名、犯人8人中5名が死亡。3人は逃亡図るが逮捕されたとされる。
この事件を受けてイスラエル側(モサド)がパレスチナに対して報復行動に。
この報復作戦映画が2005年「ミュンヘン」である。
こっちの映画は昔観ましたが、なんか電話取ったら爆弾でドカンとホテルの壁に穴が空いて・・・すんごい映画だったのを覚えてます。
確かエリック・バナさん主役でしたね。
今作の方は、ドキュメンタリチックな報道クルーの視点からの展開となってます。
よって 何やってんだか? 凄い慌ただしさは分かるのですがもう一つ重要さや
過激な部分のクロ-ズアップがほぼ無く、音声だけが語っている感じなんですよ。
立て籠もる犯人像と人質の安否とか、ヘリに乗せられた流れとか警察交渉とか、空港での銃撃戦がなぜ起こったとか・・・大事な所がぼやけてて。
何やネンの残念な思いが大きいです。
必死にドイツ語を通訳する女性だけがファインプレ-だった様な思いです。
空港でのヘリ移動後の銃撃戦。一時は人質解放とか?
一斉に喜んだとか思えば それは誤報で。
直ぐに訂正で 全員死亡とか・・・。
メディアの右往左往場面とか 未確認発表(人質安否)の半ば丁半博打的報道とか、誰が責任取るとか、まるで 巷のFテレビとB誌との報道の様相を呈してます。その程度の捉え方と 初めてのテロ中継をどうやって行ったとか、そっちの方が重点となっており ちょっと全体的にがっかりな構成を感じましたですね。
題材はシッカリしたテーマなのにね。
誰が報道側のドタバタに興味あって観るんだと思いましたね。
このミュンヘンオリンピック事件ですが
これも 米国大統領のガザに対しての動向注視しての公開なのでしょうね きっと。私的には、セプテンバー5 + ミュンヘン作品を足してちゃんと大作に再構成し直して公開されたら評価したい所でしょうか。あくまで希望ですがね。
公平でかつ平和な枠組みを持つ事が最優先されるべきだと感じます。
ご興味ある方は
今の内に劇場へどうぞ。
「真実」という言葉の功罪
例えば、ベトナム戦争は、初めてテレビでリアルタイムで見る戦争だった、という話を聞きます。その時に流れていた、アメリカ側(所謂「西側」)の野蛮で凄惨な行為がブラウン管をとおしてお茶の間に流れた結果、アメリカのみならず世界中で反戦デモが起き、アメリカ国民のベトナム戦争への意欲はみるみるうちに減退していったと言います。それが、結果的にベトナム戦争からアメリカ軍を撤退させたとも言います。わたしは、その時代に生まれてもいないので、実際のところは知りません。
真実というものは、とかく、「真実のようなもの」ほど「真実」と言われるように思います。そしてもう一つ、真実を求めることは「正義」だと思われています。特に、ジャーナリズムにおいて、真実の追求こそが職業倫理の頂点であるかのように信奉されてきたのだろうか、と思うのです。
ですが、果たしてその考えは合っているのだろうか、とこの作品を見て考えました。
1972年9月5日。ミュンヘンオリンピックに湧くドイツは、第2次大戦での苦い傷跡からの復興(精神的な意味でも)を込めて、平和の象徴とされるスポーツの祭典に国の威信をかけていました。その気持ちがどれほどのものか、世界中に見てもらうためにと用意したのは、選手宿舎も見渡せる膨大な数のカメラでした。
一方、世界中の関心が向く平和の祭典で自分たちの気持ちを知らせようとしていた者たちが、その時、暴力という手段でもって命をかけた行為に及んだのでした。
わたしが、この事件を知ったのは、かの有名なスティーブン・スピルバーグ監督作品である「ミュンヘン」を子供の頃に鑑賞した時です。まさか、オリンピックという平和の祭典の真っただ中でテロが起きていたなんて、と思ったことを覚えています。また、その頃は第2次大戦後から今も終わりなく続いている中東情勢(イスラエルとパレスチナを中心とした情勢)のことなど知る由もなかったため、何の話をしているのかまったく分からず、スピルバーグ監督がユダヤの血を引く方ということなど知りもしませんでした。それから十数年の時を経て、再びこの事件について映画をとおして知ることができるという事実は、端的に知的好奇心が擽られました。
ところで、最近まであったイスラエル(というのかネタニヤフ首相の個人的怨嗟なのかは分かりかねますが)の徹底的ともいえるほどのパレスチナ自治区への容赦なき攻撃が、実際にどのようなものだったのか、そもそも今回の攻撃は、ハマスによる強襲に激怒したイスラエルによる報復だったと思っているのですが、それらについて、結局わたしは真実を知りません。わたしは、そこにいないからです。
このように、わたしにとってテレビの見せる所謂「真実」とは、「真実のようなもの」でしかなく、わたしにとっての「真実」を引き寄せるための道具のような感覚があります。それは、「真実」という言葉に危険な中毒的作用が含まれるからだと考えるからです。つまり、「真実」という言葉は時として「正義」の象徴のように祭り上げられるのですが、その実、真実を知ることで傷付くこともあるし、余計にパニックになることもあるという副作用が大きいということ、何よりも危険だなと思うことは、そもそも人間という欲求の権化のような存在である我々にとって、「真実を知る」という行為は、一種の支配欲に通ずる快感を引き起こす麻薬的作用があると考えるからです。そして、その欲求を逆手にとって情報を金に換えた(あくまで個人的見解ですが)のが、メディアという職種だと思っています。時には嘘を振りまきメディア王(「市民ケーン」のモデルになった人のことです。)になった者もいれば、上記の通り真実を振りまくことで戦争を終結に導こうとした者もいました。なので、情報を取り扱う職業人には高い倫理観が必要なのだと思います。
この映画では、その倫理観について考える場面が幾つもあります。テロ事件が勃発した際に、テレビの放映権を巡って幹部が争う場面、嘘を吐いてまで進入禁止区域にカメラを入れようとする場面、その中で、警察の突入をテレビに映してしまい、その後、突入が中止になってしまう場面(テレビに突入作戦の模様が映ってしまったせいなのかどうかは明瞭ではなく、あくまで主人公が自責の念に駆られるだけではありますが。)、空港での銃撃がどうなったのか不明瞭な時に主人公がどう決断したのか、その結果がどのようなものだったのか、など。
確かに、「真実」はその時、その場にしかなかったのだと思います。オリンピックの試合よりも命のやり取りに気持ちが傾くのは、一人の人間として当然の欲求だとも思います。正直、色々書いているわたしも、この映画は単純にテレビのお仕事ものとしてすごく見応えがありましたし、一種のスパイサスペンスのような臨場感すら終始画面の中に感じられて、ホラーでもないのに無意識で座席を握りしめてしまいました。どうして、主人公が「カット」と言うだけでこんなに緊張するのかと思うほどのスリルを感じられ、当時の(というより常に報道の最前線にあるであろう)緊迫感を少しだけ体感することができました。
しかし、一方でそのようなスリルやスパイアクションのような快感こそが、当時の現場に流れていた「真実を知っていち早く伝える」という免罪符(個人的に言えばですが)の裏に隠されていた一種の「罪」のように思えてなりませんでした。
結果的に人質にされたイスラエルのオリンピアンは全員死亡、警官も1名死に、パレスチナ人(恐らくテロリストかと思われますが)も死亡し、事件は「終わり」を迎えます。あまりに悲劇的な終幕に肩を落とす主人公ですが、その翌日には追悼のための番組を仕切るよう上司に言われ、車に乗り込んだところで、この映画は唐突に終わります。まるで、一連の報道番組の終了とも被るような呆気ない幕切れでした。
この映画では、敢えてなのかも知れませんが、当時の中東情勢やPLO(パレスチナ解放機構)、ブラックセプテンバーについて、詳細に語られることはありませんでした。もしかすると、あまりその辺の情報を流さないことで政治的恣意性を排除しようとしたのかも知れません。また、あまりバックミュージックも流れず、現場に流れる音で当時の緊迫感を出していました。だからこそなのか、わたしは上記のような面白さとともに、わたし自身も受け入れていた罪を、最悪な最後でもって罪悪感というかたちで思い知ることになったのです。もしかすると、主人公たち報道陣も、自分たちが行っている行為の裏にある「特ダネをどこよりも最速で流してヒーローになる」というような功名心に対する罪悪感を、人質の救出というかたちでなかったことにしたかったのかも知れませんし、だからこそ、最悪な結果を受け容れられずにいたのかも知れません。つまり、自分たちの行為を正当化できるだけの「奇跡」や「勝利」が欲しかったかも知れないということです。答えは分かりません。そこにいた人たちにしか分からないのです。
現代、上記のとおり中東情勢は変わらず、血で血を洗うような憎しみの連鎖が続いています。家族を殺された子供が、大人になって敵側を殺す悪循環から、抜けられそうにありません。1972年9月5日に起こったことにどのような意味があったのか、当時テレビをとおしてその様子を見ていたおよそ9億人の視聴者たちだけでなく、この映画を観たわたしも、考えなければならないのかも知れません。
メディアの倫理観については、最近の日本でも、事件の被害者に対する対応から始まり、加害者側への悪質で恣意的な報道の仕方、その割に自身の不正を正そうとしない上層部の在り方や誤情報の発信についても取り沙汰されていますが、一方でそれをSNSで無遠慮に叩く市井による、一種数の暴力とも思える動きも多く見受けられ、わたし個人としては、どうにも「真実を追求する」とか「真実こそ正義」という風潮が、そもそも人間の在り方として正しいのか分からなくなってきたため、このような感想を書かせていただきました。
色々書いてきましたが、この映画だけを取り上げてみれば、上記で書いたとおり所謂「お仕事もの」としても十分に面白く、このような大事件を、ほぼスタジオの中だけで完結させているという点でワンシチュエーションものとしても想像力を駆り立てられるエンターテインメントになっていると思います(事件の被害者にとっては何とも言えないとは思いますし、上記したとおり、このような気持ちになること自体が危険なサインなのかも知れませんが)。個人的には、もう少しエモーショナルでも良かったかな、と思ったため、☆一つの半分を除かせていただきました。
極めて今上映されるに相応しい映画
1972年のミュンヘン五輪で起きたテロ事件を描いた映画。事件の当事者ではなく、事件の報道をするテレビクルーの視点で描かれています。
で、その視点こそ、この作品に対する好みが分かれるポイントじゃないかなと思います。描かれているのは、事件の犯人でも被害者でも、警察でもなく、その家族でもありません。報道するテレビ局です。だから基本的に事件を外から見るだけ。「外野じゃねえかよ」と思う人や、人質に感情移入する人は共感できないかもしれません。
奇しくも先週公開された『ショウタイムセブン』に続き、メディアのあり方を問う作品を2週連続で観ました。片方は現在を舞台にした作品。もう一方は生まれる前の事件を描いたもの。断然1972年のこの映画の方が、今この時代にマッチした映画だなと思いました。
メディアのミスリードが世論や事件の結果を変えてしまう。その危険性について、僕たちは改めて考えねばならないのではないかと思いました。
日本の大手映画会社ではほとんど作られないタイプの作品だと思います。こういう作品がたくさんの人に見られて、日本でももっと作られるようになればと願います。
世界がそれを目撃した日。
映画「ゾディアック」を観たときと、非常に似た気持ち、感触。
これから観る方は、事実に基づくドキュメンタリーとして、観てほしいと思う。
-----
当時の技術、仕事ぶりの再現は、素晴らしいものがあった。
半田付けして、その場で、線をつなげちゃう。とか
写真を新たに撮影して、拡大した写真にする。とか
テロップ入れがアナログ。スロー映像もアナログ。等々
主にキャスター、レポーターに光があたるが常だが、
技術スタッフ、管理職、裏方に光があたっているのが良い。
また個人的に、音楽表現も凄いと感じた。
------
私は、恥ずかしながら、この事件を知らなかった。
鑑賞後、某国で飛行機テロが起こった際、
テレビをずっと観ていた自分のことを、ふと思い出した。
世界がそれを初めて目撃した日。
その日を境に、多くのことが変わっていく世界。その後の追及と、復讐。
この 9/5 も、きっと、そういう瞬間だったと想像する。
「生放送するべきだったか!?」という問いにも、賛否はありそうだ・・。
初めてのことをやり遂げた人々へのリスペクトが感じられない
人質事件の現場や、それを取材するテレビクルーの様子などは一切映されず、テレビ中継の調整室と、それがある建物から画面が離れることはない。
そのため、まるで、スタッフの一員になったかのような臨場感と緊迫感が味わえるし、密室での閉塞感もひしひしと伝わってきて、観ているだけで息苦しくなってくる。
それに加えて、外部との連絡手段が、トランシーバーと有線電話と電報しかなく、おまけに、ドイツ語が分かる通訳が1人だけという状況で、欲しい情報が手に入らないもどかしさと、焦燥感も追い打ちをかけてくる。
人質が処刑される瞬間を放送しても良いのかと悩んだり、テロリストに警察の情報を与えてしまっていることに気付かなかったりと、史上初めてテロを生中継することになったスタッフたちの葛藤や失敗も生々しい。
極めつけは、事件の結末に関する「誤報」で、スクープをものにするための迅速性の追求と、複数の情報源による信憑性の確認という、ジャーナリズムの永遠の課題が、ここでも胸に突き刺さってくる。
エンディングでは、登場人物たちの疲労感と暗澹たる気持ちが痛いほど実感できるのだが、その一方で、仮に、事件が無事に解決されていたならば、彼らもこれほど落ち込むことはなく、むしろ、初めてのことをやり遂げたという達成感を得たのではないかと思われる。
その点、せっかくテレビマンたちの奮闘ぶりを描いておきながら、テロの生中継のマイナス面ばかりが印象に残り、その意義や功績がほとんど感じられなかったことには、やや釈然としないものが残った。
インターネットが普及した今の時代にも通じるマスメディアの問題点を、批判的に描くのは大いに結構だが、史上初の難題に取り組んだ先人たちに対するリスペクトが、もう少しあっても良かったのではないだろうか?
【”リアル、テロ・ライブ”ミュンヘン五輪で起きたイスラエル選手人質事件を生中継するアメリカABCクルーの、視聴率か人命かを問いながら放送する臨場感が凄く、ジャーナリズムの在り方を問う重き作品。】
■1972年9月5日。西ドイツ、ミュンヘン五輪の開催中、選手村でパレスチナ武装組織”黒い九月”は、パレスチナ人テロリスト500人の解放を要求し、選手・コーチ二人を殺害し、残り9人を人質として立てこもる。
その様を、アメリカABCスポーツクルーは、世界に向け生中継するのである。
◆感想
・中継を担当したのは、報道クルーではなくスポーツクルーである。専門ではない彼らはそれでも、報道する責務と他局との視聴率争いとの狭間で揺れて行く。
・西ドイツ警察は中々機能しないし、苛苛する中、彼らはドイツ人女性スタッフを通訳にし、更にはスタッフを選手村に潜入させスクープを撮影しようとする。
■だが、スポーツクルーたちは、途中で自分達が映しているTVが、選手村の部屋でも観れることに気付き、西ドイツ警察が放送を止めようとしても、彼らは一時は放送を中断するが直ぐに再開するのである。
選手たちが、テロリストたちと空港に向かい、銃撃戦になった時に、彼らはスタッフを空港に向かわせる。
そして、選手たちが救出されたという連絡が入り歓喜するが、それがあやふやな情報だと分かり翻弄される姿が、生生しい。
<ラストは、異様に重い。結局人質は全員死亡という連絡が入るのである。本作は、ミュンヘン五輪で起きたイスラエル選手人質事件を生中継するアメリカABCクルーの、視聴率か人命かを問いながら放送する臨場感が凄く、ジャーナリズムの在り方を問う重き作品なのである。>
■尚、この事件後、イスラエルの諜報機関モサドが、パレスチナに行った苛烈なる復讐劇はスティーブン・スピルバーグ監督の逸品「ミュンヘン」で描かれている事を、敢えて記す。
リアルタイム中継放送の是非を報道する側の視点で描く
誤報(ぬか喜び)の後の結果に青ざめるアメリカABC放送の
クルー‼️たち・・・
その姿ががとても印象的でした。
人質全員解放から、人質全員死亡‼️
この落差は人命尊重する重大なスクープに暗い影を落としました。
人質の家族は、解放無事の報から、その直後には
奈落の底へ突き落とされたのですから、
《報道の重み》《報道の責任》
それは計り知れないですね。
【ストーリーは実話】
1972年9月7日(=題名)のミュンヘン・オリンピック選手村で起きた、
パレスチナの武装派集団(黒い九月)による、
イスラエル選手団の人質テロ事件。
それをアメリカABCテレビのスポーツ担当のクルーが、
寄りによって報道knowhowのないスポーツクルーによって、
衛生放送で世界に同時生中継をしてしまったのです。
視聴したのは9億人。
日本でもテレビや新聞で見聞きしましたが、リアルタイムの
衛星中継はなかったと思います(家族に確かめたのですが、)
リアルタイム中継。
①その是非と、功罪。
②ABCにあったCBSへのライバル心と焦り。
③ドイツにとっての、このオリンピックの持つ意味。
③は特に重要な気がします。
ナチスドイツに恨みを持つイスラエル人が、
ドイツで開かれる戦後初のオリンピックに参加したこと。
【平和の祭典=オリンピック】で、
イスラエル選手団の全員11名が
今度はパレスチナ人に殺されたことの意味。
人質を連れたパレスチナのテロリスト集団(黒い九月)は、
空港で人質が全員解放された・・・との偽情報が、
ドイツ側広報、ドイツ高官から流される。
その誤報の原因は、映画を観ても私には分からなかった。
❹人質のイスラエル選手の部屋では、ABC放送の映る
カラーテレビがあり、
テロリストには警察の動きが筒抜けになっていた。
・・・では何故?
❺選手村の電源をシャットアウトなかったのか?
競技の中断はすぐに終わり、またすぐにはじまったのか?
この事をABCクルーは悔いて責任を感じているが、
気づかない警察と、オリンピック事務局にも疑問を感じる。
撮影したクルーでただ1人のドイツ人として生放送に貢献した
通訳を兼ねたマリアンヌ(レオニー・ベネシュ)、
そのマリアンヌの立場も微妙だった。
イスラエルへのドイツ人として複雑な感情を込めつつ、
職場ではアメリカ人にドイツ語を訳して、
警察無線の傍受やら、そしてドイツラジオ局の情報も
同時通訳する。
(これはある意味スパイ的立場に似ている)
ABCスポーツクルーは、特に撮影責任者のジョン(ジョン・マガロ)、
そして番組責任者のスポーツ担当デスクのルーン
(ピーター・サースガード)が仕切った。
ここの2人が、事態が変わるたびに、何度も重要な決断を迫られる。
特にルーンはアメリカにいる報道スタッフにスクープを
横取りされないために、
必死で、喧嘩腰でアメリカにいる報道チームと電話でやり合う。
(実際問題としてニューヨークから来たって間に合わないのだ、
(たった一日に起こって終わった顛末なのだから、)
撮影は1972年を実に詳細に再現、
その場にいたスタッフそしてカメラマン、
機材(望遠カメラの大きさと重さ)
テレビ局のモニター画面も本当に小さくて、
覆面を被ったテロ犯は窓辺に何度となく姿を現すやら、
ドイツの警官が屋上から人質の部屋に侵入計画も、
犯人たちにバレバレだったのだ。
それほどに警察にもテレビクルーにも判断の時間が持てないほどの
スピードで進んだ奇襲作戦のテロだった気がします。
ジョンはトップを切って“人質の無事“を報道したくて、
“多分“を付ければ、良いか!?
「多分人質は全員解放された」との一報を流す。
それは瞬く間に世界中に流れる。
しかし実際には空港での地獄の銃撃戦の末に、
イスラエル選手団の11人全員と警官、パレスチナ人5人が
全部で17人が死亡したのです。
世紀の誤報・・はあっという間に塗りかえられて、しまったわけですが
ジョンの青ざめた顔、そしてABCスポーツ担当責任者のウィアーに
とっても苦渋の選択だった。
咄嗟の判断を迫られるリアルタイム放送の難しさを、
思い知らされました。
この映画を観る前に「ミュンヘン」2005年を観たのですが、
「ミュンヘン」はこの映画の「黒い九月事件」とその後、
その後のイスラエルの報復とパレスチナの報復への報復・・・に、
重きを置いた映画でした。
そしてパレスチナとイスラエルの問題は、50年後の今もなお
報復の連鎖は続いているのです。
余談ですが、調べたら1972年は私の住む「札幌冬季オリンピッ」が
2月にあって、その秋の9月がミュンヘンオリンピックだったのです。
ドイツが戦後の復興の象徴的立ち位置がミュンヘンオリンピックで、
札幌冬季オリンピックは“札幌に地下鉄が通って便利になったよー“
そんな楽しいお祭りだったのに、ミュンヘンでは今も歴史に禍根を残す、
“血塗られた平和の祭典“だったとは!!
報道する側の伝え方、倫理観を、
今改めて問いかけたい・・・
ティム・フェールバウム監督はそう語っています。
ジェフの知り得る内容で画面が展開するのだが、彼が事前に知っている情報(内部の人間関係)が語られないので、内容把握はかなり難しい
2025.2.24 字幕 イオンシネマ京都桂川
2024年のドイツ&アメリカ合作の映画(95分、G)
実際に起きたミュンヘン五輪テロ事件を放映局目線で描いた伝記映画
監督はティム・フェールバウム
脚本はモリッツ・ビンダー&ティム・フェールバウム&アレックス・デビッド
物語の舞台は、1972年9月5日のドイツのミュンヘン
五輪中継を行なっていたアメリカの放送局ABCのスポーツ局は、スポーツ運営局長のマーヴ(ベン・チャップリン)の指揮の下、管制室長のジェフ(ジョン・マガロ)を中心としたチームでライヴ中継を行なっていた
その日は男子水泳の決勝戦が行われていて、ジェフは冷静に試合を見つめ、的確なカメラワークを指示していた
そして、朝の4時40分頃、「黒い九月」のメンバーが選手村に侵入し、イスラエル選手団の宿舎へと突入した
その後、AK-47による銃撃が起こり、ABCのスタジオでは複数の人間がその音を聞くことになった
ジェフたちは事実確認を行うために各方面から情報を募ると、どうやら選手村にて何かが起こっているらしいということがわかった
その情報は即座にラジオ放送やドイツの公共放送などを通じて流れるようになり、ジェフは通訳のマリアンネ(レオニー・ベネシュ)に翻訳をさせて、事態の進展を見守った
オリンピックタワーから選手村は一望できたが、そこを移すためのカメラはなく、そこでスタジオカメラを1台外に出して撮影を試みることになった
また、現地に16ミリを持たせたカメラマンを配することになり、カメラアシスタントのゲイリー(Daniel Adeosun)、カーター(Marcus Rutherford)とマリアンネを派遣していく
マーヴは社長のルーン(ピーター・サースガード)に伺いを立てて許可をもらい、方々から情報の裏どりを始めて、他局との番組枠の争奪合戦を繰り広げていく
現場はジェフに一任され、アンカーのピーター(ベンジャミン・ウォーカー)に指示を出して原稿を読ませ、ジャック(Zinedine Souailem)はカメラワークをコントロールしていくことになった
状況が全く掴めないまま、ようやくイスラエル選手団のいる場所がわかり、その窓からテロリストたちの様子も見られるようになった
イスラエルの内相も現地に赴き、料理人のふりをして中に入ろうと試みたりするものの、なかなかうまくはいかない
そんな折、警察のサンシャイン作戦が動き出し、外壁や屋上に警察が配備されるのだが、その様子をABCのカメラが捉え、放送に乗せてしまったのである
警官隊が放送を止めるようにと乱入し放送は一時中断するものの、結局は追い返して放送を続けることになった
そして、そうこうしている内に犯人グループが移動するという情報が流れ出す
マリアンネたちも動き出し、移送するためのヘリも到着してしまう
行き先は近くの空軍基地だと推測され、スタッフもそこに向かう
だが、なかなか中の様子を捉えることができず、マリアンネの叫びだけがスタジオ内に響きわたるのである
映画は、テロをライヴ中継してしまったABCの顛末を描き、ドイツが軍隊を突入させられなかった実情などが飛び交っていく
マリアンネが超有能キャラなので何が起こっているのかが手に取るようにわかるのだが、実際にはここまではっきりしたことはわからなかったと思う
事件の概要がわからないために「テロリスト」とも呼べず、選手のふりをして選手村にスタッフを突入させるなどの無茶もやっていく
そんな中、ドイツの報道官が「人質は無事に解放された」と発したことから、ABCもそれを信じて流してしまう
だが、その言葉の端々に違和感を感じたマーヴは裏どりのない情報は流すなと忠告する
それでもルーンの命令によって、ジェフは「噂では」という言葉を付加して、アンカーに話させてしまうのである
その後、現場にいたマリアンネからの一報が入り、まだ銃撃戦が続いていることが知らされる
祝杯ムードのスタジオの空気は一変し、そして、公式的な発表として「人質は全員死亡」という事実が突きつけられるのである
映画は、ジャーナリズムの裏側を追いながら、リアルタイムに感じるような構成になっていた
実際の事件は、午前4時40分に始まり、午後11時30分頃に応援部隊が到着して、全てが終わっていたことがわかっている
人質9名、警察官1名が死亡し、犯人側はリーダーを含む5名が死亡し、3人が逃走を図った
その3人も後に逮捕されることになるが、同年10月20日に起きたルフトハンザ航空615便ハイジャック事件にて解放されている
また、オリンピック自体は、9月6日の午前10時に再開し、中断していたのはわずか34時間だった
いずれにせよ、約18時間ほどの出来事なのだが、ほぼリアルタイムに感じられるほどに濃厚な凝縮がなされていた
無駄なシーンもほとんどないのだが、あまり説明がないので、放送局内部の人間関係というものがほとんどわからないまま話が進んでいく
なんとなく雰囲気で掴んでいくしかないのだが、この内容ならパンフレットを作って解説してくれないと厳しい
あの現場には約15人ほどいて、1カメにピーター、2カメにジム・マッケイが別スタジオでゲストを招いて放送を切り替えていたが、それ以上を把握するのは難しい
また、外に出たマリアンネたちを追う映像がなく、ジェフを中心として、外の音と見える範囲の映像だけを使っている
俯瞰するショットがほぼゼロなので、それが没入感を生んでいるのだが、画面が暗く、かなり疲れる映画なので、覚悟して臨んだ方が良い作品であると思う
まあまあだった
ミュンヘンオリンピックの事件を報道するテレビ局のお話で、ほぼスタジオの調整室内で物語が進む。調整室がやたらと薄暗くて閉塞感がずっと続く。短いわりに退屈で眠くなる。『ミュンヘン』などを見てなかったらあんまり意味が分からないかもしれない。衛星中継のテレビの放送枠を局どうしで交換したり奪い合うのがどういうことなのだろう。ABCでずっと放送しないのだろうか。
人質のことを本気で心配する人たちばかりなのも違和感がある。もし自分があそこにいたら、もちろん死ねばいいとは思わないし、助かって欲しいとは思うけどあそこまで親身になれない。所詮他人ごとだ。家族か友達、知人でもなければあんな気持ちにならない。全員が悲痛な面持ちで、一人くらいオレみたいな人物がいないものだろうか。
1972年に本当に撮影しているかのような表現がすごい。
放送は二度と同じではなくなった。
まだテロが始まっていない時、ABCスポーツのチーフプロデューサーは、競技での勝者ではなく敗者を先に写すように指示をする... これはモチーフとしての意味なのか?
そしてその事の回答のメタファーがドイツ人臨時通訳に対しての言葉なのかもしれない。この話は、ドイツのチーフプロデューサーが会見で述べた言葉に対して放送責任者ベーダーに彼女が説明しているシーンより。
Gipa: He's saying that the games are an opportunity to
welcome the world to a new Germany to move on
from the past.
Bader: Yeah, sure.
Gipa: I mean it's what we all hope for, but as can we do,
but move on. Try to be better.
Bader: Are your parents still around?
Gipa: Yes.
Bader: Let me guess. They didn't know either, right?
Gipa: But I'm not them.
Bader: No, no, you're, you're not. I'm sorry.
I'm Marvin Bader.
当時、駆け出しで未熟だったプロデューサー・ジェフリー・メイソンはプッシュ式の電話の幕開けと共に世界的テロリズム、開催国の躍進と不安定さ、CBSとの衛星放送権の争いと衝突、そこには、ただ単に自尊心を含んだ報道の取り組み方を映像化している... それは以下のセリフより
テロ行為が目の前で起こっている緊張が張り詰めているスポーツクルーに電話口でニュース班からこんな事を言われている。
No offense guys, but you're Sports. You're in way over
your head. News should take over.
ABCスポーツの社長ルーン・アーリッジがそれに対して、クルーにゲキを飛ばす(※彼は後にABCニュースの社長に就任している。)
Okay, look, I know this isn't a responsibility that everyone wants.
But does it make more sense to have a talking head from News
take over from halfway across the fuc*ing world? Our job is to tell
the stories of these individuals, whose lives are at stake, 100 yards
away. And our job is really straightforward. We put the camera in
the right place, and we follow the story as it unfolds in real time.
News can tell us what it all meant after it's over. And I'm sure they're
gonna try. But this is our story. And we're keeping it.
もちろん、この前半のセリフで見ている側にも緊張感が伝わってくる。来るが、この作品『セプテンバー5』が今この瞬間にぞっとするような衝撃をもたらしているとは思わないし、言えない。それはサブ・コントロール・ルームというワンシチュエーションであり、時代が半世紀前の事でもあり、現実味がなく、そこには隔たりが第四の壁のように強く意識させ悲しいことに常に存在するイスラエルとパレスチナの緊張をアナログ的に思い出させるものと個人的には捉えているために... だから決してそれに対する過剰な反応は起きやしない。
2年前のハマスの襲撃が起こったとき、この映画はポストプロダクション中だったそうで、いずれにせよ、この映画のメインプロットは襲撃やそれに対する治安部隊の対応や制圧、あるいは襲撃が何故、起こった理由などを表してはいない。つまり『セプテンバー5』は主に、襲撃がどのように報道されたかについて焦点を当てている。
Bader: Black September, they know the whole world
is watching. If- I'm saying if- they kill a hostage
on live television, whose story is it? Is it ours, or
is it theirs?
ドキュメンタリー風映画が「真実の映画」との差とはどのようなものなのか?
アーカイブス映像と撮影された映像をシームレスに繋ぎ合わせることで映画から虚構上のトリックを排除し インタビューや録音の肉声などを多用するのことで、作り手の存在を意識させるとともに、ダイナミズムを感じさせないカメラワーク、編集技術 、当時のプッシュ式電話や持ち運びの不便なカメラなどの小道具などと組み合わせて、プレッシャーにさらされているニュースルームの混乱を強調するはずが、 16 mm スタイル映像が落ち着いて見えさえする。従来のニュースルームのドラマのような言葉による派手さは排除され、その慎重なセットアップによるペース配分が、リアルタイムでの意思決定の断片化と不確実性が強調されたことで、より真実味が生み出されそうに見えたが...しかしながら
機械のボタンのように、意識的または無意識的に、道徳や感情を簡単にオン・オフにすることもできないのは、そのような事が映画に限らず芸術において非政治的産物ではないと言い切れる夢遊病者が抱く幻想なのかもしれない。だから本作のような映画はこうした概念が真実味を見失ったために空虚化を招いている。
先ほど登場した Gipa こと雑用係のような通訳のマリアンヌがこのように語っている。
No... Innocent people died in Germany again. We failed.
Germany failed.
(※ "again" この言葉が何時の事を指しているのかで作品の重みが変わってくる。この言葉を発したマリアンヌを演じた女優さんは非常に評価が高い。)
3大ネットワーク、全盛時代。視聴率や宣伝効果というお下劣な勝者がいるとするなら... 多くの方が犠牲になっているのを知ったうえで、 その事を踏まえて不謹慎でもいえるのは、勝者は彼らパレスチナ武装組織「黒い九月」なのかもしれない!?
全33件中、21~33件目を表示