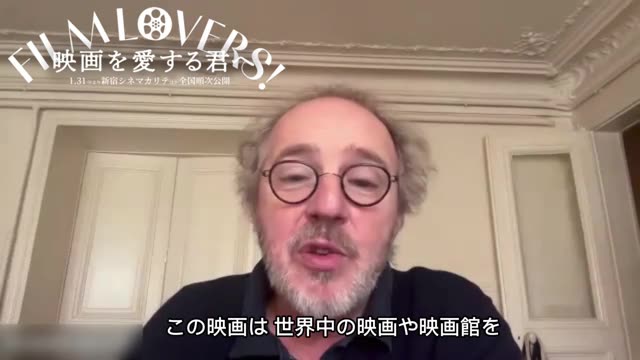映画を愛する君へのレビュー・感想・評価
全5件を表示
監督が大学の講義で学んだという観客の視点の話しは面白かった
監督の自伝的シネマエッセイ。
期待もしていなかったけれど、全体としてはあまり面白くなかったです。
監督が大学の講義で学んだという「舞台劇の観客の視点」、「映画の観客の視点」「テレビの観客の視点」についての捉え方は面白かった。
今なら、「web配信の観客の視点」を新たに加えるべきかもしれません。
タイトルなし(ネタバレ)
デプレシャン監督の分身ともいうべきポール・デダリュス。
6歳の時(ルイ・バーマン)、祖母に連れられて初めて映画館で観たのは『ファントマ危機脱出』。
テレビではヒッチコック監督の『白い恐怖』なんかを観ていた。
14歳の時(ミロ・マシャド・グラネール)には年齢を偽って、イングマール・ベルイマン監督の『叫びとささやき』を観に遠征した。
学生時代には自主上映会を開く。
映画はチェコのヴェラ・ヒティロヴァ監督『ひなぎく』。
文献で知っただけで観たことはない。
同胞の学生たちはチェコがどこにあるか、名前すら知らなかった。
大学生(サム・シェムール)になって、映画と演劇の違いを大学で学び、ガールフレンドの友だちと寝たこともある。
30歳(サリフ・シセ)、『大人は判ってくれない』を観て至福の時を過ごし、映画監督になることを決意する・・・
といった物語。
先に挙げた映画のほかにも『ヨーロッパ一九五一年』『SHOAH/ショア』など数十の映画の引用とモノローグでもって、青春時代を再現していくさまはドキュメンタリーと言ってもいいかも。
特に『SHOAH/ショア』に関するエピソードは、現在の時制で本人も出演しているので、ほぼほぼドキュメンタリー。
ある種の映画論のような映画でもある。
観ながら思い出したのは、次のような大林宣彦監督の言。
映画は1秒24コマの動かない画がスクリーンに連続して映し出されます。
それを観て「動いている」と錯覚するものだけど、コマとコマの間はシャッターで閉じています。
シャッターが閉じている間、スクリーンに映し出されているのは暗闇で、暗闇を観ているとも言えます。
暗闇を観ている間は、目を瞑って、自分自身の思いを観ているとも言えるでしょう。
と、まさに、本作を観ながら、わたし自身のことを思い出し、自分自身を観ていたような気がします。
ただし、引用されている映画のうち、先に挙げた重要作品(デプレシャンを形づくった映画)のことを観ているか知っていないと、本作は、たぶん眠くなるはず。
わたし的には、半分ぐらいはわかったので、そんなことはならなかったですが。
なお、エッセイ映画なので、デプレシャン監督作品にしてはとても短い90分ほどの尺です。
業界全体史と個別体験史の融合
映画の草創期から歴代の代表作品を取り上げながら、監督自身の幼少期からの関わりをもドラマ化して混入させ、結末には自分自身の分身を登場させる一方で、自分自身も別役で登場している。著作権処理はどうしているのか気になった。
劇場は居場所。
祖母に連れて行ってもらった映画館、…で観る映画は格別だと知った6歳少年ポール(アルノー…)の話。
劇場で観た映画を機に、映画にのめり込み、映画部、評論家、映画監督に転身する本作監督アルノー・デプレシャンの自伝的作品。
アルノー・デプレシャン監督をポールという名の役名で見せ…、本作観てて嬉しかったのは映画好きと変わらないスタンス、基本1人映画、座る場所は決まってる、好きな作品は2度、3度と観て作品を解ろうとするなど。
レビューサイトでレビューする方は基本観る専だと思うけれど、監督ならではの目線、カット割り?!撮るシーンのアングル、拘りを作品を観ながら、この撮り方は考えられたとか…、流石にそこまで考えて作品は観ませんしね私は。
ただ子供から大人へと行き来する見せ方がちょっと分かりにくかったかも。本作のタイトル「映画を愛する君へ」ってタイトルは120点!このタイトルに惹かれ観に行った!
映画としてどうなのか
レビュー評価が高いのを見ていたせいか、観る前にハードルを上げてしまっていたようです。面白くなかったわけではないですが、観終わっても「1本の映画を観た」という印象がなく、ふわっとした感想しか湧きませんでした。完全なドキュメンタリーではなく、かといって監督の人生をドラマチックに映画化したわけでもない。そこがどっちつかずになった感じがしました。
前半の、映画誕生や、映画を観る異議、映画館自体をテーマに様々な意見をインタビュー等で取り上げて紹介するパートは非常に興味をそそられました。中でも、大阪のミニシアター「シネヌーヴォ」の看板や館内が唐突に映ったところは驚きました。監督の若かりし頃を再現するようなパートも、それなりに興味深かったです。モテモテ自慢したかったただけみたいなシーンもありましたが。ただ、通常の映画とは異なって、後半にクライマックスがあるわけではなく、マチュー・アマルリックの登場シーンがそれにあたるのかな、と思わせる程度で、最後のほうは睡魔と戦いながら観ていました。
そもそもこういう構成の映画だから、こんな指摘をするのは的外れかもしれませんが、正直もの足りなさを感じたことは否めません。「映画1本観た」という感覚がほとんどなかったので、そのまま「リアルペイン」を観に行きました。
全5件を表示