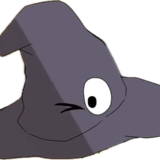お坊さまと鉄砲のレビュー・感想・評価
全89件中、21~40件目を表示
2006ブータン王国は改革の時を迎えた。しかし国民は民主制を知らない。
与えられた民主主義
チベット仏教への信仰厚い、「幸せな」人々。
政府が民主主義を持ち込み、選挙なんか導入するもんだから、仲良く暮らしていた人々に対立が生まれる。「私達は今までもずっと幸せだったわ」と言う主婦の言葉は、ここに住む多くの人たちの代弁のよう。
こんな人達を敢えて近代化する必要があるのか、とも思うけど、世の中は甘くない。
ネイティブアメリカンとか、アボリジニとか、自分たちのペースで満足して生きていたであろう人々が、外から突然入ってきた知識と技術と武器を持った野蛮なこすっからい人々に騙され迫害され、生きてきた土地を追われ生きる術を奪われる理不尽は、歴史上たくさんある。
国内でも全員がチベット仏教への信仰に沿って善きように生きて、善き国王の善政に従う人々なら良いが、外部からの刺激はすでに一部に浸透していて、何も知らない善き人々を食い物にする者共が出てくることに、国民自らが身を守る知識が必要にもなってくる。
国の近代化は、生き残りのためには必須のよう。
なので国王はまずは自ら退位して国を民主化、国民の近代化を図る。さすが民に慕われる人物だ。
「幸せ」なのは「知らないから」という側面があって、ここの生活が貧しいとか不便だとか、相対的なことは他を知らなければ分からないので満足していられることもある。権利も、あることを知らなければ、そういうもの、と思うのでは。
全員が「知る」ことで困るのは、知らない人々の上でいい思いをしてきた、既得権のある人々でもある。
ウラの人たちが民主主義や選挙に困惑するのは、それが自分たちが希望して得たものではないからというのが大きいでしょう。
他にも、やはり民主主義を上から「与えられた」国を知っている。
「与えられた」当初は戸惑っただろうが、あっという間にそれがどれほど国民ひとりひとりを守るものであったかわかるようになったと思う。
そういうものではないでしょうか。
ブータンは今、どのように進めば良いのか模索している、とエンドタイトルに出ていた。
基本的にほのぼの笑える映画だが、困惑する様をちょっと面白く描くのみで、押し付けられた民主主義の皮肉を露悪的に見せているわけでもないのが良かったです。
銃が必要だったのは、平和を祈るためだという理由にぐっと来ました。
本当は全世界の人たちがこんな気持で生きていけたら良いのですけどね。
幻の高価なビンテージ銃を目の前で埋められ、大枚はたいてインドから取り寄せたでかいAK-47を2丁もお供えしたコレクターは可愛そうだけど、逮捕されたり命取られたりよりマシ。あの返礼品は、持って帰れないよね。
選挙の仕方を教えるのに、他の陣営と対立せよ、までするってどうなの❓
銃を担いだ物騒な仏僧とか、お坊さまの説法、じゃなく鉄砲、とかしょーもない日本語のダジャレが浮かんで来て脳内で脱力しました。
目にも心にもやさしい映画
黄金色の麦畑ではじまり、ピンク色の蕎麦畑で終わる、目にも心にもやさしい映画。
「お坊さまが、何故鉄砲を?」という問いに最後まで惹きつけられ、その理由がわかった時に、何とも言えない世界観の広がりと感動を覚えた。
脚本のスマートさと共に、構図や色の美しさを大切にしたカメラワークも好き。
考えさせられたことを一つ。
近代化や民主化といった世界共通の価値観と、仏教を根底においたブータンならではの伝統文化の対比が描かれたことで、自分が間違いなく正しいと思っていることは、本当の意味で、端から端まで正しいことなのだろうかということ。
「民主化」も、選挙の意味も、近代化も、情報機器等をはじめとしたテクノロジーも…。
鉄砲の代わりが、「鉄砲」だったところは爆笑でした。
幸せってなんだろうなあ
民主主義を知らない国での初選挙の話。
模擬選挙で、主張の違う相手と憎みあえと煽る役人。
選挙の後の未来(支援後の見返り)を信じ、村の大勢とは違う候補を強く推して周囲から浮く男。
男が選挙にのめりこみ、母や村人との心理的解離や疎外感を感じ、選挙なんてないときのほうが幸せだったと言う妻。また妻は役人に、命がけで私たちが選挙権をもとめなかったのは、私たちにそれが必要なかったからだと言う。
ラマの弟子であるタシ師は、仏陀の教えでないなら、なぜ民主制が善であるとわかるのか、と、どこまでもフラットに役人たちに問う。
全編に渡って、それぞれの登場人物の求める幸せや思惑が語られるなか、幸せってなんだろうなあとずっと考えてしまった。
役人や警察などは仕事を達成することが幸せ(目標)で、男は子供の未来のために特定候補が勝って見返りをしてくれる(と見込んでいる)ことが幸せで、妻は選挙なんかしなくても家族が仲良くいたときが幸せだったと言う。
少しずつ、または全く掠りもしないそれぞれの幸せを彼らは思い描いている。
これまでに聞いたこともないやり方(選挙や近代化)で、これから彼らは「幸せ」を擦り合わせなくちゃならない。そして、彼らが今求める幸せは、彼ら自身にとって、本当に善の結果になるのかすらわからない。なぜなら、既知の過去からしか幸せは思い描けないから。
村の中で、家族が仲良くうまくやっていっても1ヶ月に一度のご馳走だけが楽しみの生活以外の生き方があるかもしれない。
でも、外からどう見えようが、彼らが幸せかどうかも彼ら自身にしかわからない。
主義主張が違っても、一見愚かしくても、それぞれの幸せを暴力や争いによることなく、擦り合わせていくしかないんだろうなぁ。望んだ幸せにならなくても。
最後にロンが手に入れたのも、暗喩としては同じものでもあるし。
真っ赤な(ティン)ポー
世界一幸せな国ブータン。オールバックヘアスタイルの若い国王はジョニー大倉にアントニオ猪木を足して割ったような感じ。お妃がめちゃくちゃ美人。そりゃ、国王は幸せに決まってる😎
チベット仏教を国教とする唯一の国(チベットが中国に侵略されたため)。ラマ(高僧)を敬う信心深い国民性。国会も選挙もなくても幸せだった。
それが、国王の判断·決定で近代化を目指し、議会制民主主義を取り入れた立憲君主制になった。一度も選挙の経験がない国民に対して選挙委員が模擬選挙を行うこととなった。しかし、小さな村に対立候補をめぐる諍いの芽が生じ、かえって庶民の幸福度は下がってしまうことに。
ラジオで選挙委員会の女性が村に来ることを知った村の高僧は弟子の僧侶に模擬選挙が行われる満月の日までに銃を2丁用意するように命じる。「世界を正すため」とだけ弟子に言う。
その頃、観光立国ブータンの観光案内人の男は病弱な妻に内緒でアメリカ人の銃収集マニアの男を空港に迎えに行っていた。インド以外とは厳しい入国制限をしているブータンでは観光以外の商取引目的の外国人の入国に警察は目を光らせる。
ある老人の家にねむっていた一丁の鉄砲の情報を探り当てた案内人。アメリカ人によれば、その鉄砲は南北戦争時に使われた超ビンテージ物で、マニアの男は350万ニュルタム(=インド・ルピー)出すというが、老人はそんな高額は受け取れないという。チベット仏教の教えにより欲が無く、慎ましく、清貧な暮らしをしているブータン人の人柄がよく出ている微笑ましいシーン。金を用意して次の日に再訪したが、老人は一足先に訪ねて来た若い僧侶にラマへの供物として銃を渡してしまったあとだった。信仰のためとあらば、私利私欲を投げうつ国民。
悪い官僚もいるには違いないのだが。
公開写真の一つの右端に何やら赤く塗装された先の丸い、エラのついた道祖神型のロケットランチャーを抱えた爺さんがいるのがとても気になっていたが、やはり最重要アイテムだった。
ポーと言うらしい。玄関の両脇に2本置いてある家もあるそうだ。魔除けの御守りの意味があるそうだ。
高僧が2丁といったのは、儀式には二本の対で一式のアイテムとして用いようとしたからではなかろうか。
ホントは高僧がいつランボーに変身するのか待っていた😅
アメリカに対するキョーレツな皮肉は(アジア人として)とてもスカッとしたし、なるほどと思った。さすが高僧。
ブータンに行って、ポーのお土産を一対買って帰り、玄関に飾りたいが、酸素が薄いからどうしょうかと迷っている。
とりあえず、1本ならあるにはあるが、2本ないとだめなのだよ。
ブータン・ヌーボ
ブータン映画と言っても、後にも先にも同じ監督の「ブータン山の教室」しか見たことがないので、ほかにどのような作品が作られているのか、全体像はわからない。人口80万人ほどの国で年間何本ぐらい公開されているのだろうか。この2本の映画を見る限り、私たちがイメージするブータンという国そのままの世界が描かれるが、この国の人々にとっては当たり前なわけで、彼らのためにはおそらくもっと違うジャンルの映画も作られているのだろう。
銃を調達するように指示する僧侶の意図がなかなか読めないので、最終的に何が待ち受けているのだろうと終始不安な気持ちのまま物語の展開を見守らざるを得ない。銃の入手に奔走する若い僧と模擬選挙の準備が並行して描かれ、満月の日を迎える(結末は納得の行くものであったが)。
王制から共和制への移行と言えば血なまぐさい政変を想定しがちだが、国王自ら施政権を手放すというのは奇特な例に違いない。ただ、民主主義の導入がかえって争いを産むという、劇中で提示された課題の答えは出ていないように思える。
田縣神社の神輿のようなファリック・シンボルも登場するが、あれはブータンの習俗に実在するのだろうか。
これは傑作!
穏やかなブータンの大自然と共に語られる幸福論。
不穏な空気を残しながらクスクスと笑え、最後はホロリとする絶妙なバランス。
ゆったりとしているが飽きない映画だった。
他のレビューにもあるように幸福とは何かを考えさせられた。
豊かさを追求する日本とは全く違う、贅沢とは言えない暮らし。
それでいて、こんな人生が良かったなと羨望を抱くほど、ブータンの人々は満たされている。
しかしきっと、ブータンの人々が感じている幸せや充足感は、志し次第で日本でも得られるものなのだろう。
金を得たいと思う気持ちも、結局は他者から優れていると認められたいという承認欲求に過ぎない。
周りに流されず、己の価値観を大切にしたいと改めて思わせてくれた。
ブータン国民の安寧と幸福がこれからも永遠に続くよう祈る。
ブータンで以前、選挙を初めてすることになった時の物語。 村の人々は...
ブータンで以前、選挙を初めてすることになった時の物語。
村の人々は、選挙の経験がなく戸惑い、騒動やら仲違いが生じ。
若い僧侶は、高僧から依頼され、銃を手に入れてきてほしいと。
一方で、希少な銃があると噂を嗅ぎ付けた、米国人の収集家も来て。
その収集家を手配追跡している警察の方々までも。
それぞれの願い・思惑・欲望などが絡まったりすれ違ったりして、
本来のどかなはずの村が、慣れない騒動の渦中になってしまう様子。
しばらくは、ドタバタ戸惑いの渦中の物語でしたが。
終盤になるにつれて、人々の穏やかな本質が出たような、とても愛らしい物語にまとまっていました。
チベット仏教の考え方…まずは人に授けること、皆がそうすれば、自然と巡り巡って、自らにも授りものがある…のようなものが、村人の言動ににじみ出ていて。
平日なのに賑わった映画館(2025-01-07火曜午後)
終盤は笑い声があちこちから聞こえてくる、和やかな場。
よき癒しの、鑑賞体験でした。
民主主義とは個人の豊かさである故のお供え物
2025年劇場鑑賞1本目 秀作 69点
公開当初から好評で、ブータンの歴史や文化に触れられる良い機会だと思い、24年年末から新年1本目に鑑賞予定を立てる
作品全体の輪郭が終始脇をくすぐられている様なユーモアがあり、世界中の誰がみてもその心地よさに好感を抱く作りである
鉄砲の取引をする異国の人と通訳とおじぃさんの会話や、お坊さんに頼まれて取引締結の前に鉄砲を強奪し、それを耳にした異国の人と通訳が追跡して、山頂あたりで新たに取引を始める会話、物語終盤の選挙後の上記二人の集団に抗えず、目論みが果たせずやるせない挙動、登場する警察や贈呈されるシンボル(?)の真剣なコメディなど、至る所に前述したユーモアが楽しい気持ちにさせる
民主主義に移行が決まり選挙を開催すると報道された初動で、弟子(?)に鉄砲を満月の日までに用意せよと告げるのが、個人の豊かさ、もっというと個人の声や言葉を尊重する国家になる上で、それまでその声や言葉を問答無用で捻り潰す暴力の象徴である鉄砲を、これからを生きる国民の地深くに埋めるという動作を集いの場で行うことを早くに企んだ先見の明が、物語を引っ張るドラマやコメディのアイテムとしても、象徴としての説得力としても秀逸でした
是非
民主主義と格差社会と幸福と・・・
2024年の大晦日の夕方にとても素敵な作品に出逢えました。
この年、最初に見た映画が『PERFECT DAYS』で、最後がこの『お坊さまと鉄砲』・・・。
全然タイプの違う作品ではあるものの、[幸福]についてヒントを与えてくれたという意味では共通項を見出せるところがあったかもしれません。
同監督の前作『ブータン 山の教室』を事前に見て惹き込まれたことがきっかけで、迷うことなく映画館に足を運びました。
選挙と鉄砲・・・?
(日本では一般的に考えられない)とても物騒なモノ(鉄砲)が出てきますが、「そっか・・・、こういう使われ方なのか・・・」と、共感しながら納得しちゃいます。
人間にとって[自己肯定感]と[他者貢献]、この両輪さえ回せるのであれば選挙も必要なく、戦争だって起こりえないのかもしれません。
道祖神のモチーフが出てくるシーンには思わず「フフッ・・・」と微笑んでしまいました。
人工的に作られた豊かさではないところに[幸福]が育まれるのでしょうね。
改めてそんなことを思わせてくれた作品です。
ピュアさと無欲さ
お坊さま、さすがです!
幸福に暮らすとはどのような事なのか、この映画を観て考える事が出来ました。
物欲が満たされることや、特に必要としていないのに選挙権を行使することは、大切なことだと教育されるのは、毎日笑って生活するのに本当に必要なことなのか。
みんな武器を捨てて平和に笑って暮らせればいいのにという願いが、穏やかに伝わってくる、心がキレイになる映画でした。
高僧の小粋な企みに乾杯
キアロスタミの時間や空気を感じる。圧倒的に新しい空間と時間。僧侶と...
キアロスタミの時間や空気を感じる。圧倒的に新しい空間と時間。僧侶とて、保守的で男根が出てくるなど、何も希望があるわけではない。ただそこには争いを諌める象徴的な技術、知恵があり、それはまだこの国に生きている。選挙広報に力を入れる政府女性や、無批判的にアメリカ民主主義に期待する補佐、007のテレビを見に来る民衆。このあと、簡単に収まるわけではないだろうけれど、今のところ、移行はうまくいってるとのことである。
お金よりも大事なもの
国王の退位により立憲君主制へと移行することになったブータン。模擬選挙が実施されることを知った僧侶は次の満月までに銃を2丁用意して欲しいと弟子に頼むが…。
銃を巡る展開はなんとも滑稽で、初めての選挙に戸惑う人々、豊かな自然などブータンの魅力が詰まった作品でした。
なぜ、銃が2丁必要なのか?と思っていたのですが銃を向け合う同士ということで2丁だったのかな…と勝手に解釈しました。
近年ブータンは色々と変化を遂げてきている訳ですが、この国が持つ心の幸せを重要視する様が滲み出ていて、銃を必要とした理由が判明する僧侶の言葉にはジーーンとしました。
年明けの1本目が本作で良かったと感じた今日この頃です。
ファンタジー❓
映画の日、元旦、新宿武蔵野館の午後でほぼ満席。王政から民主化へ田舎の小さな村を舞台に模擬選挙が開かれる事になるが、何故か瞑想中の高僧が修行をやめ銃を持って来いと弟子に命じるが。ブータンの知識が国力や国民生活を国民幸福度で計る小国と言うぐらいしか知らず、それって貧しさを誤魔化してユートピアみたいに見せているだけ❓と穿って見てしまうけど。
ストーリーはドタバタでもなくニヤリとするぐらいで、アメリカを皮肉り物欲を否定するスピリチュアルさがどうも気になってしまった。
でも、高僧が銃を欲しがる意味がラスト近くでわかるのは上手く、しかも弟子の僧が欲しがる銃が007慰めの報酬❗️世界一有名な銃、自由戦士の銃、カラシニコフ❗️
見終わり、ナイフまで仏塔に埋めていたけど、やり過ぎだよ。
全89件中、21~40件目を表示