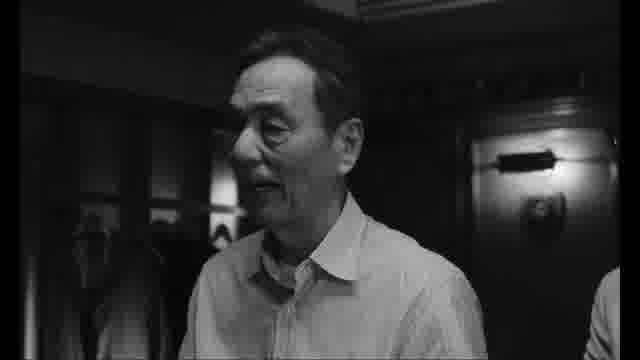敵のレビュー・感想・評価
全363件中、61~80件目を表示
自分で意味づけができる作品
予告でとても気になったので見てみました。
予告で予想していた通りの内容で自分としてはとても良かったと思います。
前半の長塚京三さんが朝起きてごはん作って食べて歯磨きしてコーヒーの豆を挽いてコーヒーを飲む、スーパーで買い物をする、昼飯や夕食を作るというこのルーティンをセリフもなくモノクロ映像で淡々と映し出すところはなんだか不思議にずっと見ていられるものでした。長塚さんがすごく細くて背が高い感じがなんとなく松重豊さんに通じるものがあり飯を淡々と食う姿が孤独のグルメの吾郎さんにも見えたり、その出てくる飯がなんだかすごく美味しそうに見えたり飯テロ要素もある作品です。
そんな中、徐々に切り替わっていき、いつのまにか見ているこちらも飲み込まれている後半の世界観については見る側の想像力が求められると感じました。
あくまで私が感じたいくつかの点を書かせていただきますが「敵」という存在を意識し出して非現実な夢を見るようになってくくだりは、あのゆっくり流れていくような毎日が夏休みな感じの生活の中で先生は日常に何かしらの刺激を求めていたのではないだろうかと思います。その心境の現れがあの夢なのかなと。一見、真面目そうに見えるが作中の様子や会話で見えてくる先生の変態性がありました。あの年の老人の独居の人にしては老いを感じないような几帳面さ、近所を双眼鏡で覗きをしたりする面、真摯に振る舞いながら女の子や教え子の女性に下心を持つ面、そう思っていながら紳士ぶるけど実は想像しながら1人でしていることを夢で白状してみたり。
このような感じからあの非現実さは先生の中に何かしらの刺激を求めていたのだろうなと思いました。
もう一つ考えられるのは認知でボケが入ってきてその妄想を映し出していたのか。作中でも非現実な世界がクライマックスを迎えて、そこから日常に戻ったらすぐポックリ逝っちゃったので。
あとは犬のうんこのじいさん、あの人も認知が入ってきていてボケていて自分でうんこをあそこにしてそれをあの女性のせいだと思い込んでいたのかなとか思いました。
ラストシーンの双眼鏡に映っていたのは誰なのかマジでなんなのかはわかりませんでしたが
とにかく後半は意味がわからない分、様々な考察ができるような作品になっていると思います。
私もこの作品を見た他の方がどのように感じたのかを少し見てみたいと思います。
なんだか良くワカリマセン
認知機能不全症一歩手前の高齢者が、孤独死までの晩年の日常生活と
幻想を映像化したドキュメントテイストなドラマ、で合っているのかなあ?
それを見たからって何て事もないわけで、怖い夢を見たので映像もホラーに
なったり、サスペンスになったり、セクシービデオになったり、でも非現実だよね。
で、最後どうなるのか、一応期待して待ってましたが、これがもう???なんです。
ラストシーンのあの一瞬に見えたのは誰だったのか? 死んだ筈の誰か?
そして、エンドタイトルの終わりで音楽がフェードアウトする中、聞こえてくる
生活音(水廻り、台所?)は何の意味があるのか???
これは、観客各々が勝手に想像するしかないのでしょうか?
こういうハッキリしない作品は嫌いなんですよ・・
長塚さんのファンなので期待しましたが、原作を知らないのが裏目に出て
理解できずに終わりました・・( 一一)
仕方が無いので、原作を買って読む事にします・・
還暦目前の鑑賞者の感想
自身還暦を前にして老いの問題が自分事になっているところで本作を観れば、孤独や痴呆やこれからの過ごし方につき考えさせられるところは少なくなかった。 感受性は老いても衰えさせたくないと思ってはいるものの、環境や病がコントロールしたくてもできないのであるから、衰えをどれぐらい許容すれば苦しまなくて済むのだろうか、などとと自問したくもなる。
映画としては、モノクロの選択は良かったと思ったがそれこそ老いが理由なのか、画面が少し眩しく感じられてキツかった。一緒に観ていた同年代の妻も同じ感想だった。劇場には自分と同年代、そして少し年配の方が多かった。老いをテーマにした作品への世の中の関心の高さがうかがえた。
これも老いのせいなのか、最後のシーンが捉えられなかった。最後に映ったのはだれ(何)で、そのカットに含ませたかった意味は? 私を含め結構な老いた鑑賞者は動体視力の衰えゆえ捉えられなかったかも知れません。
でも興味深く観ることはできました。
敵とは…
77歳の方に世界がどう見えるかにスポットを当て、白黒の情景にしたり、極力BGMを抑えているようでした。
敵=死に対して怯えたり、先に生き別れた方のことを考えたり、過去へ後悔したり…
そして、敵が近づいてきた時には逃げ、向き合う決心をして、受け入れる…そんなことを感じました。
どんなに年齢を重ねても、死というのは近づいてくるまで怖いものなんですね…
私も年齢を重ねること、死ぬこと、怖いです…
時間をおいてまた鑑賞したい映画
これは観るときの年齢によって解釈が大きく変わりそうな作品。
カメラは通常客観的な視点で映すが、この映画に映し出される映像は主人公の主観。夢を白黒で見る人がいると聞くが、これはそんな主人公が見た夢(混濁した意識?)なのかしらとも思えた。
Xデーを決めて生きる主人公。しかし普通の人間に、日めくりの様に薄くなっていく自分の人生を見つめながら冷静に生きられるものだろうか。もし出来たとして、不用意に大金を失い大幅にXデーが前倒しになるような事態を受け入れられるだろうか。
そんな事を考えていると、Xデーを決めるという行為自体に生への執着を感じる。そして、それが性への執着とも重なる所に妙な納得感がある。
本音と建前、認知と非認知、客観と主観のギャップ、時間による変化。様々なことから生まれた矛盾に責め立てられる。その姿はセクハラという言葉の広がりに恐怖した当時の男達の姿を思い出させる。
そんなドタバタの末に主人公が口にした「春が来たら皆に会いたい」と言う一言。これがパンドラの箱から最後に出た希望の様に感じたのは楽天的すぎるだろうか。
それにしても、自分で作った自分らしさという体裁の中で悶えた男の遺言が何とも押し付けがましい内容だったところに、人というものの度し難い独善性が現れているようにも思えた。
…
焼鳥とハムエッグがとても美味しそうに見えた。お蕎麦、胡麻はすり鉢であてるが山葵はチューブを使うところに、生活臭のあるリアリティを感じた。
…
最後、遺言を開封した後のシーンはどう言うことなのか、残念ながら自分には理解が追いつかなかった。
生活が若干乱れていくのが妙にリアル
元大学教授のお年寄りが一人暮らしする姿が描かれる序盤。炊事、洗濯、掃除をキチンと行う姿に悲壮感はない。むしろ美しく見えるくらいだ。教え子たちに慕われているのも大事な要素。教え子とは言え美しい女性と自宅で2人で食事できるだけで、相当な上級老人と言える。こうしたシーンが淡々と進むのだが、長まわしが少ないからなのか、不思議と退屈はしない。
さぁ、敵はいつ出てくると思っていたが、意外と出てこない。敵が襲ってくるという妄想だけでなく、様々な妄想が登場する流れだった。お年寄りだし、これはもうアレだよなと思っていたが、はっきりと認知症とわかるつくりにはしていないところがニクい。それでも、カップ麺をすするようになったり、服装が若干ラフになったり、儀助の生活が若干乱れていくのが妙にリアルだった。
最後まで観ると、バーで出会う大学生や教え子の女性でさえ妄想だったのかと思うほど、何が本当のことだったのかがわからないつくりになっていた。最後もよくわからない終わり方だったし。でも、観終わった印象は悪くない。これから自分にも似たようなことが起きうると想像すると本当に怖い。そう感じる映画だった。皆、老いであったり認知症に対しては恐怖しか感じないのだろう。だから、年寄りが主人公の物語はこんな怖い話になりがちだ。もう少し穏やかでハッピーな物語が増えてもいい。
死に際がSFチックすぎて残念
深く考えさせられる
とりあえず観た直後の感想としては、とにかく面白かった😂どこまでが現実でどこからが夢なのか、想像なのか?わからないが、そこは重要では無い気がする。その事を考えてると、まてよ?でもそーゆー事は?えっ?って事は?…とどんどん考えが膨らむ。きっとそーゆー事だろう。主人公は自分の死に際を考えて視野に入れて生活をしている。そんな時に彼の頭に浮かぶのはいったいなんなのだろうか?そして、敵とはいったいなんだったのか?考えれば考えるほど……🤔謎は深まるばかり。ただ、1つ思ったのは、この話は自分にも言えることで、自分自身も過去を振り返ると負い目や後悔、過ちを繰り返してるわけで、今後の人生どうして生きていこうかなと考えてしまった…まだ早いが自分が歳を重ねた時に死に際どうするのかと思う時がくるのかもしれない🤔💭
老いゆくひとの生の姿
なかなかの力作。
多くの人が抱えている潜在的・顕在的な不安を、独特の物語世界をもとにして映画で表現した作品——ということでいいでしょうか。
とりわけ中年以降の男性には(あるいは女性にも)切実に響くのではないでしょうか。
容赦なく迫り来る老いと、その先に待っている死。生きている限り誰もそこから逃れることはできません。
老境の生活の不安、将来の不安……。
この作品には、生々しいともいえる生の姿が描かれていると感じました。
生きるって、人間の生って、残酷だなぁ。
「敵」というのは、人間の「生」そのものなのかもしれないなぁ、なんて考えたりして。
何度も映し出される料理と食事のシーンが印象的でした。
食べるということは、まさに生きるということ。
それから、「音」も。主人公の発する様々な生活の音。生きているということは、音を立てるということなのだと今更ながら思った。音を立てなくなったとき、ひとは死ぬのだな、と。
情報量を絞ったモノクロの映像で表現することによって、それらの「音」が際立っていると感じました(これも監督の狙いであることは確かでしょう)。
主演が長塚京三というのもよかった。熟練の役者の演技は、安心して鑑賞ができました。
追記
それにしても、河合優実ちゃん。これだけ多くの監督がつかいたがるということは、やっぱり「持ってる」んだろうなぁ。相当に。
まあぼくも『サマーフィルムにのって』で彼女の魅力の虜になった一人ですが。いずれにしても“選ばれたひと”であることに間違いはないですね。
敵は何処に?
原作を読んだのは大昔だったがあらすじはある程度覚えている。当時は30代だったので普通に娯楽小説として楽しめたが、正直70を過ぎてこの映画を観るのは辛いかも?僕の記憶では主人公は長塚京三のような紳士的な大学教授ではなくもっと尊大な(筒井康隆のような?)イメージだったが。瀧内公美は笑っていても怖く、河合優実は笑っていなくても、父親が破産して寸借詐欺を働こうとする時でも、幸せそうに見える(少なくとも僕には)のが対照的。パーフェクトデイズを思わせる歯磨きのシーンが多いが、ここまで何度も観客に見せる必要があるのかは疑問。モノクロにしたのはよかった様な気がする、下血シーンはカラーでは観られなかっただろうから。一人の食事でもきちんと材料から手作り(一人焼き鳥は初めて見た)する几帳面な主人公が途中からカップヌードルを食べる(僕と同じ)ように変化していくのは象徴的。敵は老いであり、そして着々と進行する認知症。僕もそろそろ老後の準備をしなくてはいけないのかもしれない。
老いの恐怖をシュールに再現
前半は儀助の生活を淡々とスケッチする日常風景で構成されている。一昨年に観たヴィム・ヴェンダース監督の「PERFECT DAYS」を彷彿とさせる作りで、特に大きな事件が起こるわけではないのだが、丁寧な描写の積み重ねに儀助の人間性、周囲との関係性が窺い知れて興味深く観れた。
自炊にこだわり、コーヒーミルで豆を挽き、原稿を書き、時々行きつけのバーで酒を飲む。何の変哲もない日常だが、キャリアを終えた人間の暮らしとしては十分すぎる幸福ではないだろうか。何とも羨ましく観れた。
しかし、そんな平穏な日々も、元教え子の靖子の登場によって少しずつ変わっていく。冷静で理性的な儀助が年甲斐もなく彼女に惚れてしまうのだ。よく”男は幾つになっても…”なんて言うが、まさにそんな感じでこれには苦笑してしまった。
ただ、ここまでならただのスケベオヤジの他愛もない妄想で片付けられるのだが、問題はここからである。儀助の妄想はどんどん恐ろしい方向へと膨らんでいくのだ。
もう一人、歩美という女子大生が登場してくるのだが、彼女もまた儀助の人生を狂わせるファムファタールとしての役割を持たされたキャラである。先の靖子についてはまだ妄想の内に己の欲望を具現化するだけで済んでいたのだが、彼女に関してはいよいよ現実と妄想の境目が見えなくなり、ついに実害を被るまでに至ってしまう。高齢者を狙う詐欺はこういう風に行われるのか…などと思ってしまった。この辺りから、この映画は虚実の曖昧さが加速してしく。ほのぼのとした前半からは想像もつかないような恐ろしいトーンが横溢し始める。
本作は筒井康隆の同名原作(未読)の映画化である。現実と妄想、悪夢、幻想が交錯した後半の世界観は、いかにも筒井ワールド的な不条理劇となっている。リアリティを重視した前半の日常描写とのギャップが上手く効いていて、予測不可能な展開の連続に興奮させられっぱなしだった。
監督、脚本は吉田大八。元々こうしたシュールなユーモアを作り出すのが上手い作家なので、筒井康隆の世界観との相性は合っているような気がした。思えば、出世作「桐島、部活やめるってよ」は不条理演劇の代表作と言わる「ゴドーを待ちながら」を意識した作品だったし、「紙の月」の宮沢りえはお金という幻想に憑りつかれたヒロインだった。現実と幻想が織りなすシュールな世界を描くことに、吉田監督はかなりこだわりを持っているような気がする。
しかも、本作は全編モノクロというのも大胆なところで、監督のこだわりを感じる。一つの考え方として現実と妄想をカラーとモノクロで表現するというやり方はあったと思う。しかし、敢えてそうせずモノクロで通している。その方が虚実の境界があいまいになり、観客が儀助の視界を追体験できるという理由からこうしているのかもしれない。いずれにせよ、人生の終末をこうした不条理なトーンで切り取った所に新鮮な驚きと興奮を覚える。
そして、本作は儀助を演じた長塚京三の巧演が光る作品でもある。これまではどちらかと言うと脇役が多い印象だったが、主役で伸び伸びと演じさせると、これほどドラマに深みをもたらす俳優だとは思わなかった。79歳になるということだが、晩年にこうした作品に巡り会えるというのは役者冥利に尽きるのではないだろうか。
さて、タイトルになっている”敵”の存在だが、自分はこの”敵”がいつ登場するのか興味津々で観ていた。ただ、これが中々登場してこなくて悶々としてしまった。正直な所、少し勿体つけ過ぎな感じがしなくもない。もっと早い段階でその片鱗を匂わせていたら、更にスリリングに観れただろう。作劇上で不満が残ったのは、この1点である。
欲
『敵』。面白かった。
終始モノクロで描かれる手法は、作品にとても合っていると思った。主人公の渡辺儀助は一人暮らし。きたるXデー(寿命)に向かって、貯金残高を計算し、ご飯を自分で作り、たまには友人と酒を飲み、それなりに丁寧な暮らしをしているように見える。だが、「敵がくる」というメールが届いてから、彼の生活はどんどんおかしくなっていく。
「敵」とはなんだろう? 私は「欲」だと思った。
妻に会いたい欲、
誰かと一緒にいたい欲、
教え子と寝たい欲、
何もかもが暴露されてほしい欲、
誰かに頼りにされたいという欲、
隣人がうるさくて早く死んでほしいという欲、
本当は寂しくて早く死にたいという欲、
欲があることを認めたいという欲……。
彼は自分自身を「真摯」で「誠実」で「真面目」だと勘違いしているがゆえに、これらの欲に襲われる。欲は次々と襲ってきて、彼に欲を認めさせようとする。
そう考えると、本当の敵とは「自分自身」だったのかもしれない。欲を認めず、跳ね除けようとする自分自身が敵だった。そう思えば、彼の余生そのものがまるで夢のようで、だから色彩を持たなかったのも納得できるような気がする。
この監督の味
なかなかにすごい作品
「敵」が姿を現す前の段階で、モノクロの画面に引き込まれた。
本当に、俳優・長塚京三がこういう日常を送っているんじゃないか、と思うくらい自然な立ち居振る舞いを見せるのだ。
敵がどうだ、こうだ、というのはほとんど意識する必要はない。
描かれる、老仏文学者の妄想と行動が実に深みがあるのだ。
「敵」が出てくると、逆にそれまでの静かな流れがひっくり返される印象がないでもない。だが、その部分は前半の流れを台無しにするようなこともなく、味付け程度と思ってよい。
全体から見れば、たいへんに良い出来栄え、と感じた。
★5つつけてもいい、と思わないでもないが、パンフレットがペラペラなのに1000円もするのが気になって、それで★半分マイナス。パンフレットは立ち読みして買わなかったけどね。
平日昼間で、封切りから1カ月近くたつというのに客入りは半分以上あったと思う。
未見の人は、ぜひ急いで見に行ってほしい。
敵(映画の記憶2025/2/12)
敵の正体は
自分自身の老後が気になり、「敵」を鑑賞しました。
去年は「九十歳、何がめでたい」も鑑賞しましたが。
「敵」とは何か、劇中では直接的な説明が無かったのですが、主人公が飲み込まれた「悪夢」、それを引き起こした「老い」、となるでしょうか。
知的な主人公は自分を安売りすること無く、自尊心を持って規則正しい日々を過ごしていましたが、そんな人でも敵から逃れられなかったのですね。
準備を怠ることが無いようにしたいです。
まずは掃除をして身綺麗にしておかないと、と反省しておきます。
筒井康隆らしい映画
老いて夢みるのが怖くなった!
自分とは違うけれど、気をつけたい
同じ元大学教授だが、主人公ほど研究面での仕事の依頼や教え子との交情が全くないところは違うので、性的誘惑にかられる心配は少ない。詐欺に遭う可能性はあるだろう。コンピュータウイルス感染のようなことはつい最近経験したばかりで、情報面で致命的で、良い助言者に恵まれることが大事だと痛感しているところだ。近隣の揉め事に巻き込まれることもまさに直面している。本作のように、妄想に呑み込まれないように気をつけたい。
パソコンが壊れ、デジタル文書に著していた遺書と、アナログ文書に遺した遺書の内容は違っていたということだろうか。最後の場面は原作にはなかったらしいが、主人公が既に、死んだはずの祖父の幻をみたように、相続人も死んだばかりの主人公の幻をみてショックを受けたというのが当然のところだろう。
全363件中、61~80件目を表示