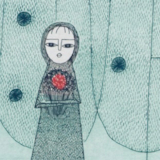敵のレビュー・感想・評価
全363件中、181~200件目を表示
気持ちがわかる年代になったか?
「敵」
長塚京三演じる 77歳元大学教授、妻に先立たれ一人暮らし、預貯金を計算して、亡くなった時に死のうと決めた男が主人公。「敵」は突然やってくる、老いること、死ぬことと向き合うことって敵なのか?日常生活が少し狂い出したところから、観ているものも妄想か現実か分からなくなります。彼を取り巻く3人の女性。亡くなった妻、教え子、文学部女子大生に惑わされ、翻弄されていく姿はは、老いていく哀れさを感じます。私は64歳ですが、共感できることが多くあり、心に響きました。長塚京三 正に適役。河合優実さん、出番は少ないですが存在感があります。
想像から妄想へ
夢や妄想、幻覚も多用すると収拾がつかなくなる。
土曜日の朝9時からの鑑賞。私は50代後半ですが、観客の中で最年少か...
土曜日の朝9時からの鑑賞。私は50代後半ですが、観客の中で最年少かも。
真ん中が空席が目立ち、皆さん端っこ席が好きみたい(年齢的にもトイレの関係?)
そういう自分も端っこの席。
「ファーザー」「PERFECT DAYS」「生きる」と大好物の種類の映画
自分も定年間際の50代後半、これからの人生をどういう風に生きるのか
迷っている最中でもあり、こういう映画は必ず何かしらの気づきを与えてくれます。
今回思ったのが、年をとっても丁寧な生活をしたいなということ
自分で食事を作る、寝るときはパジャマに着替えて布団で寝る、人と接するときは
相手への配慮を忘れずにとか当たり前のことを日々生活としてするようにしたいなと
改めて思いました。
ただ、前半の丁寧な生活をしていた時よりも、妄想の中で抗っている主人公の方が生きてる!という感じはし、やっぱり人間が生きていくというのは苦行みたいなものなのかなと思いました。
老いと死を見つめることによって、生きる目的を知ることができる。
映画レビューにひかれて鑑賞。
主人公の渡辺儀助が長塚京三なのか、長塚京三が渡辺儀助なのか分からないぐらいのハマり役。
また、久しぶりに観たモノクロ映像から新鮮な印象を受け、全体がシャープな作品となったのではと思う。
「敵がやって来る」とは何か?を上映中ずっと考えていて終盤になり、敵が“老い”であり“死”を指すことではないかと分かり、起きている出来事が少し滑稽に思えてきたが、観ているこちらも妄想と現実の境が段々分からなくなってきて画面に没入していった。
主人公が規則正しい生活を心がけ、特に食材にこだわり、調理に手間暇かかった焼き鳥やローストチキンには、昼前に鑑賞したため、お腹が減って仕方なかった。
冷麺でキムチを食べ過ぎて下血したのには笑ってしまった。
モノクロ映像だからこその場面かなと思った。
70代後半の老齢であっても性欲には勝てない性にも笑ってしまった。
わが身に当てはめて解らないわけではないのと、“エエ格好”したいことが若さを保つ秘訣であることも大事かなと思ってしまう。
観客がかなり年齢の高い方が多く、自分自身を振り返ってみても、この映画の持つ意味は大きいと考える。
2503
敵は自分の心の内に有る‼️❓
筒井康隆は六十過ぎに七十過ぎの主人公の自称録のようなこの小説を書いたらしい。
綺麗な教え子、バーのバイト女子大生、エロい、ジジイには刺激が強すぎる、妄想だとしても、そのソースは、多分、ジジイの同時進行では無く、現役時代に源があるのだろうが、妄想で自慰する爺い、良い響きだ、そんなジジイになりたいもんだ。
料理もする、これも妄想なんだろうな、カツプメン食べてるシーンもあるし。
原作が生々しく挿入するとこまで妄想するけど、映画は高潔なので、減点した。
はるばる観にきた甲斐が有る、主人公は映画と同じくらいの年齢なのだから、その覚悟たるや尊敬に値する。
白黒なのに、この表現力たるや、驚愕に値する、私もこのように老いたいものだ、敵は無しにして、良い映画でした🎞️🎟️ありがとうございました😊😭
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 身につまされました。“それ(敵)”は突然やって来る⇐人生の真理です。
①序盤は、引退した(実はクビになったことが終盤で分かる)大学教授の隠居生活を淡々と描いていく(白黒ということもあって)のかな、と思いきや、中盤からは夢とも妄想とも幻覚ともとれる映像が次々と差し挟まれて主人公の内面が暴露されていく。
映像で語る映画という媒体はこういう表現方法にやはり適しているなあ、と思う。
②成熟した立派な大人、終活バッチリ、俗世を超越している、嘗ての生徒達に慕われる優れた教授という表面(これも本人の願望、プライドなのかも知れない…)の下に、実は切れ痔に悩まされ、様々な煩悩(亡き妻への慕情、後悔、捨てきれない嘗ての教え子への欲望、性欲、劣等感、体臭-これよく分かるわァ、未練、不安、恐れ、虚栄心)が渦巻いているのがあからさまになっていく。
でも、自分も60過ぎて分かるけれど、残された時間も指折り数えられる段階に入ったし、世の中のことも少しは分かってきたと思うし、ちょっとしたことには驚かなくなっては来ていても、なかなか悟りの境地には程遠い。
でも、それが人間だし人生だと思う(開き直っております)。
そういう点ではとても人間臭い映画だ。
主人公が見ているのが夢なのか(夢精したから夢とも思えるし)、妄想なのか、そろそろ認知が入ってきたせいの幻覚なのか、死ぬ前に走馬灯のよう見る映像なのか、の解釈は観る次第だろう。
③「朝ごはん食べてから歯を磨く人なんだ」
というのが何故か印象的。
④長塚京三は、生徒達から慕われる教授だったのが納得できる懐の深さと、教え子から慕われる色気、そして少々世間に疎いピュアさもそこはかと漂わせて流石。
⑤時間軸が歪んでいるようなところや、古い家につきまとう幽霊譚ぽい味付けも、なんとなく筒井康隆らしい。
長塚京三さんの演技が妙に心地良い、観終わっても直ぐまた観たくなる摩訶不思議な傑作
主人公は老い先が短いとはいえ、いつまで続くのか分からない人生の終わりを予測し毎日淡々と過ごす元大学教授の老人
でも歳をとっても瀧内公美さん演じる元教え子に「私としたいの?」と言われ欲情したり、河合優実さん演じるBARでバイトするミニスカ女子大生に会いに“自分なり”にオシャレして出かけたり、と現役男性の様に振る舞うが、やがて“敵”の存在によってシームレスな世界に身を投じていく、というメチャクチャ難しそうな役を長塚さんが演じ素晴らしく見ごたえがあります
主人公が毎日ひたすら作り続ける食事が毎回メチャクチャ美味しそうだった
確認したらいろんな映画やドラマを手掛けてきたフードスタイリスト飯島奈美さんのデザインとのこと、モノクロなのに焼き鮭や串焼きなどが匂いまで伝わってきそうに撮られていて流石だなあと感心しました
そして、もちろん料理だけでなく日本家屋など全編においてもモノクロ映像がすごく綺麗、作品に引き込まれて直ぐに忘れてしまうぐらい違和感がないのが不思議でした
最後に
自分の中で強烈に印象に残ったのが、瀧内公美さん、今まで全然そんな風に見えた事はなかったけど、本作ではモノクロのレトロな雰囲気が似合っていて、とても綺麗ですごく色っぽく素敵でした
河合優実さんはいつもと一緒の安定感で良かったです
中高年向き、高尚かつ下世話な深み
単に「面白い」という表現では表せない、深みのある、多面的な印象を持つ映画でした。
観る人の年齢によっては、面白いどころか、身につまされる怖さを感じる映画でもあるでしょう。
何人かの方が書いておられるように、61歳の私も「PERFECT DAYS」を想起しながら観ていました。独身男性の、日々の生活を丁寧に描写するところが共通点。ただ、あちらは現役ブルーカラー労働者で、こちらは余生を過ごす高齢の元大学教授なので、生活のベースはかなり異なる。あちらは自然の木漏れ日を美しく描写し、こちらはモノクロで四季の移り変わりを定点観測のように日本家屋の中で描いている。どちらも、派手さはないけど中高年者が観て、人生の何たるかを感じる描写が多い。
この映画の原作は未読ですが、筒井康孝の小説、特にナンセンスもの(というべきか)は若い時にハマッてかなり読んだことがあります。映画の後半、どんどん不条理な描写が増えていき、現実と妄想の境がわからなくなり、夕食の鍋をひとりで全部食べて、殺されて井戸に投げ込まれる編集者のくだりや、犬のフン騒ぎ、内視鏡検査、夢精などなど「これは確かに筒井康孝の世界やん」と、昔読んだ小説を思い出しながら、笑いをかみ殺して観ていました。
高尚さを感じる場面と、バカっぽい場面、また「敵」が階段の下から集団で上がって来る、強烈に怖いシーン等が、作品の中に違和感なく同居していて、ちょっと他にない味わいを感じました。この監督の作品は初めて観ましたが、少なくとも筒井康孝作品を相当読んでおられると思いますし、演出レベルの高さに圧倒されました。
もともとは洋画・韓国映画好きで、あまり邦画は観ない方だったのですが、昨年は「夜明けのすべて」「アイミタガイ」「侍タイムスリッパー」等、良い作品をたくさん観たので、今回の「敵」も含めて、邦画に対する印象も良い方に変わってきました。
主演の長塚さんが素晴らしかった!
特に長塚さんの前半の演技にrealityがあった。日常の繰り返しだが、routine(同じ動作)ではなく、食事の準備をして、それを食べ、食器を片付け、洗うところまで、しっかりこなす。朝食には、ハムエッグや鮭の焼いたの、昼食には、蕎麦を湯掻いて冷水にさらし、ネギと共に、あるいは卵を茹で、スーパーの韓国系店員と相談して求めたキムチと、冷麺に載せて食べる。夕食には、レバーを牛乳につけて血抜きし、切って串に刺し、炭の上で焼いて食す。フレンチのレシピに挑むこともあり、ワインも時として食卓に載り、弟子たちとの会食も。77歳にして、あの食欲。身体が強くないと出来ない相談。朝と夜の歯磨き。夜は、少し前によく見た「糸ようじ」。
ただ、彼自身は、教授を退職してから、原稿を書いたり、講演を依頼されたりすることもあるが、退職後の境遇に決して満足していない。訪ねてくるのは教え子のみで、周りの人たちから尊敬を受けているわけでもなく、親から引き継いだ大きいが古びた二階屋の日本家屋に住み、食事に丹精を凝らすのも贅沢に見られているとこぼす。貯金の目減りにいつも気を配り、生きるために生きるだけの生活には満足できず、今の生活レベルが維持できなくなったら、一生を終えることも覚悟しており、遺書も準備している。
やがて彼は、老化からくる強い不安を背景として、夢とうつつの間を彷徨う。願望、妄想、不条理の三段階があったようだ。一番、現実に近い願望としては、よく訪ねてきて食事を共にすることもある教え子との性的な交わり。妄想としては、20年前に亡くなった妻が出没するようになり、教え子たちと同席したり、言葉を交わしたりする。亡妻が出てきたら、全部、夢の中と思ってよいのだろう。面倒なのは、非現実的かつ原作者の発想に基づく不条理。愛用のMacに「北からの脅威」がウイルス・メールとして現れて後、現実感を以って、暴力的に襲ってくる。これがタイトルにある「敵」の正体だし、内的な「不安」に呼応する外的な「不穏」、原作者の主題なのだろう。いくら想像の産物とはいえ、現実感ありすぎ。個人的には、この不条理だけは何とかして欲しかった。ただ、この映画にある種の活気をもたらしたことも事実か。
年齢を重ねることによる、認知症とは異なる、内的な不安との戦いをよく描いた映画だ。
北から来るものThat Which Comes from the North
原作は未読。
権威になる、と
どうなるか?
権力を持つ、と
どうなるか?
歳をとる、と
どうなるか?
多くは、良くも悪くも、
権威=自分
権力=自分
になってくる、なってしまう。
歳上というだけで・・・以下同文。
でも、その最中、自ら気がつくことが
難しかったりする。
その間、イコール自分が日常を侵食する。
主人公は【フランス近代演劇史の権威だった】人。
悪気はなくても、
権威=自分、権力=自分になるだろう。
いわゆる【偉そうな】人に描かれていないし、
そんな人ではないように見えた。
むしろ権威から遠く見えた。
それでも、知らず知らずのうちに
彼は妻との約束を果たさず、
教え子との関係性にも問題が
あった【かも】しれなかった。
そうやって
気づかず
取りこぼした
数々の事どもが、
気がつかないふりをしてきた事が
一人になった刹那、
北からやって来る。
そんな風に観てて思いました。
I haven’t read the original work.
What happens when someone becomes an authority?
What happens when someone gains power?
What happens when someone grows older?
In many cases, for better or worse,
authority becomes oneself.
Power becomes oneself.
And simply being older… well, the same applies.
But in the midst of all this,
it can be difficult to notice it oneself.
During that time, the equation “I = authority”
slowly infiltrates one’s everyday life.
The protagonist is a man who used to be
an authority on modern French theater history.
Even without ill intent,
it’s likely that authority and power
became synonymous with who he was.
He wasn’t portrayed as the stereotypical “arrogant” type,
and he didn’t seem to be that kind of person either.
In fact, he appeared far removed from authority.
Even so, unknowingly,
he failed to keep promises to his wife,
and there might have been issues
in his relationships with his students as well.
And so,
the countless things he neglected,
the countless things he pretended not to notice,
all come rushing at him the moment he is left alone—
from the North.
That’s what I thought as I watched.
敵
考えても分からないと観終えて実感
大昔、ワタシが高校生だった時分、一時期筒井康隆作品にはまり読み漁ったことがありまして、その後も何冊かは読んでいるのですが、当時から「何だか分らん」世界なのに、なぜだか読んでしまっていたのを思い出しました。
スクリーンに映し出される映像はワタシにとって筒井ワールドそのもので、クスクス笑いながら観ていました。
この原作は未読で、吉田監督はどのようにご自身の脳内で嚙み砕き、何を表現したかったのか、そして筒井康隆は言葉だけでどのように数々のシーンを紡いだのか、とても興味が湧き、是非とも原作を読んでみたい!そしてその後再び映像を確認してみたい、そう思える作品でした。
まあ、万人受けする内容ではないのだと思いますが、はまる人は結構いるんじゃないかと思います。
そして、モノクロ映像は陰影が濃くてとても良いですね。
敵がやって来る
静かなモノクロの世界。物腰の軟らかい元大学教授の独居老人。フランス文学を専門とし、その権威としての自負もある。身の回りのことは自分でこなし、凝った料理もお手のもの。自分の身の処し方に手も打ち終えた。どこを切り取っても、元大学教授的『PERFECT DAYS』。ところが、もう人生の終末を穏やかに迎えるものと思っていた矢先、様々な出来事が舞い込んでくる。ささやかな、それでいて逃げきれない。いや、本当は心の奥底にまだそれを期待していたのだろう。興味がないふりしていながら、実は欲していたのだ。いろいろと。
さあそこでだ、突然の警告、「敵がやって来る」。もしかしたら、このメールを見つけた時ぐらいから、儀助はボケがはじまったんじゃないだろうか。たまにいるでしょう、強迫観念に支配されて暴れる老人が。儀助はそれだ。その視点で彼を見ると、すべてが納得できる。彼に迫る敵とは、達観していそうでいて本当はあった「不安」、若いものへの「嫉妬」、教え子への「欲情」、そんな隠れていた妄想のことだ。それが、ボケ始めることでタガが外れて顕在化したのだ。抑制も効かずに。それを傍から見れば、とうとうこの爺さんボケ始めた、となる。"あの裏窓の主人公はゲスだね。いたく共感するよ″とか、″フランス語は、愛を語るための言葉だからね″とか、つい少し前まで気取っていた姿はどこへやら、見るに堪えない妄想老人へと変わり果てる。いまそれに気づいている自分でさえも、あるとき、敵がやって来るかもと思ったら、戦慄が走った。長塚京三、絶妙。
老いと向き合う
元大学教授で仏文学研究の権威となればプライドもあるし弱みも見せられない。悟ったように教え子に語りながらも,内面は押し込められた煩悩が渦巻いていた。こんな矛盾を抱えて老後を生きるって辛すぎると言うのが最初の思いだ。最初はリアルな夢から始まり、その後はどんどん夢と妄想の境目がなくなっていく。
老いて自分がどうなるかはわからないし、想像するのも怖い気持ちがあるが、自分の気持ちに正直に生きたいなぁと思う。少なくとも,彼が日々の食事をきちんと作り,丁寧にコーヒーを入れて飲む姿は理想の老後に見えた。
原作は未読ですが筒井康隆ぎこの本を書いたのが63歳と観終わった後に知った。その年齢でこれを書く筒井康隆もすごいし、この本をこのような形の映像にする吉田大八もすごい。モノクロなのに色彩を感じる映画だった。
モノクロながら、鮮やかな色彩を感じさせる一個人の老後生活
『時をかける少女』『パプリカ』の日本文学界の巨匠・筒井康隆による同名小説を『桐島、部活やめるってよ』の吉田大八監督が映像化。生い先短い老人の慎ましやかな生活と、自制していた欲望が次第に表出していく様を、モノクロの映像で鮮やかに描き出す。
主人公の元大学教授・渡辺儀助を、ベテラン俳優であり儀助と同じくフランスと強い縁のある長塚京三が演じる。
妻に先立たれ、余生を都内の山の手にある古い日本家屋で過ごしている元大学教授・渡辺儀助は、年金と講演や執筆の仕事で得た預貯金を切り崩しながら、“来るXデイ”に向けて過ごしていた。それは、「毎月の支出からいつ預貯金がゼロになるかを割り出し、ゼロになった時に自殺する」というものだった。
日々の食事を全て手作りし、僅かな友人やかつての教え子、行きつけのバーで出会ったフランス文学を専攻する女子大生と過ごす。時に自らの加齢臭を気にしたり、身体の不調に悩まされながらも、季節は過ぎて行った。
そんな中、突如自宅のパソコンに送られてきた「敵が来る」というメッセージを皮切りに、次第に儀助は現実と妄想の狭間に飲み込まれてゆくー。
タイトルにある「敵」についての意味を探る時、ともすれば我々は、現在の世界情勢と結び付けて考えてしまうかもしれない。しかし、原作が発行されたのは1998年。本作で描かれる「敵」とは、全て儀助の中、それを見守る我々観客一人一人の中にある問題である。その事にアテンションするように、作中ではカトウシンスケ演じる新米編集者の犬丸が「ロシア問題か…」と呟いた際、すかさず靖子が「先生はメタファーの話をされているのよ」と訂正する。
現在31歳である私が思うに、本作で描かれている「敵」の正体とは、月並みだが“死”であり、“孤独”であり、何より“自分自身”に他ならなかったのではないかと思う。
預貯金から割り出した「あとどのくらい生きられるか」という計算に裏打ちされた“死”に対する覚悟も、ラストでは脆くも瓦解する。
外見では常に余裕を持ち、穏やかな姿勢で元教え子の鷹司靖子(瀧内公美)や女子大生の菅井歩美(河合優実)と接しながらも、密かに靖子への劣情を抱き、亡き妻である信子(黒沢あすか)の幻影を追って遺品のコートをクローゼットから引っ張り出して書斎のハンガーに掛ける。歩美の大学の授業料を負担すると申し出て、まんまと預貯金から300万円も失ってしまう。知人の湯島に語った「不思議と腹が立たない」という台詞にも、僅かな見栄があったのかもしれない。
トランクケースに溜まり行く、独りでは使い切れない程の量の石鹸は、儀助が妻を亡くしてから積み上げてきた“孤独”なのではないか。妄想の中で難民に向けて「好きなだけお持ち下さい」と自宅の塀の前にそれを置く様は、妻に先立たれ、友を失い、若い女に騙されて預貯金を無くした事で、自らの理性と自制心が限界を迎えてしまった儀助の「誰かこの孤独を消し去ってくれ!」という静かな叫びだったようにも思えるのだ。
だからこそ、儀助は自宅の庭に振り続ける冬の雨を前にして、「この雨があがれば春になる。春になればきっと、また皆に逢える」と、心の中で呟く。静謐で厳かな雰囲気を漂わせていた儀助の生活の下には、孤独と虚栄心に塗れたごく普通の老人、どうしようもない「人間」、「男」という性別の生き物の本質があったのではないか。
しかし、パンフレットを読むと、主演の長塚京三氏は更に深い領域まで渡辺儀助という人物を捉えている事が分かる。それは、フランス演劇・文学という高尚でインテリジェンスな分野に人生を費やして来た事から来る傲慢さ。妻の信子に注ぎ切れなかった愛情と侮り(「夫婦揃って貧乏暮らしをするなんて、君は耐えられなかったはずだから、先に逝ってくれて良かった」と口にする様や、フランス文学・演劇を専門としながら、一度たりともフランス旅行に行かなかった事)。性欲を自制心と虚栄心によって律する中で密かに、しかし確かに抱いていた下心。儀助が向き合う「敵」の正体とは、つまり彼がこれまでの人生で蔑ろにしてきたもの、それらからの“復讐”なのだと。
この事を受けて、私の中では心理学者のユングが遺した【向き合わなかった問題は、いずれ運命として出会うことになる。】という言葉が思い起こされた。
他にも、“老い”や“恐怖”といった様々な「敵」を、観客一人一人が想像するだろう。その正体が何であるかが明確に語られない以上、それぞれがそれぞれの「敵」を想定して鑑賞し、考察して行く他ないのだから。
しかし、こうした内容やポスタービジュアルが与えるシリアスな印象とは裏腹に、本作は意外にも儀助の人間的・男性的な滑稽さをコミカルな表現で描き出す様も目立ち、それが魅力の一つとなっていた。
靖子を想って無精し、翌朝無様に下着を洗う姿や、痔の検査で内視鏡を挿れられる際、まるで掃除機のコードのように内視鏡が勢いよく入って行く様などは、場内からクスクスと笑い声が漏れていた。
また、信子が儀助に「この人(靖子)の事を考えて。勃起して。一人でしてたんでしょ?」と問い詰めるシーンでは、「…した。でも、想像の中だけだ!」と返す儀助に「想像するのが1番悪いのよ!」と激昂する姿が面白かった。
モノクロながら、その彩りの豊かさを感じさせてきた数々の料理シーン・食事シーンは、本作の最大の魅力だろう。本作は一個人の老後の私生活を描くと同時に、優れた飯テロ作品でもあったと思う。
物語冒頭から、起床した儀助は米を研ぎ、電気コンロで鮭を焼く。自ら豆を挽いて食後のコーヒーを嗜むのがルーティン。
湯島からの土産の手造りハムは、ハムエッグにして手際よく蒸し焼きにする。
たまの晩酌では、焼酎のお供に焼き鳥を自作する。レバーは血抜きし、葱間を作って焼き上げる。
朝食の白米を少し余らせて、塩昆布でサッとお茶漬けにする手際が美しかった。
好物の麺類は、素麺や冷麺を楽しむ。この冷麺の為に、拘りを持って買ってきた辛口のキムチが、翌朝痔を発症する原因となってしまうのだが。茹で卵を四つ切りにし、白胡麻を挽く手際の鮮やかさからは何とも悲惨な末路。
しかし、そんな食材や栄養に気を遣った食生活も、「敵」を前にして次第に現実と妄想の区別が付かなくなってからは、最終的には簡単なカップ蕎麦になってしまう。こうした食に対する姿勢の落差にも、抗いようのない“老い”を感じさせる。
渡辺儀助役の長塚京三氏の演技力には、今更賞賛を贈るまでもないだろうが、監督がキャストを想定して脚本の初稿を書き上げたと語るだけあって、儀助という人物のリアリティのある説得力は素晴らしい。時に滑稽な姿さえ晒してしまう振り幅の豊かさも、長塚氏が積み上げてきたキャリアの賜物だろう。
鷹司靖子役の瀧内公美の美しさは、モノクロの世界に於いて抜群の存在感を放っていた。本人も「モノクロ映えする」と言われた事があるというだけあって、妖艶さと成熟した大人の女性さを兼ね備えた靖子役はハマり役だったと思う。
老いるの怖い
今はYouTubeで年配女性のおひとり様暮らし動画なんかけっこうあって、老後も何とかなんじゃね?って思えてたのに…本作見ると「老いるの怖い」がぶり返してきた。キムチ食って血便出んのかよ!怖いよ〜!
自分が儀助くらいの年になる頃には、もっとライトな死に方が許される世界になっててほしい。歯医者行くくらいの感じで安楽死させてほしいし、死後のもろもろもネットでポチッと決めさせてほしい。
あとは、教え子の女性が色っぽかったですね。モノクロだと色彩がない代わりに陰影が強調されて、身体の凹凸がより目立つ感じがしました。
全363件中、181~200件目を表示