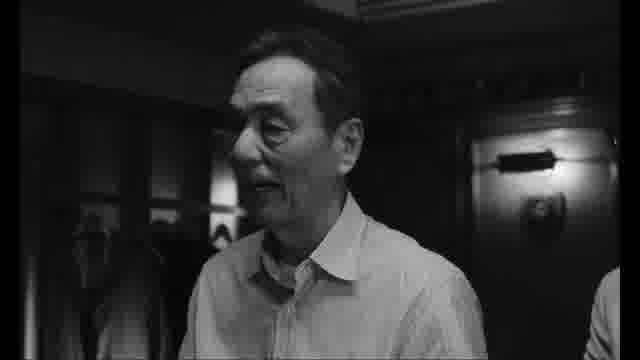「生と死を行きつ戻りつ」敵 M.Nさんの映画レビュー(感想・評価)
生と死を行きつ戻りつ
原作未読で映画だけ、感想を記載させていただきます。
長塚さん演じる元教授(今後は「先生」と書きます。)が送る、最後の一年ということが、物語の表面的な時間経過となっている本作ですが、そこに先生のたくましい妄想力が加わることにより、時間は意味を成さず、むしろ逆行することすたあるかのような状態になっていくのが、個人的にとても魅力的な作品であると感じ、たった一人の老人の、人生の最後をひっそりと描くだけにも関わらず、強烈なインパクトを残していると思いました。
恐らく、表題である「敵」とは、己のうちに潜むものであることが、予告編など様々な媒体で、ぼんやりとですが予想できていました。それでも、ここまでしっかりと描写するのは色々な意味で挑戦的で勇敢であり、素晴らしい試みであると考えます。
まず書いておきたいこととしては、冒頭も書かせていただいた「時間」や「夢か現実か」など、そういうものはまず取っ払って観た方が分かりやすい作品なのかな、と個人的には思いました。どの作品でも、感想は十人十色でありますが、その感想に物語上のギミックを混ぜすぎると、時として本当に思っていることが沈んで行ってしまうと思うからです。なので、わたしは、上記の「時間」や「夢と現実」、「空間」なども含めて、敢えて考えずに思ったことを書こうと思います。もちろん、「敵」について送られてくる正体不明のメールについても、夢か現実か分からない舞台装置に過ぎないと思っていますし、分かったところで個人的にあまり意味を持たないため、あまり考えないことにします。
この物語のほとんどは、先生が日々を淡々と生きる描写で構成されており、先生が朝起きて、コーヒーを豆をゴリゴリ潰すことから始めて、朝食を作り~というような流れを淡々と音楽なしで表現します。この淡々としていつつも「生命活動」をしっかり描くところも魅力的だな、と思っています。そんな先生は、その中で出会う友人や井戸を掘ってくれる元教え子に、自身の死を予期したかのような発言もします。そういう時の先生はとても理知的で、所謂「理想の老後」を悠々自適に送っているのようにも、わたしには見えました。つまり、人間は老いて死を待つだけになる、つまり「必要とされなくなる」存在であると言外に示しているのだと思います。先生も割と自虐的に「わたしの話に10万円の価値があるという根拠はない。」などと、達観したかのような発言をしていますので、多分、そういうことなのかな、と思いました。
そのような中で、先生は3人の女性と主に関わります。3人は様々なかたちで先生と出会いますし、年齢も境遇も、関わり方もそれぞれです。しかし、唯一同じであることは「必ず先生から離れていく」ということだと考えます。
率直に言って、わたしはこの物語における「女性」とは、「生命エネルギー」のメタファーのような存在なのかな、と思いました。そして、反対にこの物語における「男性」とは「死」を連想させるメタファーとなっているようにも思えたのでした。それが、タイトルにもある「生と死を行きつ戻りつ」にも繋がっています。
物語は先生の人生の終わりを分かりやすく表現しているのか、蝉の生命ほとばしる鳴き声で埋め尽くされる「夏」を始まりとして、段々と静寂が忍び寄って来る「秋」、そして遂に「敵」が襲い掛かる「冬」と経過していきます。その中で、先生の友人は検査入院のはずが危篤状態に陥るほどの大事を患ってしまい、先生が寄稿していた雑誌への連載は打ち切りとなるなど、ネガティブな事件が立て続けに起きます。その辺から、先生の所謂「夢」は急激に肥大化していくように思えます。わたしは、上記で「男性=死」という考えを書きましたが、もう一つ加えると、それは「現実」という要素だと思います。ちなみにもう一人、元教え子の編集者についてきた若手編集者も男性であり、ある場面で殺されてしまう描写があるのですが、ここでも先生の周囲にいる男性は「死」を想起させますし、元教え子が掘っている井戸は、やはり「下の世界=黄泉の国」を想起させるものとも思えてしまい、同様に「死」のメタファーのように感じられました。
つまりわたしが言いたいのは、この映画においては「男性=死=現実」という方程式が成り立っているのではないかということです。先生の世界において、男性の登場は現実世界との接触であるとともに、自分の死を連想させる装置になっているのではないかということですね。
では、反対にわたしが上記で生命エネルギーのメタファーとして考えていると書いた「女性」はどうかを書かせていただきます。その前に、この「女性」にも、もう一つ「男性」と対となる言葉があると思いますので、先に書くと、それは「夢」です。これは「幻想」とも言えるように思います。これは物語のギミックとして先生が彷徨う「妄想」ではなく、あくまで象徴としての「夢」だと思っていただけると幸いです。
そんな女性の中で、一番象徴的なのは、瀧内さん演じる元教え子であり、先生が最も性的に見ている女性でもあると思います。この元教え子が実在するのか否かは置いておいて、少なくとも過去に自分が教えた生徒であったことは確かなのだと思います。その教え子が「来てくれる」ことで、先生は分かりやすく明るくなり、教え子が「誘ってくれる」からセックスに及ぼうとする、という夢を観ます。つまり、先生にとってこの教え子は、自分の男性性を優越してくれる、とても都合の良い存在のようにも思えるのです。
次に、「夜間飛行」(フランス人作家で飛行機乗りだったサンテグジュペリの作品ですね。)というバーで出会う河合さん演じる女学生ですが、この女性にも先生は知的マウントから男性的な優越を図ろうとします。しかしその実、女学生の言葉にすっかり舞い上がっていることには気づいていない様子です。
結果、この二人の女性は先生から離れていきます。女学生は、先生から300万円をだまし取るようなかたちで消え失せ、教え子はかつての自分への対応をコンプライアンスに抵触すると非難し、気持ち悪いものを見るような目で蔑みます(恐らく幻想だったのですが。)。何かを期待していた女性たちからの手痛いしっぺ返し(というか、これも先生が勝手に舞い上がっていただけなのですが。)を受けた先生は、上記友人の入院や連載ストップなども重なり徐々に死へと向かっていきます。周囲から「女性」――つまり生命エネルギーがなくなっていき、代わりに残るのは死を待つ自分だけだからです。
しかし、ここで注目すべきなのは、「生」の象徴でありながら「死」そのものでもある存在としての奥様です。奥様は、ある場面からふと先生の前に至極当然のように現れ、先生の心をかき乱します。ある種のクライマックスである鍋を囲んだ食事シーンでは、先生の性生活を暴露し、教え子の性根の悪さも暴露するなど、物語を動かしていく役割を担っているのですが、これは端的に先生にとって奥様が「罪悪感」そのものだからかな、と思いました。フランス旅行にも行かせてやらなかった奥様、マンションに住まわせてやらなかった奥様、早くに死なせてしまった奥様、そんな奥様の愛を裏切るように若い女性に現を抜かす先生。そういった様々な後ろめたさが、常に奥様に対しては言い訳がましい先生の台詞によって感じ取れました。なので、この奥様が出て来るシーンは少し複雑で、奥様を追い掛ける先生と冷たくあしらう奥様というような「死」を連想させるものと、一方で一緒にお風呂に向かい合って入り、笑顔で話す「生(性)」を連想させるものとが同居しているように思えます。ただ、ここで注意しなければならないのは、この先生にとっての奥様は「生」であるとともに「死=現実」の象徴でもあるので、他の女性(つまり「夢」)と食い合わせが悪い様子で、だからこそ上記の鍋シーンのような修羅場が描かれることになるのではないでしょうか。夢ばかり見ている先生が、フッと現実に引き戻される象徴として奥様が現れる。こうしてみると、先生が如何にして夢と現実を行っては戻っているのか――もっと言えば、生と死の境界を行きつ戻りつしているのかが分かりやすいと考えました。
あまり関係はありませんが、夢の一つとして、病院の女性医師(?)に下半身を露出させられる夢を見たり、奥様と一緒にお風呂に入りたかったりと、先生は本当のところでは女性に自分の恥部を曝け出したい人だったのではないかと思いました。一方で、夢の中の教え子は自分にセックスを誘っておきながら時間制限を持ち出してある種の管理をしようとしたり、「服は着たまま」と命令したりと徹底しています。服を「理性」や「壁」とメタファーを考えると、反対に裸や恥部の露出は「欲求」や「解放」とも考えられ、最も性的に見ていたであろう教え子の夢が理性によって固くガードされているところは、興味深いところかな、と個人的には思いました。
と、ここまで書いてみて、わたしが思うのは、やはりというべきか先生は本当は全然死を受け入れてはいないのだろうな、ということでした。教え子や友人には見栄を張って達観している風情を出していますが、その実、いつやってきてもおかしくない死を恐れ、それが先生の妄想力によって肥大化し、最終的には「敵」という茫漠だったはずの存在として顕現した。そういうことなのかな、と思いました。
物語のラストになると、突如として「敵」は先生に襲い掛かります。先生は必死に逃げて庭の納屋に逃げ込むのですが、これは恐らく「母親の胎内で大空襲を経験した」と語っていた先生の胎内回帰願望が見せる妄想なのだろうと思います。それでも、ふと棒を持って納屋から出て来て「敵」に立ち向かう先生の姿は、母親の中から生まれた赤ん坊とも取れると思いました。結局は撃たれてしまうのは、「敵」が先生にとっての「死=現実」だからなのでしょうか。母親は女性の象徴ともいえるので、この時ようやく先生は「女性=夢」から飛び出して「敵=現実」と向かい合ったとも取れる、とてもテクニカルなクライマックスだと思います。
その後は、とても切なく、夢から覚めた先生は縁側で春の前ぶりともいえる雨を眺めながら「春になればみんなに会える。」と、ようやく本当の願いを言葉にするのでした。要するに、これまでのすべては、忘れられて不必要だと言われていく自分の存在を少しでも世界につなぎ留めたいと願う一人の孤独な老人の話であった、というように思える構造なのですね。
ただ、最後の最後にとても個人的なわたしの「妄想」を書かせていただくと、これらすべては最後にやってきた「春」の章までの「夢」だったのではないかと考えてしまいました。春という季節は、生命が再び活気を取り戻す訳ですが、そこで思い浮かんだ生き物に「蝶」がいます。「蝶」と「夢」で思い浮かぶのは「胡蝶の夢」という、それだけの話なのですが、最後に(恐らく)甥っ子(先生のおじい様(お父様?)にソックリ)と思われる方が納屋にあった望遠鏡を覗きこむと、家の二階に先生の姿を捉えるのですが、そこでふと甥っ子は消えてしまいます。わたしは何となく、これまでのすべては「胡蝶」(あるいは「敵」という名の「何か」)が先生に見せていた夢に過ぎず、甥っ子は先生を「見て」しまったことにより「胡蝶」の夢に取り込まれてしまったのではないか。
そんなことまで、考えてしまいました。そういえば、映画の途中で夜に何者かが庭をうろつき、先生が追い掛けるとそれは自分のお爺様(それかお父様)だったと奥様に嬉しそうに報告(という名の言い訳)をする場面がありましたが、あれは単純に夢と現実が曖昧になっていたことを表していたのかな、とも思いました。「パプリカ」を書いた筒井先生だし、それをやってもおかしくないな、などと。
上記のように、色々と自分なりに考えて楽しむ余地の非常に多い作品ではありますし、男性という存在の脆弱さを心身ともに表してみせた表現力はものすごいのですが、もう少し明瞭でも良いのかな、と個人的には思ったので、☆を一つ覗かせていただきました。