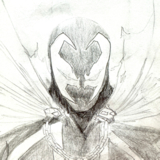「グァダニーノ渾身の一作」クィア QUEER ヘルスポーンさんの映画レビュー(感想・評価)
グァダニーノ渾身の一作
GAGA様本社試写会で観賞。
グァダニーノ監督は今1番好きな監督。特に前作「チャレンジャーズ」はこんな面白いことも出来るのか!と今までの重厚で詩的でアーティスティックな雰囲気とは打って変わり、明るくポップな雰囲気になっていた。
というのもグァダニーノ監督自身の私生活の影響もあるのではと感じていて、ちょうど若くてイケイケな彼氏が出来てハッピーな時期であったということも要因だったのかなとも思う。
そんなグァダニーノ監督の人としてのチャーミングさ、面白さが本作「クィア QUEER」ではそのままウィリアム・バロウズ(リー)を演じたダニエル・クレイグに乗り移っている。
本作のダニエル・クレイグは凄まじかった。007のクールな印象とは全然違う。可愛らしいおじさんになっている。(私は特にジーンを初めて観た時の分かりやす〜い恋に落ちる瞬間の顔、そしてその後カフェで見つけて周りを気にせず帽子を取ってルンルンでお辞儀をして挨拶するシーンなど。最高である。)
本作「クィア QUEER」がグァダニーノ監督が若い頃から敬愛する作家ウィリアム・S・バロウズの自伝的小説「クィア(昔の邦訳小説では「おかま」というタイトルだったが、本作公開を期に「クィア」として新装版になった)」を何十年も温め続けた企画だそうで、なんとか映画化権を取得して撮影開始!物語の舞台はメキシコ〜中南米だが、メインの撮影はグァダリーノの地元でもあるイタリア、そしてイタリアの撮影スタジオの本拠地であるチネチッタで行われた。
「君の名前で僕を呼んで」、「チャレンジャーズ」でも同性愛を描いていたが、同性愛者の呼称自体は出て来ていなかったと思う。しかし、本作では昔、同性愛者を軽蔑する差別的用語でもある「クィア QUEER」という言葉をハッキリと用いている。
また、本作のテーマは"蛇"や"ムカデ"のモチーフが象徴するように"孤独"と"別れ"である。
本作でのウィリアム・リーはひたすらに他者を求めて生活をしている。しかし一夜を共にすると関係は終わってしまう。"ムカデ"のネックレスをかけたその人とはもう出会うことはない。これ以上近づけない。ある一定の以上の接近(本作に出て来る「テレパシー」の意味するところでいう心と心の接近)を拒否するような象徴として"ムカデ"が用いられていると感じた。
そして、ラストシーンでウィリアム・リーがドールハウスになった愛用のホテルを覗き見るシーン。(このシーンもめちゃくちゃ良かった。この映画の舞台セット自体が模型"ドールハウス"のような作り方をしていて、この映画を観る私達視点と、このウィリアム・リーの視点が初めて交わり、本当に彼の心の奥底を覗き見る構図になっている。)
そこに現れたのが、もっともインパクトのある象徴"ウロボロス"である。自らの尾を噛んで永遠の象徴となっている蛇が涙を流している。蛇とは"孤独"の象徴であることからウィリアム・リーが永遠に孤独であるということを暗示しているとても悲しいシーンだ。そしてユージーンの頭を拳銃で撃ち抜いてしまうシーン。(これはウィリアム・リーが戦略結婚をしたと言われている元妻を射殺したという事件がモチーフとなっている。)
その後もリーはユージーンの思い出の場所を辿っている。
年老いてもただ1人でユージーンを想いながら息を引き取る。とても孤独で悲しい映画だ。
しかし、ただ一つ、映画として出来る唯一の方法でリーを優しく包み込むユージーンを描いて物語は幕を閉じる。
私はグァダニーノ監督作品に登場する"足の絡み"のカットが好きだ。
・「君の名前で僕を呼んで」ではベッド脇にすわった2人がお互いの足を近づけたり踏みそうになったりと遊ぶカット。
・「チャレンジャーズ」では学生時代にアートが食堂いたパトリックの隣に座ろとした時にパトリックがアートの座ろうとしている椅子を足で自分の近くに引き寄せるカット(細かいシーンですが!)
そして本作ではリーを優しく包み込むユージーンの足!!ポスターアートがここで登場するとは。ここで思わず落涙。
グァダニーノ監督の念願のウィリアム・S・バロウズの「クィア」の映画化。原作でのバロウズは人間関係に関してドライで自分自身を客観的に観て小説にしてしまうほどロジカルで軽いノリの話だったのだが、グァダニーノの長年の重い愛によってドロッドロに重い映画になっている笑
物語の結末にとても悩んだようだが、グァダリニーノ監督らしい演出、そして優しさに溢れたラストがとても好きだ。
音楽は毎度お馴染みのトレント・レズナー&アンティカス・ロス
衣装デザインはなんとロエベのJW・アンダーソン!(ユニクロとのコラボでお馴染み!笑)がグァダニーノ組に参加しました。
「チャレンジャーズ」とほぼ同時に製作が始まったとは思えない重厚な作品でした。
次作も楽しみです。