十一人の賊軍 : 特集
キレイごとはいらない。気休めもいらない。ほしかった
のは“本物”だった。嘘があふれる世界で、この映画は
ただ“リアル”を突きつける――こんなところで死んで
たまるか【魂が震えた11人&映画.comの本音レビュー】

観終わった後にうまく感想が出てこなかった。
11月1日から全国公開される「十一人の賊軍」。この映画はなんだったのだろう。あまりにもすさまじい生きざまを目の当たりにし、僕は言葉を失っていたのだと思う。
国の存亡をかけ、罪人たちが命を擲(なげう)つ。砦での壮絶な死闘。刀が火花を散らし大砲がさく裂する。1人の男が絶叫した。「こんなところで死んでたまるか」――体中の血液が沸騰するのを感じた。生きろ。生きろ。生きろ。僕はずっと、こんな映画を待ち焦がれていたのかもしれない。
主演は日本が世界に誇る名優・山田孝之と仲野太賀、監督は「孤狼の血」「極悪女王」の白石和彌。ネットやSNSを中心にフェイクがはびこり、自分たちが生きる意味さえもフェイクに浸食されつつある現代社会に、ただただ“リアル”を突きつける。
「そこまでやるか」と目をそらしたくなる瞬間があり、一方で「永遠に観ていたい」と凝視する瞬間が同時に存在する上映時間。おそらく50年後も語り継がれているであろう一作――。
本特集では「十一人の賊軍」に魂を揺さぶられた“11人の著名人”のアツい感想をご紹介するとともに、映画.com編集部のレビューを掲載。あなたの“生の価値”を取り戻し、アグレッシブに人生を歩む原動力を与える映画体験を、ご堪能あれ。
【11人の決死隊の“生命”をかけた戦い】
フェイクも忖度もいらない…魂が震えた11人の本音感想

あらすじやキャスト・スタッフは予告編、もしくは作品情報ページでご確認を。本作を最も観たくなるには、実際に鑑賞した声を聞いていただくことが一番だろう。
ということで。興奮と高揚の無慈悲なまでの波状攻撃に“やられた”人々の、生々しい絶叫を書き記す。普段は競合する映画メディアの編集長・記者や、スタジオジブリの鈴木敏夫氏、一流の映画監督・評論家、作家・ジャーナリスト、インフルエンサーと、ちょっとやそっとでは称賛の言葉を送らない11人が、本記事のために寄稿してくれた。
※掲載はあいうえお順
(映画監督)
時代の大きなうねりに、 巨大な権力と策略の狭間で 繰り広げられる幕末ノワール作品に
(映画監督)
必死に生きようとする男たちが、 反骨に身を投げ出そうとする男たちが、

(「映画.com」副編集長)
現代に唐突に蘇った、東映の集団抗争時代劇。どこまでも不器用な11人の生き様に、
(「スクリーン」編集長)
これぞ時代劇版『特攻大作戦』! となれば、

(作家・ジャーナリスト)
疾走感あふれる演出で、最後まで突っ走る。
(映画監督)
黒澤明監督の七人の侍。 仲間が集まってきて、 大きなものと戦う。 というストーリーが好き。 十一人の賊軍はまさにそれ。 しかも

(スタジオジブリ)
首を取る。この映画は日本人が“首狩族”である事を教えてくれる。だから、
(「キネマ旬報」元編集長、「Variety Japan」元編集長)
見ている間、何度も黒澤明の「七人の侍」を思い起こした。ただし現代を生きる我々にとってリアルなのは、白石和彌の「十一人の賊軍」だ。

(「ぴあ」編集部)
あの頃の映画のコピーでもオマージュでもなく徹頭徹尾、現代の観客に向けた「令和六年の東映時代劇」。
(映画評論家・映画監督)
東映集団時代劇のDNAをしたたかに受け継ぎながら、ペキンパーやフリードキンを彷彿とさせるアメリカン・ニューシネマ的な反骨と破滅の美学が、
(映画と推しを尊ぶツイッタラー)
迫り来る無数の砲弾と銃弾と刃。それらを紙一重で凌ぎ、命を燃やして躍動する罪人たち。彼らの“生”への渇望が観客の血を極限まで沸き立たせてくれる。まさに
【映画.comレビュー】一切媚びず、絶対に日和らない。
観れば絶対分かる──本作をつくる要素全てが“本物”

熱狂具合を体感していただいたうえで、お次はもう少し具体的かつ詳細に「実際に観た『十一人の賊軍』の魅力」を語っていこう。
本作は簡単に言えば「最高純度の妥協のない映画」。観客に見えないところも含め、あらゆる面で手を抜かず、極限を志向し、ありったけが注ぎ込まれている。
観ればわかる。本作は“本物”が映画の形で顕現したものなのだと。
●執筆者紹介
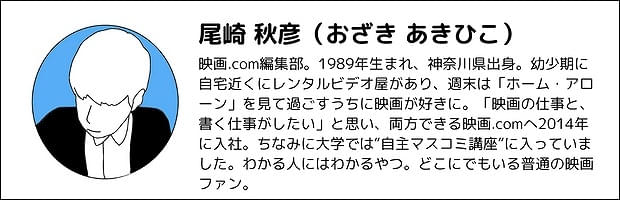
●奇跡の《脚本》:60年前の幻のプロットが、今の日本に真っ向から刃向かう…権力への壮大なアンチテーゼに挑む

象徴的なエピソードとして、「仁義なき戦い」シリーズなどで知られる名脚本家・笠原和夫が執筆していた“幻のプロット”がある。
時は60年前の1964年。勲四等瑞宝章を受章している笠原は、脚本を通じて時代の反骨精神や、都合によって変わる正義に抗う人物を数多く描いてきた。新作として「憎き藩のために命をかけて砦を守る罪人たちの葛藤」を構想し、旧幕府軍と新政府軍が争う激動の時代を舞台に、“果たして勝つことだけが正義か?”と一石を投じる物語を書き上げた。
ところが当時の東映京都撮影所所長・岡田茂が、物語の結末を気に入らずボツに。激怒した笠原は350 枚ものシナリオを破り捨ててしまい、日の目を見ることはかなわなかった――。
しかし……笠原が描こうとしたドラマこそ、今の日本が抱える社会問題とシンクロすると確信した現代の東映が映画化を企画。「孤狼の血」チームが旗を揚げ、実力派俳優陣とともに“権力への壮大なアンチテーゼ”に挑むこととなったのだ。
●いま最も新作が見たい《監督》の1人:白石和彌が、極限のリアリティを克明に描ききる

メガホンをとったのは、Netflix「極悪女王」が絶賛を浴び、いま最も新作が待ち望まれるクリエイターの1人である白石和彌監督。
映画は基本的には人々の夢や幻想を描くものだ。事実、そうした傑作が星の数ほどあるなかで、白石監督作はむしろ「現実の本物の過酷さ」を真正面から描き切り、リアルだからこそ観る者の人生に深い傷跡を残す。この姿勢に心酔する人も多いのではないか。筆者もまさにその1人である。
そんな同監督が、ともに「日本で一番悪い奴ら」「孤狼の血」などを手がけた脚本家・池上純哉と創出した「十一人の賊軍」は、これから詳述していくが、妥協の痕跡を一切見つけることができない。観る者のバリアを貫通し、魂を直接揺さぶるような映画体験をもたらしてくれるのだ。
●配役が神すぎる《キャスティング》:あまりに豪華な面々が、ひと目で誰と判別できぬ “あり得ない存在感”を発揮

主演の山田孝之と仲野太賀のほか、目を瞠(みは)るほどの俳優陣が結集した。紙幅の関係で全員を挙げられないのが悔しいほどの面々である(全容はこちら↓でご確認を)。
驚くべきは、この俳優陣(特に賊軍側の罪人たち)の顔が、泥や土、血で黒々と輝いていたり、シーンによっては一目で誰と判別できぬほど“汚れている”ことだ。「自分の存在を見せる」商売である俳優が、「自分の存在がわからない」形でカメラの前に立つことは避けたいはずだが、彼らは“それ”をしている……。
さらには日本有数の俳優たちがここまで過酷にやるか、と唖然とするショットが山ほど。山田孝之に至っては「地面に首まで埋められたまま、斬首処刑の巨大なノコギリが迫る」というシーンもあり、全編の撮影はさぞ苛烈を極めたことだろう。
なぜマイルドにせず、過酷に描き切るのか? どうして一流の俳優たちが、一目でわからないほど汚れているのか? それは「当時の人々は本当にそう生きていたから」だろう。つまり本物を追求したのだ(もちろんあらゆる映画が本物を追求しているが、本作は特に驚愕するほど強い、と感じる)。
秩序維持のため、見せしめの処刑は残酷極まりなく行われていた。栄養状態も悪く、争いが絶えない世界では「生き残ること」「死を遠ざけること」が最優先であり、罪人たちが清潔に保つことは二の次だった。
こうした現実に「十一人の賊軍」は真正面からぶつかっていったのだろう。この選択に筆者はひたすら敬意を表する。
●圧巻の《絵力》:セット、描写、アクション、どこをとっても絶句するほど“鬼気迫るクオリティ”

本物を追求する精神は、画面の端々からも否が応でも感じられる。
例えばセット。主な戦いの舞台となる砦は、人里離れた山奥に建てられた広大なオープンセット(広さは東京ドーム1個半、制作期間は約2カ月)で撮影。地面を重機で掘り起こし、川を創出するなどダイナミックなこだわりが詰まっており、仲野太賀も「これほどの壮大なセットは初めて」と感動していたようだ。
そんな舞台で繰り広げられるアクションも“本物の凄み”をとことん描く。ワイヤーやCGは使わず、肉体のスピードと躍動感、ときに優美でときに無様な殺陣の型など、“スーパープレー”というよりは“生身の殺し合い”のヒリヒリ感が忘れられない。
爺っつぁん役を担った本山力(「東映剣会」所属の殺陣のプロフェッショナル)の一騎当千の活躍は筆者の度肝を抜いた。さらには仲野太賀も30人を相手にする殺陣をみせ、一太刀ごとに寿命が縮まっているような壮絶な剣戟を披露している。必見でしかないわけだ。
そして傷口のリアリティ、常軌を逸した荒天を約200トンの水で表現した雨降らしなど、スタッフの入魂具合はとてもここでは語り切れない。技術や演技力を総動員して出現した映像は鬼気迫っており、その一瞬一瞬が腰を抜かすほどの生命力に満ちている……この映画、はっきり言って事件だ。
●魂に来る数々の《セリフ》、そして容赦のない《音圧》:この映画の影響は、一生残り続ける…人生に残る“傑作”の誕生か

このまま永久に語ってしまいそうなので、本項目で最後にしよう。
山田孝之演じる侍殺しの罪人・政の「こんなところで死んでたまるか」というセリフが本当に好きだ。「岬の兄妹」「福田村事件」などの怪優・松浦祐也扮する一家心中の罪人・三途が、砦防衛のつかの間の夕食で、茶碗にこんもり盛られた真っ白な米を一口頬張り、「うんめえ~」と声を漏らす。体の芯から出たその言葉は、何気ないが(いや、何気ないからこそ)いつまでも頭に残り続け、自分と、食べること、もっと言うと生きることへの姿勢を改めさせた。
かように、壮絶な生き様を際立たせ、観る者に勇気を与えるセリフのなんと多いことか!
また、戦闘シーンでの音圧は容赦がない。特に大砲の爆裂はまさに轟音で、事前に予想していたボリュームの5倍は大きく、「耳をつんざく」とはこのことだと思った。「本当に戦場のど真ん中に放り込まれた感覚」においても類まれな映画体験だったと筆者は断言する。
――本作が志向した“本物”はとても重要だ。今の世界で、SNSやネットに触れていると、自分の身の回りが嘘やフェイクで塗り固められていると感じる瞬間がとても多い。極端に言えばこの世のすべてはフェイクであり、自分自身の生さえもフェイクではないかと感じてしまう。
そんななか「十一人の賊軍」は本物を描き切る。自分たちが死力を尽くし、本物を追求する限り、この世界はすべて本物であり、あなたの生も本物であると、不安を抱える僕たちに声をかぎりに叫んでいるように思えてならないのだ。
この映画を体感する時間は“ひととき”だが、影響は一生、残り続ける。そんな可能性に満ち満ちた“人生に残る傑作”を、ぜひ見逃すことなきように。
©2024「十一人の賊軍」製作委員会


















