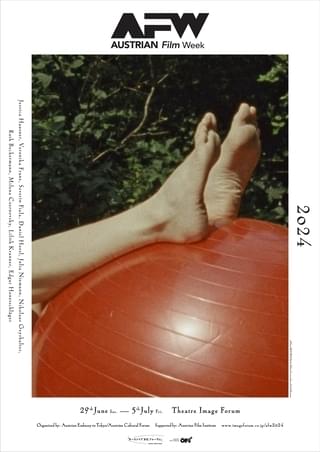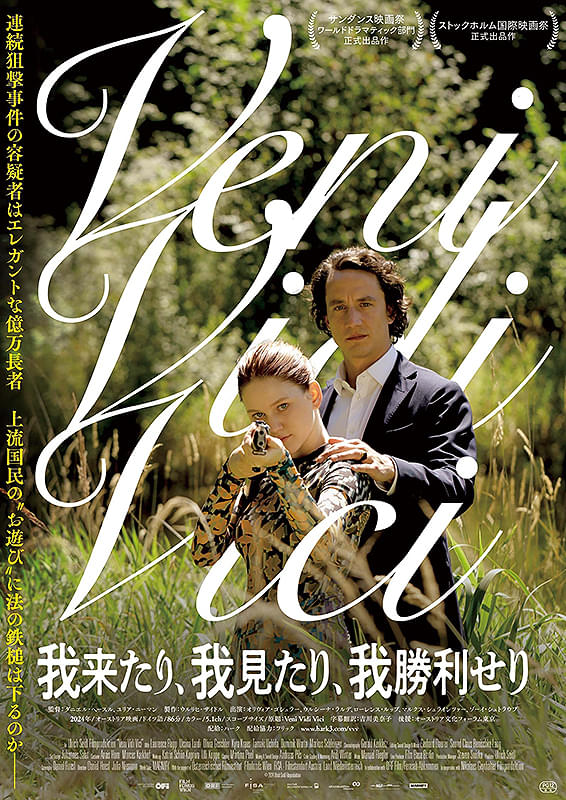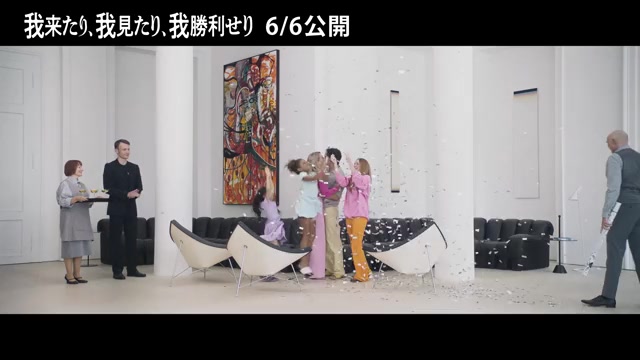我来たり、我見たり、我勝利せり
劇場公開日:2025年6月6日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
本編を見るPR

解説・あらすじ
「狩り」と称して人間を狙撃するエレガントな億万長者の姿を通し、資本主義の終末的世界をシニカルなユーモアで描いたオーストリア映画。
起業家として成功し、莫大な財産を築き、幸福で充実した人生を送るマイナート家。家族を愛する父アマンは趣味の狩りに情熱を注いでいるが、狩りの対象は動物ではない。“上級国民”である一家は何を狩っても許され、アマンは何カ月にもわたって無差別に人間を射殺し続けていた。時にはその様子を目撃する者もいるが、誰も彼を止めることはできない。娘のポーラはそんな父の傍若無人な姿を目の当たりにしながら、上級国民としてのふるまいを着実に身につけていく。そしてある日、ついにポーラは父と一緒に狩りに行きたいと言いだす。
「失恋セラピー」のローレンス・ルップが父アマンを演じ、「さよなら、アドルフ」のウルシーナ・ラルディ、「フィリップ」のゾーイ・シュトラウプが共演。「パラダイス」3部作のウルリヒ・ザイドル監督が製作を手がけ、ダニエル・ヘースル&ユリア・ニーマンが監督を務めた。
2024年製作/86分/PG12/オーストリア
原題または英題:Veni Vidi Vici
配給:ハーク
劇場公開日:2025年6月6日
スタッフ・キャスト
- 監督
- ダニエル・ヘースル
- ユリア・ニーマン
- 製作
- ウルリヒ・ザイドル
- 脚本
- ダニエル・ヘースル
- 撮影
- ゲラルト・ケルクレッツ
- 美術
- ヨハネス・サラート
- 衣装
- アナイス・ホーン
- マーカス・カルコフ
- 編集
- ゲルハルト・ドーラー
- 音楽
- マニュエル・リーグラー
- ゲルハルト・ドーラー
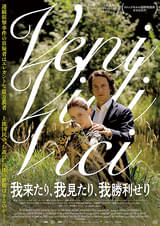

 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子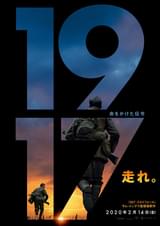 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令