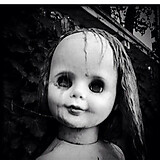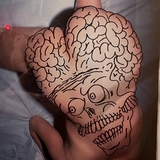雨の中の慾情のレビュー・感想・評価
全128件中、1~20件目を表示
現実のふくらみ
最初のシーンで、義男ー成田凌と夢子ー中西柚貴がカメラを無視したかのように全裸になって、それを自主映画ではないからとモザイク処理するあたりにこれは片山監督作品であり、とても期待できる作品とも思った。ただ監督は片山慎三がやって、原作はつげ義春、主演は成田凌ぐらいにしか事前情報を入れていなかったから、どこまでが片山監督のオリジナルな部分なのか分からなかった。そしてエンドクレジットで、脚本協力に大江崇允の名前。大江さんは濱口監督作品『ドライブ・マイ・カー』に脚本としてクレジットされている。そこから、本作もまたつげ義春のいくつかの作品を重ね合わせた脚本なのではないかと推測された。
そんなわけで、パンフレットと原作が所収されているちくま文庫の『ねじ式/夜が掴む』を購入した。パンフレットから本作が「雨の中の慾情」の他に「夏の思いで」と「池袋百点会」、「隣りの女」の要素を重ね合わせたことが分かった。そして戦争を描いたのは、片山監督のインタビューでロケハンのために金門島を訪れたことがきっかけとのこと(p.14)。尾弥次ー竹中直人が、片手と片足がないことは衣裳デザイン・扮装統括の柘植伊佐夫の提案であった(p.22)。この尾弥次の人物造形は、戦争の苛烈さと本作の主題になる現実と夢のアンバランスさを表現するため、脚本が要請したと思っていたから驚きの発見であった。
さらに原作を読んで驚いた。「男が雨宿りをしているうちに女に慾情する」ただそれだけの短編だったからだ。もちろん高野慎三の「解題」によると絵コンテの段階で発表されたものであり、エロマンガを描いて生活苦から逃れるために下書きとして試みられた作品ーただエロマンガの依頼はなかったーであること(p.334)が分かった。だから原作の良し悪しはここでは評価しない。だが本作の始まりである「戦時中、義男が雨宿りをしているうちに夢子に慾情し、それは夢であった」ということは、かなりオリジナルな要素を含んでいることが分かる。
ではなぜこのオリジナルな要素が追加されているのか。原作の3コマ目には次の文章が書かれている。
「(前略)ただ、こんな空想をしたというだけのことです」(p.85)
「ただ、こんな空想」ができる現実。それがいかに夢物語であるかを本作は描いているように思えるのだ。
ーーー
再び高野の「解題」によれば、原作が所収されている『ねじ式/夜が掴む』は、「「ねじ式」にはじめる“夢の作品群”と、それらとあたかも並行するように発表された。マンガ家の若夫婦を主人公とする“日常もの”が収録」(p.330)されている。その分類に従えば、「雨の中の慾情」は“夢の作品群”、同じく所収され義男がマンガ家であることとひき逃げの出来事で翻案される「夏の思いで」は“日常もの”といっていいだろう。これらからこの2作品を折り重ねた本作は夢と日常が並行して語られていると言えるはずである。
マンガ家の義男は、未亡人の福子に惚れ込み一緒になることを夢見ている。しかし福子は義男の知人で小説家の伊守と既に付き合ってしまっている。そんな現実に嫉妬し、羨望するしかない義男は彼らのセックスを窃視するしかできない。この窃視による義男と福子の隔たりは、夢が決して果たされない不条理さを物語っている。
さらにその現実もまた夢なのである。「マンガ家の義男が、福子に惚れ込み一緒になることを夢見つつ、それが実現できない現実」は、戦争で片腕と片足を失った義男が病室でマンガにして空想した夢なのである。義男は福子と一緒になれないばかりか、その一緒になれない現実さえも夢なのである。
しかもここで終わらないのが片山監督である。「「マンガ家の義男が、福子に惚れ込み一緒になることを夢見つつ、それが実現できない現実」を戦争で片腕と片足を失った義男がマンガで描き夢見るしかない現実」もまた夢なのである。残された現実とは何かと言えば、戦場で現地の人びとが無残に殺され、爆撃が轟くことに怯えるしかない義男が、現地の少女に撃たれて死ぬ逝くことである。福子もまた戦地に連行された娼婦であり、義男と福子の関係は娼婦と客の関係でしかないのだ。
義男は娼婦を運命の人≒福子と空想し、戦争が終わったら平穏な日常を共に生きることを夢見ている。しかしそんなただの空想さえもできないままに死ぬ、現実を生き延びられない。そんな現実の幻≒虹を描く本作はかなり残酷である。
本当は私たちだって、つげ義春の世界観のようなただの四角い部屋で夢をみていたい。しかし部屋の外から現実がふくらんでくる。夢が果たされない〈私〉の残酷な日常が、腐敗した政治が、資本の論理で駆動する経済が、終わらない戦争が。だから「ただ、こんな空想」ができる現実も大きな隔たりを伴った夢なのである。
そんな現実から背かず目を見開ける?それを問うているのが本作であり、片山監督であり、原作に戦争を導入しながら夢と日常を並行して語った翻案の素晴らしさなのだ。
参考文献
『『雨の中の慾情』公式パンフレット』(2024)カルチュア・パブリッシャーズ
つげ義春(2008)『つげ義春コレクション ねじ式/夜が掴む』筑摩書房
「超大作」の体をなした「猛毒映画」か
あながち関係ない話でもないのだが、映画「ルックバック」について、ちょっと触れる。
映画「ルックバック」は確かに興味深く観させていただいたが、やっぱりオレは原作の「間」や感じるアングラ感が好きで、音楽や声も本当に必要なく、静止した画に十分感じる躍動感を動く絵で表現するのは映画なので仕方ないとは思うものの、どんなに斬新であろうとも「ああ、そうするんだ」と冷めて観てしまった。
つげ義春。オレは映画「ねじ式」(’98)から入って、原作を眺めた程度だが、原作を見るまでは、映画は非常に面白く観させてもらったが、原作を読むと、映画のほうは、役者の演技、映像表現、録音そして音楽と、目いっぱいアングラ感が出ているものの、原作の一コマのパワーの前では、「ああ、ここをこういう風に映画はやりたかったのね」と冷めるわけだ。
こればっかりは漫画と映画の決定的な「文化の差」として映画を見る側としては、割引くしかない。この辺はオレが言わずとも、誰もが、そして映画関係者が一番感じることだろう。(そして原作者。)
なので、原作とかどうとかは、これが最後でここでは触れないようにしたい。
「雨の中の慾情」
・
・
・
それでは、どうしてわざわざ原作と映画について、前置きを置いたかというと、まさかこんな超大作にしてしまうなんて思ってもみなかったからだ。
すごい!!
「さがす」で一躍名を馳せた片山慎三監督のこれまでのキャリアが爆発。
オープニングの雨のシーンから撮影がすごい。そこからアングラの真逆を行くロケ撮、カメラワーク。時に大自然、夕日、海を大作感たっぷりに美しく撮り、戦場での1カット長回し、時にあえての手振れを起こす手持ち撮影、新旧合わせ技のトリック撮影、まさしく「総動員」。
大枠は「ねじ式」と同じく、いくつかのストーリーを足し合わせての構成だが、うまいのはちゃんとラストが収まるように、つまり「超大作」としての体をなすべく物語を完結させている点。
映画なので、集客はしなければならないため、戦場シーンを予告にいれたのは、ちょっとばかし驚きを殺してしまってはいるが、それでもそんなシーンがあんなところで、と鑑賞中でもインパクトは絶大。
ただ公式で「あの作品」を参考にしている、と監督が発言されたらしいが、それを言ってはダメ!!(主人公の顔のぐるんぐるんして逃亡するカットもこれのオマージュですかね)
ということだから、というわけでもないだろうが、「ラブストーリー」ということで宣伝はされているが、必然的に「反戦映画」としての一面も持ち合わせている。天井のシミが「あれ」になって「始まる」のだから、絵描き志望の想像力か、童貞の想像力か、ともあれなんとも切ない。
ただしちょっと物議を醸しだす設定、描写もあるため、批判も多いとは思う。
だけど、激しい性描写も含め、「超大作」の体をなした「猛毒映画」というバランスが、オレはとっても心地よかった。
序盤は我慢しなさい。
追記
中盤、「アマポーラ」が流れることからも、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」、個人的には、ジャコ・ヴァン・ドルマルの「ミスター・ノーバディ」('09)あたりの語り口の良さも感じていい気分で帰った。
追記2
同時に「ルート29」のことをちょっと思い出した。「詞」を「詞的」に映像表現することもそりゃあ、もう大変なことだ。ただ森井監督には次作はスコーンと観られるものをお願いしたいなと。
いずれにせよ、片山監督と森井監督には今後も大注目。
胡蝶の夢
本作については当サイトの新作映画評論の枠に寄稿したので、ここではまず前半で補足的なことがらと、後半で評論では触れなかったネタバレ込みの映画の仕掛けに関することを書いてみたい。
【前半:参考資料やトリビアなど(ネタバレなし)】
・映画の原作となった短編漫画は、評論でも紹介したように4編ある。いずれもeBookJapanの電子書籍シリーズ「つげ義春作品集」に収められていて、執筆前にすぐ読むことができて大いに助かった。作品集#8『リアリズムの宿/下宿の頃』に「夏の思いで」、#12『近所の景色/少年』に「雨の中の慾情」、#13『隣りの女/ある無名作家』に「池袋百点会」「隣りの女」がそれぞれ収録。興味のある方はぜひ。独立した4編を巧みに継ぎ合わせて映画の本筋を構成していることが確認できる。
・義男の作業スペース(芸術空間)の壁には「目」だけを描いた絵が多数貼られている。つげファンなら、すぐに代表作「ねじ式」の印象的な一コマ、大けがをして医者を探している主人公が迷い込んだ目の看板だらけの通り(吹き出しの文字は「ちくしょう 目医者ばかりではないか」)へのオマージュだと気づくだろう。この通りの景色はかつて実在し、台湾の写真家・朱逸文が地元の台南で撮影したものが1963年に日本の写真雑誌に掲載され、それを見たつげが漫画の一コマに描いた。台湾の古い街並みにあった「多数の目のイメージ」をつげが日本の漫画に描き、半世紀以上を経て、台湾でロケをしたつげ原作の日台合作映画のシーンに再登場したことは、ちょっとした奇縁のように思われる。
【後半:映画の仕掛けについて(ネタバレあり)】
ここからは本作を鑑賞済みの方を想定して、映画の重要な仕掛けに関連することを書く。もし未見の方が読むと鑑賞時の新鮮な驚きを損ねてしまうので、この先には進まず観たあとに再訪してもらえるとありがたい。
また、関連作として2005年の「ステイ」、2007年の「コッポラの胡蝶の夢」、2010年の「レポゼッション・メン」についても触れる。この3作を未見の場合、やはりそれらのネタバレになってしまうので読み進めるのはおすすめしない。3作とも面白いので、ぜひ事前情報少なめで先に鑑賞していただきたい。
では、ここから本題。評論のテキストでは少しぼかして、「映画『雨の中の慾情』は、先述のつげ漫画をベースにしたパートのほかに、予告編で示された戦場の場面を含む映画オリジナルのパートがある」と書いた。すでに鑑賞済みの方なら、つげ漫画をベースにした本筋が、実は戦場で瀕死の状態にある兵士が見ている夢だったと気づいただろう。死の間際の一瞬に人生が走馬灯のようにフラッシュバックするのはよく聞く話だが、最近の研究でも死の間際に脳内麻薬のエンドルフィンが出て苦痛を緩和することがわかってきたそう。本当の人生の代わりに、願望の日々の夢をリアルな出来事として一瞬のうちに体験することもあり得るだろう。
先に挙げた「ステイ」「コッポラの胡蝶の夢」「レポゼッション・メン」はいずれも、この「雨の中の慾情」と同じ仕掛けが使われている。つまり、本編で主人公の実体験として観客が受け入れていたストーリーの相当部分が、終盤で実は主人公が見ていた夢だったと明らかになる。3作の中でも、「ステイ」が特に「雨の中の慾情」に近いと思う。推測だが、片山慎三監督がつげ漫画4編で組み立てたプロットと、台湾でのシナハンで追加した戦争の要素を含むオリジナルの筋をどうつなげるかを検討した際に、「ステイ」の仕掛けが使えると思いついたのではないか。「ステイ」ではユアン・マクレガー演じる主人公が死の間際に見た看護師(ナオミ・ワッツ)が、夢の中では恋人になっているなど類似点も多い。
紀元前の中国の思想家・荘子の有名な説話「胡蝶の夢」のように、現実だと思っていたら夢だった、あるいは夢なのか現実なのかよくわからない境地といった考え方、アイデアは古くからあるが、現代も多くのクリエイターたちを惹きつけてやまないテーマでもある。とりわけ映画というメディアは、暗闇に映し出された他者の人生や非現実的な出来事に没入するという、映画を観る行為そのものが夢を見ることに似ていることから、これからも「夢と現実」を扱う映画は手を変え品を変え作り続けられるのだろう。
つげ流カルト映画
好きな人はたまらなく好き、だろうし、
ハマる人にはハマる、んだろうなぁ
と僕はシラケにシラケて観ていた。
成田凌さんファンであっても時計を見るとまだあと1時間ある。
って、あと、これをまだ観るの?
と驚いた。
カルト映画の部類ですね。
片山慎三監督作『岬の兄妹』『さがす』は傑作だと評価しています。
ただ、僕は昔からつげ義春さんのファンタジーに嫌悪感しかないので、合うわけがない。
いくら成田凌さんがどの角度から撮ってもイケメンと分かっても、僕の中ではムリだった。
(だだ終盤に成田凌さんの目のアップがあり、
こんなに睫毛が長く美しいなんて世の女性は嫉妬や羨望をするだろう、と驚かされた。)
車に跳ねられた女性が10メートル以上飛んでいる。
滑稽に飛んでいるので、同情より嗤いが止められないが、
その女性が抱擁され接吻するという、
つげワールド的に
ツッコむより呆れて、もうこのセンスは自分には理解不可能ですと退散したほうが利口かもしれない。
片山慎三監督作の割に、撮影は凝っていましたね。
つげ義春の漫画を合体して映画をつくりたいんですよ ダメー
2024年公開作品
原作は『無能の人』『ねじ式』『リアリズムの宿』のつげ義春
監督と脚本は『岬の兄妹』『さがす』『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』の片山慎三
脚本協力は『チャチャ』の大江崇允
負傷した日本兵の妄想?
漫画家の構想?
エログロナンセンスの典型
原作は『雨の中の慾情』『池袋百貨店』『夏の思いで』『隣りの女』の寄せ集め
台湾ロケ
つげ義春の世界を表現するには必要か
これ絶対入ってるよね案件
成田も中村も頑張ってるが出番が少ない中西も高く評価したい
走るときの激しく揺れるプルプルが印象的
喫茶店で「こんど映画でヌードになるの」と中村映里子に言われても「へーそうなんだ」と空返事するかもしれないが中西柚貴ならびっくりして椅子から転げ落ちるかもしれない
配役
売れない漫画家の義男に成田凌
喫茶店で働く未亡人の福子に中村映里子
自称小説家の伊守に森田剛
営業の須山に足立智充
バス停の夢子に中西柚貴
広告に出資する靴屋に松浦祐也
出版社のXに梁秩誠
女子高生に李沐薫
日本兵に伊島空
富豪の娘のシェンメイに李杏
怪しい商売をしている義男の大家の尾弥次に竹中直人
尾弥次の愛犬にミコ
商店街に店主に張宗佑
前半は中々楽しめるのだけれど
成田凌さん、中村映里子さん、森田剛さんのトリプル出演という位置付けの映画。
実際は、成田さんが主役です。
ほとんどのシーンを台湾で撮影していて、物語もその雰囲気が色濃いですね。
前半は中々楽しめるのだけれど、途中からはあーあ、という感じになり、私はついていけなかった感じです。
つげ義春の同名の短編漫画を原作にして、独自の解釈を加えて136分にしたというから、然もありなん。
余談ではありますが、中村映里子さんのスレンダーで素敵なオールヌードが、相当な時間で映されます。
不可思議な人間関係を描くミステリアスな作品
『ねじ式』等で知られる漫画家、つげ義春の原作をもとに作られた不可思議な人間関係を描くミステリアスな作品。
現実と幻想の区別が入り混じって描写されるため、「現実があって夢想する場面が挿入される」的な分かりやすい構造ではなく、どちらが現実なのかが見れば見るほど分からなくなってくる。
一つ恐らく確実にそうだろうと思えることは、作品自体が太平洋戦争後のPTSDに苦しむ戦地に赴いた主人公(あるいは原作者)のトラウマがベースになっているということ。
そして、そのことは原作者のつげ義春が一時期、水木しげるのアシスタントをしていた事実とも決して無関係ではなかろう。鬼太郎等の妖怪もので知られる水木しげるは生々しい南方での従軍記の漫画でも知られており、過酷な生と死が背中合わせの体験をしてきたことが現世とあの世の合間に生きる妖怪に惹かれた理由だとも言われている。
なお、タイトルからも想像できるように性的な場面も全編を通して散りばめられている。原作は未読なので、それがどれだけ原作に忠実なのか、どの程度が映画的演出なのかは分からない。ただ、場合によっては不必要に思えるものを含めた性描写は、死や絶望と直面した際の対極の表現として、生を希求する渇望の描写として描かれているのではないだろうか?
決して一筋縄ではいかない作品なので、観に行くのは精神的に少し余裕のあるときの方がいいかも知れない。
前半は面白いが後半はなかなか難解
俳優、成田凌を鑑賞
最近気になっている俳優の一人だ。
断っておくが、私は至ってノーマルなオジサンだ。
彼は典型的な「男前」と評されるタイプではないと思っている。
しかし、個性的な顔立ちでもなく、むしろ端正な造形の持ち主だ。
ただし、その整い方が華やかでも、威圧的でもない。
佇まいにギラついた自己主張がなく、どこか静かで含みのある空気が漂う。それが単なる無邪気さなのか、それとも深い思索の表れなのかは判然としない。
同様に知性を感じさせるものの、本当に賢いのか、それともそう見えるだけなのか(失礼)も測りかねる。
それが彼の魅力の一端だろう。
短い台詞を発するたび、その言葉の裏に何かを感じさせ、惑わせる。
そして時折、穏やかな佇まいの奥に、ふと凶暴性を秘めているのではないかと思わせる瞬間がある。
それでいて、どこか安心感をも与える不思議な存在。
彼の魅力は、明確な個性にあるのではなく、その曖昧さと余白の中にこそ宿っているのかもしれない。
歌のないオペラ
つげ義春原作の短編漫画4作品をベースに創作されたラブストーリーだそうだ。学生時代つげ義春の漫画が一時流行った記憶があるのだが、サブカルにはまっていた友人から貸してもらった漫画を読んでも何が面白いのかサッパリ。要するに当時の私がガキすぎて、つげの魅力がわからなかったのである。現代のウォークカルチャーの枠に当てはめるとすべてNGになりそうな、エロ、エロ、エロのオンパレード。しかしながら、無機質な絵と乾いたコメディに漂うなんともいえないペーソスが癖になった人も多いのではないだろうか。
なぜこの令和の時代につげ義春をピックアップしたのかは不明だが、片山監督が今までの路線とはまったく違う映画を撮りたかったことだけは伝わってくる。ポン・ジュノ譲りの生臭いバイオレンスとカタルシスを捨て去って、監督は本作で“(歌のない)オペラ”をやりたかったのではないか。日本統治下の台湾で瀕死の重症を負った一兵卒が死に際にみた支離滅裂な“夢”を、ベルトリッチ風に幻想的につなげた作品ではなかったのだろうか。監督御本人は本作を撮るために、『ジェイコブズ・ラダー』や『エターナル・サンシャイン』を参考にしたと語っていた。
男が死の床で思い出すのは、初恋の女や長年連れ添った女房のことではなく、娼婦と交わった激しいSEXのことらしい。義男(成田凌)が最期に思い出したのも、従軍慰安施設に暮らす娼婦“福子(中村映里子)”のことだった。義男の夢の中で、小説家の情婦やアドレノクロム採取施設の看護婦、ピンボールのように車に撥ね飛ばされる女、はては義男に漫画を描くためのカリグラフィーをプレゼントしてくれた恋人へと、次々とそのキャラ設定を変えていくのである。『マルホランド・ドライブ』のナオミ・ワッツのように。
映画冒頭はつげ義春原作の『雨の中の慾情』とまったく同じ展開だが、映画ラストをあえて原作漫画とは異なる終わらせ方にしている。原作では、田んぼの中で激しい情事に及んだ義男と人妻が、雨上がりの🌈がかかっている中を、何事もなかったようにバスに乗り込む場面で終わっているらしい。しかし、片山はその“🌈”だけ拝借した独自の解釈で本作を終わらせている。聞くところによると、ロケ地となった台湾では🌈の橋を渡って死人があの世に向かうという言い伝えがあるそうで、(漫画も映画も)エンディングは誰かさんの“昇天”を暗示していたのではないだろうか。
台湾でロケハンの最中も、中国軍艦がこれ見よがしに近郊の湾に停泊していたらしく、日本人が想像する以上の緊張感が周囲に漲っていたという。片山監督はその雰囲気を察して、戦争シーンをわざわざ後から付け加えたのだとか。私は思うのである。男と女が本能のままに激しく交わってさえいれば、そもそも戦争なんて起こりえないのではないか。それを法律や道徳、カルチャーで無理やり抑えつけたりするから戦争が起こるのではないか。人間の本能の中に隠れているエロスには、生殖以外にも我々がいまだ気づいていない役割が他にあるような気がするのである。たとえそれが、雨上がりの🌈のごとく、女の記憶からはかなく消え去っていく男の幻想だったとしても。
騙し絵のような映像
冒頭、義男の部屋の壁にプリズム様な光が映り細かに動く、これがラストシーンに繋がる。
物語の前半は所謂夢落ち物かと思いきや、やがて二重三重に畳み掛ける多重構造であることに気付かされる。夢の断片が儚く舞い散る様を映し出し、登場人物の内面に潜む複雑な感情や欲望を象徴する。夢の中でしか存在し得ない非現実的な光景と、幻覚のように錯綜する映像表現は、観る者に多層的な解釈を促す鍵となっている。監督は、意識の深淵に潜む夢と幻覚を大胆に表現し、その斬新な演出と緻密な心理描写は、観る者に深い感動と衝撃を与える。
ラストシーン、義男が今際の際に冒頭のプリズム様の光を再び見る。細かく揺れながらやがて臨終を迎えると同時に消えさる。死を迎え瞳孔が開き眼球の虹彩が消えるという比喩なのか。
結局、義男が見ていた夢幻は銃で撃たれ死ぬ間際に見た一瞬の走馬灯だったのだと観客は気付く。良くぞこれ程、複雑で綿密な構成をしたものだと感服した。
虚構の数珠
つげ義春先生はご存命
短編がほとんどとは言え膨大にあるつげ義春作品は大昔にねじ式を読んだだけ。幻想的でよくわからなかった上、今となっては魔太郎みたいな顔の主人公とメメクラゲしか記憶にない。その程度のつげレベルで本作を観たのだが、話をどう解釈するかは人それぞれでも、夢と現実を行き来する構成は原作ほどの意味不明さはなくけっこうわかりやすい。
福子がポーンと車に撥ねられるシーンや子どものつむじから液体を吸いとるエピソードなど、所どころで違和感ありありのつげ義春世界を、壁のシミを福子の裸体と被らせたり日常から惨劇の戦場に突然切り替えたり、片山慎三監督の演出で見応えある映像にしていたと思う。夢と現実との交錯は、思えば序盤から女子中学生のぎこちない日本語からすでに始まっていたのだろうけど、鑑賞したのがすでにひと月近く前なので、オレの記憶もどこまで本当なのかあやしくなっている…。
様々な時代、夢と現実を往来するつげ義春原作の映画化作。 「欲情...
つげ義春の、というのではないエロスと平和と戦争
2025年最初の映画。思いの外と言っては失礼かもしれない力作にしてそこそこの大作風。タイトルが小品感を醸しているのと、予告編はこれまたまったくそれとも違う感じで派手な感じもしたのだが、見ればもっとずっしりな野心作。まあ片山慎三なのでそりゃそうだ。エロスを包み込む戦争と平和。なんじゃそりゃ、と思うが本当にそういう出来。但しパーツパーツは野心みなぎるが物語設計は夢物語風味だからか大きな推進力に欠ける。最も単純なふたりの男とひとりの女の構図だけでも決して巧みに見せきれてるとは言い難い。成田凌はとてもいいし、なんとなく昭和エロス的シチュエーションはあるが長編を引っ張るほどのスリリングなアイデアはない。かといってつまらないかというとそんなこともなく、断片断片ははっとさせられる表現はてんこ盛り(雷、雨、車ですっ飛ぶ女体、シームレスに入ってくる日本軍の攻撃) 片山真三はサービス精神の塊なのかもしれない。力技でそうはなっているけれど、本来短編で強いエッセンスのものは短編のままのほうが強い印象を残すんだな、とは思った
なので予告編的要素とはぜんぜん違う面白さではあった
全128件中、1~20件目を表示