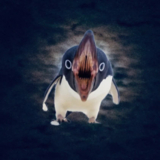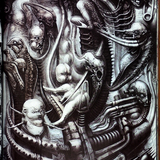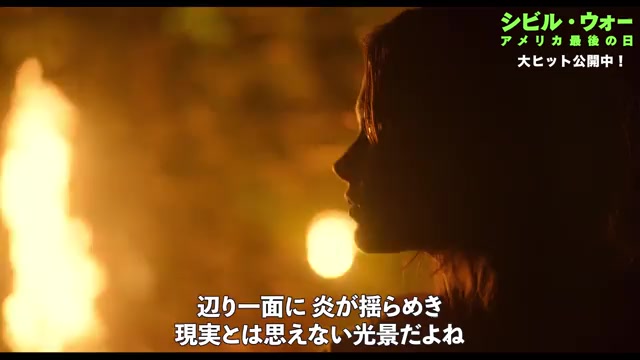シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全231件中、101~120件目を表示
「どの種類のアメリカ人だ?」---近い未来の南北戦争。
予告を見て興味を惹かれ鑑賞。
あらすじとしては、そう遠くない未来のアメリカ。大統領の横暴に20近い週が独立を宣言。アメリカ国内で同じアメリカ人同士が殺しあう「内戦」を描いた作品。
上記の状態に陥ったアメリカにて、戦場カメラマンの主人公ら4名が1,000km以上の道のりを経て、途中、同じ「アメリカ人」でありながら殺しあう人々に直面しながらもホワイトハウスまで「大統領に話を聞きに行く」っていうのが本筋。
正直「ブラックホーク・ダウン」のような銃撃戦を期待していたのだが、はっきり言ってそこまでの迫力や激しさはない(予告で戦闘機も出ていたので、そういったものを期待させられていたのだが)。ただ日常が一変する「リアル」さは感じられたし、恐らく日本人には理解しがたい(私に学が無いだけの話であるが)「人種差別」というアメリカにおける根の深い問題を大きく取り扱った作品だと感じた。
自身の学の無さを棚に上げつつも印象的だったシーンは、主人公らが危機に陥り「どこ出身だ?」と問われるシーンがあるのだが、その前後に銃殺した死体に「白い粉のようなもの」を振りまいている場面がある。最初私は「疫病防止か何かのためにやっているのか?」ぐらいの認識だったが、ただ単純に「白くしていた」のかと解釈するとゾッとした。私が思うにこの感覚は日本人には到底理解できないと思う。
少々予告やタイトル詐欺感は正直否めないが、色々と考えさせられる作品であった。欲を言えば、アメリカ史や地理などを教養として身に付けていれば、さらに楽しめる(という表現はどうかと思うが)作品だと思う(教養が皆無なため、家に帰って南北戦争などを調べるいい機会になりました)。
※なお、途中お手洗いに離席し、10分程観れていないためレビューの☆は少しプラスしております。動画などで配信されたら見返してみる予定です。
怖い怖い
超大国アメリカが南北戦争以来のシビル・ウォーだなんて突飛な話、さすがA24。
でも、大統領選の両陣営の対立見ていると、あながち突飛ではないかも、と思えてしまうところがアメリカだと思う。
一切説明無くいきなりアメリカが内戦状態というところから始まる。
テキサスとカリフォルニアが中心の反乱軍と政府軍の戦いらしいが、政府軍は圧倒的に劣勢という状況。
「ソウルの春」を連想した。
兵士の話かと思っていたら、戦場カメラマンの話だった。
特ダネをものにしようと、ニューヨークからワシントンD.Cに向かう老若男女4人のロードムービーらしき部分は、遭遇する各地のニンゲンが怖い。どさくさに紛れて大量虐殺実行中の赤サンのアタオカレイシストには、出身を聞かれたらなんと答えるのが正解なのか、州名を言ったところでアジア系の二人は、殺られただろう。
アメリカはひとつの国だが、多様性、といえば聞こえは良いが、時代が変わろうが関係なく頑固頑迷に自分、または自分たちの主義主張や生活習慣を貫き通して他者を理解しようとか歩み寄ろうとかまったく考えない人たちがそこそこの力を持って存在しているのだとよく分かる。
自分たちの正義のみがこの世の正義、反するものは暴力で排除するのも正義、な人々は、かなりの数が脈々と、現在でも生息し続けているのだ。
歴戦のヒーローのはずのリーは、ワシントンD.Cの戦闘にビビってすくんでしまうが、ジェシーは怯まない。
そして、戦場カメラマンにあるまじき、「人助け」をしてしまうリー、それは、一流の戦場カメラマンの資質が劣化していることであり。代わりに、自分を庇って撃たれた先輩の一連の死に様をカメラに収め、値のつく写真をモノにして平然とその場を去っていくジェシー、鮮やかな世代交代劇だが、戦場カメラマンは、人間らしいところがあっては一流になれないということがよく分かった。自分のわがままで周囲に多大な迷惑をかけても、犠牲者を出しても全然平気なジェシーには、その素質が備わっていると思う。
この映画、ヒトの「怖さ」のバラエティを見せつけていると思う。
そして戦争は、それらの坩堝、集大成のようなものなのだ。
ワシントンD.Cの市街戦が大掛かりでど迫力の臨場感、激戦を渦中で見ているようだった。
お金がかかっていて驚き。頑張ったね、A24。
絶望の庇護
Civil War
戦闘の最中に、大義を語る時間はない、内戦なんてそんなものだ。差別意識はあるかもしれない。
報道の価値を見失っている。
人が死ぬ瞬間ばかりを映し、もう誰も草花の可憐さには目を向けなくなっているからだ。
PRESS(報道機関)の文字、それが含まれた写真は不出来だ、だが最後はそれのみが写った写真が混ざる。その後奥地へと向かう。
百戦錬磨のリーが怯えていたところから、吹っ切れたように動き出し、そして最後は経験から後輩を守る。何かを託しているのだろう、でもそれは誰かが、確かに受け取るものだろうか。
ANARCHY in the USA
『フルメタルジャケット』ではThe Trashmen「Surfin' Bird」がとんでもないシーンで使われていてショックを受けたけど、本作も同様かそれ以上な演出効果。映像スペクタクルはもちろん音楽演出と音響効果がまた凄まじかった。
敢えて残虐な場面を狙ったタイミングなDE LA SOUL「say no go」には、極限状態の戦時下では飲み食い寝ると同様に撃ち撃たれ酷い目に遭う遭わせるは茶飯事だという冷徹描写を感じた。因みにこの1989年にリリースされた曲でデラソウル彼等がサンプリングしてるのはHALL&OATS「I can't go for that」(そんなの無理、俺には出来ない)で、場面と曲タイトルと元ネタタイトル含め受け取るものが重なり感心したというか衝撃だった。冒頭のデモがヒートアップしてくる場面空気にネチネチとシンクロしたSilver Apples「Lovefingers」のアンダーグラウンドな浮遊感も現実とのコントラストが乖離し過ぎて恐ろしく聴こえ、4人がボーダーラインを越えるシーンでのSUICIDE「Rocket USA」も同じ残忍さ。アランヴェガの陰湿なVoと無機質なマシンビートが気持ち良い位にこれから起きる恐怖を煽っている。客に容赦しない攻撃的な演出。
環境音も凄まじい。M16の乾いた発砲音や地鳴りの様な重火器にヘリの爆音など全て衝撃波喰らいそうな程の臨場感。西部軍駐屯地から出撃するシーンはひたすらヘリの爆音を何機も何機も重ね、これから更に酷くなる逃げ場の無い閉塞感を爆音で象徴。目の前の惨劇で状況を受け入れられないパニックでのミュート描写には心と理性の飽和状態をイメージさせられた。初めて体験すれば誰でも処理不能だろうな。
太陽光に輝く大自然やファンタジックな美しい映像が激烈な場面の合間に挟まれるけど、この強烈な場面構図コントラストも互いを引き立てていて、戦時下の感覚が麻痺するであろう状態に誘導されていく様だった。もうトリップ感覚ですよ。
戦場ジャーナリストとして急激な成長を遂げるジェシーと豊富な経験値が故の嗅覚で本丸に突き進むリーのアクションには強いキャラクターが現れていて分かりやすく、それがDCの激烈な戦闘シーンで描かれるクライマックスには人間の明確な物語がある。逆に各勢力の主義主張も明らかではない設定の本作は、政治イデオロギーや経緯全て客に丸投げしている。現実として実際に分断を経験しているアメリカが産んだ優れたかつアナーキーな仮想現実作品。
なんだこりゃ
そもそもなぜアメリカ国内が内紛状態になったのか、頭が悪い俺用に説明して欲しかった。これまたそもそもなんだが、従軍記者ってヘルメットも無しでノコノコと軍隊に付いて行くばかりか、兵士よりも前に出て写真を撮るもんなんですか?俺が兵士だったら記者を蹴り飛ばしますけどもね。外交官みたいな免責特権があるんでしたっけ。見習いのような人間はまだしも、歩行困難な肥満体のオッサンも付いてくると来たもんだ。アジア人記者が中国人と告白した瞬間に忖度なしに即射殺されたのには笑いました🤣
主人公たちはどういう種類の記者なのか
背景を敢えてぼかして語られるアメリカの内戦。
劇中の大統領は3期務めていることから大統領時代のトランプの発言をベースにしているようにも見えますし、武装蜂起を許す脇の甘さや喧嘩慣れしていない政府軍の動きからすると、今の民主党政権のようにも見えます。
現実のアメリカが現在進行形で突き進んでいる地獄にタバスコをひと瓶ぶっかけて過激にしたような設定は、見事でした。
ただ、ストーリーの面で言うと、背景をぼかした副作用で少しピンボケになってしまったように感じました。
最初の大統領の場面以外は、主人公4人の視点から逸れることはないので、足取りをずっと追うことになります。彼らの目的は、大統領が死ぬ前にインタビューをすること。バーでそう話している姿を見たとき、ジョエルとリーからただならぬジャーナリスト魂を感じたわけなんですが。
蓋を開けてみると、彼らは内戦全体を俯瞰しているジャーナリストというより、西部勢力側の記録係のような位置づけでした。
なので、私は最初から最後まで4人の誰がどう死んでも構わないと思って観ていました。彼らがカメラで切り取っているのは、西部勢力が戦う姿。彼らの写真が教科書に載れば、西部勢力が英雄として描かれます。
その後、仮にフロリダ連合と仲間割れして、フロリダ連合が西部勢力を追い出せば、彼らについていたカメラマンが写真を『上書き』します。
それはジャーナリストか? 単なる軍属のカメラマンでは?
そういう違和感もあり、リーがサミーの遺体の写真を消す場面では、この人は報道する側としての矜持を完全に捨てたなとがっかりしましたし、ジョエルがサミーの死を嘆く場面でも、情緒やば…ぐらいの感想しか出てきませんでした。
なんとなく、それまでの彼らの『楽しそうな』ノリに、振り落とされた感があります。
ただ、それを打ち消すぐらいに戦闘が派手なので、銃や爆発が大好きな私としては、いい塩梅に楽しませてもらいました。
小道具まで凝っており、例えば民兵が持っているAR15は民間仕様の16インチ銃身が多く、西部勢力のような兵士はちゃんと素に近い10.3インチ銃身のCQB-Rを持っていたり、芸が細かいです。
あと、民間人が普通に生活している中での戦争だからだと思いますが、地雷が出てきません。
そんな中、最も記憶に残ったのは、赤メガネの軍団がリーたちを拉致した後、乗っていたランクルを隠さずに道端へ放ったままにしている場面でした。仲間を敢えて呼び寄せて、1人でも多く殺すことしか考えていないような、独特な思考回路。
赤メガネ自身がどういうアメリカ人なのか分からないままなのも、怖いです。
今は愛想笑いで日常生活を送っていても、みんな一枚めくればあんな感じで、必ず『どっちかの側』にいるのではないかと、良くもない想像をさせてくれます。
?で不快な作品
銃社会のアメリカで政府が崩壊し秩序や正義が守られなくなると、どうなるのか?
その景色をまざまざと見せつけられる作品です。
銃と物資をもつ個人の価値観が正義であり、法となり、そのルールがアメリカ自体を覆っているなかで、この凄惨な状況を世界に伝えることこそがジャーナリズムの使命ではないか。
そのために主人公であるジャーナリストたちは大統領のインタビューを撮るためにNYからワシントンDCへ向かうのだ。
と、勝手に思ってました。
でも、物語の最後にジャーナリストが大統領に聞いたのはたった一言。
しかも、投げかける言葉はそれ?
公平を伝える役目のジャーナリズムもこの世界のアメリカではすでに機能していない、というもう一つの絶望を見せつけられました。
観終わってすぐは「?」で不快な作品なんですが、自分なりにその不快感を見つめていると絶望が色濃く現れました。
人は殺しあう
戦争カメラマンという危険な職業がありますが、そんなに危険を冒してまで、誰に何を知らせようとしてるのか。
自分だけかもしれないけれど、TVを観てる側からしたら戦争のニュースも大谷のニュースも変わらない重さで観ている。
わたしが住んでる近くに御殿場の米軍基地がありますが、たまに通ると戦争に対するアメリカの本気度を伺い知ることがあります。
おそろしい。
題名の「CIVIL WAR」は直訳すると「内戦」そのまんま。
日本語で変な題名を付けられなくてよかったよかった。
最近このような映画がトレンドなのだろうか。
内戦として各々の主張がハッキリしているでもなく、戦場カメラマンの目を通して淡々とフラットに戦争が切り取られていく映画だと感じた。
1917という映画が少し前にあったがそれに近い雰囲気がある。
ただ、映像としては面白かったが正直期待はずれ。
個人的な想定としては、南北戦争のような世界観で敵味方がもう少しハッキリしており、内部分裂の結果勝利を収めた側が新しいアメリカを打ち立てる、その様子を戦場カメラマンが劇的に収める、そんな革命的展開の映画を想定して期待を持っていた。
しかしながら正直想定とは異なり、内戦そのものについてはそこまで説明がないので日本人的な感覚を持っていると着いていくのが大変であった...。
(流石に見始めてからは、そういった映画は例えばMCUが担うか...と納得はしたが。苦笑)
何より戦場カメラマン志望の子の動きがあまりにも足でまとい過ぎて、始終イライラ。
23歳と若いとはいえ彼女のあそこまて向こう見ずな行動が許されるのはせめて10代までだろうし、彼女の行動のせいで何人の人が命を落としたり迷惑を被ったりしたと思っているのか。
また、映画の中でその緊張感のなさを叱咤されることもなく話が流れていってしまうために、戦争の壮大な描き方と人々の心情に乖離が生まれており、折角のリアルな描写が生かしきれていないように思う。
その感覚すらなくなり自分の在るべき姿にあくまでも夢中になったり、生死も自己責任となるのが戦争だということでもあるのかもしれないが、報道というひとつの目的の元でチームとして動いているのであれば、そういった部分もしっかり描写して欲しかった。
彼女のせいで初めから終わりまで、見ているこちら側は始終ハラハラ、心臓がいくつあっても持たない。
かつそういった彼女の行動に共感ができる訳でもないから、映画の持つメッセージ性や画としての強さ以上に、鑑賞後に非常に疲れが残る。
このレビューで書くことでは無いかもしれないが、最近はメッセージ性を込めるのに、わかりやすい暴力を伴う必要でもあるのだろうか。この1年は血の気が多い映画ばかりが配給となっているように思う。
もうウンザリ。正直脱落しそう。
せっかく非日常を味わうなら、派手なことは起こらなくてもいいので、画面が美しくてうっとりしてしまうような映画が私は見たい。
A24は振り幅が大きく沢山のジャンルの映画を撮れる会社であると思うので、一癖ありつつも穏やかな作品を期待します...
アメリカン・ニューシネマのような肌触り
「もし現代のアメリカで国家を二分する内戦がおきたら」と云う情報以外何も摂取せずに鑑賞。
アメリカ人にとってCivil Warと云えばただの内戦の事では無く、自国の歴史上の南北戦争を想起することぐらいは知っている(私にとってはキャプとトニーのヤツ)
だからてっきり社会が分裂する過程描く話だと思ってた。
今のアメリカの現状、超インフレや持つ者と持たざる者の間の拡大等の国家への不信感が増大する中で大統領選挙が行われる上で、保守や権威主義に傾く恐れからリベラルな視点での反戦を訴える映画なのかなぁと。
だが良い意味で期待を裏切って、全く違う映画だった。
凄い映画だと思う。
冒頭から既に内戦状態、しかも情勢は一方的になりつつある状況で始まる。
何故国が分断したのか、何が原因か、イデオロギーの衝突も描かれない。
保守とリベラルが組んで、国を倒そうとしている。権威主義体制に対する民主主義の抵抗、あるのは狂気のみ。
政府軍の敗北に傾くなか、ジャーナリストとカメラマンが大統領にインタビューするべく、内戦下のアメリカを移動して地獄巡りするロードムービーとも言える展開で、道中の狂気が描かれる。
戦時下の狂気を巡るロードムービーと言えば「地獄の黙示録」、ある狂気を止める為に正気の巡回者が、その狂気に同化して止める話で、ある種の神話に昇華しようとした物語であるのに対して、本作は主人公を含めて皆、始めからまともではない。
戦争行為の大義名分を決して描かないので、それを報道する行為も殺戮の記録でしか無い事が際立つ。
狂気と死しかない。
アメリカ人のジャーナリズムにおいて、戦場の風景は必ず異国であり、自国の内戦の経験は無い。
平時には同級生であった者を殺したり、強烈なレイシズムから大量殺戮したりする無政府状態の中、その経験の無い違和感の中で、それを切り取り残そうとするカメラマン、敗戦の将となりそうな大統領の肉声を録ろうとするジャーナリスト。
一応、主人公に憧れる女の子の戦場カメラマンとしての成長や、ホワイトハウスで市街戦が繰り広げられる中、ある種の人間性を取り戻したかの様な主人公が、戦場に恐怖感じて蹲るのだが、ジャーナリストの鼻が効いて、大統領の存在に気付く矜持(狂気)は、捨てられなかったりする話はあるが、あくまで描かれてるのは狂気と死のみであると思う。
女の子を庇って主人公が亡くなる所も、女の子は一瞥するが放っておくし、主人公がアップになる事もない。
劇中散々映る死体と同じ扱いである。
ある意味反体制を描く本作は、彩度を抑えたドライな映像に、60年代末から70年代初頭のバンド、シルヴァー・アップルズのラブフィンガーズで始まり、まるでアメリカン・ニューシネマの様な雰囲気が漂う。
市街戦のパートだけは、制圧作戦のシミュレーションの様な映像となるが、あくまで、全体の印象はニューシネマの様で、鑑賞後の心に残る感じも近いと思う。
最後に映し出される切り取られた写真の狂気を観客に提示して終わるのも、ニューシネマぽい。
中々の秀作だと思います。
追記として現実的には、強大な軍の最高位にいる大統領があの様に制圧されるのは、リアリティに欠ける。攻撃ヘリや戦車、装甲車で制圧されるが、それ以外の強大な力を持つ軍備は登場しない。戦闘機も攻撃機もドローンもミサイルも。
その気になれば軍を掌握している内に戦略爆撃を加えていれば、ああ云う情勢にはなってないと思うのだが。
軍の掌握を失った時点で逃亡してる筈だし、少しでも命令系統が残ってたなら、DC制圧前の基地に爆撃を加えたら逆転するし、そもそも最高機密の地下脱出路やシェルターもあるだろうから、劇中の様な追い詰められ方をするとは思えない。
ただアメリカがこの様な内戦状態になったなら、東アジアの情勢はとんでもない事になってるので、軍事力は大方そちらに流れてるのかなぁと忖度しながら観ていた。
半端ない緊迫感
戦場カメラマンのリーをキルスティン・ダンストが、ジャーナリストのジョエルをヴァグネル・モウラが、戦場カメラマン志望の女性ジェシーを、ケイリー・スピーニーが演じる。
赤いサングラスの男を、まさかあの俳優さんが演じていたとは。。或るレビュアーさんから頂いたコメントで初めて認識したという 😆 ホント、びっくりでした。
危険を顧みず戦場に赴き、次に何が起こるか分からない緊迫感の中、果敢に被写体を追う姿がリアル。
ただ、ジェシーの危うい行動に、ラスト迄違和感が拭えなかった。
… ホワイトハウス、さすがに地下シェルター設置してそう 👀
映画館での鑑賞
起こりうる未来
アクションものを期待しているとかたすかしをくらうので注意。最後30分くらいだけか。あとはロードムービー。
誰と誰がたたかってるのか?それらはそこまで重要ではない。撃たれてるから、撃っている。が、正解なのか。という現状。。
未来なのか、それとも現在もどこかの国では起こっているリアルな現実を突きつけられたようなきがした。
国際法に従って、一般人が理解していないレベルで縛られている戦争ではあるが、それを無視した暴力は時として存在する。赤いサングラスの男に話が通じるわけがない。これは、硫黄島からの手紙や父親たちね星条旗、プライベートライアンなどで描写されてきた事実であるとおもう。この映画の感想としては、ただただ、暴力。という感想。争っている陣営は共に正義を掲げるのだろうか、そこには正義も悪もない。
ストーリー云々よりも音がとてもミリョクテキだった。IMAXシアターで観るのに適している。
分断の末に起こり得る未来
観る人の捉え方次第でジャンルが変わる映画だった。戦争映画であり、ロードムービーであり、成長の物語でもあるように思う。
「どのアメリカ人だ」と問われるシーンは分断の行く末を生々しく突き付けてくる。日本でも外様という言葉が未だに使われているのを耳にするが、考え方の根っこは赤サングラスの男と変わらないように思う。
アメリカ大統領選のある年に公開されたのも、警鐘なのだろう。
生温い映画ではないので注意。
つい先日『エイリアン ロムルス』でお目にかかったケイリーちゃんが、またまた主演!スパン早!
『スパイダーマン』シリーズでMJ役だったキルステンが大人になり過ぎて最初疑ってしまったが、ベテラン感出てていい役作りだった。
冒頭は大統領の演説練習のシーンから始まる。
ものすごく緊張を感じる演技だった。
物語はいきなりアメリカが内戦状態で始まり、心の準備もなく初っ端から戦闘に出される気分とでも言おうか。
悲惨な戦場と化したアメリカの映像とは真逆に、軽快なBGMが流れる。
映画はD.C.に向かう戦場カメラマン達のロードムービー風だが、幾度となく緊張感のあるシーンで心拍数があがる。
危険な戦闘域真っ只中へ飛び込む戦場カメラマン。
感情をコントロールする術を持たなければやっていけない。身の危険もあるなか、事実を伝える為にシャッターをきる。
もしこれが現実だったら、、、と思ってしまうようなリアルさ。オブラートになんて包まず、戦争の悲惨さを映像でバンバンだされる。
映画と言えども、銃殺される瞬間や血みどろの遺体の数々は目を覆いたくなった。
(ウォーキンデッドで耐性あるから大丈夫!と思い込まないと無理だった。)
内戦が起きても無関心が一番安全だと言う店員。
店の外では銃を構える人。
無関心がいつまで自分を守ってくれるのか。
ホワイトハウスまで迫ってきた矢先に主人公リーが取り乱すシーンは、私も引きずられたのか、いや、今まで平気そうにこの悲惨な映像を見てきて堪えてきた感情が溢れてしまったか、恐ろしくて恐ろしくて涙が流れた。
殺された大統領の周りで微笑む兵士達。
彼らはマトモな人間なのか、それとも悪魔なのか。
自問自答は諦めろ。
目の前の事実をカメラに収めるんだ。
分断された内戦の米国の中で描かれるジャーナリストの成長を描いたロードムービー
【はじめに】
本作『シビル・ウォー』で監督と脚本を担当したアレックス・ガーランドのデビュー作は『28日後』というゾンビ映画の脚本でした。その来歴もあってか、この映画は戦争よりも分断に伴う終末世界を描くのに多くの尺を使い、14ヶ月間インタビューに応じていない大統領(ニック・オファーソン)に突撃取材を敢行するために自動車で旅をするリー・スミス(キルステン・ダンスト)ら一行のロードムービーと、23歳のジャーナリスト志望のジェシー・カレン(ケイリー・スピーニー)の成長を軸に構成されています。
【所感】
リーたちジャーナリスト一行が遭遇するのは、『分断』です。一行がガソリンスタンドで遭遇する自動洗車機に吊された“略奪者”の拷問された姿に、ガソリンスタンドのオーナーはハイスクールの同級生だが、在学当時よりも拷問の時に一番言葉を交わしたと言い放っています。
かつての身近な人であり、会話の糸口になるような共通項は罪を許すような慈悲にもならず、ただ同じ地域に住んでいる持つ者と持たざる者だけの対立がそこでは描かれます。
ここでジェシーが“略奪者”の姿を撮れなかった事を悔やむことが描写されます。しかし、拷問を受けた”略奪者”の存在に気付いたのは、ジェシーなのです。彼女には間違いなく才能があるのです。
だからこそ、このエピソードの後にリーは破壊されたヘリ(H60?)を被写体に撮影するように、ジェシーに特訓をするのです。
本作の広告で何度も繰り返された「どういう種類のアメリカ人だ?」という質問をする赤いサングラスの男(ジェシー・プレモンス)のエピソードでは、ジェシーの未熟な行動が招いた故のトラブルだと捉える向きもあるでしょう。
ただ、赤いサングラスの男はあの道路で検問をしており、ジェシーが車を乗り換えなくても遭遇していた事態であります。
赤いサングラスの男に関して、パンフレットのインタビューでガーランド監督は、人種差別主義者だとカテゴライズしていました。けれども、彼は一人目は無言で射殺していますが、香港出身のジャーナリストは、外見がアジア系だからではなく、質問の回答によって殺されています。人種差別主義者の中でもさらに絞り込むならば、赤いサングラスの男は新規の移民を歓迎しない移民排斥派なのです。香港出身の男も例えばアメリカ最大の中華系居住州のカリフォルニア出身とでも偽ればその場は乗り切れたのではないか、と思えなくもありません。
もちろん、脚本の段階ではどんな俳優がキャスティングされるか分からないから、相手の視覚情報から人種を特定して射殺する流れにしなかったとも、一連の台詞を大切にしたかったなどもあるのでしょうけれど…。
いずれにせよ、私はジェシーを責めるのは酷だと思いますし、リーたちは14ヶ月インタビューに応じていない大統領にインタビューをさせるのにどんな取引をできるだけの材料を持っていたのでしょうか? PRESSSという事やリーの知名度でそれなりに尊重されると思っていたのでしたら、やはり脳天気だったと思います。例えば、サミーはラジオから流れる大統領の演説をいつもと同じだと言って切ってしまうシーンにもそれを感じました。
同じ演説でも何度も聞き、声の調子や使用している言葉の違いやスタジオの音響から現状を推測するのもジャーナリストの役割ではないでしょうか。現実の世界では、北の指導者の体型や歩き方からどんな病気を患っているのか推測される報道がなされています。非言語化されない部分や微かな違いにも、カーテンの向こうの事実が影を落としているはずです。
色々割り切れない思いもありますが、サミーをはじめ大量の死に直面してゲロを吐きながらも、大統領官邸に突入するシーンで自らをかばってくれたリーの死に様にも迷いもなくシャッターを切り続けるのは、戦場カメラマンとして彼女は確かに成長したのでしょう。
しかし、ワシントンでハンヴィーと激突する大統領専用車と、そして大統領官邸への突入の戦闘シーンは圧巻でした。この場面の戦闘の激しさや、ニュースでよく見る個々の部屋を戦場にして徐々に占拠していく様は、アメリカ政治の当事者ではなくても無理な要求を突きつける同国に鬱屈した感情を抱いたことがある日本人としてはある種のカタルシスを感じます。
ただ、交渉をする秘書官の女性も、命乞いをする大統領を拘束もせずに全て銃殺というのは、ビン・ラディン並みの扱いで、DNA鑑定を経て特別法廷で裁かれたフセインのようにもならないのは少々唖然としました。
グアンタナモ捕虜収容所で米軍が行っている虐待は知っていますが、日本人は80年前の戦争で『生きて虜囚の辱めを受けず』という思想から捕虜になると恥だし悲惨という考えを元に、沖縄や南洋の島々で軍人や民間人の集団自決を招きました。実態は、捕虜になった人々は意外な待遇や尋問への訓練を受けていなかったために様々な情報を提供する事になり、米軍は対日戦に捕虜の情報を役立てました。
この映画は元軍人を撮影に参加させてリアリティを追求したのに、そこは果たしてリアルだったのか、疑問を感じました。
エンタメや戦場という狂気を表現するには必要な描写であり、戦場ではどんなルール違反も悲劇も起こりえるという事もあるでしょう。また、西部勢力が支配してきた地域が正常で常識が通用する地域でもなく、国際法が通用する正規の軍隊と描写しない事で、この後のアメリカの苦難を表しているような場面だともいえるのかもしれません。
【妄想というか今後の展望】
そもそも本作の大統領が3選を目指して実現できたのはなぜなのでしょうか? パンフレットでは、トランプ前大統領が3期目の当選を目指した事を発言した事からこのような大統領を創作したと語られていますが、一人の大統領の意思だけではアメリカといえども憲法改正は容易ではなく、全州議会の75%の同意が必要なのです。
史実で3選以上を果たしたのは、フランクリン・ルーズヴェルトでした。4選という例外的な彼の長期政権を支えたのは第二次大戦という非常事態があったからでした。
続くトルーマン政権の1951年に3選を明示的に禁止する憲法修正22条がなされました。
アメリカ建国の際にワシントンが自ら3期を固辞したことからアメリカ大統領は伝統的に2期のみだと思われがちですが、それまでは一種の不文律のような慣習だったのです。
大統領はひょっとして、中国かロシアなどの大国との第3次世界大戦を背景に3選を果たしたのかもしれません。
そう考えると、米国の内戦において大統領が治める地域にNATOなり自衛隊なり米国外の勢力が存在しない理由も納得が出来るかもしれません。もはや、外国にも米国を助けたり関与する余裕がない世界なのでしょう。
私としては、この映画は壮大なプロローグとして、真面目にシビル・ウォーの世界をNetflixか何かで連続ドラマにしてほしいと思うのですが・・・特定の党や人物をぼかして観客に会話することを求める本作の監督の意向とも得意とする分野とも異なるので、ないと思いますが…2時間映画で終わるには惜しい作品だと思わされました。
戦争の理不尽さを描いた良作
アメリカが分断、州連合軍と政府軍が内戦状態。その要因も内戦に至る経緯も作中では語られない。当然、諸外国の動きも一切、触れていない。(ロシアや中国が沈黙している筈がない)
描かれているのは、個々人に降りかかる、戦争がもたらす理不尽さ、非常識さが、ひたすら描かれている。
その舞台がアメリカ国内というのが、ポイントで昨日まで同じ国の市民だったのが、内戦だからと、いとも簡単に同じ市民を殺害してしまう事の恐怖。
「同じアメリカ人だろ!」「どのアメリカ人だ?」という台詞に、戦争の醜悪さが現れている。多分、ウクライナで、ガザで、レバノンで同じ理不尽さが繰り広げられているのだと想像させられるだけで、この作品の価値はある。
ラスト、捕らえられた大統領に一言インタビューを行い、その答えを聞いて「充分だ」と言い放つジャーナリストの態度は、戦争を始めたのは権力者、だから、その責任を自分で取れという痛烈な批判なのだろうと感じた。
アベンジャーズは最後まで登場しなかったけど、続編から?
近未来に起こってもおかしくないシチュエーションの描写。ひょっとすると製作者はAIか?と想像してしまう位に現代アメリカを多角的に立体的に抉り取った手腕は素人にはすごいとしか思えない。兆、京、垓の情報の断片を組み合わせて、起こりうる状況を画像に落とし込むトランスフォーミングも人間業離れしていた。すごかった。
「アベンジャー」を期待して観に行くと外れた感が半端ないかもしれない。レビューもそういった感想があふれていたけど。さすがに現代のアメリカ人でキャプテンアメリカが登場してワルモノをぶっ倒す作品とそうでない作品の差は理解しているんだろう。ちなみにジョンウェインは赤いサングラスつけて出てました。
ニューヨーク、ワシントン、シャトル便で1時間くらいの距離だけど、交通事情を加味して今回はぐるっと遠回り。結果としてエグイくらいあの辺のアメリカ人を描いてしまうところもすごかった。偏見と差別むき出しで銃をぶっぱなし、強奪者には死をもって報いさせるという伝統的な米国流の問題解決法、古くはホロコースト、近くは中東での人命軽視の死体処理等、州兵、私兵、自警団、正式軍(東、西)の使い分けとか、作戦時のヘリコプターの使い方とか、軍の作戦プロトコル等を知り尽くした人が制作人にいたんだろうと感じた。緑地の多さ、芝生の濃さ、湖畔を進む軍事車両等、はなに野宿しているおっさんの奥で軍用トラックが下手へ、ヘリコプターが天へフレームアウトしていく静と動、映像美とも言えるなにげない風景、無機質な戦闘兵器と夜空にくぐもった音で聞こえてくる砲撃、銃声の音、さらには”Go stealers!" のペイント。大いなる力を持った3期目大統領が引き起こした惨劇の様子をドキュメンタリーとして描いたのかと錯覚してしまう。
更に主人公の世代交代、ジャーナリストの宿命である非人格に徹しなければならないプロ意識の発現とトラウマになる心の傷跡、それを新旧の世代交代にかぶせていくシナリオワーク。主人公を虫けらのようにヤッテしまうことで、レンズを通じた意思の継承を見せてしまう小業等、挙げだしたらキリがないほどすごい作品だと思いました。
アメリカが内戦状態になった理由が全く判らなかった
星条旗の星が2つになっていて、なんで2つになったのかその経緯もよく判らないし、そしてよく判らないままDCが陥落していた。
なんで?
何があったの?
戦争ジャーナリストの人たちが大統領のインタビューを取るために命がけでNYからDCに向かうのだが、その道中でやたらと人が殺される。
虫けらのように殺される。
最初は怖がっていた若いカメラマンが、段々戦場にいることに慣れ、人間同士が殺しあうシーンをカメラに収めることに恍惚感を覚えるようになっていく。
こういった心の変化も戦争が生む『狂気』なのではないかと思った。
これが『戦争』なんだと現実を見せられた気がした。
いや。
現実はもっと悲惨なんだと思う。
でもこれはアメリカの内戦の話ではなく、アメリカの内戦という設定で戦場カメラマンを描いた作品。
紛らわしいタイトルを付けるな!
今この時も東欧や中東が戦場となっている。
今日スクリーンで目にしたシーンよりももっと悲惨な状況が繰り広げられているかと思うと、なんとも言えない気持ちになる。
戦争がこの世の中からなくなる日がいつか来るのだろうか?
何とも言い難い
この映画の主題が何なのか、どんなメッセージを送りたいのかを観た人が勝手に考えてねという感じの映画だった。
とにかくストーリーに関する説明が少ないのだ。
内戦が起きた国では国民同士が戦っているわけで本当の意味での敵味方を判別するのは難しい。普段は人権人権と叫んでる国でも恐ろしく簡単に国民が国民を殺す。
見分けが付かなければ自分を守るために殺すしかないのだ。
ジャーナリズムも真実を伝えるという本質から逸脱して手柄をあげることに固執し始める。
ラストの若いカメラマンが自分の身代わりで撃たれた先輩カメラマンに見向きもせず先に進もうとする場面が象徴的だ。
観終わった後に思い出しながら考えると色々浮かんでくるのだが映画ってそういうものなのか?
戦争を扱った映画は反戦のメッセージを送るものとエンターテイメントとして楽しむものに大きく二つに分けられるのだがこの映画はどちらでもなかった。
正直なところ見終わった後に不快感しか残らなかった。
申し訳ないですが、自分はダメな映画でした
(完全ネタバレなので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
結論から言うと、今作は自分にはダメな映画でした。
鑑賞前はアメリカの分断社会の現実の中で、遂に内戦状態に陥り、双方の戦闘が主張と共に繰り広げられる内容を期待していましたが、ほぼ全くそういう内容ではありませんでした。
今作のストーリーは簡単に言うと、著名な女性報道カメラマンのリー・スミス(キルステン・ダンストさん)らと、彼女に憧れている女性報道カメラマンの卵であるジェシー・カレン(ケイリー・スピーニーさん)との4人が、権威主義的な大統領(ニック・オファーマンさん)にインタビューを試みる為に、内戦の中、ニューヨークからワシントンD.C.のホワイトハウスへ向かうロードムービーです。
すると、著名女性カメラマンのリー・スミスのカメラマンとしてのポリシーが映画の初めの方で伝えられます。
リー・スミスは女性カメラマンの卵のジェシー・カレンと共に、道中のガソリンスタンドの裏で武装した男に吊るされて半死になった2人に遭遇します。
しかし、リー・スミスは特に感情を動かすこともなく、武装した男を吊るされた2人の真ん中に立たせて、報道写真を撮影します。
リー・スミスは、暴行されて吊るされた2人を救うことなく、カメラマンの仕事は記録に徹することだとジェシー・カレンにその後の車中で伝え教えます。
私は(映画の1観客としても)、この報道カメラマンとしてのリー・スミスの報道ポリシーは(それがリアルだとしても)受け入れることは出来ません。
なぜなら人命を超えて報道が優先される考え方に、私は反対で同意出来かねるからです。
そんな私のような感想はさて置かれ、女性カメラマンの卵のジェシー・カレンはリー・スミスの報道ポリシーを受け入れて、例えば戦場であればジュネーブ条約違反の国際法違反である、人質を処刑する場面の報道撮影を心を動かすことなく遂行して行きます。
物語は進んで、4人の内の1人のジョエル(ワグネル・モウラさん)の報道仲間の車と遭遇し、走行している互いの車の窓を伝って移動遊びをしたりしている内に、1台だけがはぐれて、いわゆる権威主義的なアメリカを信奉しそれ以外の人間はアメリカ人とは認めず虐殺を続けている集団にジェシー・カレンらが捕らえられます。
リー・スミスやジョエル達は、捕らえられたジェシー・カレンらを助けに行くのですが、結局はジョエルの友人の香港出身のジャーナリストやその同僚が、純粋のアメリカ人でないということで権威主義的なアメリカ信奉の人間に殺害されます。
この場面は、もちろん現在の極右思想の持ち主が差別的に排外的に振舞っている帰結が大量虐殺であることを現わしていて、個人的にもその短絡思想の延長線上の殺戮に対し、激しく嫌悪する場面でした。
ところでその後、4人の内の1人のベテランジャーナリストのサミー(スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンさん)が、機転で車を権威主義的なアメリカ信奉者にぶつけて倒し、銃殺された2人以外の、リー・スミスとジェシー・カレンとジョエルの3人を救い出すことに成功します。
しかし、サミーもその救出の過程で凶弾に倒れ命を落とします。
そしてその後、リー・スミスとジェシー・カレンとジョエルの3人は、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる「西部勢力」の陣地に合流し、その部隊に従軍することで、ついにワシントンD.C.のホワイトハウスの大統領に迫ります。
しかし、大統領に会う直前にリー・スミスはホワイトハウス内で凶弾に倒れ、3人の内、大統領に到達出来たのはジェシー・カレンとジョエルだけでした。
そして大統領は命乞いだけをして、「西部勢力」の兵士に殺害されて映画は終了します。
で、さてこの映画はいったい何を伝えたかったのでしょうか?
そして、この映画が伝えている内容の趣旨に対して、私は全く同意出来ないなと思われました。
おそらくこの映画で言いたかったことは、戦場あるいは無秩序な空間での報道カメラマンは感情を殺して記録することが出来るぐらいしかない、事だったと思われます。
では、その事でその先に一体何を伝えたかったのでしょうか?
感情を殺して記録に徹することで人間性が壊れていくリー・スミスを通して、このような非人道的な戦闘や戦争を起こしてはならない、だったのでしょうか?
その割には、ホワイトハウスに乗り込んで、大統領の周囲の人間や大統領の条件を伝えていた報道官などを簡単に「西部勢力」の兵士は殺害し、命乞いをする大統領も簡単に殺害し、ジョエルも大統領の殺害を喜んでいたと思われます。
この「西部勢力」による大統領や周辺に対する一方的な殺害は、道中の差別的で権威主義的なアメリカ信奉者による香港出身の人間などを一方的に敵とみなしていた殺害と、何か違いはあったのでしょうか?
それぞれの自身の陣営の思考を正当化し、相手に対する殺戮を正当化している時点で、他者を抹消したい欲動の帰結の点では(コインの裏表の)全く同じ思想だと思われます。
感情を殺して記録に徹することで人間性が壊れていくリー・スミスを通して、とてもこの悲惨な戦場や戦闘における殺害を、この映画は否定しているとは思えませんでした。
この映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で描かれていたのは、(権威主義的な思想の信奉者であろうが、それに対峙する「西部勢力」の人間であろうが)敵とみなしたものに対する容赦のない殺害であり、一方の側の殺戮に加担するか、あるいは、それを否定することなく感情を破壊して記録する報道機関の姿でした。
私は、他者への想像力を抹消し他者の存在を消滅させようとする思想には(それが右派的であろうと左派的であろうと)組することは出来ません。
そして、それを記録する事を感情を消すことで可能にし、相手の蛮行に対して異議申し立てをしなくて良いとする報道機関の考えに同意することも出来ません。
報道機関の人間が感情を殺している事を1人になった時に苦悩されても、目の前に存在する他者に対して想像力を辞めたことで起こっている問題の責任から、免れることなど出来ないだろうと、映画を観ていて思われました。
であるので、徹頭徹尾、この映画が提示している考えに合わず、申し訳ないですが僭越ながら個人的にはダメな映画だったと思われました。
全231件中、101~120件目を表示