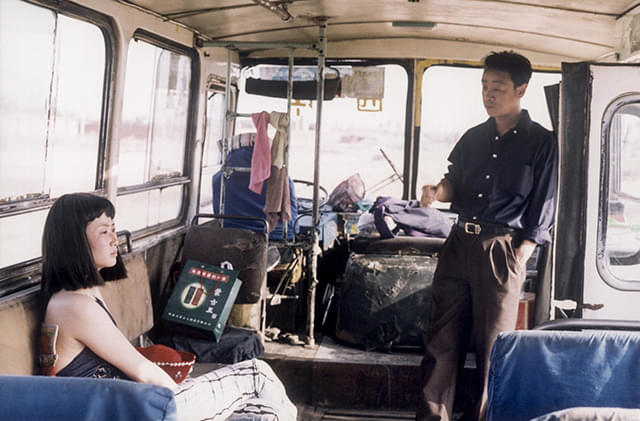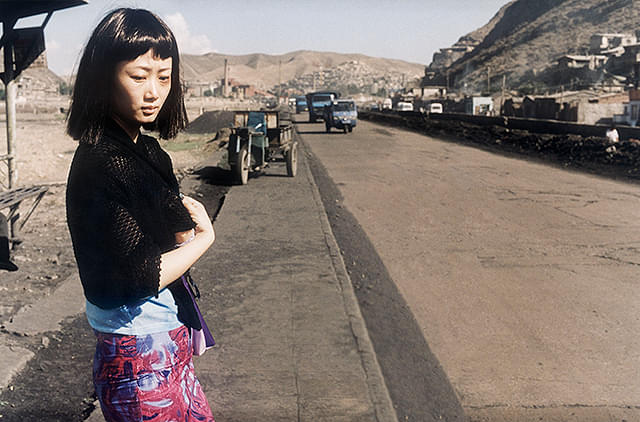新世紀ロマンティクス
劇場公開日:2025年5月9日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
本編を見るPR

解説・あらすじ
中国の名匠ジャ・ジャンクーが製作期間に22年をかけ、21世紀初頭から劇的な変化を遂げた中国の街を、ひとりの女性の人生の変遷とともにとらえたドラマ。
2001年、炭鉱産業が廃れ失職者で溢れかえる山西省・大同。2006年、三峡ダム建設のため100万人以上が移住を余儀なくされた長江・奉節。コロナ禍の2022年、マカオに隣接する経済特区として発展する珠海と、すっかり都会となった大同。チャオは大同を出て戻ってこない恋人ビンを探して奉節へ向かい、ビンは仕事を求めて珠海を訪れる。時は流れ、ふたりはまた大同にたどり着く。
主人公チャオ役に、これまでもジャ・ジャンクー監督作で主演を務めてきた妻チャオ・タオ。同監督の過去作「青の稲妻」「長江哀歌」などの本編映像や未使用映像、ドキュメンタリー映像なども使用しながら、実際の24歳・29歳・45歳のチャオの姿と共に、変化していく街の景色を映しだす。2024年・第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。第25回東京フィルメックスでオープニング作品として上映。
2024年製作/111分/G/中国
原題または英題:風流一代 Caught by the Tides
配給:ビターズ・エンド
劇場公開日:2025年5月9日
スタッフ・キャスト
受賞歴
第77回 カンヌ国際映画祭(2024年)
出品
| コンペティション部門 | |
|---|---|
| 出品作品 | ジャ・ジャンクー |



 帰れない二人
帰れない二人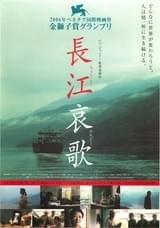 長江哀歌
長江哀歌 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク