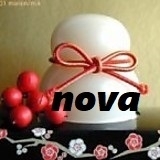大きな家のレビュー・感想・評価
全64件中、21~40件目を表示
その人なりの幸せを願って
現在進行形で施設にいる子は「ここは家ではない」と話し、施設を卒業した子の心には、よりどころのようになっていたのが印象的でした。
映画の冒頭で施設職員の方が「卒業した子の中には、連絡が取れなくなる子も相当数いる」とお話されていたので、それだけこの世の中は、「世の中が考える一般的なレール」からはずれて生きている人々に、厳しいのだということなのでしょうか。
施設職員と子どもとは、わりと関係良好なシーンが多く映っていましたが、現実では、長所も欠点もある人間同士、どうあがいても上手くいかないことはあるでしょう。
「世の中が考える一般的なレール」の枠内に収まっているはずの私でさえ、親子関係、家族関係に日々悩むのですもの。
この世に生を受けたすべての人が、それぞれの環境で、その人なりの幸せを感じながら毎日を生きていけますように…そんな気持ちになりました。
人間、ずっと生き地獄だよ。
作中、少女のつぶやいた言葉が、耳に残った。
彼女が今の状況を選んだわけではない。
あきらめと怒り、両方を感じた、やるせなかった。
私は、50代で一念発起し、社会福祉士の学習を始めた。
福祉系以外の大卒の場合、受験資格を得るためには、1年8ケ月の間、通信教育での学習と1ケ月間の実習への参加が必須だった。
社会福祉士取得後は、高齢者、障がい者、児童など様々な現場で、専門職として働くことができる。
私は、児童分野で働きたいと考えていたので、児童養護施設で実習を受けることにした。
この映画同様、児童養護施設の子どもたちは、衣食住、十分な支援を受けている。
私が滞在したのは1月15日から2月13日までだったが、節分の行事もあった。
夏休みには山にスタッフと子どもたちでキャンプに行き、クリスマスプレゼントもある、寝る前には1対1で順番に絵本の読み聞かせもしてもらえる。
数人のスタッフが、シフト勤務で子どもたちをサポートし、中学生以上の子たちへは、自立に向けて自分の身の回りのことを担当するように促す。
児童養護施設の印象は、家庭というより、寮のようだと思った。
映画の中で、子どもたちが、ともに過ごす人たち(子ども・スタッフ)を、「家族ではない、他人だ」というのは、感覚としてよく分かった。
どの子も、家族とのお出かけやお泊り、家族からの電話などをとても楽しみにしていた。
家庭ではなく、社会的養護施設で育った子は、特定の大人と親子のような絆を持つことはできない。
スタッフは、配置転換があるし、3年から5年ほどで燃え尽きて退職する人も多いと聞いた。
退勤後は、スタッフは各々の家に帰り、本来の自分として過ごす。
その顔を、子どもたちが知ることはないだろう。
相談したいことがあれば、その時、施設にいるスタッフに言う。
家庭というより、むしろ学校に近いかもしれない。
政府は、社会的養護を受ける子どもたちが、できるだけ家庭的な環境で過ごせるように、里親制度と、児童養護施設等でも小規模なグループでの養育することを進めようとしている。
家庭的な養育によって、子どもたちが、身近な大人との間で本来得るはずだった絆を得ることができるようにだろう。
児童養護施設では、できるだけ10人以下の小グループで養育するよう努めているが、スタッフの充足具合と資金繰りがそれを実現できるかのカギとなる。
里親に関しては、基準が厳しく、そもそもなり手が少ないという問題点もある。
これらの自分の体験を踏まえてこの映画を鑑賞すると、かなり実態に近い映像作品だと感じた。
ひとりひとりの子どもたちの不安や心もとなさに、目の前にいたらハグしたいと思った。
実の親に育てられていても、社会に出て、自立する時は、しんどい。
いっぱい恥をかくし、失敗するし、泣きたくもなる。
そんな時、心から信頼できて、頼ることができる人が身近にいないのは、つらいだろう。
子どもたちの心情が、少しずつ、足元から降り積もり、だんだん息苦しくなってきた。
思わず、途中で終了時間までどれくらいか確認してしまった。
こんなことは、映画鑑賞に来て、初めてだった。
幸せな気分になる映画ではない。
けれど、今、生きている大人として、受け止めなければいけない日本の現実だ。
微力ながら、今後、目の前の子どもたちの力になっていきたいと改めて決意した。
7歳から19歳まで、全員が全員、自分の考えを自分の言葉でしっかりと...
今年一本目がこの作品で良かった。
「人生のヒントがたくさん」
「普通」であることの幸せ
日々の日常を淡々と綴った静かな映画です。それは、製作者の意図に沿った演出でもあり、そのことにまず志の高さを感じます。
日々は淡々と過ぎていくものであり、それが「普通」なことなのですが、児童養護施設で「普通」であると言う事は、なんと尊い営みであろうと思います。
それぞれの事情、それぞれの思い〜複雑
色々評判になっていたので鑑賞。
様々な事情で親と暮らせない子供たちが集まって
職員さんにサポートされながら暮らす養護施設を取材したドキュメンタリー。
賑やかに誕生日を祝うシーンや、施設で行われる様々な行事など
子供たちの遊ぶ姿や軽く喧嘩する姿も織り込んで、
幼稚園に通う年齢の少女から、18歳で施設から退所して
施設の近くで一人で暮らす大学生まで、数人の子供たちに密着して
日頃の暮らしへの感想と施設の仲間や職員に対する本音を
インタビューしている。
この映画は撮影に協力してくれた子供たちのプライバシーに配慮し
ビデオ化や配信はされないので、興味のある方はぜひ劇場で!
で、月に8回ほど映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
私の頭の中が養護施設と言うと「タイガーマスク」に出てくる
ちびっこハウスからアップデートされてなくて(何十年経ってんだ!)
今時の施設の充実度にまず、驚いた!
それぞれ個室になってて、食事も担当の職員さんが作ってくれる。
洗濯物や身の周りの物も、年齢の低い子供たちには、
本当の親がするように職員さんが片付けて準備したりしてくれる。
本当の親子ではないけれど、一般家庭に少しでも近づけるように
色々工夫されているんですね。
一緒に暮らす仲間と職員さんたちを子供たちはどんな風に思っているのか?
例え一緒に暮らしていなくても、親との関係がそれなりに良好な子供たちは
「血が繋がっていないので家族とは言えない。」と答える。
親との関係が破綻しかけていて、薄々それに気付いている子供は
「家族みたいなものかも〜」と曖昧ながらそっちの方向で答える。
それぞれの実の家族との関係性によって、施設生活のポジションが違う。
それぞれに複雑な感情〜〜
子供によって、施設の仲間を「家族」として認めてしまうと
自分が本当の家族と暮らせていない寂しさと現実を
丸ごと、受け止めないといけなくなる。
あくまでも施設の暮らしや仲間は「仮の存在」としておく事で
「本当の自分」を保とうとする様な健気な姿がほの見える。
兎に角、
みんな元気で!
みんな自由に生きられる様に!
願わずにはいられない。
出演された施設の皆さんの映画
タイトルとおり大きな家
2日連続で鑑賞。
居場所。
児童養護施設。その昔、履修科目中の一部として学び、触れたことはあった。しかし、実際にこの目で目にしたことはないし、同施設で暮らしていたという人物とも出会うことのない人生を歩んできた。
鑑賞後、パンフレットを購入し読んだ上で。24時間・365日、施設の職員として働く方々の懐の深さを思う。もちろん、様々な事情で施設に入所している子どもたちが、それぞれの日常をちゃんと生きている、その姿にもグッとくるものはあったのだが。
その子どもたちの生活の基盤を維持し、より良いものへと日々奮闘する職員の方々。職員が子どもの成長に涙する姿をみて、私自身は他者に対して、これほど想いをもって関わっているのだろうか、と自問自答した。そして本当のところ、そんなに想いをもって他者と関わってはいない自身に気づいてしまう。私は薄っぺらい人間なのだな、と。
施設を出て、彼ら彼女らがどんな人生を歩んでいくのか。願わくば、未来にわたって自身で選択できる人生を歩んで欲しい。
観る者の思い込みを排す
【大きな家】
東京の或る養護施設で暮らし旅立って行く子供らを見つめたドキュメンタリーです。ここには、何らかの事情で親と暮らせない子供らが預けられ、18歳になると退所して行きます。と聞くだけで、「周囲とぶつかり合いながらも職員の人々の愛情に支えられ成長して・・」という感動物語が思い浮かんでしまいます。しかし、本作はそうした思い込みを排する所から始まっています。
子供の一人は、同じ施設の仲間を「家族でなく一緒に暮らしている他人」とクールに語ります。児童養護施設を「暖かな家」、共に暮らす仲間を「家族」と見ず、早いカット割りの映像は観る者の安易な共感を拒絶している様にすら映りました。かと言って勿論ここは冷たい施設である訳ではなく、職員の人々が子供を観る眼差しは暖かく感じます。
それでも、子供らはやはり「本当の」父母の許に帰りたいのだろうか、施設に預けた親を恨む事はないのだろうか、そんな問いへの答えは全て観る者に委ねられるのでした。
一方、本作で描かれるネパールの擁護施設の子は「みんなが家族」と言います。その差は何なのでしょう。文化の違いなのでしょうか。日本の子が悪ぶっているだけなのか、ネパールの子が言わされているだけなのかな。その答えも観る者に預けられます。
表情、景色が眩しすぎて
**「美しい映像と心揺さぶる物語――今観るべき映画『大きな家』
家族ではない
変えられない過去より、変えられる未来志向で
東京にある児童養護施設で、死別・病気・虐待・経済的問題などの事情で親と一緒に暮らせない子どもたちが、職員や他の子どもたちと生活していた。そんな彼らは、両親への思いや、職員との関係、学校の友だち、施設を出たあとの暮らしなど、さまざまな葛藤を抱えながら暮らしていて、養護施設は18歳で出ていかないといけない。そんな話。
おねがいのパンフレットを貰った。
この映画に登場する子どもたちや職員に対するプライバシーの侵害や誹謗中傷をご遠慮くださいとの事。
全国に42,000人も居るらしい。親がいるのに一緒に暮らせない、って悲しいなぁ、と思ったし、親は無責任じゃない?とも思った。
卒業して5割はうまくいっていないという話があったが、5割は頑張ってるんだとそっちに感心した。
何を感じれば良いのかわからないが、過去のことは変えられないから、今からのことを考えて未来を変えていこう、という話をしていたのが印象に残った。
それと、ネパールへボランティアに行った子、向こうで同級生で児童養護施設の子がインタビューに英語で答えてたことにどう感じたのか、興味深かった。
全64件中、21~40件目を表示