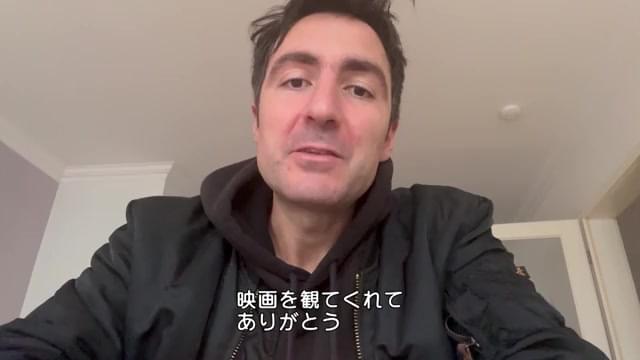ありふれた教室のレビュー・感想・評価
全125件中、21~40件目を表示
「ありふれた教室」が全然ありふれていない件。 小学生くらいの児童が...
「ありふれた教室」が全然ありふれていない件。
小学生くらいの児童が授業をボイコットしたり、停学処分が下されたり、学内で頻繁に金が盗まれたり、校内新聞が有料で販売されるのはドイツでは普通なのか。
カンニングの現場を押さえられたのに逆ギレする児童、人のカバンに手を入れたと思われるところをカメラで撮影されているのに犯行を否定する職員の女。
絶対に自分の非を認めようとしないのはドイツ人の国民性なのか?
様々な問題が全く解決されないまま映画は終わってしまうが、結構おもしろかった。
♨️☺️ これだよこれ🤗
だよね ありふれてたよね 普通はあーだよね(な訳あるか〜い🤬)
と言うかどんだけ観てる人にストレスかけてくんねん🥰
起承転結がしっかり無いとダメって人やエンタメ好きや落下の解剖学とか全くダメって人には絶対合わない作品ですね🔥
これ単純に過度にかかるストレスを楽しむ作品です👍
結局全方位からの詰められる状態になるとか🥹
被害者なのになんでこうなるかなあ👌
上映時間の長さも適度でいいし⏳
絶叫するシーンあったけど🤬心の叫びやんけって❤️🩹なりましたよ🤕
色々考えてベストアンサーを考えてもいいけど別に自分は深掘りしようとはならなくてシンプルにストレスを楽しもうってなりました💩
あとオスカー最後まで信念貫いて頑固やなあ🙁
自分はこの変な疲労感のある作品がそもそも娯楽エンタメよりもエンタメって思える人なのでめちゃくちゃ疲れたので大変良かったし面白かったし いつもの許容範囲を超えた時に怖すぎたり🥶ストレス😡🤬の向こう側に行った時に発生する爆笑してしまう場面もあったので😆(悲しい時に😭笑う🤣ジョーカーみたいなもんです🤡)楽しめたという証明になってます👍👍👍
あの変な空気感を作り出すって自分は凄い事だと思いますよ(はい撮影開始って言って あの感じになるってマジで凄いと思うのよ🫡)
ストレス度でいうと今年は落下の解剖学🇫🇷とありふれた教室🇩🇪の2本がずば抜けて気持ちいいくらい最強最高にイライラできましたよ🥰
楽しかったなあマジで😘
教員の総括的な判断
7(8?)年生のクラスの生徒、アリが金を盗んだとして、両親が呼ばれ、偏見の目で見られる。担任である主人公カーラ(レオニー・ベネシュ)が、真相を明かそうとしようとして盗難カメラを仕掛ける。この結果、問題が拡大し、他の生徒、オスカーにも影響が及ぶという藪蛇になってしまうストーリー。映画のポイントは何か考えてみると、新人の教師のある問題解決の仕方が生徒一人ひとりを考えてあげているようで、正義感が強いが、優柔不断である。学内で盗難カメラをセットしたり、自己解決の及ばないこともあるので、もっとアドミと寄り添った方が、いいいのか?それとも、これがいい解決法なのか? 判断は我々に任されている。
機内で見た映画なので、あまり真剣に考えていなかった。このレビューはただの第一印象。
引き込まれたけどモヤモヤする
どの国にも、どの場所にも
ありふれているのか?
レギュレーションとコンプライアンスに絡め取られた教員室。カーラ先生の真摯な姿勢が心を打つ。
原題の「Das Lehrerzimmer」は「教員室」という意味になる。邦題はストーリーに一般性を与えるためかどこでも起こり得る話ですよ、という気持ちを込めて「ありふれた教室」というタイトルにしたんだろうけど、これは教室で起こった事件ではない。学校のガバナンスについての物語である。
一つはっきりしているのは校長のリーダーシップのなさと、教師たちの定見のなさ、混乱である。
まずは最初の盗難の件で生徒の持ち物検査をしてしまったこと(この盗難はどこで発生したのかを見落としてしまった。映画館内でスマホを点灯した馬鹿者がいて気を取られたから。横浜シネマリンの7月11日13時10分の回、E列に座っていたお前だよ)、そしてカーラ先生の上着からお金が抜かれた件でカーラ先生が撮ったパソコン映像によって犯人を決めつけてしまったこと。要はこの校長は自分で不寛容主義と言っているようにレギュレーションには厳格なのだが、コンプライアンスについての考え方がゆるゆるなのである。
誰からも同意を得ていない動画(盗撮と言ってよい)の証拠能力ぐらい少し考えれば分かりそうなんだけど。ここはまだクーンを犯人として決めつけず、信用できる数人での監視を強化するってくらいが適切だったのだと思う。
これから教員になろうとする方は、学校はあんなひどいところだと思わないでください。実際の教育機関のガバナンスは今はもっとマシです。
可哀想なのはカーラ先生で、保護者には突き上げられ、生徒にはボイコットされ、学校新聞にはボロクソ書かれます。ただそれでも彼女は教育を放棄せずもがき苦しみます。そしてオスカーに対する態度は真摯であり(普通はあの母親の子供だっていうだけで嫌になると思うが)彼に向かい続けます。最終的にはオスカーについては残念な結果になったようですが(それもおそらくあの校長の差し金だと思うけど)カーラ先生の姿を観ている限りではそれほど後味は悪くないです。ところでカーラ先生を演じた女優さんですがちょっと市川実日子さんに似てませんか?
教育現場の問題をちゃんと考えたい
その昔、学校の先生は生徒への熱い愛情を注ぐ感動のドラマも多数あり憧れの職業であった。しかし昨今は生徒だけでなく複雑な人間関係と膨大な仕事量とそもそもの教員不足が影響し、長時間労働は日常化し不人気な職業になっている。日本の優秀な人材が教育の世界に入っていかない現状は嘆かわしい限りである。
映画の舞台のドイツでも同じようなのだと思われる。
学校の不寛容方針により、自分の生徒が窃盗犯に疑われた主人公カーラは正義感からおとりの盗撮で窃盗現場をとらえることが出来たが、これが間違いの始まりで生徒からもPTAからも他の教師からもバッシングを受ける。さらに母親が窃盗犯に疑われた優秀な生徒オスカーからは証拠のパソコンを奪われて、殴られて、遂には川にパソコンを放り投げられてしまう。普通の人間なら精神崩壊してもおかしくない。
でもカーラは強い。生徒たちと大声を張り上げ鬱憤を晴らす(いいシーンである)し、停学になったオスカーとも向き合おうとする。
いよいよ感動のラストが!と思われたが、物語は意外な終わり方をする、、。
映画はこれで良いのだが、子供達の将来は?教育は?どうする?
日本もドイツも色んな国の指導者はこの映画を観て考えてください!
Das Lehrerzimmerがなぜ。
原題はDas Lehrerzimmerなのに、なぜ邦題は『ありふれた教室』などというありふれた題名になったのだろうか。
Das Lehrerzimmerを邦訳しても、ありふれているのかもしれないけれど、しかし、そのありふれ方が違う。
学校の普段のあり方を、das Lehrerzimmerから描き出す。
そこには、学校のポジとネガが逆転しているとも言える。
das Klasszimmerではなくdas Lehrerzimmer
その逆転にこそ、この映画の核心がある。学校の狂気がある。
描き出されているものは、まさに「聖域」のおぞもましい姿である。
それは、無邪気な中に潜む闇から、つまりdas Klasszimmerから描き出そうとするのではない。
それは、邪な空気に包まれたLehrer/inの立場から、das Lehrerzimmerからのものではなければならない。
そう見方をしてみると、
alltäglichな世界に見えてくるのだが・・と思う。
ありふれてたら嫌な教室
真面目なアルアル譚。面白くはない。
もはや解決できない問題。
音響効果もあり、最初から緊張感のある映像。主演女優の演技が素晴らしく、又、子供達(日本で言えば中1くらいか?)も実に自然。ドイツ人の我の強い所、移民問題、など色々考えさせられる?が、どうすれば良かったのか?自分でも色々考えたが僕にもわからない。いずれにせよ、ギムナジウムの教師、生徒のストレスが伝わってくる作品だった。
ゼロ・トレランス(不寛容)方式
冒頭の話し合いで一瞬だけ主人公が見せた、ニヤけるような表情が印象的。
ただの微笑みとも取れるし、“熱心な教師像”に酔ってるようにも見えた。
学内で頻発する窃盗に纏わる顛末を描いた本作。
日本ではまず考えられないくらい直球でガッツリ調査する姿勢は、不寛容方式故か。
物語のキーとなるのは、職員でありオスカーの母でもある、クーン。
同じ柄のシャツを同日にたまたま着てる人物がいるとは思えず、99%クロである。
しかし彼女の財布に現金はなく、これが演技なら女優になれるという剣幕で無実を主張。
星柄シャツのファッションショーはまだしも、最初の一人が現実かも明示はされない。
この不安定さが、1%の可能性を捨てさせない。
ノヴァクの人物像も、誠実かつ真摯でありつつも、これも不寛容方式からかやや厳し目に思えた。
生徒から反抗される要素も十分に感じられる描き方。
中一らしい幼さと賢しさが同居した生意気さは、どの生徒も上手かった。
ただ大人の相関図が分かりづらく、初登場時では誰がどの立場か理解できなかったのは残念。
多人種化や多様性もあってか、生徒も男女の区別がつきづらいコもチラホラ。
ノヴァクの盗撮が法に触れることもあり、調査はほぼ進まず真相は闇の中。
最後はクーンも学校に顔を出し、オスカーもルービックキューブで歩み寄りを示して終幕となる。
微かに希望が見える演出ではあるが、やや中途半端かな。
2時間あっていいからもう少し突っ込んだところまで見たかったが、題材も描写もとても興味深かった。
「体を動かす」
ラストの切れ味と余韻がいい
バビロン・ベルリンのグレータ主演ってことで。子どもたちが窃盗犯だと疑われる状況に対してカーラが職員室でとった行動が波紋を呼び、すべて子どもたちのために、教育者として正しいと思ってやったことがどんどん裏目に出て悪夢のような状況に追い込まれていく…
カーラがあの白い服の幻想をみてしまったようにすべて悪い夢みたいなものだと思う。ラストのオケの真夏の夜の夢がそれを強調している。あんな形で締めくくられるこの作品は一種の悪夢を描いていると思う。善意だろうがなんだろうが問答無用に、気持ちを踏みにじられ誇張され孤立していく悪夢は十分「ありふれた」話だ。残念ながら。でも、この作品に関してはカーラが苦しみながらとっていた態度や行動からは一種の希望を感じた。オスカーはカーラが作ったこの状況に興奮し激昂していながらも、カーラの教育者としての側面にちゃんと触発されてる。そのシーンのうまさと切れ味に、ちょっと唸ってしまった。
【”教師の正義と生徒の正義。そして教師のアルゴリズムの間違い。”今作は、夫々の正義を貫こうとする態度が、学校内で様々な軋轢を生み出して行く様を描いたスコラスティックスリラーなのである。】
ー 冒頭、カーラ・ノヴァク(レオニー・ベネシュ)が教鞭をとるドイツの中等教育機関ギムナジウムで、盗難事件が頻発する。
「非寛容」を謳う学校のゼロ・トレランス教育方針(どんな、方針だ!)により、教師たちはノヴァクのクラスの生徒を調べていく。
そんな学校の姿勢に対し、ノヴァクは反発し、自身の服の中に財布を入れたままパソコンの動画機能で、犯人を突き止めようとする。-
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・序盤から、教師たちは口調は丁寧だが盗難事件の犯人は生徒と決めつけ、犯人捜しをしていく。
・だが、そのやり方に疑問を持ったノヴァクは、パソコンの動画機能を使い自身の服から財布を盗む人物を撮ろうとするが、そこに映っていたドレスは同僚のクーンが着ている服であった。
ノヴァクは穏便に事を済ませようと、クーンに話しかけるが彼女は激昂する。ノヴァクはその動画を校長に見せるが、クーンは認めずに逆にノヴァクのやり方を非難する。
・その事実は、徐々に校内に漏れて行き、クーンの子である優等生であるオスカーは、クラスの友達から嫌がらせを受け、逆にその生徒を突き飛ばす。そして自宅待機になったクーン。
・クラス内の秩序も崩れ、ノヴァクは逆に精神的に追い込まれて行く。
■再後半のシーンは、何とも暗喩的である。オスカーは無理に学校に登校し、級友の好奇の眼がありながらも最後まで教室に残る。
そしてノヴァクが、且つてオスカーに”アルゴリズムの問題よ。”と言い”一面だけ揃えてあげたルービックキューブ”を、オスカーはノヴァクの前でいとも簡単に”全面を揃えて”机の上に置くのである。
このシーンは、ノヴァクのアルゴリズムよりもオスカーのアルゴリズムが優れている事を示している。
広義で言えば、教師のアルゴリズムよりも、生徒のアルゴリズムが優れている可能性があるという事を示唆しているのである。
ノヴァクは今作に登場する教師の中では、生徒想いの良き教師であるが、盗難事件の問題解決手順を間違えてしまったのである。
故に、校内に留まっていたオスカーが警官達に校外に運ばれる時に、彼は周囲を睥睨する王のように、警官達に椅子ごと持ちあげられ、学校を後にするのである。
<今作は、教師の正義のアルゴリズム<この場合、問題を解決するための手順と読み替えた方が良いであろう。>に基づき、盗難事件の問題解決をしようとしたノヴァクや教師達が、<問題解決の手順を間違えた事により>様々な軋轢や負の感情を生む怖さを描き出したスコラスティックスリラーなのである。>
<2024年6月30日 刈谷日劇にて鑑賞>
私は一体どうしたら良いんだ…
その場にいないのにずっとそんな風に考えちゃって胃が…
そしてそんなこと考えあぐねてなにも行動に移さない内にあれよあれよと事態がコロコロして…
私は…俺は…ムリョクダ…(; ;)
子供も教師も全員の一つ一つの言動を、同じ立場なら私もしてしまいそうと思える妙があり、様々なシーンの空気感がリアルで身につまされる感覚を休まずずっと味わいました。
生徒に怪しい人を聞くのがそんなに悪いことか?
抜き打ちテストがそんなに?
盗難問題解決のための録画が?
新聞で真実(多分)を暴露するのが?
というテンションで私も「やれー!やるぞー!」ってなりそう。
この映画では俯瞰して見てる立場だから「一度立ち止まれ?」って思えるけど、問題の渦中に居るとアドレナリン的物質が生成されるんですよね…分かる…
何の問題も解決しないけどそれがやはりリアルで良いですね。
しねーのよ、解決なんて。しねーの。
だから今すぐ警察呼んで国家権力で思う存分監視カメラつけまくって尋問しまくって。
盗難は犯罪だから。
学校だけで解決しようとしないで国家権力に頼って。
まあ盗難事件に目を向けるとモヤモヤエンドですが、「お金が盗まれたときに問題なのは金額ではなくその行為そのもの」である通り、この映画の主題は盗難事件ではなくそれをきっかけに試される人間力なんでしょうな。
エンド直前の二人きりの教室、なにも明確なことはありませんけど…
カーラの「こんな展開は望んでいなかった」を受けて、何かノートに書いたものをうけて、カーラから託されたルービックキューブのアルゴリズムを解読したみたいに、二人でこの問題のアルゴリズムを解読したんだろうなと信じます。
明らかにオスカーの勝利を宣言するラストカットでしたけど、オスカーに水を渡して見つめるカーラからは敗北や絶望を感じませんでした。
オスカーも母親のために立ち上がったようなものなのに、着信には答えないし…
そもそもオスカーVSカーラではなく、集団に追い詰められた2人VS生徒や教師陣だったのかも。
こういう考察は普段人任せですが、オスカーは学校という権威に勝利し、カーラは教師として納得のいく"解答"に辿り着いたんだと信じる。信じます!
全125件中、21~40件目を表示