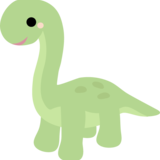瞳をとじてのレビュー・感想・評価
全102件中、61~80件目を表示
色々考えさせられた作品
ビクトル・エリセ作品は初見だが、初見でも過去作品のキーワードがシーンごとに出てくるので問題ない。
こんな作品もありなんだと唸らされたし考えさせられた。素晴らしい作品を観る事が出来感謝。
ただ、時間はやはり長いし、30年前に公開した時の世界と今の世界は違う。ビクトル・エリセには今何を伝えたかったのかラストにメッセージを残して欲しかった。垣間見る事はできなかったのは残念。
2024年ベスト洋画作品にはあがるだろうし、私は候補に入れたい。
人生と老いについても考えさせられた作品でも
ある。
カルテの記録が人生のすべてじゃない
劇中映画「別れのまなざし」
瞳をとじて
神戸市内にある映画館「シネ・リーブル神戸」にて鑑賞 2024年2月13日(火)
スペイン生まれの映画監督、ピクトル・エリセの31年ぶりの長編映画「瞳をとじて」
背景
劇中映画「別れのまなざし」は1947年という時代設定。
スペイン内戦(1936年-1939年)で台頭、軍人フランシスコ・フランコによる独裁政治となっていた。政治的抑圧、閉鎖経済政策がおこなわれ国民は困窮した。本作は内戦後の混乱が続いているスペイン社会を描いている。
「ミツバチのささやき」に当時5歳で主演に抜擢されたアナ・トレントが、50年ぶりに同じく“アナ”の名前を持つ女性で出演したことも話題に。
------------------
ストーリー
劇中映画「別れのまなざし」 冒頭部分
邸宅「悲しみの王(トリスト・ル・ロワ)」にはヤヌス像があり、ユダヤ人ミスター・レヴィ(Mr. Levy)とフェランが住んでいる。
フランク(フリオ・アレナス(ホセ・コロナド))を呼んだ。フェランは高齢となり、行方不明となった娘ジュディスを探して連れてきてほしいと依頼する。
今は母と共に上海に住んでいて「チャオ・シュー」と名乗っている。写真を差し出すと扇子を使って視線を強調する舞踊のポーズ「上海ジェスチャー」をしている。
-------------------
劇中映画「別れのまなざし」の撮影中に、主演俳優フリオ・アレナス(ホセ・コロナド)が失踪した。当時警察は、近くの崖に靴がそろえられていたことから投身自殺と断定。結局、遺体が発見されることはなかった。22年が過ぎたある日、元映画監督でフリオの親友でもあったミゲル・ガライ(マノロ・ソロ)は、事件の謎を追うテレビ番組「未解決事件」の出演依頼を受ける。
---------------------------
番組プロデューサーのマルタ・ソリアーノ(エレナ・ミケル)はミゲルに取材する。
海軍の兵役で出会った、マドリードで再会した。若いころの二人の写真がある。フリオが好きなポジションは、ゴールキーパー。彼と私は第2級の受刑者でした。
逮捕の理由は?「治安紊乱罪と、扇動罪および不法集会罪です。当時のよくある罪状だ。フリオは無関係だったが、私と同居していたので連行された。」
マルタはフリオの娘、アナ・トレント(アナ・アレナス)に取材を申し込んだが断られてしまったと言い、アナの電話番号をミゲルに通知。
アナはミゲルと喫茶店で再会「父が生きてる夢を何度か見た。」
番組の終了後、「フリオによく似た男が海辺の施設にいる」という思わぬ情報が寄せられる。「未解決事件」を見たと、ベレン・グラナドス(マリア・レオン)から、プロデューサーのマルタへ連絡があった。ベレンはとある老人介護施設に勤務している女性だった。
----------------------
深夜バスに乗ったミゲル。とある海辺に面する老人介護施設に向かう。
それらしき男がいるという。修道女シスター・コンスエロ(ペトラ・マルティネス)は、行き倒れた男を「ガルデル」と名ずける。よくタンゴを歌っていることから。
確かにその男はフリオのようだ。ただフリオは、記憶喪失の状態であることがわかった。
ミゲルはしばらくこの施設に滞在することにし、施設のシスターたちも合意。二人だけの時間となった。
ガルデルが、古いタンゴの曲を口ずさむと、ミゲルはその続きを口ずさむ。ガルデルは喜んだ。
ペンキ塗りの仕事があると、ミゲルはそれを手伝った。
水兵時代に習ったロープの結び方をやってみせると、ガルデルもそれはできる。
-------------------------
そんなある日、ミゲルはアナを再び呼び寄せて、父であるフリオが寝ている部屋へひとりで向せる。シスターたちとミゲル、ベレンはそっと見守っている
「私はアナよ」・・・「私はアナよ」・・・ 記憶が戻らず返答はない。
静かにそう言うのが精いっぱいであった。
ミゲルにはひとつの案があった。「別れのまなざし」の後半を上映しようと企て、記憶が戻るのではないかと仮説
マドリードに戻りたいというアナを引き留める目的もあった。
--------------------------
保管している親友マックス・ロカ(マリオ・パルド)に連絡し、「別れのまなざし」のフィルムを送ってもらう。
施設の近くに、最近閉館された映画館があり、そこで上映されることになった。
映画館の支配人はアナとガリデルは最前列の席に並んで座るようにしたのは「親子」の関係だからである。
シスター二人、ベレンとマルタが後ろ座席に並んで座った。
そうして「別れのまなざし」(後半)が始まったのである。
邸宅「悲しみの王(トリスト・ル・ロワ)」に向かうフランクとジュディス(チャオ・シュー)をフェランに見せるためである。
フェランは面会を果たすことができたのだがフェランは病で瀕死の状態
フェランは布切れを取り出し、花瓶の水を使い湿らせて、娘のチャオ・シューの顔を拭う。化粧が剥がれる。素顔が見たいんだろう。
そこで倒れてしまい、死んでしまう。父は目を開いたままであったが、チャオ・シューはやさしく父の顔に手を当て、目を閉じた。
あまりにもかなしいフランクとチャオ・シューがそこにいる
「別れのまなざし」上映終了
「瞳をとじて」上映終了
--------------------------
感想
スペインの映画 ピクトル・エリセ監督の作品「みつばちのささやき」「エル・スール」
楽しませてもらえたことに心から感謝します。
ムーチャスグラシアス! 大岸弦
上海ジェスチャー
映画愛!
今年はウディ・アレンの「サンセバスチャンへようこそ」もそうだったが、老境の映画監督が「映画愛」を全面に描いて、さらに自らの人生の再検討をしている作品に出合う年のようだ。本作も、エリセ監督の「もうひとつの可能性ある自らの人生と映画についての決着」を描いたように思える。
物語は、失踪した友人でもある俳優フリオを探すミゲル監督のロードムービー的な、仕立て。しかし、31年も映画監督としてのブランク、さらにデビュー作のヒロインだったアナ・トレントが、「ミツバチのささやき」の役名と同じアナとして出演するという、スクリーンに描かれる虚構が現実と合わせ鏡のようになっている。
さまざまな名作映画への目配せやオマージュ、そしてデジタルなんかじゃなくて「フィルムであることが必須」という思い。閉鎖したフィルム上映の映画館でのクライマックス。エリセ監督の「映画の葬送」に思えてならない。
エリセ監督の復讐?
前情報なく鑑賞したもので、オープニングからの流れは「映画館間違えたのかな?」と確認してしまいました。
本作は約3時間と冗長で、無駄な情報も多く、前半あそこまで長回し使って後半そんなに端折るか?など疑問符もつく出来栄えです。でも、それは人生も同じ。無駄なことや、間違いがあって味わい深くなるものです。映画を愛するものとして、どんな映画にも寄り添っていきたい。ポジティブに観たいと思っています。
前半の薄暗いイメージから後半のスペインの海沿いの風景が目が眩むようで良かったです。トマトを紡ぎながら、魚を採り、犬と暮らし、音楽とともに眠る主人公は羨ましい。演じている方も、相応のお歳ながらセクシーな演技でした!
エンディング、ちゃんと語らないのはエルスール未完になってしまった監督の世間への復讐かな?と思ったり思わなかったり。
長い映画でしたが、味わい深い人生のようで、観て良かったです。
映画への思慕
欧州映画らしい
作品紹介を読んで、男の失踪を追うミステリー要素のありそうな展開に興味を引かれて観賞。
でもちょっと違った・・・
【物語】
舞台は1900年代のスペイン。
マドリードのあるTV局の“未解決事件”を取り上げる番組で、22年前に映画撮影中に主演俳優が突然姿を消した事件を取り上げる。
その映画の監督であり、いなくなった人気俳優フリオ・アレナス(ホセ・コロナド)とは戦友の関係でもあるミゲル(マノロ・ソロ)が番組制作者に呼ばれる。ミゲルは取材に協力し、番組に出演し、フリオと過ごした青春時代と自らの半生を振り返る。
番組の終了後、「フリオによく似た男が老人施設にいる」という情報が寄せられ、ミゲルはすぐに駆け付ける。
【感想】
全体を通じて言えるのは、欧州映画らしい、情緒感溢れる作品であること。
ただ前半は、(これも欧州映画に良くあるパターンだが)延々と登場人物2人が同じ場所で話し続ける会話劇。これが、どうも俺は苦手で段々息苦しくなってしまうし、今回はこちらのコンディションが良くなかったこともあって、ウトウト・・・
後半、フリオの噂を聞いたミゲルが施設に駆け付けるところから急に物語が動き出して、やっとスクリーンに入り込むことができた。
作品紹介などを読んでミステリー作品的な展開? と思ってしまったが、 そういう作品ではなかった。本作はスペイン映画だけど、フランス映画とか好きな方にはスンナリ入って行ける作品だと思う。
逆にハリウッド映画のような刺激強めの作品をお好みの方には向かないかな。
期待度◎鑑賞後の満足度◎ これは『映画』『記憶』『人生』「生きてきたこと」「老いること」「忘れること」を綴った豊穣な映画。
※2024.04.01. 2回目の鑑賞。【ユナイテッド・シネマ橿原】
やっぱり1回目の鑑賞の時はこの映画を充分に理解していませんでしたね(今は理解出来ていると言い切れる自信は勿論ありませんけれども)。
だから下記のようなよう分からんレビューを書いてる…
《「記憶」と「映画」。『ドライヤーが死んだ後は映画で奇跡は起こらない』というマックスの台詞…そしてラストシーンのその先…
①【ヤヌス像】
冒頭から映し出されるのがこの像。ギリシャ神話の時間の神で、前後を向く二面像。一つの顔は過去を向き、もう一つの顔は未来に向いており、物事の始まりと終わりを見据えている。
②個人的には、本作においてはストーリーを追うという映画の見方は余り意味がないと思う。冒頭は何がどうなっているのか少し混乱するし(ラストに至って意味が分かるけれども)、映画中映画も余り面白い話ではなさそう。
③『映画』というものを描いた映画だろう。
また、記憶を繋ぐものとしての映画…”現代“の映画も突然現代になって今の形になったものではなく、過去の「映画」の記憶を繋いでいく延長線上にある…これからの映画も恐らく…
ラストシーンはあれ以外には考えられないな…
“「映画」は観るもの”…なのに『瞳を閉じる』
という意味深な原題に込められた想い…
★★★★》
④
私には合いませんでした
何か月も前から楽しみにしていた今作でしたが、私には残念ながら合いませんでした。
老いや過去、記憶の喪失に対する考え方に違和感がありました。
大変良かったとおっしゃる方が多く、うらやましいような、悲しいような…まぁ仕方ありません。
設定も、若人あきらさん→我修院達也さんのように、人気俳優なら顔も知られているし、生きていればすぐに見つかると思うのです。その辺りが許容できませんでした。
役者の顔にズームしていかず、ショットの切り替えでアップにしていく技...
役者の顔にズームしていかず、ショットの切り替えでアップにしていく技法に引き込まれる。
同じ映画でも自宅で観るより映画館で観る方が評価が上がると感じる人は多いのではないだろうか? 私は顕著にそれがある。そしてこの映画は特にそれに当てはまる。冒頭から引き込まれっぱなしだ。
出来るだけ映画館で観たいと思う個人的3つの理由が
1.一時停止も巻き戻しも出来ない状況に体調を整えて着座し 映画に向き合う事で作品価値が上がった様に感じる事
2.自宅では不可能な大画面、大音響で観れる迫力と臨場感が得られる事
3.待ってられない
と3つあるが、今作はやはり1番目である。
ビクトル・エリセの前の作品達とある要素が凄く似ていて、全く違うストーリー展開である。知っとくべきは監督の名前とアナ・トレントが出演する事だけでチラシに記載のストーリーすら事前に調べずに鑑賞したかった。だから内容は語りません。
エリセ監督作を2本観れたお得な気分。
人生における喪失を抱え追い求める
失われた二人の人生と記憶が紡いだものとは
失踪した人気俳優を巡るミステリー!ではない
完成間近だった映画撮影中に突然失踪したフリン。それがきっかけで監督を辞めて作家や翻訳家としてその後の22年間を生きてきたミゲルに舞い込んだ未解決事件を扱うテレビ番組の収録。ミゲルの中で止まっていた時間が動き出す。それでも事件にかくされた陰謀を明かすかのような素振りを見せるのはほんのしばらくで、誰も死んでいないし、誰も殴られない。
3時間の長編映画
長い映画だ。そして見た直後にははっきりしない結末にストレスが残る。でもなぜか後からわかってくる。映画が展開するテンポはゆっくりだ。それがために目に焼き付けられた登場人物が見せた様々な表情が甦り、この映画の伝えたかったものをじわりじわりと伝えてくれた。
掘り返される過去がミゲルに与えるもの
腑に落ちない過去に思い掛け無い形で向き合うことになったミゲルは、フリンの消息を掴もうと過去の人間関係に再び向き合う。そうして出会う人々もまたそれぞれがフリンに対する想いがある。それは語られる言葉だけでなく行動や表情という形で表現される。浮世離れしたような生活をしていたミゲルも、ミゲルに接する人々も淡々としているようでどこか優しい。それぞれが22年もの長い時間のなかでフリンのいない人生を築いてきた。いろんな関わり方でフリンと関係した人々に再会するミゲルは淡々としているようで何か心地良さを感じているかにも見える。
心の中の人生の記録とは
誰もが人生の記録を心に刻む。それを思い出と言ったり記憶と表現したりする。思い出は美化されると言う人もいるが、そのなかには決して美化されない誰もが忘れたい、閉じ込めたいものを持つ。それでもその記憶の中でも関わった人たちがいて今もどこかで生きていている。何も思い出を雄弁に語る必要なんかない。寄り添い合って生きていくだけで価値がある、そんなメッセージが届いた気がした。
全文はブログ「地政学への知性」で
映画の奇跡
原題:Cerrar los ojos(仏語)には、思わず目を瞑る、見て見ぬふりをするといった意味合いがあり、邦題である「瞳をとじて」は〈とじてください〉の指示語ではなく、〈とじてしまう〉と解釈するのが正しいと思う。このタイトル、エンドロールの直前まで何が何だか。だがそのシーンを見た途端、普遍的なテーマでありながら監督が31年振りに長編のメガホンを取ったことが瞬時に理解できるほど、とんでもなく綺麗で、その反動から涙が出てしまった。ビクトル・エリセ作品初挑戦だったから身構えていたけど、これはやられた...。
169分とかなりの長尺だけど、退屈ゼロ。こんなシンプルな人生ロードムービーなのに、巨匠の凄腕に永遠と入り込んじゃう。主人公・ミゲルの監督映画と本編の両方でじっくりと描かれる、喪失と再会。たった数日の物語。それでも、ミゲルにとっては一生分の物語。彼のような経験をすることは中々無いだろうけど、ふと自分が生きていることに価値を見出すことって、誰しもあると思う。後半からのミゲルの表情はまるで少年のようで、自分にしか出来ないと行動する姿はカッコよすぎてハッとさせられた。
何万とあるコマのどのコマも、部屋に飾りたくなるほど魅惑的。タバコを吸うシーンや、スープをスプーンで少しずつ飲むシーンだって。流石としか言えない。新作なのに往年の名作を見ているよう。劇中でも昨今の映画事情について、フィルムについて言及される場面があるように、監督自身31年間、カメラを持たなかった間に映画について思うところが沢山あったのだろう。本作のノスタルジックな雰囲気には、古臭さは感じず、フィルム時代の良さを継承したまま、現代の映画にも影響を与えるような目新しさがあった。だから、惹かれちゃうんだろうな...。
語りたいところは山ほどあるんだけど、中でも好きなのは、いくつかあるミゲルらが歌を口ずさむシーン。ギターと共に海辺で、古屋の外のベンチで、そして映画の中で。自分の映画史に残り続けるだろう、かつてない名シーンたち。ここまで食らってしまうとは思ってもみなかった。映画ってなんていいものなんだ。映画は奇跡を起こす。彼らにその奇跡が降りかかったように、私にもまた映画という魔法にかかった。ありがとう、また撮ってくれて。
もう二度と観られない巨匠作を是非に
ほとんど神格化された「ミツバチのささやき」1973年、日本公開1985年の作品自体そして監督ビクトル・エリセご自身も。果たして映画監督と呼んでいいものか悩ましい程の寡作家。もとより本当の寡なのか、撮りたくても撮れない状態もあれば、本当に31年ぶりに新作をここ数年で作ったのか、30年間費やして作ったのか? 真実が見えないから余計に神がかってきた。
「ミツバチのささやき」をいったいどれだけの日本人が鑑賞したのでしょう? 念のため調べたら一部の有料配信で観られる現況、アマプラでは2500円支払っての購入しか選択肢がない。そして正直に言いましょう、クレイジーな程の映画鑑賞ですが、私は(まだ)観ておりません。岩波ホールを頂点としてごく一部の単館系での公開だったはずですから、チャンスがなかったと言い訳しておきます。
よって人生初体験のビクトル・エリセ監督作品を映画館のスクリーンで鑑賞したわけです。重厚かつ静逸な雰囲気を覚悟したもので、失踪した俳優フリオを求めての意外やミステリー仕立ての口当たりの良さに驚いた次第。フリオを探す映画監督ミゲルが本作の主役ですが、明らかにエリセご自身を重ね合わせているでしょう。失踪により映画制作が中断したまま20数年、物書きとして湖口を凌ぐ設定。全編を覆うのは映画への愛おしい程の情景が匂い立つ。デジタルとかの映画を取り巻く環境激変への軋轢から、カール・ドライヤーの名まで出しての映像への追憶、そして「ニュー・シネマ・パラダイス」1989年よろしくフィルム映写室を登場させ映画を慈しむ。
撮影途中で主演男優が失踪で、カギとなるのが撮影済みのラッシュ・フィルムとなり、編集者マックスが保管していたフィルムが本作後半の主役となる。そもそもラッシュなのに、クライマックスでの上映では編集も音入れもなされているのはちと不思議ですが。なにより本作冒頭で始まるのはフランス郊外の古城の所有者である老人の依頼を受けた中年男の登場である。正面からフィックスで撮ったような舞台様式で始まる静寂のドラマは、緊張感を維持しミステリアスに包まれ、やがてバストショットの切り替えしとなり、肝心の人探しの要件が明かされる。怪しげな中国人の執事と言い、中国人とのハーフとなる美少女を上海まで探しに行け! と展開されれば「インディ・ジョーンズ」かと期待が膨らんでしまった。示された少女の写真の妖艶なこと! 時1947年の設定ですから無べなるかな。依頼を受けた男が館から出てくるショットで、画面は止まる。「この撮影の後主演役者は失踪した」とモノローグが入り、映画の二重構造が明かされる。
戦後の混乱期の上海での探偵ごっこはお預けとなった代わりに、テレビ局からの「未解決失踪事件」への出演依頼に繋がり興味は途切れない仕掛け。もとより、冒頭の「悲しみの王」は果たして本作の入れ子構造のための映像なのか? ひょっとするとエリセが以前に撮りだした別作品のラッシュだったかも知れない。これを活かして本作を構築した可能性もあるわけで。いよいよもってミゲルがエリセと重なる構造。
ミゲルが動き出し、映画としてのベクトルも明確となり、関係者への聞き込みが続く。切り返しの連続が続き単調に陥ったきらいはあるものの、マックスとの会話シーンでは流石の描写を紡ぎ出す。ソファに座ったマックスと立っているミゲルとの視線が合わないカットバックが続く、まるで噛み合わない会話のように。実はマックスの座ったソファのすぐ後ろにミゲルは立っていた訳で。劇中映画が起承転結の「起」となり、マドリッドでの調査が「承」となり、ミゲルの現在の住まいに移動しての海沿いのミニ・コミュニティが「転」となるが、ここのシーンが実に心地よい。多分スペイン南部の地中海の大海原が望める景勝地での平和な暮らし、ここで遂に「フリオ」の消息情報がもたらされ、一挙にクライマックスの「結」に突入する。ボルテージ爆上がりです。
しかし、そんな簡単に明かされない「結」です。そもそも本作のタイトルからして、ラッシュ・フィルムを見せられた失踪者本人であるフリオは静かに瞳を閉じて映画は終わるのですから。いじわるかも知れませんが、この余韻も佳きものです。果たして映画により記憶喪失の復活と言う奇跡は起きたのでしょうか? ご丁寧にエリセはヒントまで観客に用意していました。冒頭の劇中映画の館の庭に据えられた「ヤヌスの像」は、エンドタイトルでも延々と全体像とアップを繰り返される。ローマ神話の出入り口と扉の守護神で、前と後ろに反対向きの2つの顔を持つのが特徴の双面神。だからどうなの? なんて聞かないで下さい、各自の解釈で十分で、決めつけられない多様性の社会なのですから。
それにしても「ミツバチのささやき」に当時5歳で主演にした純真無垢な少女アナ役を演じたアナ・トレントが、同じ役名でフリオの娘として本作に登場の事実に驚愕しても、本作にとって何の意味も持たないわけです。これを以って妙な解析は馬鹿馬鹿しい限りと思います。
多分、次作は望めないわけですから、是非ご鑑賞をお薦めします。
二度目の囁き
寡作にもほどがある。
本作は実に三十一年ぶりの新作。
監督の『ビクトル・エリセ』は
1967年から五十六年間の活動歴で撮った長編は僅かに四本。
そのうち一本は{ドキュメンタリー}なのを勘案すれば
もう呆れるほかはない。
もっとも、先の二本
〔ミツバチのささやき〕〔エル・スール (1982年)〕は
何れも佳作なのだが。
本作は映画〔別れのまなざし〕の撮影場面から始まる。
監督の『ミゲル(マノロ・ソロ)』にとっては二本目の長編。
しかし旧友であり主演俳優の『フリオ(ホセ・コロナド)』が突然に失踪したことから頓挫、
作品は未完に。
それから二十有余年、『ミゲル』が未解決事件を取り上げるテレビ番組に出演したことから
物語りは動き出す。
『フリオ』らしい男が海辺の施設に居るとの情報が寄せられ
『ミゲル』は現地に向かう。
三時間に近い長尺も、刈り込めば二時間程度に収めることは可能だったろう。
しかし先の劇中映画の撮影場面も含め『ビクトル・エリセ』は多くの要素を盛り込む。
とりわけ狂言回しとなる『ミゲル』の過去の記憶については
執拗との表現があたるほどに。
とは言え、それらは何れも直接的ではなく、
あくまでも婉曲に。
二人と関係のあった女性とのエピソード、
『ミゲル』の家族が壊れてしまった理由やイマイマの彼の生活、
或いは互いが知り合うことになった経緯について。
潤沢にとられた時間の中で
主人公たちの今と昔に仔細にふれることで
あたかも彼らが実存するようにすら感じてしまう。
ここで存在感を発揮する登場人物がもう一人。
『フリオ』の娘『アナ(アナ・トレント)』は
長い間行方不明だった実の父が見つかったとの報に
最初は半信半疑ながら施設に赴く。
しかし『フリオ』は過去の記憶を喪失してしまっており、
旧知の『ミゲル』をも認識できない。
では『アナ』と会うことで記憶は蘇えるのか、が
新たに提示されるサスペンス。
そして、もう一つの謎、
なぜ彼は失踪したのか?の疑問も
解き明かされるのだろうか。
ここで昔からの映画ファンは
〔ミツバチのささやき〕のあの科白が
おそらく発せられるだろうと予感し期待する。
そのために役名を『アナ』として統一したのだろうと。
劇中劇の〔別れのまなざし〕は
生き別れとなった娘を父親が捜すとの真逆の構成。
完成版はないものの、数巻のラッシュは残っており、
それもストーリーに強く関係させるのは
やはり監督の映画愛なのだろう。
1972年の制作の〔ミツバチのささやき〕が日本で公開されたのは
1985年のこと。
スクリーンでは五歳の姿も
1966年生まれの『アナ・トレント』は既に十九歳だったわけで。
それから幾年月、再び本作で姿を見せた彼女は
いかにも年相応の外見。
過ぎた年月の永さを想わずにはいられない。
ミツバチの遺言
ビクトル・エリセも今年で84歳、おそらく本作が遺作となることだろう。本人もその点は十分承知の助で、この『瞳を閉じて』を通して映画人生の集大成をやろうとしている。が、困った点が一つだけ。なにせ半世紀以上のキャリアの中で本当の意味で完成にこぎつけた長編作品は『ミツバチのささやき』の1本だけなのだ。次作『エル・スール』はプロデューサーに後半1/3をカットされ、本作におけるエリセの分身であるミゲル同様、本人の中では未完成作品のままなのではないか。エリセと同じく反フランコの立場をとり佳作を連発し続けているアルモドバルとは正反対なのだ。
『エル・スール』後は短編制作やドキュメンタリー作品にも手をつけてはいるが、それ以降31年間の長きにわたって沈黙を守り続けていた映画監督なのである。実をいうと私はビクトル・エリセの過去作を観たことがない。本作がビクトル・エリセの初体験で、かつおそらくは最後となることだろう。この映画、何十年もメガホンを握らなかった監督の言い訳にもなっているわけで、“静謐の魔術師”の異名をとるエリセにしては、かなり饒舌な作品に仕上がっている。
『ミツバチ』撮影中実在のフランケンシュタインを相手にしているとすっかり信じこんでしまったアナ・トレントが、失踪した映画俳優の娘役で登場している。記憶を失った父親に向かって「私はアナよ」と囁くシーンは『ミツバチ』のオマージュだそうだ。が、セルフオマージュ作品として本作を成立させるためには絶対数が足りなさすぎる。そこで苦肉の策として盛り込んだのが、ニコラス・レイの『夜の人々』やハワード・ホークスの『リオ・ブラボー』等のマイ・フェイバリットだったのだろう。
日本の映画監督溝口健二についての論考を書いたことでも知られるエリセだけに、(劇中あまり効果は発揮していないものの)溝口お得意の水平移動カメラを随所に発見できる。要するに、自らの映画人生を映画で語る時、他人のふんどしで相撲をとらざるを得ない、それほど寡作の人なのである、エリセは。映画全体の構成(&辿った経緯)がテオ・アンゲロプロスの壮大な失敗作『ユリシーズの瞳』とクリソツなのも気になるところ。
映画内映画『悲しみの王』のラスト・シーンで、中国人ハーフ少女の無垢な眼差しをカメラ目線で映し出すエリセ。批評家連中の心ない突っ込みを拒絶するズルい演出をして見せている。その無垢な眼差しで見つめられた我々観客は、記憶を失ったフリオ同様にやはり瞳を閉じて(心を無にして)、エリセの数少ない過去作品に思いを馳せるのだろうか。ていうか実際、瞳を閉じたら映画を観ることができないんですけどね。
失踪への一時的な憧れ
2023年。ビクトル・エリセ監督。20年前の映画撮影中に主演俳優が失踪した。監督は撮影を中止し、その後はいくつか小説を書いて話題にもなったものの、現在は海辺の村で静かに暮らしている。そんななか、失踪者を扱うテレビ番組に出演したところ、放送後に失踪した俳優が記憶を喪失した状態で見つかった、と連絡があり、、、という話。
主人公にとって、俳優は兵役を共にした親友でもあり、テレビ番組を機会にその関係者に会うことは、自らの過去を振り返り、老いと直面することでもあるが、その過程で、若いうちに姿を消した俳優について、この世の外へと羽ばたいたように感じられている。老いを前にしてこの世界から抜けだした俳優への憧れのようなものを否定できないのだ。それでも、生きる喜びを感じないらしい現在の俳優の姿はやはり求めるべきものではなく、この世界で、記憶とともに、生きるための「奇跡」(カール・ドライヤー)へと挑戦していく。一時的ではあるものの失踪への憧れ、それでもこの世界を捨ててはいけないという倫理。この展開が切ない。それが映画と記憶に関わる倫理なのだ。
映画を監督する、映画を保存する、映画に出演する、映画を鑑賞する、さまざまな人々の映画への関わり方が丁寧に描かれている。
全102件中、61~80件目を表示