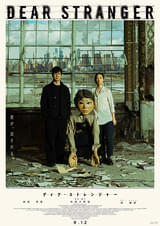1990年代に生まれた中華圏の世代にとって、日本文化との出会いは特別な意味を持ちます。アニメやドラマをきっかけに日本語を学び、やがて日本の映像業界に身を置くようになった人たちは少なくありません。その代表的な存在のひとりが、プロデューサーのIsabel Liさんです。
私が彼女と出会ったのは、すでに6年前のことです。常に「どうしてここまで映画にまっすぐでいられるのだろう」と驚かされ、その姿勢を頼もしく感じてきました。毎年、上海国際映画祭では、日本チームの動きを誰よりも丁寧に支え、現場を明るくしてくれる存在でもあります。
日・中・英の三言語を自在に操り、さまざまな国の現場を経験してきたIsabelさんは、いまや国際プロジェクトにとって欠かせない人材です。文化を越境しながら映画を紡ぎ続けるその歩みをたどることは、これからのアジア映画の未来を考えるうえでも大きな意味を持つでしょう。
今回は、Isabelさんへのインタビューを実施。彼女の原点から現在に至るまでの軌跡を振り返りながら、国際映画制作における課題と可能性を探っていきます。
●幼少期、日本との出会い
――まず、日本文化との最初の出合いについて教えてください。
最初の出合いは、小さい頃に父が買ってくれた「
名探偵コナン」のDVDでした。上海にいた頃だったか、ニューヨークにいた頃だったかは曖昧ですが、とにかくそれが最初です。吹き替え版と日本語版の両方を観ていた記憶があります。
――その体験ですぐに日本に惹かれていったわけではないのですね。
そうですね。最初はコナンから日本のアニメに興味を持ち始めました。その後、小学3年生で上海に戻った時に、「
カードキャプターさくら」や「
テニスの王子様」が学校で流行っていて、そこから一気に日本のコンテンツにのめり込んでいきました。そしてアニメを経て、人生で初めて観た日本のドラマが「1リットルの涙」でした。
――「1リットルの涙」との出合いはどんなものでしたか。
夏休みに、5歳年上のファミリーフレンドのお姉さんの家に泊まりに行った時に、「これ面白いらしいよ」と勧められて一緒に観ました。夏休み中、毎日のように泣いて、本当に“1リットル”の涙を流したんじゃないかと思うほどでした。
●ドラマが教えてくれた「日常の物語」
――その作品をきっかけに、実写作品を積極的に観るようになったのですね。
はい。そこから一気に日本のドラマを観るようになりました。当時は「プロポーズ大作戦」や「
花より男子」「
のだめカンタービレ」などの人気作品に夢中になる一方で、
野島伸司の「あいくるしい」のように、日常を丁寧に描く良作にも惹かれていました。アニメとはまったく違うジャンルでしたが、日常の機微に寄り添う作品群が、自分の中で大きな位置を占めていったのです。
――特に心に残ったのはどんな点ですか。
「1リットルの涙」は主人公・亜也の日常を丁寧に描写していて、感情移入がとても大きかった。家族の物語という点も心を揺さぶりました。一緒に観ていたお姉さんがちょうど亜也と同じくらいの年齢で、「もし自分の身近な人がこうなったら」と想像せずにはいられなかったんです。日本のドラマは大事件ではなく日常に焦点を当て、その細やかさが私を引き込んでいきました。
●音楽から始まった日本語との出合い
――日本語の勉強はどのように始めたのでしょう。
最初は音楽です。
倉木麻衣や
浜崎あゆみの曲、そしてアニメやドラマの主題歌を歌いたくて、歌詞をひらがなやローマ字に書き出し、とにかく歌いました。意味が分からなくても、繰り返すうちに自然と覚えていったんです。
また、アメリカで日本から転校してきた同級生との出会いも大きかった。英語ができなかった彼女と仲良くなりたくて、拙い日本語で必死に話しました。あの経験が大きな転機でした。
――日本語試験にも挑戦したのですか。
はい。親に「本当にできるの?」とからかわれて悔しくなり、日本語能力試験を受けました。まず2級に合格し、自信がついて次に1級も合格。すべて独学で、必死に勉強しました。
●上海国際映画祭で芽生えた「映画の道」
――大学時代には映画祭のボランティアを経験したそうですね。
上海国際映画祭です。
岩井俊二監督が来場した時、「
Love Letter」の再上映を観て感動しました。日本語が少しできたので、ゲストの通訳やコーディネートを担当し、
川村元気さんの作品チームや東宝の方々、
水原希子さんの対応もしました。
――その経験は大きな転機になったのでは。
はい。通訳を通じて多くの映画人と出会い、「人に感動を与える作品を作りたい」と強く思うようになりました。
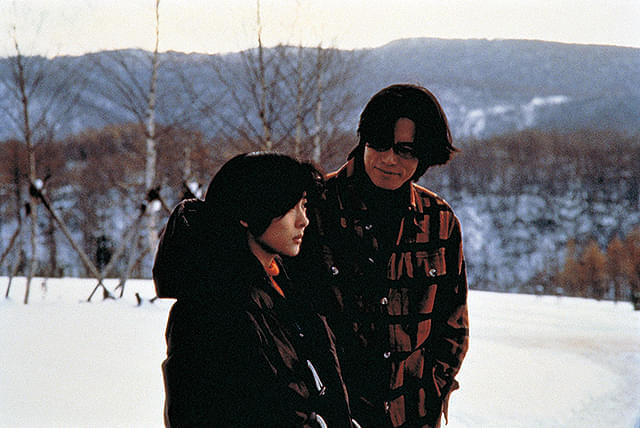 「Love Letter」(C)フジテレビジョン
「Love Letter」(C)フジテレビジョン●日本映画業界への挑戦
――大学卒業後、日本での就職を決めた理由は。
上海国際映画祭でお世話になった
川村元気さんがSTORY inc. を立ち上げ、そのタイミングで声をかけてもらいました。日本に住んだ経験もなく、留学歴もありませんでしたが、日本映画の独特さに挑戦したいと決意しました。
――外国人第一号社員としてのスタートはいかがでしたか。
ビジネス日本語はまったくできなくて、「お世話になっております」すら分かりませんでした。メール一通に時間をかけ、緊張しながら送っていました。でも先輩方が本当に優しく、支えてくれました。
――最初に手がけた作品は?
「
唐人街探偵 東京MISSION」です。入社が決まったタイミングでいきなり走り出していた企画で、しかも舞台は東京。準備期間がとても短く、キャスティングやロケ地調整、各種の許可申請まで同時進行でした。加えて中国からは大規模なスタッフチームが来日し、現場は常に300~400人規模。日本映画の現場では100人でも大作とされるので、まさに桁違いのスケールでした。
――通訳や調整は相当大変だったのでは?
はい。通訳はほぼ全部署に必要で、細かい指示を伝えるだけでも一苦労でした。限られたロケ地には人数制限もあり、外での撮影では人員をどう分散させるかが常に課題でした。それでも、役者が演じる瞬間にカメラ、照明、美術のすべてが奇跡のように噛み合い、画が生まれる。あの“現場でしか起こり得ない奇跡”を目撃したときに、私は心から「映画の現場が好きだ」と実感しました。
 「唐人街探偵 東京MISSION」(C)WANDA MEDIA CO.,LTD. AS ONE PICTURES(BEIJING)CO.,LTD.CHINA FILM CO.,LTD “DETECTIVE CHINATOWN3”
「唐人街探偵 東京MISSION」(C)WANDA MEDIA CO.,LTD. AS ONE PICTURES(BEIJING)CO.,LTD.CHINA FILM CO.,LTD “DETECTIVE CHINATOWN3”――作品の反響を振り返って、どんなことを感じましたか。
結果的に作品は中国で大ヒットし、興行収入は900億円近く。東宝スタジオには毎日のように中国スタッフが出入りし、日本側の関係者も「これが中国マーケットのスケール感か」と驚いていました。あの経験は、国際合作に携わるうえでの貴重な土台となりました。
はい。コロナ禍の中での企画開発でした。STORY inc.はもともとアニメーションに強い会社で、
新海誠監督の作品にも深く関わっていましたが、私は実写への挑戦を強く意識していました。そんな時に出合ったのが「
舞妓さんちのまかないさん」です。
――最初に原作を読んだとき、どんなところに惹かれましたか。
料理が大好きで、食べることをテーマにした作品には自然と惹かれます。しかも、舞台は京都・祇園。舞妓や芸妓の世界と日常の食卓が交錯する物語は、私にとって「日本文化の粋」と「普遍的な人間ドラマ」が同居しているように思えました。この題材なら日本国内だけでなく、海外の視聴者にも必ず届くと確信しました。
 「舞妓さんちのまかないさん」(C)小山愛子・小学館/STORY inc.
「舞妓さんちのまかないさん」(C)小山愛子・小学館/STORY inc.――実際に企画を社内に持ち込んだ時の反応は?
企画を社内に提案した際、
川村元気さんも強く共感してくださり、
是枝裕和監督に声をかける流れになりました。コロナ禍という厳しい状況のなかでも、皆さまのご尽力により、プロジェクトは順調に進めることができました。本作は、アニメーションの強い会社であるSTORYから生まれた実写ドラマであると同時に、“食と文化をめぐる普遍的な物語”としても、大きな意味を持つ取り組みとなりました。
――しかし、その後は帰国を選ぶことになった。
はい。本当はもっと日本で挑戦したい気持ちがありました。「
舞妓さんちのまかないさん」は心から好きな企画で、やり残したこともたくさんあったからです。でも、コロナでアメリカにいる両親や上海のおばあちゃんに何年も会えない日々が続き、画面越しの会話では安心できなくなっていきました。ひとり暮らしの部屋に閉じこもると、心細さや不安ばかりが大きくなって、仕事への情熱だけでは埋めきれない空白がありました。
最終的に会社とも何度も相談し、「一旦帰る」という決断を下しました。日本での生活を手放すのは苦しく、心のどこかで“悔しさ”のような気さえしましたが、それでも家族を優先せざるを得なかった。私にとっては痛みを伴う選択でしたが、同時に次の道を考えるきっかけにもなったのだと思います。
●インディーズ映画、そしてニューヨークへ
――帰国後は中国のインディーズ映画にも参加しましたね。
スタッフはわずか60人ほどで、規模だけ見れば小さいですが、そのぶん決断も実行も速く、現場は驚くほどスムーズに進みました。日本の現場は「段取り」を重んじ、準備を徹底してから撮影に入ります。一方で中国のインディーズ現場は柔軟性が求められ、想定外の事態にも即座に対応していく。どちらが良い悪いではなく、制作文化の違いとして強く印象に残りました。少人数だからこそ各人の責任が重く、無駄のない進行はむしろ心地よいリズムさえありました。
 「Dear Stranger ディア・ストレンジャー」(C)Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.
「Dear Stranger ディア・ストレンジャー」(C)Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.ニューヨークでの撮影に、ロケハンから参加しました。真利子監督、撮影監督の
佐々木靖之さんと共に現地を歩き、アメリカのプロダクションと何度も議論を重ねました。印象的だったのは、脚本ディスカッションです。文化の違いが生む新しい視点に何度も驚かされました。「こういう読み方もあるのか」と気づかされることが多く、創作の幅が広がっていくのを感じました。
撮影はブルックリンのチャイナタウンでも行われました。スタッフの多くはアメリカンスタイルのケータリングに飽き、撮影の合間に地元の中華を食べに出かける。その小さな逸話さえも「国際プロジェクトらしい現場の風景」として忘れられません。文化の交差点で作品が形を帯びていく、その瞬間に立ち会えたことは、私にとって大きな財産になりました。
●「合作」ではなく「仲間」として
――国際共同製作を経験して感じる課題や可能性は。
一番大事なのはコミュニケーション。本来は仲間であるはずなのに対立してしまうことが多い。でも本当は「どう解決するか」を一緒に考える立場であるべきだと思います。「合作」という言葉より、「仲間」という感覚でやっていきたいですし、経験を重ねれば理解は深まり、最初は大変でも将来は「いい思い出」になる。だから恐れずに挑戦していきたいんです。
――これから挑戦していきたいテーマを教えてください。
「愛と感動」を届けたいです。世界共通の物語は難しいけれど、人を動かす力がある。文化交流を大切にしながら、映画を通して共感や感動を与える作品を作り続けたいと思います。
アジア映画の現場で繰り返し露呈するのは、コミュニケーション不足です。言語の壁、制作文化の違い、組織間の理解の浅さ――それらが小さな誤解を積み重ね、大きな摩擦へと発展することは少なくありません。本来であれば協力できるはずの場面で、歩み寄りが足りないために機会を逃す例を、私は映画祭や撮影現場で何度も目にしてきました。
だからこそ、異なる文化を理解し合い、つなぐ姿勢そのものが求められています。
Isabelさんの歩みはその一例に過ぎませんが、国境を越えた制作において「仲間として対話すること」の重要性を改めて浮き彫りにしています。国際プロジェクトを未来へと進めるには、まずコミュニケーションの質を高めること――それが何よりも優先されるべき課題でしょう。

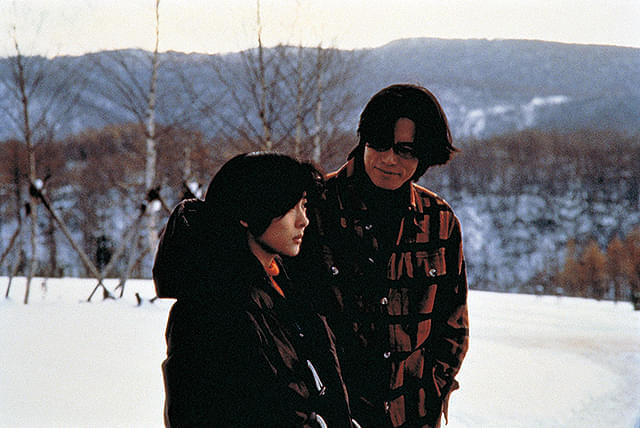









 本日公開 注目特集
本日公開 注目特集  本日公開 注目特集
本日公開 注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集