【「パリ13区」評論】リズム感あふれる瑞々しいモノクロの映像が織りなす、2020年代のヌーヴェル・ヴァーグ
2022年4月16日 21:00

最近ギャスパー・ノエにインタビューをしたとき、彼が本作のことを挙げ、「自分は子供の頃、この地区に住んでいたことがあったけれど、映画でこれほど美しく描かれていることに驚き、感動した」と語っていて、深く同意せずにはいられなかった。なぜなら、本作の舞台となっているパリの13区は、60から70年代の性急な都市開発のせいで、やたらニョキニョキと不揃いなコンクリートの団地が立ち並び、もっぱらパリらしからぬ景観を見せているからだ。さらに中華街をはじめ多彩な人種に溢れる点も、オスマン建築の並ぶクラシックなパリとは異なる。そんなエリアを選び、モノクロという選択を用いてここまで映画的な空間に仕立ててみせたジャック・オディアールの手腕にまず、脱帽する。
もっとも、ここに写し出されるのは特別な場所ではない。平凡な通り、よくあるカフェ、大学。そんな月並みな風景が、柔らかな光、挑戦的なアングル、俳優たちの生き生きとした佇まいにより、はっとするほど新鮮な風景に生まれ変わる。
ルームメイトを探していたエミリーは、応募してきた男性教師カミーユを見て、その晩すぐにベッドを共にする。ふたりの共同生活が始まるものの、エミリーにとって彼は「セックスもする」ルームメイトでしかない。
一方、社会人を経て大学に復学するため、地方からひとりパリに来たノラは、若い学友たちと馴染めず孤独な日々を味わううちに、ネットで知り合った元ポルノスターのセックスワーカーの女性と親密になっていく。そんななか、学友の悪戯が元で大学をやめることになったノラは、不動産会社の職に就くが、そこにはパートタイムで働くカミーユがいた。
個々のスケッチがやがて交差し、今を生きる若者たちの等身大の姿を描く鮮烈な絵巻となる。その瑞々しさは、脚本にセリーヌ・シアマ(「燃ゆる女の肖像」)とレア・ミシウス(「アヴァ」)という若手監督が加わっていることもあるのかもしれない。
さらにその滑らかな語り口を支えているのが、本作の音楽性だ。この映画の音楽はたんなる伴奏でも効果音でもない。音楽が物語のリズムの根幹を支え、カメラワークもまたそのリズムにのって躍動する。たとえばエミリーが中華レストランで踊り出すシーンのなんと自然で軽やかなことだろう。まるでゴダールの映画でステップを踏むアンナ・カリーナを彷彿とさせるようだ。
実際本作のところどころにヌーヴェル・ヴァーグへのオマージュを感じることは、難しくないだろう。そう、いまの若者はジャン=ポール・ベルモンドとジーン・セバーグが歩いたシャンゼリゼではなく、さまざまな人種が共存する13区を歩くのだ。2020年代のヌーヴェル・ヴァーグを生み出したオディアールの意匠を祝福したい。
(C)ShannaBesson (C)PAGE 114 - France 2 Cinema
関連ニュース





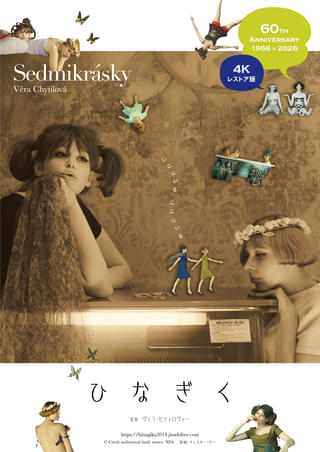
映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント









































