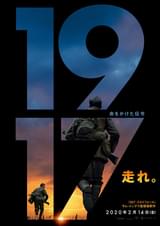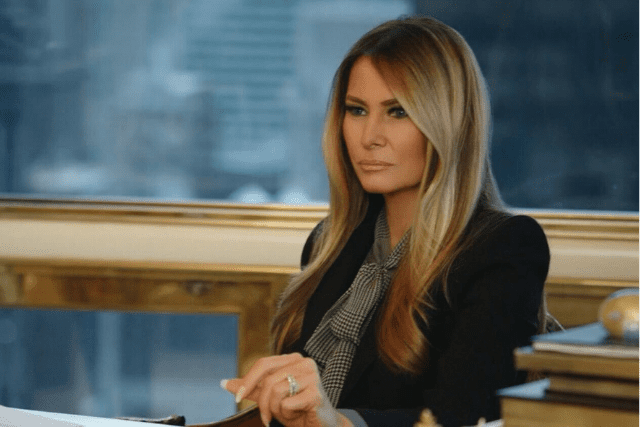「詩人」監督&キャストが描いた、個人の運命が時代のうねりの中で漂流していくさま
2018年11月1日 12:00

[映画.com ニュース] 鉱山で働くリー・ウー(チュー・ヤーウェン)は、詩人として大成することを夢見ている。妻のチェン・フイ(ソン・ジア)がガリ版で刷った詩集が認められ、ようやく名をなすが、改革開放政策が進むと人心も様変わりし、しだいに名声を失っていく。「ようこそ、羊さま。」(2004)で海外映画祭受賞経験のあるリウ・ハオ監督が10年来企画を温めてきた本作は、夫婦愛をベースに、時代に翻ろうされる中国民衆の姿を描いた力作。念願の作品を引っさげて来日した監督と、甲斐甲斐しい妻を演じたソン・ジア、主役の詩人を演じたチュー・ヤーウェンに話を聞いた。
――これは釜山映画祭の企画コンペで、05年に表彰された作品です。完成まで苦労されましたね。
リウ・ハオ監督(以下、ハオ監督):釜山プロモーション・プラン(PPP)で1位に選ばれて賞金をもらいましたが、それだけでは足りず、出資者をさがしていました。その後、上海映画祭の脚本コンペでも特別賞を獲得して、ようやく注目されるようになりました。一般的な商業作なら資金集めは簡単ですが、文芸作品の場合そうではありません。ここにいる、名のある実力派俳優の出演が決まり、資金集めもだいぶ楽になりました(笑)。
――主演のおふたりは、いつ出演を決めたのでしょう。
チュー・ヤーウェン(以下、ヤーウェン):私もほぼ同じ時期に脚本を読んで感銘を受けましたが、実は色々と迷っていました。自分はこの詩人ほど一途じゃない。それに、資金繰りやスケジュールの面でまだ不確かな部分があったからです。でもソン・ジアさんが出演されると知って、私も参加を決意しました。われわれは10年来の友人であり、彼女が出るなら心強いと気持ちを固めました。

ハオ監督:ふたりは今の中国映画界ではいちばんいい俳優です。所属事務所が大手で、そこの幹部が製作に加わってくれたおかげでこの映画は完成できました。
――仲睦まじい夫婦の物語です。気心の知れたおふたりだから表現できた部分も?
ジア:共演相手がよく知っている方だと、やはり信頼感があります。チュー・ヤーウェンさんとはあうんの呼吸で通じるところがあって、目の動きで「こう来るな」とわかるから感覚が刺激されます。共演できてラッキーでした。
ヤーウェン:本作は1980年代から90年代初めまでを舞台にしていますが、この時代を体現できる女優はあまりいません。人民公社の爪痕を留める集団生活が終わりを迎えようとしている時代の空気感、残り香が彼女にはあります。妻以外では私のいちばんの親しい友人であり、その息づかいや気心もよく知っているので、力の入れどころも掴めた感じがありました。この種の作品は、初顔合わせの俳優が一過性的に関係を構築していくのでは、時間の無駄です。脚本はよくても撮影スケジュールはタイトなので、一発で決める必要があったんです。
――炭鉱町の広場に毛沢東の壁画があって、物語が進行する中で、出入口の看板が差し替えられます。それで1970年代後半から80年代にかけての物語と思いましたが。
ハオ監督:78年に三中全会(中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議)が開かれ、トウ小平の時代になって、中国は近代化の道を歩み始めます。本作が描いたのは、それよりもさらに後、80年代半ばから90年代に入って、江沢民が後継を継いだあたりまでです。三中全会以降、時代は変わっていきますが、すぐさま一変したわけではなく80年代中頃から徐々に変わっていきました。

――中国の現代詩というと、北島(ベイ・タオ)や芒克(マンク)が日本でも知られていますが、映画に描かれる詩人にモデルはおりますか?
ハオ監督:80年代にいた様々な人物のミクスチャーです。あの時代は誰もが自身の運命を変えたいと切望していましたが、その手段は非常に限られていた。文才があれば詩を書いてという具合に。だから、特定の個人の立身出世を描いたものではありません。
――鉱夫から詩人になる主人公もさることながら、職業替えして裕福になりたい庶民も登場しますね。彼らも監督が若い頃に、見てきた人々のイメージでしょうか?
ハオ監督:主人公夫婦も周辺人物も、自分が見てきた大人像から作り上げたキャラクターです。誰もがみな新たな社会に直面し、精神的な困難と向き合いながら未知の自分を探し求めていた。個人の運命が時代のうねりの中で漂流していく姿を見つめました。
――鉱山の街が映画に風格をもたらしていますが、どこでロケされたのでしょう?
ハオ監督:新疆ウイグル自治区にある炭鉱で撮影しました。ここは露天掘りの炭鉱が今も営業していて、蒸気機関車が毎日石炭を運んでいます。ロケ中、お世話になった方々が「記者会見がんばって」と、今日の午前中、WeChatでメッセージをくれました(笑)。また、紡績の染色工場は石河子市で撮影しました。後者は同じ新疆ウイグル自治区にありますが、600キロ以上も離れているのです。ロケハンには苦労しました。美術スタッフは特に大変で、炭鉱の町は結局いい場所が見つからず、1万平米のセットを建造したんです。

――1万平米というと、野球のグラウンドくらいの広さですね。
ハオ監督:美術スタッフが優秀で、280万人民元(約4500万円)ほどの経費で済みましたが、誰も信じてくれない。中国の映画プロデューサーは一様に、3000万人民元(約4億8000万円)は少なくともかかっているはずだと。なので、美術スタッフには本当に感謝しています。低予算で苦労してかくも見事なセットを作ってくれたことに。
――俳優のふたりは、東京国際映画祭のレッドカーペットも今日のインタビューも凄くモダンで、映画とはまるで違う雰囲気です(笑)。役作りのご苦労はありましたか?
ヤーウェン:リー・ウーのキャラクターは、あの時代からすれば凄くモダンです。役で着ていた服も当時とてもファッショナブルなものだし、詩を書いて運命を変えようという人格も、時代設定からするとかなり垢抜けている。集団化したままになっている旧弊な社会を抜け出し自身の表現を追い求め、抜け出そうと藻掻くあまりに、妻との間に取り返しのつかない溝を生じさせてしまうんです。
ジア:チェン・フイと普段の私は全然違います。脚本を読んだとき、このキャラクターは男性の思い描く夢だと思いました。どの国の男性も、あんな妻でいてほしいという理想がある。チェン・フイは自己犠牲をもいとわず夫のリーに尽くします。そうすることで、母子関係のような情愛が芽生えるんです。
取材・構成 赤塚成人 (四月社・「CROSSCUT ASIA」冊子編集)
Amazonで関連商品を見る
関連ニュース


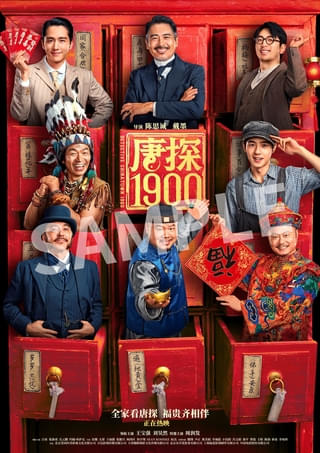



映画.com注目特集をチェック
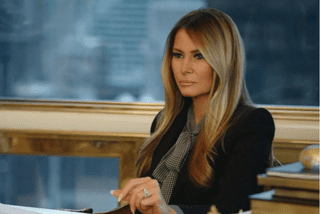 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント