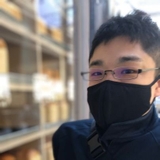悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全252件中、181~200件目を表示
森の中の父娘
濱口竜介監督の新作。音楽用の映像作品から長編劇映画に発展したとのことで、冒頭、森の木々のあおり映像に音楽がかぶるあたりから、独特の雰囲気がある。
森の中に住む寡黙な父と可憐な娘という設定が、ヨーロッパ映画のよう。薪割り、水汲みといった日々の労働をじっくり長回しで見せるのも、それっぽい。
森を開発するグランピング計画によって巻き起こるドラマ部分は、取ってつけたような感じもあるが、「偶然と想像」を彷彿とさせる車内での会話シーンなど、濱口監督の持ち味を発揮している場面もある。
しかし、ラストは雰囲気のまま流したような感じがして、残念。次回はぜひ、がっちりとドラマに取り組んでほしいと、大いに期待する。
悪とは
スマホのある時代に生まれたことを強く悔やんだ。
最初の森の長回し。
すごくその森のことが気になったし
物語に入り込むには十分だった。
男の棒読み感に
ああ、大学サークルの延長か、OBか、と思った
がっかりした。
女の子もベルギー映画に出てくるような、
2人共にバランスの悪さを感じた。
チープさ。
荒いカメラワーク、
暗くて絵が見えないカット
チカチカする長回し
けれどそれでいて
むしろ身近に感じられるという作用。
途中からはもう男のような存在が欲しく、花が羨ましかった。あんな存在が欲しい。
私はずっと子供なのだと思った。しっかりしてなければいけない、子供。
男の包容力を感じてからは
少し良いなと、思うようになった。
あの生活、あの落ち着き。良いなと思った。
羨ましいなと思う良いなと、これって良いな、の気づく良いな、だ。
東京から来たプロダクションの2人、
最初は背景に過ぎなかったが
女の意志を感じ、そして車の会話劇は名シーンだ。もうすんごい多幸感。こういう映画を見ていたいし、作りたいし、でたい。かと言ったら
もしかしたら作りたいが一番強い。
そこからはどの登場人物も愛おしかった。
それはすごいよなあ。
最初意識的に引き込まれていなくても
掴んで離せない何かはあって
最終的に持っていかれる。
わたくしはこういう関わり方をしたい。
こういう環境にいたい。
有機体のような恐ろしさ
自我の気化 人の希釈
我々にとってのGIFTのような作品‼️
まず長野県水挽町の自然がホント息を飲むように美しい‼️湧水の汲み場とか、鹿の水飲み場とか原っぱとか、まるで日本じゃなくて北欧みたい‼️長野県水挽町で便利屋として水を汲み、薪を割るような質素な暮らしをしている巧とその娘の花。しかしある日、水挽町にグランピング場を作る計画が立ち上がり、その計画を立ち上げた会社の社員、高橋と黛がやってくるが・・・‼️冒頭、水を汲み、薪を割り、野草を摘む巧の描写や、自然の中を走り回る可愛らしい花ちゃんの様子が丹念に描かれ、濱口竜介監督の腰の座った演出ぶりは、サスガと思わせる‼️そしてグランピング場の説明会による社員と住民たちのまるで法廷劇のようなやりとり‼️そのキレの良い話術は濱口監督の円熟ぶりが感じられます‼️そして会社の社員たちが再度、水挽町を訪れる後半から、この作品はまた違った顔を覗かせてくる‼️社員の高橋と黛は、巧をはじめとする住民たちの生活に触れ、都会の暮らしとは一味違う水挽町での生活に憧れのようなものを抱いてくる‼️高橋に限れば薪割りの楽しさに目覚め、自分がグランピング場の管理人になると言い出す始末‼️自然を汚す人間たちの欲の深さを描くのかと思ったら、なんとなく微笑ましい展開‼️常に我々と共にある自然の厳しさや美しさ、そしてその自然に魅了されていく人間たちの姿‼️そして花ちゃんが行方不明になってしまう‼️住民総出で捜した結果、怪我した花ちゃんを巧が必死に担いで運ぶ‼️そしてここでエンドクレジット‼️エッ、ここで終わるの⁉️みたいなエンディングだし、ここでしか終われないとも思える完璧なエンディング‼️登場人物たちがどうなったかは観る者に委ねられるという事でしょうか⁉️多分、水挽町の自然に何の影響もないグランピング場が出来たんだろうし、高橋や黛が管理人となって水挽町の住民になったかもしれないし、花ちゃんも無事助かったと思う‼️なぜなら "悪は存在しない" のだから‼️
僕の期待が高過ぎた、期待してる部分が監督の描きたいことと違っていた...
僕の期待が高過ぎた、期待してる部分が監督の描きたいことと違っていた(偶然と想像は年間ベスト、寝ても覚めてもは生涯ワースト)という鑑賞態度の不義理さでスコアはこんなものになるけど、とんでもない作品なのは間違いない。
グランピングの説明会のピリピリした会話劇が本当に面白かった。安直に『都会vs田舎』『革新vs安寧』に留めることなく、住民の中にも『自然側からすると我々は部外者である』という認識を持ったキャラクターが出てくるからこそ、ラストの衝撃の展開が「ただ単に突飛にしたかっただけではない」という説得力を持たせている。実際説明会する側がみんな乗り気なのか、前向きなのかもわからないしな。どうしてもこのタイミングで観ると、静岡のリニア問題を想起させる。
濱口監督の素晴らしい「車シーン」は今回も健在。何となく車の空気を重くしないようにふわっとしたトークからプライベートな話に入っていく自然さ。
自分は『誰の視点に立つかによって見方が変わるので絶対悪は存在しない』と解釈した。
音楽があまり好みじゃなくて、ぶつ切り演出もくどいなと思っちゃったところはある。前半の内容が必要なのは承知の上で、説明会までのシーンが長いなというのもある。
裸の王様
どんな話
ドライブマイカーの様な心地良さと偶然と想像の様な企み
2024年劇場鑑賞32本目 佳作 59点
濱口竜介監督の昨今の躍進から、注目せざるおえない作品
んんん、当方2018年くらいから意識して劇場に足を運んで、レビューを残し映画文化に触れて目も肥えてきた方だと自負していましたが、その日常が7年目になっても今作の様な奥ゆかしい味わいのある作風に理解が追いつかない作品との出会いが時折あり、ドライブマイカーなんかは玄人に比べれば半分も楽しめていないと思うけど、それでもその年の年間10位くらいに位置付ける程には楽しめた記憶で、反対に偶然と想像は年間ワーストクラスと堪能できるか否かがまだ定まりきっていない感覚ですが、今作はどちらかというと後者よりの味わいでした
タイトルや物語として伝えたいことというのは、要は侵略や継続を望む多様な人間もそこに本来住んでいた動物や木々などの自然含め、誰かの正義は誰かにとっての悪なのかもしれないけど、共通として残る残したいのは温かさであり愛なんだよね、ってことなんだと思う、抽象的な表現ですが
主人公が確か技術さんかなんかなんでしたよね、演技の力の抜け具合やハツラツとしていない発声、よそ者であったり達観している様は、会議の場でも客観的な立場からの物言いであったり、淡々と営みに励んでいるのが、妙な怖さにも見えた
確か東京から来た男女の一方の彼の簡単なやつっぷりがまさしく滑稽で、仕事しかりいい年して自分を貫く軸の無さが伺える
配信くんのかな、ドライブマイカーは結構時間かかったし、上映館も都内渋谷下北沢のみと渋っていたため観れてない人も多いだろうから、また理解を深めたいですね
わかる人にしかわからない映画
人間はもろく弱く愛おしい。くだらないことだらけで何も爪痕残していない人生だとしても魂はみんな懸命に生きている。
映画に理屈を求める人にはたぶん向いてない映画。
高橋のあのラストシーンをつくった監督に脱帽。傷ついた鹿のように思えたのは私だけだろうか。あのシーンだけでももう一度観たい。
後で色々思い出す映画
最初は森の木の光景が延々続くが、途中から濱口監督の面白い会話劇となり、劇場内でも笑いが起こっていた。個人的にはコンサルとの会話がおかしかった。ラストシーンが衝撃的であとで色々思い出している。悪は存在しないというタイトルも効いている。
悪は存在しないが
狂気は人間にはいつでもどこでも存在する。主人公の最後の行動は普通ではない。どう考えても狂っているとしか思えなかった。悪は存在しないけど、善も存在しない。
鹿に襲われそうな子供を助けようとした人間を、おそらく殺した。殺された(ように見える)人間は生き返ったように立ち上がったが、また倒れたのが、不気味だ。殺した方の男に無表情に抱えられた子供もおそらく死んだだろうし、生きていたとしても、幸せな暮らしが待っているとは考えられない。殺人を犯したように見える主人公は何を考えているかよくわからない人間として描かれていて、子供を迎えに行く時間も忘れる。いつも子供を危険な目に合わせても、本気で反省していない。自然が好きなのかどうかもよくわからない。グランピングの話を持ちかけらたせいでそのようになったようにも解釈できるが、そうではないと思う。というのは、グランピング説明会の地元住民もみんな変だ。住民の意識自体が変。自分たちは本来の地元民ではないと言いながら、地元の利益だけを主張する。
一番変なのは自治会長?のじいさん。上(自分たち)がしっかりしないと下(下流の大多数の住民)が困る、と言い出す。自分たちは上だと思ってる。地元住民はその異常さに気づかない。上が下をグランピングで一時的に受け入れればいいだけの話なのに、排除する。
主人公は何が真実か、何が現実か、探し求めているのか、さまよっているのか、よくわからないが、正気と狂気との境界線をうろついている。グランピングのことを気にしているようにみえて、一心不乱に描いている絵はグランピングの説明をする男女。子供の相手もせずに、男女の無表情な姿の絵を鉛筆で描く表情には狂気を感じた。一生懸命にグランピング問題を考えているのか、どうか、怪しい。木を切り倒して、薪をくべる自分の生活を悔いているのかもしれないし、悔いてもどうにもならないことに絶望を感じていたのかもしれない。答えはないだろう。人間が自然に干渉せずに生きることは不可能だ。どこかで、人類は狂ったのである。
前作では、人類の中でのコミュニケーションの問題を多言語を扱って映画にした。今回はコミュニケーションの問題を人類と自然との関係に広げようとしたのだろう。しかし、人類内の問題の延長で自然との問題を解決できるはずがない。その結論を提示した映画だ。
「ドライブ・マイ・カー」でも、自分の写真を撮った人間にひどい暴力を振るった(と推測できるシーンがある)男の表情が狂気をはらんでいるように描かれるシーンが印象的だったのを思い出した。このような狂気をはらんだ人間の衝動に動物(自然)とは違う人間の本質を見ているように思う。本作のラストもその映像の展開に息をのむ。
映画は音楽と騒音が効果的に使われていたり、映像の焦点が定まらずにカメラが回っていたりして、緊張感を切らさずに見ることができた。前作と同じく、不気味さというか不安定さが映画全体に持続するので、時間を忘れて映像を凝視し続けられる。映像が切り替わる直前に次のシーンの音がかぶるのは、構成上必要なのかどうかよくわからなかったが、少し気になった。「ドライブ・マイ・カー」と同じく、車の運転シーンが多いが、後方や側方の場面が多い。車が見られているような感じで、観客が見られているような感じになる。これも不気味な感じだった。
比較する対象がない。映画史に刻まれる傑作だと思う。
他者を理解すると言う事。表象だけの理解では、物事の本質に触れる事は...
悪とは?を本質的に問う映画
長野県水挽町の住人と東京の芸能事務所によるグランピング建設計画を機にコンフリクトが起きていく
のが話の軸です。
冒頭の長い森の風景・圧巻の自然を美しい映像で見せることで、鑑賞者へ本作の世界観をインプット
しようという試みであろうと感じました。そのくらい長い。長いと感じるくらいの長さです。
そこから主人公 巧と住人たちとのコミュニケーションから、巧と住人の関係性などがわかるように
描かれていきます。
そうすることで、まずは巧及び住人たちへ鑑賞者は感情移入していくこととなります。
そんな中でも、巧の娘である花が纏う不穏な雰囲気は、割と冒頭から気になるところではありました。
グランピング計画の住人への説明から、ますます住人への感情移入が深まるわけですが、
芸能事務所の黛が真摯な対応をすることに好感を覚えたと思えば、
住人説明会で苦労していた高橋と黛が、実は東京では、社長&クソみたいなコンサルにも辟易している
ことがわかり、ここで高橋&黛にも感情移入していくこととなります。
そうすることで、“悪”とは、その人の立場によって、また、観る人がどの視点で観るかで変わり、
また、絶対悪は存在しないのでは?という気づきを得ることになり、
なるほど、タイトルの『悪は存在しない』とは、言い得て妙だなと思いました。
本作最大の事件、花が行方不明になってからの展開がまた面白いと言いますか、読めない展開になるのですが、
花と鹿🦌が対峙している場面(割りかし鹿の顔のドアップが長いです)から、
巧が高橋へスリーパーホールド!!
えっ!?って感じです。何が起きているかわからないくらい動揺しましたが、
次の場面で花が倒れていて、鹿はいない。なるほど、花が倒れているところを巧は高橋に見せたくなかったんだろうと思いました。
一瞬、高橋は死んだ!?と思いましたが、起き上がっていたので生きていますね。気絶していただけということがわかります。
一方、花は死んでいるかもしれないし、生きているかもしれない。
巧が花の鼻に手を当てて、呼吸をしているかどうかを確認するやいなや、すぐに抱きかかえて歩き出すことから、
私は、花は生きているんじゃないかと捉えました。
このラスト以前に、巧は高橋&黛に対して車のなかで「人間を襲うのは、手負いの鹿ならあり得るかも」的な話をしているので、
花は鹿に襲われたであろうことは想像に難くありません(鹿の顔のドアップがその示唆かと)。
とどのつまり、動物も含めて皆生きることに必死であり、誰も悪いことをしようと思っているわけではないんですよね。
だから「悪は存在しない」というタイトルなんだろうし、ただ、答えはひとつではないと思うので
本作を観た人が、この映画を通じて色々な事に思いを馳せてほしいというのが、濱口監督からのメッセージなのだろうと解釈しました。
実に深い作品です。時間が許せばもう一度鑑賞し、理解を深めたいと思いました。
オチが分からなーい。
巧と花は鹿なんかな?野生の鹿?
それとも花が怪我した鹿に襲われたってだけでええのかな?
花が行方不明になって、近所の人たち総出で探して、夜になったまではわかった。
で、高橋と巧が平原?原っぱ?に出た時には、なんか明るくなってたから夜通し探してたんかな?
で、花見つかって、花の近くに怪我した鹿がいて、怪我した鹿は人間襲うかもというフリが前に提示されてて、なのに花は帽子とって怪我した鹿に近づこうとする。
それを止めようと走り出した高橋を巧が絞める。あれは本気で殺すつもりのやつ?よく分からんけど高橋は白い泡?吹いて気を失う。
で、鹿がもういないけど巧が花に近寄ると、花は鼻血出して気を失ってて、巧は花を抱き抱えて原っぱを去る。
取り残された高橋もフラフラと立ち上がるけど、再度倒れる…これは?死んだ?
この後は誰かの走る息と森の木々の映像でおしまいとなる。
オチに来るまでは特に謎もなく、ふんふんと進んできたのだけど、このオチをどう解釈すれば?となりました。
面白かったんだけどもね。
タイトルの意味は、悪(だけの存在)は存在しないってことかなぁって思った。完全な善も、完全な悪もないという意味かなぁと。
関西では5/3は公開初日で混んでた。多分満席。でも一番大きいスクリーンじゃなかったし、1日2回公開。まぁ、監督の名前以外で観にくる動機の薄い作品だもんね。
そして、映画には全く関係ないけども。
多分隣の人が、うっすらドブ臭い・うんこ臭い口臭・体臭の人で、このうっすら臭いの、昔の恋人の口臭と同じで、彼のことが頭に浮かんで仕方なかった。
においの記憶、強いわぁ。口が近すぎる訳でもないのに薄いけどちゃんと香るあのにおい。鼻が全然バカにならず、ずっと香り続けるから途中からハンカチて鼻を覆うしかなかった…あーなつかしくさかった…
悪は存在しなくても、衝突も罪も存在する世界
冒頭から映像と音楽を贅沢に味わい、自然の恩恵と不穏さにゆっくり浸る。
ストーリーとしては八ヶ岳でのグランピング施設のための説明会、それに携わる二人の心情が語られ、無機質な悪でもなくどこにでもいる自然体な存在だなと感じる。
やはりこの物語はまさしく「悪は存在しない」なのだと思う。手負いの鹿が稀に見せる凶暴性、嫌悪感や怒りはあっても普段は抑え振るわない暴力の存在。それは悪とは言い難いはず。仕事で担当だからと結果的に水を汚してしまう人も、手負いだから興奮して人を襲う鹿も、悪ではない。ということは、なされた罪の多くは悪の問題ではなくて。
自然体な物語だけど、ラストの展開はまさに手負いの鹿の豹変のような、起きないはずのことが起きたと感じさせられた。ただ、ここの解釈がここまでブレるのは想定内なのだろうか。
私としてはどちらとも解釈できるような曖昧さとか、そこをはっきりさせることは重要じゃない描き方というのは、基本的に嫌いじゃないほうなのだけど、この作品については、ラストの展開とその語られなさはあまり好みじゃなかった。映画は答えを提示するものであるとかその答えが関心事だとは思っているわけではないけど、あまりに解釈のブレを招いてしまう突き放し方で。答えを求めるのは貧しい考え方だという指摘は、監督の知性からすれば酷くブレる解釈をする層はおよびじゃないということなのかなと思うけど、うーん…
悪は存在しなくても、相互理解は容易じゃない。
自分の解釈としては、たくみのあの行動は悪がゆえではないよ、でも罪ではあるねってことかと。悪じゃなくても罪はおかされる。手負いの鹿の暴走のように、声を荒げることのないたくみが暴走をしてしまう。なぜ暴走したのかは、娘を失ったことを東京から来た薄っぺらい男に結びつけたか、それともただやり場のない怒りが彼にむいたか、その原因はたくみにもわからないかもしれない。ただ、たくみはずっと怒りをためていたはず。黛と対比するかのように、高橋は、無責任で無神経でしかも結果的に罪を犯すであろう人間として描かれていたし。
どこかで響いた銃声によって手負いとされた鹿がはなを傷つけ、はなは死に、そして遠目でもそうと確信したたくみが暴走をする。
ラストシーンは、はなを抱えたたくみなのかな、息遣いのみ聞こえる。映画冒頭の雄大さと不穏さのコラボがここでも。無力で不穏でちっぽけな、それでいて必死な息遣いで幕が閉じられる。
うーん。
全252件中、181~200件目を表示