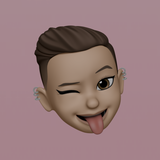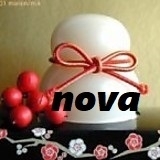月のレビュー・感想・評価
全287件中、61~80件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
UNEXTで鑑賞🎥
すごく胸が痛くなる映画でした。
実話の事件を元にした映画で
だからといって殺していいわけでは
ないけどなあ。
終始暗かったです🥲
問題の外からみているものをみていた
エピソードが多すぎる。本題を誤魔化しているようにしかみえない。施設の職員や利用者のエピソードがあってほしかった。障害者の方を出演させたからOKじゃない。そもそも職員が近寄ったことがない部屋の利用者さんってなんなの?放置とかないでしよ??初めて行きますって何??ファンタジーなの?
小説を書いている人の話とかはこの映画では本当にどうでもいい。
だいたい主要人物の周りの人が嫌な人すぎない?同じ職場の人とか、あんな人いるの?? リアリティがなさすぎる。映画ってそういうもん?映画によってはアリだけど、この場合はなしだと思います。なんであんな嫌な人なのかの理由づけがほしい。
こんな中途半端につくらないでほしかった。
とても腹が立ちました。
自分が被害者になるということを考えて観てほしい映画
私は学生の時からボランティアで重度障がい者の方の介護をしており、
毎日一緒に過ごしただけでなく、学校から帰ってからも近所の重度障がい者の方のお世話をしたり、
大人になってからも老人ホームや病院の介護の仕事に関わったこともあります。
要介護になると喋れなく手足口と全身硬直の利用者さんで食事排泄諸々全て手伝わなければいけません。
水分は全てとろみをつけておかずは全て細かく刻んで火傷をしないようにフーフーして、ゆっくりあげます。
力が強い方だと何度も殴られたり噛まれたりしましたが、
なりたくて障がいになったのでは無いし、
私はやり返したりしませんでした。
なのでその人達を殴ったりする人がいるというのを見た事が無かったので、そういう人もいるのだとびっくりしました。
障害者という属性を理由にした殺人は、憎悪犯罪です。
そういう属性を持っている人は誰でも対象にするという酷い犯罪であり、
殺人はいけないけど、考え方は分からなくもない」とネット上で平気で言う人々もいたり、障害者団体などが「誰の命も大切だ」と意見を公表すると冷笑する人たちがいたり、植松被告に同調するような人が見られるのは
理由があれば人を殺して良いと考えている人が多いということであり、その事実が一番恐ろしいです。
植松死刑囚は
世の中に役に立たないと思った人を狙った。
つまり、今障害を持つ人だけじゃなくて、
私たちがこれから交通事故に遭って動けなくなったり、
年を取って寝たきりになったりしたら
全員殺害すべきだという主張です。
限られた人を狙ったものじゃなくて、
「誰でも役に立たなくなったら殺害すべきだ」というのが植松死刑囚の考え方なのです。
「考え方は分かる」と言う人は、自分が被害者になるということを考えていないから、言えるのだと思うのです。
神奈川県相模原市の障害者施設に元職員の男が侵入して45人を殺傷した「津久井やまゆり園事件」
を元にした映画
重くてズーン 考え込んでしまう映画
何の予備知識もなく見たのですが、かなり重い作品でした。
それだけなく、観る者を突き詰めるような「問いかけ」があり、とても苦しかったです。
映画というのは、万人とは言えなくとも、皆に「感動」、「衝撃」、「感慨」、「伝達」等を投げかけるものが多いのですが、この作品は、そんな紋切り型が決まったものではありませんでした。ラストになって、夫婦の再出発という予感が多少見えても、「救い」が見えてきたわけではありません。
2016年に起きた相模原殺傷事件。
津久井やまゆり園事件がモチーフになっていますが、映画はあくまでもフィクションです。
しかし、監督が投げかけてくるものが苦い現実というか、誰でも心に秘めている「見て見ぬふり」「他人事」「差別感」、これをどう説明したらいいのかと、映画を観たあと、考え込んでしまいました。
さと君が洋子(宮沢りえ)にいいます。
「僕は洋子さんと同じ考えです」
洋子が妊娠して、「子供に異常が見つかった場合、中絶を」と悩んでいるのだから、「無駄なものは排除しないといけない」という考えは洋子と同じというのだ。
かなり偏った言い分でもあると捉えられますが、もしも、私自身が同じ立場にあってそんな言葉を投げかけられたら、やはり考え込んでしまいますし、どんな言葉で返事をすればよいのか。
映画を観る数ヶ月前に、たまたま、知人と「障害者に対する強制不妊手術」について、少し語り合ったことがあります。そのとき、少し調べたのですが、1948年から1996年までは、「旧優生保護法」というものが存在しました。つまり、「不良な子孫の出生を防止する」ために、精神障害や知的障害などを理由に本人の同意なく強制的に不妊手術を行うことを国が認めていました。
そのことの賛否についてはここでは触れませんが、戦前からこうした「産児制限運動」を主導していた知識人の一人に「太田典礼」という医者がおりました。その人の主張とさと君の主張が似通っているのにはびっくりしました。(太田典礼は『安楽死のすすめ』という本を出し、避妊具リングを開発した人です)
太田典礼は「もはや社会的に活動もできず、何の役にも立たなくなって生きているのは、社会的罪悪であり、その報いが、孤独である」と言い切っていますし、また、「植物人間は、人格のある人間だとは思ってません。無用の者は社会から消えるべきなんだ。社会の幸福、文明の進歩のために努力している人と、発展に貢献できる能力を持った人だけが優先性を持っているのであって、重症障害者やコウコツの老人から〈われわれを大事にしろ〉などと言われては、たまったものではない」とも言っているのです。
さと君の「心がないなら人間ではない」という主張は、意味はわかっても、とうてい理解納得できるものではありませんが、太田典礼という医者であれ、さと君であれ、今後、同じようなことを主張する人が出てくる可能性は否定できません。
命の尊厳、生命の尊さって、一体、何だろう。
ただのむごたらしい殺傷事件を再現しただけの映画ではないことは間違いないですが、美辞麗句と言われようと、「生きているだけで愛」も否定したくない自分がいます。
違う意味で社会風刺映画
希望と絶望
十人十色を感じすぎる映画です。
捉え方考え方受け取り方って本当に人と人は違うなと。
苦しいお話ですが現実にたくさんある話なのだろうなと思ってしまいます。
正義ってなんでしょうね。正解ってなんですかね。
あなたも俺なのでは?その問いに、私はすぐにNoが言えない。
苦しい映画だった。あなたはほんとうは重度の障害者にいなくなって欲しいと思っているのではないか?問いは、質問者と回答者の立場を何度も逆転させながら、映画を観る私に、繰り返し突きつけられる。多くの人が答えに詰まる瞬間を味わうはずだ。
題材となった2016年7月の「相模原障害者施設殺傷事件」を調べてみる。死刑囚となった実在の人物と、劇中で事件を引き起こす人物と、否応なく巻き込まれる登場人物たちと、それを安全な場所から観ている私たちとの間を、問いが串刺しにする。あなたはどうなんだ?ほんとうか?嘘をつかずに答えてくれないか?あなたも俺なのでは?
石井裕也監督が宮沢りえに与えた原作にはない役割が、磯村勇斗の「さとくん」と二階堂ふみの「ようこ」が繰り返し突きつける「問い」を、さらにリアルで説得力あるものにしていた。
映画を見たあとに、Wikipediaで実際の事件直後にどんな議論が巻き起こったのかを調べると、多くの人がその問いにまともに答えられなかったことがよく分かる。
苦しい映画だったが、かすかに希望も読み取れた。それが救いだった。
伝える本質
善と悪。こういう作品もあって良い。
モチーフにされた事件を知った時、私の第一声は「ははっ、ぶっ飛んだやつがいるなぁ!」だった。詳細を知った後も「へぇー」って感じだった。何ならまだ若い犯人の人生が終了してしてしまった事に同情さえした。
自分はさとくん側の思考だった。だから彼の言わんとする事が理解できるし共感もできた。
でも実際それを口に出しちゃいけない・行動を起しちゃいけないよね、という正常さもある。そこが彼との違い。でも、もしゲームの世界なら罪にならないから同じ事をしていると思う。
少なくとも私は大切な人生を、彼のようにこんな事で棒に振るような事はしない。知らん顔してスルーができる。
遺族や関係者の気持ちも分からない。なぜなら私には遠い世界の話だから。もちろんある程度想像はできるが、無理に共感する必要性も感じない。そこはしたい人だけがすればいい。
ま、その辺は各々考え方が違うから何でも良いですけどね。考え方は人それぞれです。
監督さんも勇気を出したな、と思った。内容が内容なだけに相当な覚悟を要したと思う。オファーを受けた演者の方にも称賛を送りたい。
「問題作だ!」と批判する事は簡単。内容からして世間の大半がそう思うだろう。
なら観るなw
話せない(心のない?)障がい者の生命は、奪ってもいいのか?
そんな心の塞がる問いかけを投げかける映画でした。
話せない、心がないのは人間ではないから、殺してもいい。
それがさとくん(磯村勇斗)の考えです。
2016年7月26日未明、相模原市の知的障害者施設
「やまゆり園」で元職員・Uにより19人が殺され、
20人が重傷を負った。
犯人のUが国家に与えた損害そして社会的悪影響は
計り知れません。
ある時期、半グレにも属したUは、大麻を吸い犯行に及んでいる。
背中には一面の刺青、
有名になりたい、世間を騒がせたい、注目を浴びたい、
自分の偏見(障がい者は無益な存在だから排除していい)
を社会に訴えたい?
Uの事件は国に数億イヤ数十億の税金を
使わせることになっている。
その事をUは一度でも考えた事があるだろうか?
心底、浅はかな思考力である。
辺見庸の小説「月」には宮沢りえ演じる元有名作家の
堂島洋子は存在せず、石井裕也監督の生み出した架空の人物です。
だから夫(オダギリジョー)並びに、重い障がいを持ち産まれて
3歳で亡くなった長男の事も石井監督が付け足した物語です。
また宮沢りえは堂島洋子と施設で暮らすキーちゃんの二役を
演じている。
キーちゃんは洋子と生年月日が同じである。
施設に入った当初は目も見えたし、歩くことも可能だった。
しかし長年の下肢拘束と、暗闇の方が“おとなしい“との理由で、
目が衰えて見えなくなり、足も衰えて歩けなくなったと言う。
実に痛ましい。
堂島洋子と夫の昌平(オダギリジョー)は重度の障がいを持ち産まれた
息子を3歳で亡くしており、心に深い傷を負っている。
そして予期せず妊娠をして、もしもまた障がいのある子供が
産まれたら・・・と、洋子は出産を躊躇っている。
重度知的障害者施設に勤めた洋子は、施設内での職員の虐待を
目撃してしまう。
ここでも拘禁をしなければ自傷行為をしたり、暴れたりするから、
との理由でさまざまな虐待的行為が行われている。
施設で働くもう一人の陽子(二階堂ふみ)は言う。
重い障がい者は社会から隠されている。
隠蔽されている。
石井裕也監督は、事前に多くの施設を見学して、
実際に見聞きしたことしか映像にしていない・・・
そう話しておられます。
私は、やはり、見ないふりをしている一人だと思う。
実の子供、実の親でなければ、向き合わない現実だと思う。
そして施設は家族には手に負えない、世話のできない人々の
受け皿になっているのが現実なのだとも思う。
そして出産前診断で障がいの可能性のある胎児を選別にかける、
もう妊娠が心から喜べる事柄では無いのは現実なのだ。
重い問いかけの問題作でした。
原作者の辺見庸さんも重病に伏せられているご様子で、
コメントを聞けないのも悲しいし、
ご本人も残念な事だと思います。
社会に問いかけた意義は大きい。
彼が切り取って残した「あの部分」は、彼の心中そのものなのか。
どうして…、あるいは、どんなことがきっかけで彼が介護士という仕事を(結果として)選び取ることになったのかは、本作では明確には描かれていなかったと思いますけれども。
いずれにしても、最初から志して就いた職ではなかったことは、間違いがなかろうかと思います。
そうして、本当の自分の気持ち押し殺して就職はしたものの、さと君がもともと持っていた優生思想的な側面が前面に出てしまった結果ではなかったのかと思うのです。評論子は。彼の…あの恐るべき所為は。
自分なりに苦心してきた取組みを、介護士仲間からあっさりと否定されてしまった(程度のこと)が直接のきっかけで、恐るべき所為に出た彼の内実は、そう考えなければ理解できないのではないでしょうか。
そして、そう理解しなければ、事前に「あなたには心はありますか」と確認するのだから、自分の所為は無差別殺戮でも、大量虐殺ではないなどと公言はできないだろうと思うからです。
つまり、彼の「独自の取組み」は、彼がこの仕事を続けていくための、いわば「安全弁」としての役割を果たして来ていたところ、同僚介護士の心ない言動によって、これが、すっかり外されてしまった―。
ただ、どうしても自分の「独自の取組み」の全部を否定し去ることはできなかったので、その「独自の取組み」のとある部分だけを切り取って残し、それが本作の題名としてら彼の心中を象徴する―。
評論子には、そう思えてなりません。
同じく「照らし出すもの」ではあっても、物事の表裏・陰陽・霽(は)れと褻(け)に例えて言えば、さと君の他人から見える外面という「表側・陽・霽れ」を象徴する太陽に対し、月は、さと君の心の内面という「裏側・陰・褻」を象徴するものとして。
その、さと君の象徴が、彼の所為によって血潮に塗(まみれ)るシーンは、本当に耐え難いほど強烈なものだったと思います。
背景には介護産業の、過重労働や慢性的な人手不足もあるでしょうし、世間一般の「障がいのある方々を見る目」というものも、根深く関わっているように、評論子には思われます。
本作は、評論子が入っている映画サークルが2022年に札幌地区で公開されたものの中からベストテン作品として選んだものだったので、鑑賞することにしたものでした。
その期待に違(たが)うことのない重厚な一本として、佳作であったことは疑いがないと思います。
(追記)
評論子が生まれた頃は、田舎では、まだまだ自宅での出産が珍しくはなかったようで。
お産婆さん(今ふうに言えば「助産師」?)のサポートを受けながらということで。
今は地方でも病院での出産が当たり前の時代でしょうし、エコー始め検診機器も充実しているので「子供の障害の有無は、産まれてみなければわからない」と言った時代ではなくなっているので、出産の安全性は格段に高くなっているはずですけれども。
それでもお産に伴う事故は皆無ではないでしょうし、後天的な事故・病気で、思わぬ後遺障害を負ってしまうこともあり得ない話ではないはずです。
そういう意味では、生きていく上で障がいを負ってしまうことは、「神の御業」にも匹敵するような、本当はいつ、誰に起きても不思議でないことなのかも知れません。
日本の社会は、徳川幕府の長い長い鎖国政策から目覚め、(経済的に)欧米列強に「追いつき、追い越す」ことだけを考え、また敗戦というダメージからの戦後復興、そして高度経済成長と、経済の階段を駆け上ってきました。
そして、その駆け上がりのスピードが、世界のどの国も経験したことのないようなものであった故に、その過程で「積み落としてきたもの」も、少なくはないようです。
その一つが、人格的にはまったく対等であるはずなのに、労働面(経済面)では社会に対する貢献度が高くはなかったが故に障がいのある方々を、ややもすれば対等に見ない風潮も否定できないことと思います。
経済の成長だけを過大に重要視してきたこれまでについて、見直すべきことの一つであると思うのは、独り評論子だけではないこととも思います。
(追記)
いかに「明るい」とは言え、やはり月明かりは月明かり。
太陽の明るさと比べれば、そもそも比較になりません。
本作の題名は、やっぱり、これでなければならなかったのだろうと思います。
本作の全体的な画面の「暗さ」も、月明かりを象徴するものと受け止めました。評論子は。
「見えない」と「見ない」は違う!
公開から随分経って、やっと観れた本作。
相模原障害者施設での大量殺人事件を下地にした話なので
観ていて心が苦しくなりそうですが
そこは映画なので、主演の宮沢りえと
オダギリジョーが演じる夫婦の
ささやかな幸せへ焔を消さない様に無くさない様に
丁寧に丁寧に優しさのステップを
重ねて行くシーンがとても心に残りました。
で、なんと言っても、磯村勇斗!!
優しい青年が少しづつダークサイドに落ちてゆく〜〜
こ〜〜〜わ!!
多分、配信とかで観ると逃げ出したくなると思います。
こういう映画こそ、ぜひ、映画館で!!
で、月に8回ほど
映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
映画的に、この障害者施設が、
ヘビが出る様な深い森の中の安物のオカルト廃病院とか
捕虜収容所跡みたいに描かれていることが
ちょっとやりすぎ感があった。
それは、世間の人々つまり「私たち」が目を向けない事、
「私たち」に見せない様にしている事の象徴だとは
理解しているのですが、とても怖い、とても悪い場所
という感じを強調し過ぎててちょっとなんだかな〜〜
と思いました。
事件自体が悲惨だし、実際、意思疎通ができない障害者も
「私たち」が知らないだけで実は沢山いるのかもしれない。
そういう人たちと日々接する施設の職員の人々が
「自身の心を守る為」に「障害者を人として見ない」様に
一種の「鎧」を心に付けるのかもしれない。
その実情を「見もしない私たち」が職員の人々を批判なんか出来ない。
でも、もちろん他人が勝手に殺して良いはずも無い。
そんな重い重い映画でしたが、あえて
この作品を作られた皆さんに感謝と敬意を捧げます。
こういう映画は海外でもあるでしょうか?
こういう映画に英語字幕を付けて海外で上映して
海外の反応が知りたいと思う。
とにかく暗い場面の映像が多い。
神奈川県にあった障害者施設での障害者は社会には要らないという理由から大量殺人事件を起こしたのをモチーフに描かれている。
小説家の洋子が障害者施設に就職して、その施設の現実を目の当たりにする。
部屋には鍵をかけ、暴力的なことも日常茶飯事、不都合なことは見て見ぬふり、衛生的にもかなり厳しい。
陽子の言葉に「洋子の東北の震災をテーマにした小説には現場のおいや音が感じられない」みたいなことがあったが、まさに外向きには障害者がその人らしく・・・みたいなことを謳い文句にしているものの、現実との乖離がある。
洋子は3歳で亡くなった、寝たきりでしゃべることのできない男の子がいた。その子と目の前の障害者の扱いにだんだん不信感を持つようになる。わが子がそんな扱いをされたらどう思うんだろう、と。
でも、そこしか行くところがない、という現実もあり、不都合なことは目をつぶらないといけないことも出てくる。
そして、スタッフもそんな環境で働いていると、障害者への憎悪や偏見、メンタルの崩壊も生まれてくる。そんなメンタルの崩壊が事件につながってしまったのがこの作品のテーマになっている。
事件そのものよりも、そこに至る雪崩のようにメンタルが崩壊し、一過性の思いではない事件への決意の狂気が静かに描かれていく。
回転ずしのような食事はよく幸せの象徴で描かれることが多いが、食べている時に事件が中継されているのは、事件もメンタル崩壊も幸せもすべて紙一重で、きっかけさえあれば誰でもそっち側になってしまうということである。
2時間半ほどだが、あっという間に感じた。
障害を持つ子供さんの家族は…
コミュニケーションできないお子さんを持つ両親だからこそ、頑張れる 日々仕事して施設代など稼いで生きていく…障害者家族は彼 彼女がいるから生きていける…
だから、気づける事だってある。
五体満足で、何処にでも存在する家族より、大事なもの…大切な事が見え気づけるのなら、蓋をしたがり、目を背ける人こそ、人間ではないなと思う。
やりすぎ感は否めない
石井監督の映画は初めて鑑賞
まず最初に、皆さんのレビューのように整理した内容にはならない。
映画を見直さなくても、これからも似たような事件は起こるのだろうけど、
そんな時に時々思い出しては書き加えていきたいと感じています。
始まりの震災イメージのショットから暗闇に懐中電灯の光が当たっているところしか
見えない状況が続く。ここにも意味があるのだろうなと思いながら観進めていく。
観終わって時間が経つが、改めて思いなおしても、問われているのはそこで、
人は見える世界しか理解できないということ
映画の感想としては、こんなに暗い病院ってあるの?
ちょっとリアリティーなくない?
こんな職場なら誰でもおかしくならない?
そこらへんはちょっとやりすぎ感が否めない。
さと君が、耳の聞こえない彼女に「今から…」と宣言するシーン、
その前に一度「本当に聞こえないの?」と聞くシーンがある。
さと君はどこかで彼女に止めてほしくて、奇跡でも起こって止めてくれ
と心の底では思っていたのではないかと思うのです。
汚い自分を汚くてはいけない。と思うのではなく
汚いことをありのままに受け入れる。
本当に難しいです。
ひとまず終了
考えたくないものを見せつけてくる
私が今まで観てきた映画の中で、これ程心苦しく自分自身に刃が突き付けられるような映画はありませんでした。
自身の中の差別意識や見ない、考えないようにしてくる部分を容赦なく見せつけてきます。施設の中の残酷な現実と一見平和な、しかし各々の登場人物たちの歪みや苦しみが察せられる生活のシーンの対比が生々しいです。
障がい者とは何か?を考え、現実に起こってしまったラストのとある犯人の行動。視聴者にもあなたはどうするのか?を問いかけてきます。
全287件中、61~80件目を表示