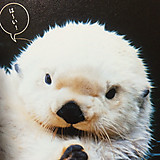哀れなるものたちのレビュー・感想・評価
全673件中、261~280件目を表示
凄いものを見てしまった…
女性の成長譚
新宿ピカデリーにて鑑賞🎥
最初は「エマ・ストーンは、いったい何者?」と思ってしまう奇怪な行動が多かったが、彼女が存在している経緯を知ると「なるほど!」と思う。
そして、彼女が様々な経験を通じて「大人の女性」になっていく成長譚が描かれた映画だった。
しかし、成長する姿を描くにしても、やはりエロすぎる😄w
また、彼女の存在経緯の奇抜な設定は、あの手塚治虫の傑作「ブラックジャック」にも無い。「よく考えたものだ…」と感心してしまった。
更に、船の造形や(赤ん坊が多く亡くなる村へ通じるはずの階段が壊れた)城砦の造形も見事であった✨
中世ものにとどまらず、未来的描写を上手く融合させた監督の手腕はアッパレ‼️
グロい場面がそんなに無かったのは、個人的に良かった🤣笑
これは、なかなか素晴らしいダークファンタジーではなかろうか。
鑑賞後に気分が楽しくなる種類のものではないが、良いものを観た(^-^)
<映倫No.49713>
驚異のランティモス監督。圧倒的な芸術作品。
まず、これは作品自体の感想ではないが、
『籠の中の乙女』(※)から十年余りで、このレベルの総合芸術を作り上げたランティモス監督の手腕に驚愕して、鑑賞後はしばらく放心した。監督の長編作品はほぼ全て見てきたが、これまでの制作ノウハウを確実かつすごいスピードで吸収し、それを壮大な掛け算にしてアウトプットしていると感じた。50年以上やり続けてもこの境地に辿り着ける芸術家は ー特に、大勢のアーティストと協業する芸術である映画の監督はー 多くないのではないか。本当に同じホモサピエンス種なのかと疑うほどの衝撃だった。
※ 単に、低予算作品、という意味で。規模こそ小さいが、テーマ表現やショット演出は初期から群を抜いていた。
本作のテーマやストーリー構成については、
監督が脚本も書いて思うがままに演出している過去作と比べてしまうと、物語の力強さ&アークの丁寧さに欠ける印象。原作の脚色への苦心が感じ取れるというか。エピローグも少し乱暴に感じた。
それで-0.5だけしてしまったが、それも畏れ多いほどにあまりに美しい映像体験で、神さまの創作物かのような圧倒的な芸術作品だと感じた。
なんか
頑張れ、頑張れ!
字だけのエンドクレジットになるな、なるな・・やったぁ!!これだけで☆一つ。ベラが洗練されてくるとちょっと魅力が無くなる、将軍の屋敷での下りは大分退屈。でも将軍の末路は良かった。
エマ・ストーンは確かに達者でしたが、ウィレムデフォーの方に強く揺さぶられました。
大人向けファンタジー
見たことのないプロットで人の進化を辿る。凄まじい!新しい!
あらすじ読んだときはさっぱり意味がわからなかった。口コミからも見る前は異様に脱ぐのね、位しか分からず、沢山賞をとっていることと、エマストーンでなければ見たかどうか。でも久々に満席でなかなか取れない映画でもあった。
結果、凄まじかった。見るべきだった。赤裸々な娼婦のセックスシーンは若い人や男性には刺激が強いかもしれないけど、感情がないからか流せるくらいに全てのシーンが美しい。たまに脳内ファンタジーが再現されているのか?現実味のないロンドン、リスボン、船、パリのシーンや入れ替わりのタイトルページも画集のようで素敵だった。覗き穴風の視点やモノクロとの対比などの演出も多用されていて美しい。
母であり、子でもある、言わば人造人間、ベラバクスター。大人の体に胎児の脳、そこから見せる、人としての急激な進化。
ただ親の真似をしてメスを振り回し物を壊す
なぜなぜ期に入り好奇心が止まらなくなる
初めての反抗で親に逆らう
外の世界に触れ人との交わりを知る
社会的通念や、人への礼儀や配慮を知る
友人との出会いと学びで世界が広がる
世の中が正しいだけではなく自分が無力であることを知る
お金の稼ぎ方を知る
人との相性を知る
自分のしたいことを見つける
親の深い愛と、元夫の歪んだ愛を知る
そして体だけ成熟してるから早くに性の快楽も知る(脳的には幼稚園児くらいの時?)
進化と同時にベラの言動もどんどん哲学的に、そして学術的になってきて正直難しい。けど展開も引き込まれるし、ベラが最後バッドエンドなのかグッドエンドなのかも想像つかないまま進行して飽きるタイミングがなかった。
子どもの素直な心で大人の世界を生きるということ、そしてこういう過程で人の脳は進化する、ということをスピーディーにみせてくれる。美しさもありながら、自分に執着せず真っ直ぐに生きていくベラに虜になっていくダンカンや周りの人々も、今ないものへの憧れか。
最後、博士が死んだ時その脳を元夫に移植するのかなと思ったけどもっと牧歌的??だった。
奇妙な前提で成り立つほのぼのとした世界のラスト、私は好きでした。
エマストーン、マークラファロイ、ウィリアムデフォーが出ていると言う...
生きている間、忘れたくない映画
鑑賞後すぐに現実には戻れなかった。
この世界は神様が創った哀れなるものたちなのだろうか。特に人間を丸裸にしたような作品だと思った。
生死貧富自由拘束欲望などが詰め込まれている。
映像も内容も宗教画みたいだな、と思った。
映像は白黒から色が入ってさらに見応えがあった。
音楽も魚眼レンズみたいな映像も面白い。
旅する街や船は観ていたわくわくした。
音楽に合わせて踊るベラは魅力的だった。
船上から見える空の色がありえないようなあり得るような色で不気味だけど綺麗だった。
本能的で幼かったベラも冒険をして発達していく。
知ることで欲しいものがわかってくる。
医者になりたいという夢ができる。
初めは倫理観が崩壊していた。
死体を刺すし、カエルは握り殺す。
残虐で、でもそれをそう思わなかった。
好奇心はいつだってある。
外の世界を知りたくて婚約者を裏切る。
お金が必要であれば娼婦になる。
かつての自分を知りたくて婚約者をまた裏切る。
裏切るなんて感覚でもないのかな。
怖いものにも怯えず向かっていく。
発達していく中でも大事な人は変わらなかった。
悪には染まらなかった。
冒険を阻止されて外に出られなかったらどうなっていたのだろう。
婚約者がひたすらにベラを愛していてよかった。
船で出会った乗客から本を読むことをしなかったらどうなっていたのだろう。
ベラの2回目の人生は幸福に向かっているようだった。
エロさとグロさはしんどい人もいると思う。
お洒落な映像をみたいだけで観ると思っているのと違ったとなるのかもしれない。
愛は
相手を殺すことも、自身を殺すこともあり得る。
キリスト教文化圏で育まれた常識や規範と言うものが、
如何に馬鹿げていて退屈なものであるかを長尺で批判
揶揄した作品だと僕は感じた。
特にそれを感じたのは、性的衝動を通じて外界と触れ
成長して行くベラ。と言う存在の提示や、彼女の元夫であった将軍が山羊へと改造され蘇生された描写などからであるが、そこまで行って、改めて鑑賞を必要とする映画があることに気づいた。
それはフランケンシュタインである。
まぁ、何故かを書く野暮は犯さないでおきたいのでここで終わるが👇
最後に記載したい内容があるのでそれだけは書き出す。
我々が生きる世界で、障碍者。と言う言葉があるが
そう呼ばれる方達は自身が障碍者であると言う自覚と
信念が有るのだろうか?寧ろ彼らから見たときは我々は障碍者ではない。と言い切れる状況であるのだろうか?
本作はそう言う当たり前の疑問を気づかせてくれる映画だと。そう評価したい◎
哀れなるものは、男も女もなく「人類」
本作について、「ベラが男たちを凌駕して強く大きくなっていく」ことや「初めはベラを征服しようとした弁護士(マーク・ラファロ)が哀れな姿になる」などの、女性が男性を超え、強くしたたかにその存在を揺るぎないものにするという、主人公や物語部分へのジェンダーの語り口でのレビューも多いな…と思いますが、私の場合は、この映画について「ジェンダー」に関する部分はほとんど引っかかるところはありませんでした。
映画の大半は「人為的に移植脳を持った、少しおかしな大人」ベラが自由闊達に生きるアドベンチャー(彼女が変化していく様も、実際にいろんな国を渡り歩いていくことも、まさにアドベンチャー)で占められ、私たち観客は見たことのない異世界に誘われ、非常にエキサイティングでダイナミックな映画体験を得られます。
しかし、終盤、本来の、今の自分になる前の自分に起きていたこと、結婚した後に夫から受けていた仕打ちを知り、死に至った理由を認識した後、ベラは、見事に発達した知能で「自分を作ったゴッドと同じこと」をやる辺りから、エキサイティングな雰囲気はなくなっていきます。
ゴッドは復讐でなく、自分のやってみたいこと=欲望を実際に持てる技術(胎児の脳を大人の女性に移植する)でやり、ベラというそれまでになかった創造物を作り、その目を見張る変化を体験する喜びを得るのですが、一方ベラは、自分を自殺に追い込んだ夫に「ヤギの脳を移植する」ことで、永遠に自分にかなわない存在まで「完全に動物への退化をさせる」という復讐を遂げます(セリフでは進化と言っていますが)。この「復讐」に少々行き過ぎ感をすでに私は感じていました。
その後のラストシーンでの、ベラとその周りで穏やかに微笑むファミリー(婚約者、自分の後に作られた脳移植人造人間の女性、パリの女郎屋で出会い同性愛に陥る黒人女性など)の姿は、なぜか全然ピースフルな雰囲気はなく、むしろ心ざわつく不穏な空気を漂わせています。
それは何故か。人間の技術力である種超越した存在となり、怖いものなしになったベラが「自分に危害を加えない、都合の良い、エゴの固まりで作られたファミリーと世界」だからなのです。
人間が作った創造物に、今度は人間がいいように利用され改変されるのです。
もう、人間は世界や地球の中心ではなく、下手すると自分たちが造った創造物に従属することになるのかもしれません。その従属する人類が『哀れなるものたち』なのです。
私は、そんな背筋が寒くなる恐ろしい世界の預言をこの映画から感じてしまいました。
こうなる前までの、ベラの壮大なアドベンチャー物語は、19世紀に起きた「産業革命」になぞらえられます。
ですが、その進歩や進化の先には、一見静かだけれど、空恐ろしい世界が待っているかもしれないのです。
今現在21世紀の先には、こんなことがもしかしたら起きるのかも知れません。
このような、これまで終わりなき進化への欲望を求め続けた「人間の思い上がりや渇望」に痛烈な皮肉を放つ、今までなかった唯一無二の「すごい作品である」ということを感じずにはいられなかったのです。
私の変な思い込みに過ぎないのかもしれませんが、この解釈について、言葉が通じればヨルゴス・ランティモス監督がどう思うのか聞いてみたいです。
自分には今イチでした
ベラの頭脳=前身だったヴィクトリアの娘と分かってからは、今イチ話に乗れなくなってしまいました。どんな事情があるにせよ、ヴィクトリアは『ベラ』を身ごもった状態で自殺したわけで。仮にその目や、耳、皮膚感覚を通じて何を知ったとしても、それって、自分を一度殺した人間の臓器にフィルターされた世界ですよねと。
私なら、自分を一度殺した人間の体に閉じ込められるなんて、それだけで発狂する気がします。そこは真実を知っても気にならんのねと思うのと同時に、最後の箱庭で暮らすベラは、怒ってくれる人がいないという意味で、相当哀れに感じました。
※最後の入れ替えの場面ですが、私は素直に死にそうなゴッドの脳をクソ旦那に入れるんだろうなと考えていました。ヤギでしたけど。
脳みそフルスワップという技術がありながら、ゴッドを簡単に見送ってよかったんかいな?
POOR THINGS
これは男性目線で鑑賞するのと女性目線で鑑賞するのとではかなり見方が変わると思う。
たしかにエロいグロいあったが重要なのはそこでは無い。
胎児の脳を移植されたベラが凄まじいスピードで様々なことを吸収し、いろんな世界を知ることで素晴らしい人間と成長していく事がすごいのだ。
胎児の脳から成長が始まり、まるで赤ん坊の状態から言葉を覚え、興味の赴くままに行動し言葉を発し、どんどん成長していく。
特にベラを創り出した科学者のバクスターの熱心な生徒で、ベラを記録するマックスと婚約するが、どうしてか心揺さぶられる弁護士ダンカンと駆け落ちする辺りからの成長がすごい。
ダンカンと駆け落ちし、それまで外の世界を知らなかったベラが、いろんな世界を知り、様々な人や様々なことに感化され急速に成長しどんどん進化していく。そして子供の脳で性を分析し、恥ずかしいものいやらしいものではなく純粋に表現していて清々しささえ感じる。そしてベラはその大切さを学び、時には生きて行くのにも必要な手段であることも学ぶ。
そしてしっかりと自分というものを確立させ、人としての自由を獲得するまでに成長する。たどたどしかった話し方や歩き方も、いつしかすっかり知性溢れた女性になり、そして温かみのある人間に成長を遂げていて素晴らしかった。それはバクスターやマックスのベラに対する愛情の深さが成すものだったのではと思えた。
タイトルなし(ネタバレ)
なんの予備知識なく見ました。
正直わかんなかったです!でも面白かったです!
赤ん坊から成長して行く過程の変化、エマストーンすごかったなぁ。
ありえない設定に対しての、独特な美術、衣装と世界観の作り込みに脱帽しました。物語の落とし所が全く見えず、最後まで楽しめましたが、SEX描写くどい。
元旦那にヤギの脳を移植してしまうことが、結局純粋に成長する事なんてできない世界の残酷さを表したように感じた。
反逆の横顔
冒頭、真っ直ぐな背中を追うように青い海から辿り着いたモノクロ世界。
ベラの成長とともにカラフルになる拘りの演出は、非現実的な雰囲気で覗きこんでいるうちに日常に帰れなくなりそうに怪しい。
ベラの奔放さはこどものわがままで終わらず、大人になる頃には何度もチャレンジする〝熱烈ジャンプ〟のとりこに。
ネーミングのあまりの明るさに笑いをこらえつつ、あくまでもあっけらかんとしたベラに何故か救われたり、憐れみに近い感情も起こしながらじわりと沁みるのは、成長過程にありがちな無知なバランス力、仕方のない滑稽さ。
大人が顔を赤らめ思いだすいつぞやの力み、本気加減。
ベラのアドレナリン大放出もピークな頃には〝搾取〟〝放漫〟〝虚しさ〟〝蔑み〟などのワードが私の頭をよぎる。
極彩色で表現されるむき出しの哀れなるモノたちの中心でベラは哀しみに触れ苦しみだす。
油性絵の具でべったべたに塗られ窒素しそうなハートでベラが旅先から届ける〝そのまますぎる〟絵葉書がちょっと面白いのだが、内容は深刻。
育ての父や婚約者の心配に拍車をかけ萎えさせ、いかにも辛そうだ。
反抗するベラはきっと邪魔者になり海に放られてしまうかも?どうする??と思いきや…目を見張る展開が来るのだ。
たゆまぬ好奇心と探究心、行動力で得た出会いと経験を栄養にして蓄えた知見が覚醒。
ベラに湧く疑問はストレートに飛び出し跳ね返るものから学び吸収する。
そうして鍛えられた判断力が迷いなき「今」からの脱出を発動。
おそらく観客の誰もが無防備すぎると思った冒険旅行。
目に見えて彼女の精神を急成長させていく過程には痛快さえ得るのだが、更にあるものを目撃する。
確かに美しいベラだが、その見かけだけの魅力ではないものが備わるにつれ周りに蔓延る者たち(異性や年齢に限らず)が内面に触れて、思わず惹かれていく姿だ。
言い換えれば、濃厚な蜜のように甘い世界にちやほやされ
うっとりと浸かりきり、外の現実に目を背いたまま楽に生きていくことも選べた彼女。
金、富、名誉、権力は魅惑的な自由を産み与える。
だけど
使い方を一つ間違えれば簡単にその身は滅びること。
その抜け殻は〝哀れさ〟を巻き付けたまま離れない。
そして、無情にもこの世が続くかぎり彷徨う負の記憶の化石となること。
喜怒哀楽のつまった実体験と見聞から心を磨きそのことに気づいたベラは学習した。
その結果、強靭な意志を組み立て自分こそは〝哀れなる者〟にならない道を切り拓いたのだ。
ラストはまるで悪いジョークのようだが、ふたりのベラの積もる思いがこれでもかと盛り込まれている。
だいぶ振り切った役柄を演じるエマが製作側に名を連ねこの衝撃力で世に出す意味、エンタメにおさまらない海のごとく深い思い入れが、フライヤーにある静かなる反逆の横顔とようやく重なる鑑賞後だった。
修正済み
愛すべき、ベラ
秩序ある社会に切り込みを入れ、常識という名の壁をフワリと越え、人の心にストンと入り込み、出会う人々の気持ちをざわつかせながら、後ろも振り返らず軽やかに進み続けるベラ。
常識、社会、しがらみ、家族、理性…色々なものに縛られて生きている私たちは、ベラのその自由さを羨み、憧れ、いつあんな感性を失ってしまったのかと悲しくもなる。
哀れなる者たちとは、ベラ以外の全員。観客さえも哀れなる者たちなのだ。
モンスターのように見えたゴッドも、最後には愛を残し、ラストの庭のシーンが、この作品の全てを物語っていたように思う。
“熱烈ジャンプ”に頼りすぎな感じもあったし、いきなり娼館で働く⁈とか思わないでもなかったが、衣装、美術、音楽の素晴らしさだけでも一見の価値あり。
ウィレム・デフォーの快演、エマ・ストーンの捨て身の演技、マーク・ラファロの欲まみれの俗物感も、役者の底力を見せつけられたようでとても素晴らしかった。
欲を言えば、ランティモスには、『籠の中の乙女』や『ロブスター』みたいな、壮大なスケールではなく、地味だけどジワリと心に忍び込んでいつまでも澱のような何かを心に残していくような、そんな作品を期待してしまう。
とは言え、この作品はランティモス以外成し得ない世界だ。
今まで誰にも許さなかったのに、ランティモスには映像化を許したアラスター・グレイ、その選択は正しかったのではないだろうか。
全673件中、261~280件目を表示