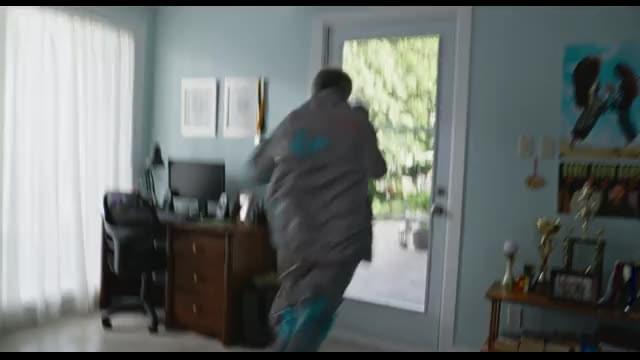ボーはおそれているのレビュー・感想・評価
全364件中、141~160件目を表示
永遠に続く悪夢の連鎖
とにかく序盤が面白すぎる。
シュールでナンセンスな怪作
ボーを演じたホアキン・フェニックスの妙演に尽きる作品だと思う。
彼は常に強迫観念に苛まれながら怯えて生きている。その原因は自分を束縛する母親にあるのだが、そんなマザコン男をホアキンが終始”困り顔”で演じている。様々な理不尽な目に遭いながら奔走する姿が強く印象に刻まれる作品である。
個人的にはポン・ジュノ監督の「母なる証明」を連想した。主人公の母親に対する複雑な愛憎の念、息子を溺愛する母親の狂気は両作品に共通する所である。いずれもシビアな結末を迎えるが、そこも含めて本作には母性が大きくフィーチャーされているような気がした。
監督、脚本は「ヘレディタリー/継承」、「ミッドサマー」のアリ・アスター。
いわゆるジャンル映画から出てきた作家であるが、コメディやホームドラマ的な要素を取り入れながら独特の作風を貫く個性派である。今回も基本的には母子愛から派生するホームドラマで、作品のテイスト自体はサスペンスである。ただ、要所で癖のあるコメディ的な演出が横溢し、一筋縄ではいかない作品となっている。
また、今回は現実なのかボーが見ている妄想なのか判別できないようなシーンがたくさん出てくるので、これまでのような分かりやすい映画にはなっていない。ルイス・ブニュエルの映画のような少し不気味で可笑しいシュールさが常に漂っており、例えばボーが住む荒廃したスラム街や中盤に登場する旅一座等は余りにも荒唐無稽で現実離れしている。こうした非現実的な世界観や登場人物たちは前作「ミッドサマー」の中にも見られたが、今回は更に奔放に進化しているように見えた。
そんなシュールでナンセンスな本作だが、特に印象に残ったのは終盤の屋根裏のシーンだった。”アレ”の意味するところは色々と解釈できるだろうが、それにしても余りにもダイレクトな表現に笑ってしまった。穿って見れば、あのシーンはボーが自分自身を見て卒倒しているようなものである。こんなシチュエーションを考え付くアリ・アスター監督の感性は、やはりぶっ飛んでいるとしか言いようがない。
また、母の死を知った後でボーは心を落ち着かせようと入浴するのだが、このシーンも傑作だった。どうしてそこに?という意味不明さに笑いがこぼれてしまった。
更に、ラストに至るシークエンスも良い。ネタバレを避けるために書かないが、これほど人を食ったオチもそうそうないだろう。しかも、映画の冒頭に繋がるような円環構造を取ることによって、ボーの地獄は永遠に終わらないという意地の悪さが感じられる。
欲を言えば、約3時間というランタイムはさすがに長すぎるので、もう少しシナリオの錬成が欲しかったか…。
悪夢の追体験映画としてマーティン・スコセッシ監督の「アフター・アワーズ」やテリー・ギリアム監督の「未来世紀ブラジル」を連想したのだが、それらに比べるとエンタメ作品としてはやや冗長に感じられてしまう。
ボーは旅の途中で様々な人物と出会っていく。これは彼が母親の元を離れて新たな家族の一員になっていく暗喩になっているのだが、外科医の娘や心を病んだ帰還兵、旅一座のエピソードは、果たしてどこまで描くべきだったのかという疑問も持った。
また、劇中にはアニメーションも登場してくる。「オオカミの家」のクリエイターが手掛けており、これ自体は大変魅力的なのだが、若干展開を鈍らせてしまった感は否めない。
期待を裏切らないすごい作品
評価4.3
アリ・アスターの新作、しかも主演はホアキンという物凄い組み合わせ。どうしたって胸踊るでしょう。
目眩くような災厄の連続と、散りばめられた伏線やキーワードの数々。
夢か現か曖昧な世界を現在と過去が前後した構成でできているので、観ている者が不安定になります。
どれも魅力的なエピソードで、ボーの人生を追体験したかのよう。
情報量も多く、だからか鑑賞後の疲労感もすごい。
途中入るアニメーションパートでは「オオカミの家」のクリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャが参加。
までは知っていたのですが、日本からも「ポケモンコンシェルジュ」のドワーフが参加してたんですね。びっくりしました。
この中盤に入るアニメーションパート。これまでのブラックなコメディタッチと違ってて、何というか潰されそうな気持ちになるんですね。中々に効いてました。
そうして今作でもありましたね、カメラの天地反転。ここから始まるのか…ってニヤリとさせられました。
そうしてひたすら悪夢の連続から逃れ、やっと家に辿り着くと数々の真相が見えてくるんですね。これはうまかったです。
マリア像、チャンネル78、外科医、タトゥの男、エレインとの再会と別れ、セラピスト、兄弟と父、そして作品冒頭から出ていた「MW」ロゴ。
羊水から始まり水に帰着する、それは母親の胎内に戻るようでした。
これは最初から最後までお母さんが作った物語だったのでしょう。
期待を裏切らない、すごい作品でした。
次作もホアキンとのタッグらしく、こちらも待ち遠しいです。
なんという展開
ボーは何をおそれる?
イメージの垂れ流し?
『ヘレディタリー 継承』は箱庭的に構築された世界とそれに見合ったイメージが嵌め込まれていて面白かったが、続く『ミッドサマー』は『ウィッカーマン』とか好きなんだろうなという、雰囲気先行の微妙な作品だった。なのでアリ・アスター監督をちゃんと追うべきかどうかは今作次第かな、と思いながら観に行ったが、結論から言うと鑑賞しながらずっと「『ハイキュー!』観に行けば良かった!」という後悔の念が湧いてくる辛い3時間だった。
冒頭から主人公ボウの見る世界は「妄想で拡張された現実そのものではない世界」という作りで、そこでボウが右往左往したり危険な目にあったりしていても全くサスペンス的な面白さは感じられない展開なのだが、ただただ全編それが続いていくのはなかなか辛かった。ほぼ無いに等しいストーリーの中をひたすら続くイメージの垂れ流しを観ていると、イメージだけで構成されたような映画で面白い映画を撮れるのはリンチやクローネンバーグ、トリアーみたいな変態的な天才だけなんだろうな、ということが改めて分かってしまった。そこそこのエグさとスタイリッシュな見せ方のイメージ映像というとロックバンドのミュージックビデオみたいなんだけど、それなら3分でお腹いっぱいなんだよな。繰り返される血族の支配とか露悪的な展開にも特段の深みは感じられないので、この監督は感覚的な作品ではなく、ちゃんとプロットや世界観を作り込んだ作品をやるべきなんじゃないのかという余計なお世話的感想しか出てこない。どうも最近そんなのが多い気がするんだが。
『ヘレデタリー継承』と『ミッドサマー』で 後味の悪さと気味悪さで定...
鑑賞動機: ホアキン5割、アリ・アスター5割。
いやこれは非常に困る。いきなり、それ? 『アメリ』の冒頭を思い出した。最初、アパートの外のカオスぶりは夢か妄想かと思ったが、そうでは無いようで。あ、一部はボーがする最悪の想像ではあるのか。
それ以外は予想もしていないこと「しか」起こらなくて、しかもほぼほぼ不条理なことばかりで、確かに「どん底」気分にはなるので、成功なんでしょうか。しかも長いので余計につらい。
『ミッドサマー』みたいに2回目からはゲラゲラ笑いながら観ることは出来なさそう。
なんなん?この映画?でも飽きない
不条理コメディの味わい
急死した母の元へ向かう主人公ボーの行く手に、次々と不可解なトラブルが立ちふさがり、一向に前に進むことができない。
わけのわからない奇怪さと必死だからこそのおかしみが混じり合った不条理コメディの味わい。例えるなら、コーエン兄弟が作るコメディ作品のようなテイスト。
最初のボーの住まい周辺のシーンから、なぜ?なぜ?の連続だが、過剰で意味不明な出来事を追っていくうちに、これは主人公ボーと同じく、観客も身を委ねて追体験するしかない、ということがわかる。
全体で4部構成になっているが、特に第3部の舞台劇とアニメーションが混じり合ったパートが独創的で面白い。「オズの魔法使い」を連想させる。
しかし、最後に謎解きと答え合わせらしきものを見せるのには、納得感とは逆に、散漫で薄っぺらな印象を持った。あのまま奇怪で意味不明なまま、観客を突き放してもよかったのではないか。
ホアキン・フェニックスが、ジョーカーの時とは全く違って、太ったさえない中年男に成り切っていて、さすがと感心した。
序盤は好きだけど
「ボーはどう生きるか」
退屈しない3時間でした。
観る価値ありです。
「自分の思っている現実が揺さぶられ、おかしなノイズが段々発生してくる」系の映画ですが、エピソードがどれも可笑しい。
天井に小太りのおっさんが張り付いてる画を始め、色々面白い。
プールの死体は「サンセット大通り」ですね。
最後の断罪スタジアムは「トゥルーマン・ショー」(これはうろ覚えですが)でしょうか?
他にも色々ありそう。
背景的なものに「マザコン(コンプレックス=抑圧)」があるのかなと何となく思いましたが、宮崎駿の「君たちは…」も「マザコン」的に読めるとこもあり、世界同時発生マザコンブームが感じられました。
最悪の事態を次から次へと観させられる変な映画
次から次へと起こる最悪の事態を、なぜか僕は自分の人生になぞらえていた。考えようによっては僕の人生もこんなものなのかもしれないなんて、とんでもないことを考えながら(しかもくすくす笑いながら)観ていた。この不思議な感覚、分かるかな。怖いんだけど、それ以上におかしいやら、せつないやら、不思議な映画だなと。こんなこと、考えながら観てた人いるかな。ただ2時間過ぎて母親とのやり取りが始まって、そういった感覚は薄れ、バカバカしい(それほど悪い意味じゃなくて)コメディになっていった感じ。ヘンテコな映画でした。★4つ。十分楽しめた。この映像体験は僕の頭の中に何かしらの爪痕を残したんじゃないかな。…★4つ半でもいいかもしれない。
気が変になりたい人には向いてるかもね。
長かったのだけが星ひとつマイナス。面白かった!
全364件中、141~160件目を表示