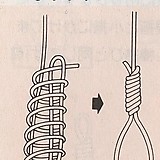「May I Help You?」北極百貨店のコンシェルジュさん いぱねまさんの映画レビュー(感想・評価)
May I Help You?
Can I Help You? でもいいのだろうが、「何かお手伝いすることがございますか?」なんていう問い掛けなんて、自分の人生の中で一度も出会ったことがない 普段の生活でも仕事上でも、自分宛文章だって然りだ
日本語に訳せば「いらっしゃいませ」になるらしいが、どうもしっくりと受け取れない やはり直訳の方がピッタリするのだ 多分、それは欧米人に於いて、社会階層がしっかり確立されている中で、裕福層に対する最大限のサービス意識を、受け身ではなく自分から能動的に勝ち取りに行くという姿勢なのであろう いや、勿論日本だってそういう世界観はあるだろうが、一般的には其処までのあからさまな態度は示さないと思う これも悪い慣習かも知れないが、「訊かずに察しろ」って事なのかな? ま、あちらは"チップ"という制度が多分に影響を及ぼしているが、外国人がよく日本人は親切という言葉を聞く度、違和感しか感じないのは自分だけではない筈だ 世界中でこれだけ不親切で不寛容な国は無いのだから・・・
今作は所謂『お仕事ジャンル』というカテゴリであろう ファンタジー要素をベースにしており、原作漫画からの映画化なのだが、自分は未読である
その昔、フジテレビでこういうお仕事モノのドラマ番組が百花繚乱だったが、あれは恋に仕事にドタバタって感じの緩さが仕事や暮らし疲れの視聴者に程良い夢心地を与えたものだが、今作はピリッと辛口も織込んでいる仕上げになっている
そのスパイスとは人間が乱獲した絶滅危惧種や既に地球上からいなくなった動物も含めた、擬人化された動物たちをもてなす百貨店での、人間のみが店員のプロットなのである 劇中に説明されている通り、直接乱獲や殲滅させた人間ではないが、人間全体を代表して、店員が動物達にサービスさせる『罪滅ぼし』、要は人間にとって"罪の自覚"と"購い"を強いる"デパートメント"ならぬ"ジュエル"の建築物なのである
世界最古の百貨店が生まれた年は、オオウミガラスの殲滅が確認された年と同年らしいので、そこからオオウミガラスがオーナーの百貨店が、3代目になり、新しい世界観を模索していく中で、一人の新米コンシュルジュの奮闘を追う内、人間と動物たちがもっと協力する中で、お互いの信用や信頼を構築出来る、その時代が来たのではないかと予感する結末に着陸するストーリーテリングだ シークエンスが細かく区切られているのは、漫画の話数の区切りであろう 一つ一つのシークエンスはそれなりに興味深い接客あるある話になっているし、現代問題のカスハラやリストラ執行人なるデパート内部事情も差込んでいて、中々のささくれだったリアリティを描いているとは感じた
だが・・・ 観賞後のこのモヤモヤ感がずっと抜けないのである ハッピーエンドに終わっているし、長い間接客業に携っている身としては、こんな上客、太客が対象ではなかったので仕事の奥深さを紹介するコンテンツとして勉強になったのだが・・・
それは前述した"罪の自覚"と"購い"の強要を何故に現在の人間に背負わせているのかの説明や構築が不十分なのであるからだ
此処を上手く"料理"しないとそれこそ日韓、日中関係と同じ構図を想起させてしまうし、ましてや動物の擬人化は、まかり間違って件の国の人達を揶揄するようなイメージにミスリードさせてしまう危険性も孕んでいると感じるのは私だけだろうか? 今現在、様々な外国人観光客が来日している中で、金持ち達が好き勝手の傍若無人振りを接客に携る人達にぶつけている資本主義の現実をこうしてメタファー化してしまうような構築に、考え過ぎかも知れないが、何か蟠りが茶渋の様に貼付いて離れない 勿論、本作ではもうそういうステージではなく、今後は客とのコミュニケーションに拠り、単にサービスの授受だけではなく、一緒に百貨店を盛り上げるコミュニティを模索しようという方向性を示唆していて、それは戦略としてのアイデアなのだろうが・・・
「出来ません」「有りません」「知りません」は、コンシュルジュにとっては御法度という、或る意味究極のSM的世界観に通ずる歪んだ関係性を想起させてしまう件や、カスハラに対する対応の不味さを指摘する際の、直ぐに頭を下げてしまうから益々カスハラを製造されてしまう説教も、人はロボットでは無く、言われたからと言って直ぐに改善出来ぬ性格や性質も有っての適切な指導なのか、単にリストラ前提の精神的追い込みなのか、その辺りのフワフワ感が、現問題のリアルをぼやかしてしまうような杓子定規感にモヤモヤしているのだと感じるのだ
とんでもなく根深い問題を、何となく多様性と共存に着床させる事の浅はかさをどうしても否定できない、しかし、アニメとしての表現力の緻密さや、コミカルな動きの信頼度の高さとの折り合いの悪さに、でも、応援したいと考える、何人もの自分が内在しているのを改めて認識出来た作品である