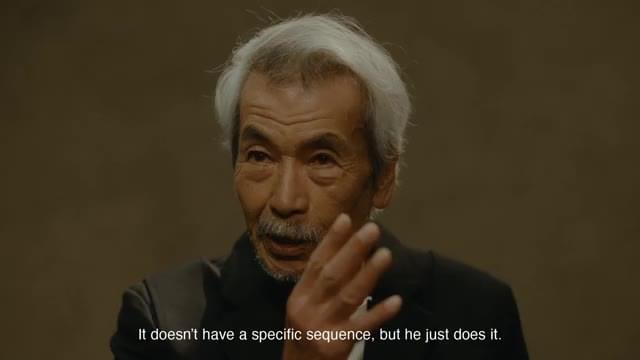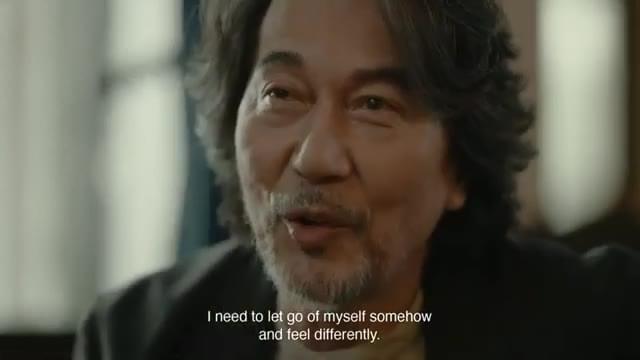「何気ない所作の積み重ねが人生」PERFECT DAYS talkieさんの映画レビュー(感想・評価)
何気ない所作の積み重ねが人生
生活は淡々と流れる(経過する)。本人が意識をしていると、いないとにかかわらず。
その流れを切り取り、見事に活写した一本。
同監督の手になる『パリ、テキサス』『ベルリン、天使の詩』などと同様に、ヴィム・ヴェンダース監督の現実からエッセンスのみを切り取って活写する手腕を、改めてまざまざと見せつけられた思いがします。
言ってみれば「日常」の何気ない所作を丹念に描くことで、その「日常」を鮮やかに描き出す―とでも形容すべきなのでしょうか。
例えば、平山は、毎朝、出勤の前に自販機で缶コーヒーを買う習慣があるのですけれども。
その缶コーヒーを買うショットを、いろいろな角度から、毎回アングルを変えて撮影するなど、彼の「日常」こ切り取り方がとても上手なのが、この監督の手腕なのだだろうと思います。
本作は「公共のトイレをアートに」という東京都の活動に賛同したヴェンダース監督が手を上げて作品化したと聞きます。
それだけに、入室してロック(施錠)するとガラスが不透明に変わるという(確か渋谷区の公園にあるという)トイレも見ることができました。
(東京を猛暑が襲った夏は、異変で、ガラスが不透明にならなくなったとも聞き及びますけれども・笑)
本作も、十二分に佳作の域に達している一本だったと思います。
(追記)
人の役に立つ仕事ということで、この仕事に彼は誇りを持って働いていたのだと思います。本作の平山は。
(反面、その対比が、いわば「やっつけ仕事」感覚でこの仕事をこなしていたタカシだったのでしょう。)
評論子も大学生の頃、清掃の仕事のアルバイトをしたことがあります。
ビルの汚水槽の清掃です。
東京の会社なのですけれども。
主として東北からの出稼ぎの農家の方々が作業員として働いている会社でした。
だから、農繁期の春から秋までは「開店休業」の状態なのですけれども。
しかし、冬になると、にわかに営業(業務)を再開することになり、毎年、その時期に汚水槽の清掃の頃合いになる得意先から仕事を請け負っていたようです。
人柄が温かい方々ばかりの会社だったので、まだまだ社会経験の乏しい学生(大学生)だった評論子も働きやすかったのですけれども。
そこの社長さんが、常々「清掃って、いい仕事でしょ。汚れていたところが、みるみるうちに、きれいになっていく。」とおっしゃっていたことを、今でもよく覚えています。
本作の平山も、きっと同じ気持ち(心がけ)であったことは、疑いがないことと思いました。
(追記)
平山は、自分の生活への他者からの介入を頑なに拒んでいたフシがありはしないかと、評論子は感じました。
その、柔和な表情とは裏腹に。
一日のルーティンをきっちりと決め、あたかも自らに「課する」かのように、少しの齟齬(そご)もなくそれを実践する―。
まるで、他者に付け入る隙を与えないようにするかのように。
それは、父親との確執(それは本作が詳らかに描くところではなかったと思いますけれども)から、でしょうか。
経済的には富裕であったはずの生活を捨てて、経済的にはあまり潤沢とはいえなさそうな今の生活を選び取った平山の「確固たる意思」みたいなものの一端か垣間見えたと思ったのは、果たして評論子独りだけだったでしょうか。
humさん、コメントありがとうございました。
描かれていないので推測の域を出ないのですが、私も、平山とその父との間にどんな確執があったのかは、気になるところです。
父との間の解けぬ誤解、行き違いだったのではないかとも考えたりします。平山の生き様だけでなく、そういう点でも「奥行きの深い」作品だったと思います。
父との関係が大きく影響していたのてしょうね。
もう引くに引けない状況というか、限界というかそんな過去から現在を感じましたね。彼は自分のためにあえて親のいる世界からあえて離れた世界を生きる道を選んだのでしょう。穏やかさから一転、ひとりきりの車内で歯を食いしばり泣き笑いをする姿には壮絶とも言える葛藤と意地を通す覚悟、人生を重ね自分も年老いて知る父への深い思い、別れを間際にした本心もあったかと。。。
共感ありがとうございます。
ニュアンスが違うかもしれませんが、主人公はこの仕事がしたくて・・という事でも無かったのでは? と思いました。只自分の仕事に対する責任感、やるなら全力で結果を出す、そういう気持ちだったんではないか。彼本来のキャパはもっと有るんでしょうが、今の仕事を淡々と極めていって週末ほっと一息つく、そういうルーティンを自分で作り上げていったのではないでしょうか。最後の涙は良く解らないやりきれなさがこみ上げたように思えました。