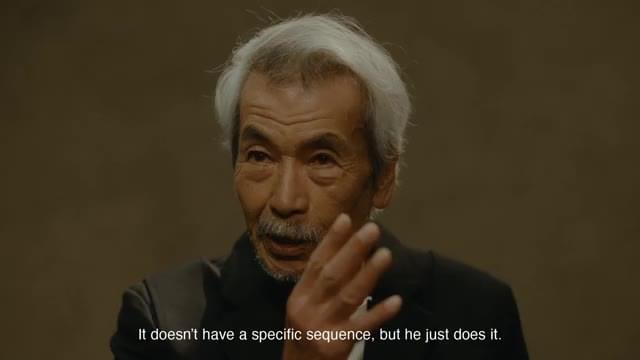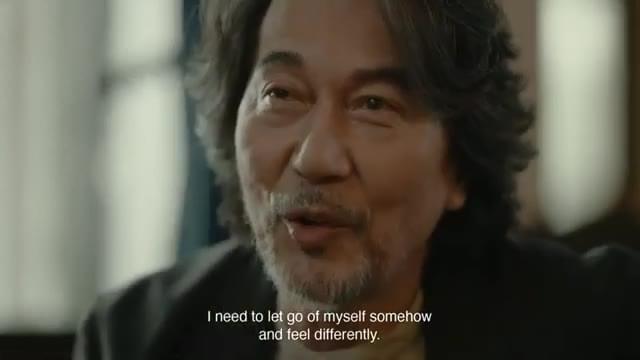「ありのままではない男の美しい生き方。外国人監督の観た、ありのままではない美しい東京。」PERFECT DAYS じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)
ありのままではない男の美しい生き方。外国人監督の観た、ありのままではない美しい東京。
正月早々、とても良い映画を観た。
役所広司の「表情」で、映画の7割方ができている。
真摯で。温和で。思いのほか、感情豊かな。
これがもし、苦悩を秘めた深刻な表情を湛えていたなら、本作はまるで別の映画になっていただろう。たとえば、マックス・フォン・シドーのような。
でも、ヴェンダースは役所広司に、
少年のような探求心と集中力を秘めたつぶらな瞳で、
繰り返される単調な毎日を前向きに受容し、
ちょっとしたよしなしごとに微笑みを浮かべ、
常に「下」ではなく「上」を見つめている、
そんな男を演じさせた。
平山は日々の生活を肯定している。いや、肯定したい。
ヴェンダースは平山の生き方を肯定している。いや、肯定したい。
『PERFECT DAYS』は、その「せめぎ合い」の映画だ。
この映画の漂わせる「肯定感」は、ヴェンダースが「信じたい」生き方を必死で模索し、それを平山(役所)が必死で「演じている」からこそ生まれる、不思議なグルーヴである。
この映画の東京が、ありのままに美しいのではない。
この映画では東京を「美しく見せようとしている」のだ。
同様に、平山の人となりや生き方が美しいのではない。
平山は自らの意志で「美しく生きようとしている」。
そして、監督がそれを「美しく見せようとしている」のだ。
たとえば、この映画は「トイレ掃除」がモチーフの映画なのに、
糞尿や、嘔吐物や、濡れたチリ紙といった「汚物」が全く出てこない。
(部下の台詞のなかで示唆されるだけだ。)
あるいは、貧困のネガティヴな側面もきれいさっぱり描かれない。
平山の所作もまた、貧困層のそれではない。
すべての動きに「型」があり、「リズム」がある。
ポケットの中のものを整然と並べ、またそれをしまう。
真っ白に洗われた使いふるしのタオルを首にかける。
手際よい手順で、神業のようにトイレを磨き上げてゆく。
彼の在り方は、どちらかと言えば「禅僧」のそれに近い。
毎日、同じルーティンをこなすこと自体に意味を見出し、
糞掃衣(ふんぞうえ)を着て、修行の一環として
一心に東司(禅寺のトイレ)を清掃する。
そんな僧侶の示すような、清浄さがある。
いい方は悪いが、
ヴェンダースと出演者は「グル」になって、
東京の美しさと、清貧の生活の尊さと、トイレ清掃労働の清廉さを、
「でっちあげている」。まあ、そういうことだ。
だから、平山の生き方は、一見、小津映画の登場人物のそれのように見えて、そうではない。
たとえば『東京物語』において、笠智衆と東山千栄子の老夫婦の佇まいがただ「ありのままに」美しいのとはまるで異なって、平山のそれは決してありのままに美しいのではない。
彼は(おそらくなら)資産家の跡取り息子の地位を捨てて出奔し、「この生き方を選んだ」人間だ。
アナクロニズムとミニマリズムは、
彼の武器であり、防波堤であり、避難所なのだ。
彼の修行僧のような生活ぶりもまた、なりゆきで身についたものではない。
そう生きようと決めて、必死ですがりついてやって来た、彼自身で選んだ生き方だ。
今の時代、ふつうにしていればスマホくらい使うし、テレビくらい買うし、もっといくらでも便利に生きられるはずだ。それをしないというのは、結局のところわざとそうしていないのであって、彼は時代に抗い、研ぎ澄まされた脳で思考し、自らのプライドと魂を守ることのできる戦略として、この生き方を敢えて「選択」しているわけだ。
会社でただひとり最後の最後までガラホを使い続け、いまだに家のテレビはブラウン管で、ラジカセでクラシックのCDを聴いている僕が言うのだから、間違いない(笑)。
平山のシンプルな生き方は、現代においてはむしろ「普通ではない」。
現代における普通の生き方というのは、スマホを使いこなし、文明の利器の恩恵に浴し、適度に居心地の良い会社で適当にお給金をもらって、なんとなく毎日を過ごしてゆくような生き方であり、平山のそれは、むしろ「こだわり」と「反逆」の人生と言ってよい(だから彼は常に70年代のロックを聴いている)。敢えて目指さないと、今の時代とうてい成立しないような生き方。意地になったかのようにシンプルで昔かたぎの生活を選ぶという意味では、都会のど真ん中で「田舎の自給自足生活」マインドを実践しているようなものだ。
「トイレ掃除」というのも、おそらくなりゆきで選択した職業ではあるまい。
父親への抑えきれないほどの「反骨心」が、彼を職業面での「極端な対極」へと走らせている。その、父親から見れば「下々の」仕事を完膚なきまでにこなすこと――さらにはそこに「生きがい」を見出すことで、平山は精神的な「復讐」を遂げ続けているのではないか。
平山の見せる「笑顔」もまた、そのまま受け取っていいものではないだろう。
そもそも、彼は地面を這う暗い「影」に惹かれながら、
いつも空を眺め、スカイツリーを眺め、雨を眺め、上を向こうとしている。
そんな男だ。
彼の愛する「木漏れ日」は、空に浮かんだ「影」だ。
明るい気分で眺められる、闇を抱えた「影」なのだ。
彼は、そんな闇への傾斜を胸に抱いたまま、そちらに滑り落ちないように、必死で同じリズムを刻み、ペースを保ちながら、淡々と時を過ごしている。
彼にとって、70年代の洋楽は、そんな自分を鼓舞するための「上げていく」音楽であり、そんな自分が幸せだと言い聞かせるための「セルフ洗脳」の音楽でもある。
彼は、日々の何気ない日常に異なる「BGM」をつけることで、それを「特別な日常」に変えてみせる。ちょうど高校時代の僕が、学校の行き帰りにそうしていたように。
彼は、ああ見えて、情動の強い男だ。
普通の無口な男は、何年も会っていない妹を、いきなり抱きしめたりしない。
普通の無口な男は、通い詰めてるバーのママが誰かに抱きついていたからといって、あんなに取り乱したりしない。
平山は、本当は人一倍、感情の起伏の激しい男なのだ。
感じやすく、涙もろく、ちょっとしたことで無様に揺れ動く。
そんな自分を律しながら、彼は敢えて単調な日々を刻んでいる。
あの印象的なラストシーンはまさに、あふれ出る感情に抗いながら、なお無理やり微笑んでみせようとする、平山という男の内的闘争が「表情」に刻印されたものだ。
小津は、そのへんのありきたりの人々の何気ない日常を、美しく描いた。
ヴェンダースは、資産家あがりのインテリ崩れが戦略的に選びとった、昔ながらの何気ない日常を目指す涙ぐましい日々を、美しく描いた。
前者を称揚しつつ、後者には抵抗を示す観客がいても、僕はちっともおかしくないと思う。
平山のPERFECT DAYSは、しょせん「まがいもの」だからだ。
でも、僕は、そんな平山の生き方を、ただ美しいと感じた。
生きたいと願う生き方を目指す生き方を、僕はただ尊いと思う。
今の日本で、昔の邦画のような生き方を目指す平山に、僕は親近感を覚える。
そして、それを「肯定的」に描いてみせたヴェンダースに共感する。
渋谷区のトイレのPRプロジェクトという得体の知れない枠組みのなかで、押し付けがましくない形で、平山という男の日常を、生き方のモデルケースとして示してくれた監督の手腕に、素直に敬服する。
― ― ―
『PERFECT DAYS』は、小津リスペクトの「古き良き邦画」の懐古的フォロアー作でありながら、海外の視点から「美しき日本」を選び取って並べてみせた「ジャポニスム」と「オリエンタリズム」の映画でもある。
ここには、ヴェンダースの感性で「濾しとられた」日本の風物が、これでもかとばかりに並べられている。
東京スカイツリー。古いアパートのごみごみした街並み。首都高(タルコフスキー!)。
畳敷の部屋。布団の上げ下ろし。濡れ新聞を用いた掃除。盆栽。
神社。竹ぼうき。鳥居。一礼してくぐる主人公。
銭湯。ペンキ絵の富士山。入浴の作法。コインランドリー。
プロ野球。大相撲。一杯飲み屋。浅草の地下街。下北の中古レコードショップ。
隅田川の夜景。下町に上る朝日。雨に濡れる街角。
そこに、汚いもの、見苦しいものは、いっさいない。
すべては浄化され、概念として美化され、結晶化されている。
そもそもトイレというモチーフ自体が、「美しき日本」の際たるものだ。
ウォシュレット。いつもピカピカの便器。温熱便座。
定期的な清掃。上質のトイレットペーパー。
日本のトイレは、世界的に見ても、東洋の神秘と言っていい優れものだ。
日本人である僕が海外旅行しても、ウォシュレットがない国じゃ暮らせないなと思うくらい、日本人の「排泄まわりの浄化への情熱」は、図抜けている。
ヴェンダースが、なぜ渋谷のトイレPRみたいな奇妙なハンパ仕事を受けたのか。
それは、彼が「磨き上げられたトイレ」に、日本の最良の部分を見出したからではないのか。(パンフが売り切れてたから、当て推量に過ぎないけど)
ちなみに、海外における「こんまり」ブームにしても、禅的な思想やアニミズムと結び付けて受容されている部分が大きい。海外の人にとって、日本人の整頓好き、綺麗好き、清潔好きは、ある種の「日本の神秘」の一環なのだ。
それから、渋谷の前衛的デザインのトイレ群は、新と旧が交錯するトポスでもある。
最先端のデザインが、神社や公園といった古い日本と交じり合い、
公園では、子供と大人、社会人とホームレスが間近に交流する。
ヴェンダースは、「渋谷」の「公園」にある「デザイナー・トイレ」と、それを清掃する「浅草」から通うアナクロ趣味の男の取り合わせに、過去と今、聖と俗、ハレとケが渦巻く日本の象徴的な「場」を見出したのだろう。
『PARFECT DAYS』の面白いところは、外国人監督から見た「日本」のイメージ動画になっていると同時に、日本人から見ても大して違和感のない「日本」のイメージ動画にもなっていることにある。
海外客の視点から見た異邦としての特別な日本。
日本人にとっての日常としてのありふれた日本。
両者が混淆し、いっしょくたになり、外から見ればやたらリアルで、内から見ればやたら新鮮な、独特の視座を提供してくれる。
しかも、汚いモノや汚い心は描かない。
透徹とした美しい日本の風物と、美しい日本の清貧たる生き方を、肯定的に呈示してくれる。
海外の観客が見れば、日本への幻想と憧れが掻き立てられる。
日本の観客が見れば、忘れそうになっていた懐かしい日本を満喫できる。
そんなヤヌスのような二面性をもった、「どちらも良い気分にさせてくれる環境映画」にきちんとしあがっている。
だから、僕は思ったのだ。とても良い映画を観た、と。
以下、どうでもいいことを箇条書きで。
●「金の力で外様をかき集めて」と揶揄されているのが読売巨人軍で、思い切り「外様」として映っているのが、丸と中田なのは笑った。
●洋楽は詳しくなくて、アニマルズくらいしかわからず。歌詞を全部聴き取れたら、ずいぶん見ている印象も変わるんだろうな。
●新人の姪っ子、可愛い! いかにもヴェンダースが好きそうなクセ強系美少女。
●最初に読んでいるのがフォークナーの『野生の棕櫚』。それから幸田文の『木』。
石川さゆりが、初見で「幸田文」を「こうだあや」と読んでいたが、ふつうは読めないと思うので(「ふみ」っていうと思う)、ママもさりげに隠れインテリなのでは?
●パトリシア・ハイスミスの『11の物語』がシレッと出て来てびっくりしたが、考えてみるとヴェンダースは『アメリカの友人』を映画化してたよな。ちなみに日本を代表する翻訳者の柴田元幸が、なぜかカメラ屋の店主役で出ていた。
●実は、ラストシーンにはあまり共感していない。なんていうのかな? Too muchっていうのか?
石川さゆりや、麻生祐未や、三浦友和のシーンは、なんか「やりすぎ」感があっても、みんな芸達者でもあるし、まだ好意的に受け止められたんだけど、あのラストは、個人的には化学調味料がききすぎてる感じがあった。『時の翼にのって』(93)で僕を幻滅させた「不必要な通俗臭」がしてね。
相変わらず、長いのにそこらのコラムより内容があって、つい読み切ってしまうレビューでした。笑
仰られる通り、平山の生き方は監督の肯定であり、またそれに対する願いであり、祈りかもしれません。
ラストカットは確かに冗長でしたが、肯定しきれない揺らぎや迷いが表れていて、私は平山に、そして監督に人間味を感じました。
「本当にトイレ掃除をしているのか」というような妹の台詞も印象的でした。
単に「そんな仕事をしてるのか」という意味にも取れますし、父との訣別の際に何かしら言及があったとも捉えられます。
連絡先は知っているのに長らく(姪の幼少期以来?)会っていなかった妹との関係も微妙なところ…
個人的には父親とはちゃんとお別れをしてほしいなぁ、などと思いを馳せてしまうくらい、実在感のある作品でした。
こんにちは
おっしゃること、納得です。
私にはそこそこのお年を召した外国人映画監督が「思い込んだ」美しい日本と日本人像を平山に投影したように感じます。外国人ゆえの日本人感で、好意的なのは間違いないのですが、描きたい日本人像を成立させるために無理くりが目立つし、諸々作為的で、素直に素晴らしいとは言えないんですよね。
平山さん、薄給で知られる業種で適度に働いてあれだけの生活ができるなら幸福度高いと思います。私は週5日あくせくフルタイム(残業あり)で働いていますがコンビニのサンドイッチなんてめったに買えません。毎日手作りのお弁当です。
長々と失礼しました。お気を悪くされなければうれしいです。
監督の目にまず飛び込んで来たのは、日本人の清潔さ(仕事の仕方、生活等々)じゃなかったんですかね。だとすれば敢えて汚い部分を描く必要はないですね。小津フォロワーと言われてますが、平山夫婦は今観てもあまり清潔感はない、それに役所平山は既婚者感が全然無かったです。