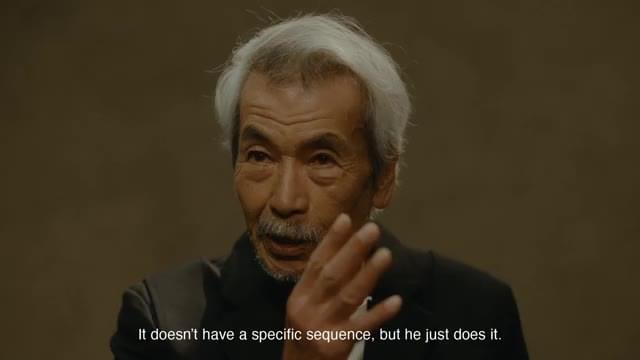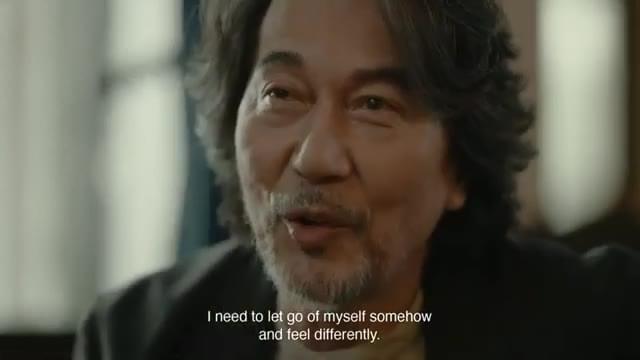PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価
全1021件中、1~20件目を表示
いつもの毎日を過ごしていても、時間は流れるということ。
○作品全体
手が届く範囲の世界で生きていく。そんな作品だ。
古アパートで植物を育て、安く買った本を読み、公衆便所を掃除し、安い銭湯と安いツマミで自分を労う。どれもがすぐに手に入り、周りに干渉されることがほとんどなく、そしていつでも手放せる。ローンを背負うでもなく、長期的なプロジェクトに関わるでもなく、人を気遣うこともない。その世界の気楽さと穏やかさが、木洩れ陽のように優しい。
作品序盤で繰り返されるそうした毎日は、変化のない理想の生活に見える。しかし、実際はそれだけではないことを後半で語ることで、主人公の世界に奥行きを作っていた。
「それだけではない」ことは、「時間」だろう。どれだけ手の届く範囲で生きていても時間を止めることはできない。同じような毎日だったとしても、それを生きる本人にとっては色々な場所に変化を見つけ、それを喜び、時に恐怖する。
主人公は「友人」と呼ぶ樹木の木漏れ日を毎日撮影し、現像した写真を保管している。興味のない人間からすれば全て同じ写真なのだろうが、主人公からすれば大切な日々の変化を感じるものだ。わずかな変化だが、確かな変化。それを大事にする主人公は、そういう点では時間の経過を楽しみ、喜んでいる。
「木」に関連するモチーフといえば、スカイツリーも同じような存在だった。主人公はスカイツリーを眺めるとき、にこりと微笑む。東京の街の変化の象徴でありながら、彼にとっては「いつでもそこにあるもの」でもある。
十数年前まではなかったスカイツリーは、大きな時間の中では“新しい東京”の象徴ともいえる存在だ。けれど、毎日の生活の中では、変わらず空にそびえていて、主人公の穏やかな暮らしを静かに見守っている。
長期的には「変化」の象徴でありながら、短期的には「不変」の象徴…そんな二つの顔を持つスカイツリーは、もしかしたら「木」と同じように、彼にとっての“友人”なのかもしれない。
毎日少しずつ違う空を背にしながら、何も言わず、ただそこにいてくれる友人。主人公が感じている時間の流れと、その中にある静かなつながりが、スカイツリーという風景にも宿っているように思えた。
しかし一方、時の移ろいが暗い表情を見せる場面もある。妹から父の話を聞いた時と、建物がなくなって街の姿が変わるとき、行きつけの店主の元夫から癌があることを聞いたとき。時が移ろうことで取り返しがつかないところへ進んでいく。手が届く範囲の世界で生きている主人公でさえも、自分ではどうしようもない領域。時の移ろいが嬉しさや楽しさだけではない、ということを小さな世界観によって映すことで、フィクションとは思えないほどの説得力があった。
いつもの毎日がどれだけかけがえのないものか、ということ。そしてそんないつもの毎日が、いつかは終わってしまうということ。日々を穏やかに生きる主人公から沁みるように感じられて、とても良かった。
○カメラワークとか
・特段明度が高いわけでも、彩度が豊かなわけでもないのに、街の映し方がとても綺麗だった。日本を舞台にしているから普通であれば街の細かい汚さとかまで見つけてしまいがちだけど、本作はむしろ美しく見えた。光の入れ方が巧いからだろうか。そういえば同じヴィムベンダース作品の『パリ、テキサス』でも「街と道路」はやけに印象に残った。
○その他
・主人公と女性の関係とかはちょっと理想入りすぎてる感じがして鼻についた。妹の感じからして主人公は本当は格上の出自だった…みたいな匂わせも少し余計だった。単純な「負け犬」じゃなくて自ら選んだ道なんだっていうことを強調したかったんだろうけど、それは役所広司の芝居で十分伝わってきてたのにな。
トーキョーではない東京
驚いた。この映画、スクリーンの向こう側に東京が広がっている。それはTokyoではなく、ましてやトーキョーでもない、誤魔化しのない東京だ。長年東京の下町に暮らした私がそう感じたのは劇中の距離感が現実的だったからではないだろうか。
映画館を出て直ぐ様スマホで地図を検索、主人公・平山の暮らす古いアパートを探し出す。更に狭い路地を歩き廻り隅田川に架かる橋を渡って彼の通う銭湯や浅草地下街の飲み屋にも足を延してみた。この行動、もしやただのロケ地巡りなのかもしれない。だとしたら中年が1人でなんだかもの悲しい。でも私はそうせずにいられなかった。
そこで気がついたのはスクリーンに流れるひとつひとつの場面が街のイイトコドリをしてチグハグに繋ぎ合わせたものではないと言う事。平山が自転車を漕ぎ馴染みの場所に辿り着くまでの景色と距離をありのままに映し出してくれている。
トーキョーでなく東京、どうしてそんな事に驚くのかと尋ねる人もいるだろう。私はこんな風に応えたい。「この映画を撮ったのは異国の人なのだよ」と。偏見だと叱られるかもしれないが東京がトーキョーになりうる可能性だってあったはず。だからこそ私はこの映画を撮ったヴェンダース監督に伝えたい。
「私のよく知る愛すべき東京を撮ってくれて、ありがとう」と。
ヴェンダース監督にこの気持ちが届く事は決してないだろうが、私はただただ、そう伝えたいのである。
「PERFECT DAYS」に幸せをみるか、苦しさをみるか。
役所広司がカンヌ国際映画祭で日本人として19年ぶりに男優賞を受賞した映画『PERFECT DAYS』はあまりにも美しい傑作でした。心の機微を描くプロット、自然で豊かなセリフ、そして見事な演技。「幸せとはなにか」を観客全員へ問う必見の作品。今回は3つのポイントからレビューしてみます。
【3つの感想】
1.役所広司の演技がエグい
本作最大の見どころは、なんと言っても主人公・平山を演じる役所広司の演技にあることはいうまでもない。カンヌ国際映画祭で男優賞受賞も納得で、その凄みは「繊細さ」に宿る。
そもそも、この映画には”大きな物語”はない。トイレ清掃員の平山の日常が淡々と描かれるなかで、”小さな物語”が泡沫のように浮かんでは消える。その微妙な変化が紡がれていくだけの曖昧なストーリーを、役所広司は見事に演じきっている。役所の表情や動作に、平山の微妙な変化が込められていて、そこに映画としての”物語”が表出してくる。
あまりに圧巻の演技に、映画館で笑みが溢れ涙すら誘われたシーンがあった。シーンの概要は次のようなところだ。
平山の同僚タカシ(柄本時生)は、ガールズバーで働くアヤ(アオイヤマダ)に夢中だ。ある日タカシは、平山の大切にしているカセットテープをアヤの鞄に入れ、気に入られようとする。しかし、タカシの恋はなかなかうまくいかないようだ。後日、アヤはカセットテープを平山に帰しにやってくる。「タカシ、なにか言ってた?」とアヤは聞くが、黙ったままの平山。アヤは突然平山の頬に口づけをして去っていく。その後平山はいつも通り、開店直後の銭湯で風呂に浸かる。
このシーンはつまり、おそらく恋愛とは無関係な人生・日常を送る平山が、年齢のかけ離れた青年たちの淡い恋心に振り回され、挙句行き場のなくなったキスをその頬に受け止めるという、それだけでも素晴らしいプロットなのだけれど、なによりも秀逸なのが、その後の銭湯での役所の演技だ。
役所は、鼻の下、口元を隠すように湯船に浸かっている。泡立つジャグジーは、なおさらその表情を読み取りにくくしている。にもかかわらず、役所は、ただその両目だけで、この絶妙な感情を見事に演じきってしまった。喜びでもない、戸惑いでもない、恋心でもない、でもどこか幸せにも似た感情が、ジャグジーの向こうでその眼に宿される。はっきり言って、この1カットだけで、カンヌ男優賞も納得だ。
こうした繊細で緻密な美しい演技がこの映画には溢れている。それはきっと、翻ってみれば、私たちが日常であらわす感情の機微に違いないのだと思う。
2.沁みすぎる人間関係
この映画にはいくつもの複雑な人間関係が描かれている。それはつまり、いわゆる相関図に描かれるような「好意」「ライバル」「尊敬」とかの”単語”で語り得ないような複雑さという意味だ。
いくつか例を挙げると。
・実家近くで裕福に暮らす妹と平山
・居心地の良さを感じる居酒屋のママと平山
・ママの元夫であり末期がんの男と平山
これらの関係性は、決して直接的には描かれることのない平山のバックグラウンドを暗示しているし、そのことが、トイレ清掃員で旧いアパートに暮らす現在の平山を物語ってもいる。なんとよくできた人物描写だろうか。
そしてこの「複雑な人間関係」は、この映画ではもう一歩先に進められている。それは、平山の職業をトイレ清掃員という”エッセンシャルワーカー”に位置付けることで、私たちの生活を支えてくれる人々と観客という人間関係をも、平山と観客の間に築こうとしているのではないか。
さらに実は、その平山も、多くの人々に支えられている。銭湯の主人、古本屋の店主、「おかえり」と言ってくれる居酒屋のマスター。なかでも特筆すべきは、劇中で描かれることのないアパートの自動販売機に缶コーヒーを補充する人。平山が毎日仕事を頑張れるのは、その名前も容姿もわからない”その人”のおかげに他ならないのだ。
「PERFECT DAYS」はこうした複雑で見事な人間関係を通して、観客に自分たちの日常で出会い、生活を支えてくれる人々への感謝を想起させる。
3.幸せとはなにか
「PERFECT DAY」の感想を友人や知人と話し合って興味深いのは、平山のような生き方、あるいはラストカットの平山の表情を、「幸せ」と捉えるか、「苦しさ」と捉えるか、ハッキリと別れるところだ。もちろん前者のほうが圧倒的に多い。
是非みなさんの感想を聞きたいし、観客1人1人がどう思ったか、が最も大切だというメッセージであり映画の意図だということは十二分に理解しつつ、ここではなぜ僕がこの映画を「苦しい」と感じたかについて書いていきたい。
まさに映画のラストカット。平山は朝日を浴びる車内で、涙を浮かべながら(正確には目を赤くしながら)笑みを浮かべて、いつもの通り首都高を走る。この表情は何を意味しているのだろうか。というのが、観客にとってこの映画をどう見たかという問いかけであり、だからこそ完璧なラストカットだとも言える。
この物語の1つの大きなテーマは”変化”だ。公式のあらすじにもあるとおり、「同じように見える」ということと「同じ」は違って、平山の日常には微妙な変化がある。変化に向き合うとき、人はどのような態度をとるだろうか。この物語では、大きく分けて3つに分類されていると思った。「変化を求める人」「変化に気づく人」そして、「変化に縋る(すがる)人」だ。
「変化を求める人」は極めて一般的な人間で、この映画ではタケシがその役割を主に担う。「恋人が欲しい」「お金が欲しい」「仕事を辞める」どれも、なにかしらの変化を自分から求めに行っている。観客の多くが無意識にこのタイプに分類されるのだろうし、「変化する=成功」という価値観が蔓延しているように感じなくもない。
だからこそ、この映画は平山を通して「変化に気づく人」を描いた。木々の木漏れ日に代表される自然の移り変わり、あるいは日常のちょっとした出来事、そこに湧き立つ人々の感情の機微といった、”小さな変化”に気づくことで、”大きな変化”を求めなくても幸せな人生が送れるというメッセージではなかったか。
公式あらすじにある「その生き方は美しくすらあった」という言葉には、こうした「変化に気づく人」を肯定し、今の忙しない現代社会へと余白を投げかけているようにも思える。その描き方に沿ってみれば、きっと平山の生き方や、ラストカットの複雑な表情の意味は「幸せ」になるのだろうと思う。(もちろん、ある程度の苦しさを前提とした)
ただ、である。この映画で描かれる平山が、僕には「変化に縋る人」として描かれているように思えてならないのだ。その最も顕著なシーンが、次のような場面だ。
平山が居心地の良さを感じる居酒屋を訪ねると、お店のママ(石川さゆり)が男性(三浦友和)と抱擁している光景を目の当たりにして、平山は急いで立ち去る。ふいに訪れたイレギュラーな出来事(=変化)に、平山はコンビニで酒を買い込み、河岸で飲み始める。するとそこに、先ほどの男性が現れ、「ママの元夫で末期がんである」と告げる。平山は、男性と影踏み遊びをして、「二人の影が重なると濃くなるのか」という男性の疑問に答えようとする。
そして、このシーンの最後。「二人の影が重なると濃くなるのか」という疑問に対して、男性が「変わりませんね」と言うのに対し、平山は「濃くなってますよ。(略)変わらないなんて、そんなハズないじゃないですか」と語る。
つまり、平山は実は変化を望んでいるのではないか、という疑問が頭に浮かぶ。そして望んでいるからこそ、大きな変化を避けているのではないかと。平山は「大きな変化を諦めた人」だからこそ、「小さな変化に縋る人」なのではないか。
平山の過去は明かにはされていない。ただ、妹との会話を考えると、裕福な家庭で育ったが、父との仲違いのすえ、トイレ清掃員として今は一人で古いアパートで暮らしている。平山はその生活を「理想」と思っているのだろうか。仮に「理想」だと思っているとしたら、妹と別れた後に見せた涙は、一体なにを意味するのだろうか。
当たり前だが、平山は感情を失った「善良な市民」ではない。急な仕事がふってくれば怒り、戻れない家族との日々を想っては涙し、行きつけのお店のママが知らない男性と抱き合っていたら動揺してしまう。平山にも「変化」に対する感情はあるのだ。「気づく」だけではない。平山の口から幾度となく「変化」が語られるたび、私はそれが「変化に縋る祈り」のように思えてならなかったのだ。
だからこそ、私は、この映画の平山に、あるいはラストカットの表情に「苦しさ」を見出した。おそらく平山にはもう「大きな変化」は訪れない。いつものように仕事場へと向かう車の中で、「小さな変化」に縋るほかないということではないか。
ただ、もちろん、そうであったとして、「小さな変化に縋る」という生き方も美しく、そこに幸せが宿るということも確かなのだけれども。
「求める」「気づく」「縋る」どのような関わり方であっても、私たちは変化のなかに生きている。そこに幸せを見出そうと僕は思った。
「PERFECT DAYS」
誰が、誰の生活を、そう呼んだのだろうか。
全てをもった人のPERFECT DAYS
ヴィム・ヴェンダース監督作品。
30年後の自分をみているような感じだったな…全然ありえる。
ただ「こんなふうに生きていけたなら」と思うぐらいがちょうどよくて、実際にそう生きたら「完璧」なんて思えない。トイレは汚いし、ずっとはいられない。「木漏れ日」に美しさなんて感じない。ヴィム・ヴェンダースが日本を美しいと感じることと同じだと思う。遠い異国を旅行するぐらいが一番美しく感じるんですよ。現にヴェンダースは日本で暮らしてはいない。だからリアリズムではなく、全てをもった(have it all)人の憧憬やノスタルジーとしての「Perfect days」とみるほうがいいと思う。ただ本作が、オリエンタリズムな眼差しで「美しさ」を撮ったとも言いづらいから全否定するのが難しい。「ニホン凄い論」とは全く違う、ヴェンダースの眼差しで現れる「美しさ」。けれどそれもまた別様のオリエンタリズムのような気もするし…いいとは思うんですね…。ただやはり、質素を楽しめるのは富裕者だけだと思うし、「こんなふうに生きろ」と言うなら便所掃除を仕事にしてからいってくれ。
生活に根ざした清貧さを主題にした映画は、何だか批判できない構造に陥っている。
清貧さを理想化し過ぎているとか社会構造に目を向けていないと批判すると、反論が起こる。「お前は清貧さの尊さに気づいてないし、鈍感であれるほど裕福で映画という『芸術』を何も分かっていない禄でもない奴だ」と。〈あなた〉と清貧さの距離の遠さの反論。真っ当のように思える。これが批判できない構造だ。けれど実はそのように反論する人ほど清貧さから最も距離の遠い人だ。だからこそ貧しい者が貧しいままで階級上昇ができず、それ故、貧しいことを美化しようとする富裕者の傲慢さがとても鼻につくのだ。
本作の出資者や宣伝者は、「こんなふうに生きているの?」。そんな疑問の答えは、渋谷のスクランブル交差点に節度もなくでかでかと広告を出している時点でお察しである。そしてこういった態度は「俗にいうつまらない邦画一般」にも言えることだと思う。
人生は何も解決しない。分かり合える家族をもつことはできないし、世界をひっくり返す仕事もできない。だからかりそめの他者と親しくなって貧しいけれど清い生活の美しさを噛み締めればいいのだ。そんな未来のないノスタルジーを抱えるのは、私が78歳のおじいちゃんになってからでよくて、今は未来のあるノスタルジーを信念に生きていたいです。
「足るを知る」人生こそが最強
観終わって思うのは、「足るを知る」人生こそが、最強なのだということ。「満足することを知っている人は、たとえ貧しかったとしても精神的には豊かで、幸福であるものだ」という意味の言葉です。役所広司さんが務めた主人公ヒラヤマの人生は正にこれでした。
立派とはいえないが、清掃の行き届いた一人暮らしには十分な広さの家。
かっこいいとはいえないが、後輩から尊敬され誇りを持って続けている仕事。
たくさんとはいえないが、数少なくとも日々の日常を彩ってくれる知人たち(行きつけの居酒屋の店長、行きつけの古本屋の店主、行きつけのバーのママなど)
大きな喜びとはいい難いが、朝の缶コーヒー、仕事終わりにの一杯、毎晩寝る前の読書、観葉植物たちの水やり、週末の行きつけバーでのひととき、毎日のお昼休みの木漏れ日の撮影などなど、ヒラヤマを幸せにするささやかな喜びたちがたくさん登場する。幸せとは、なにも特別な日を飾る赤いバラである必要はないのだと思わせてくれる。
ないものをいつまでも欲しがってダダをこねたり、不必要な人間関係に疲弊して自分をすり減らしている現代社会に生きる人たちとは、ある意味別次元で生きているヒラヤマの生き様は尊くすら見えてくる。
全ての人がこんなふうに生きられるとは思えないが、幸せの根本とは、こういうことなんじゃないかと思わせてくれた作品。
心からとてもいい映画を観たと、他人に言いたくなるとても素晴らしい映画でした。
「ふつう」という事
とくに何も起きないです。いや、嘘です。嘘というか、語弊のある言い方でした。
「映画」という娯楽において、「展開」という意味で「何も起きない」です。
生きる限り、なにかしら起きているのが世の常。小さな悩みや失敗だったり、しあわせな出会いだったり大きな成功だったり、それは人によって一大事になったり、他愛のないことだったりするけど、大小は関係ない。はたまた、それへの対処の仕方も、人それぞれ違います。
本作は、何事においても「後悔のないように」たんたんと生きなさい、と諭しているに感じました。一所懸命でも真面目にしていても、失敗することはあるだろうし、他からもたらされる予期せぬ出来事や、病気や事故・事件、自然災害、避けられない不幸というものがあると思う。
そういうのも含めて、人生だから。後悔のないように、真摯に生きましょう。出来れば笑顔になれる自分でいなさい、どうしたって生きなきゃならないんだからね。そんなことを言ってる作品に感じました。
ふつうって、そういうことと思います。ふつうって、難しいですよね。
観たかった作品が通う劇場に無かったので、気になっていたこちらを観賞しました。
すごく良い作品だと思うけど、エンタメ作品が好きな自分にとっては失敗、、。観賞後、説教されたような気分になってモヤモヤしました。そしてすごく悔しい気持ちになっています。こういう衝動に駆られるのは、良い作品に出会えたとき。そこもまた悔しい。。
スマホで下向いてばかりだと、木漏れ日に気づくこともできない
近所の人が道を掃く音が目覚まし代わり。布団を畳んで隅に置き、隣の部屋で育てている鉢植えたちに霧吹きで水遣り。狭い階段を降り、狭い台所で歯磨きを済ます。髭を鋏と電気カミソリで整え、玄関に並べている持ち物を順番にポケットにしまいドアを開けてボロ屋の表へ。そこで空を見上げて微笑む。駐車スペースの横にある自販機でBOSSのカフェオレを買い、仕事道具を積んだ軽バンに乗り込む。本日のカセットを選び、シートベルトを締めて出発。早朝の東京の道路とカセットから流れる洋楽が合う。
担当する1件目の公衆トイレに到着。荷物を持って車を降り、「清掃中」の看板を立てて作業開始。まずゴミ拾いをクイックにおこない、便座、手洗い場と順に掃除していく。鏡をつかって裏側の汚れも確認。便器の中も拭き上げる。バケツに水をはり絞ったモップで床掃除。トイレのドアや取っ手も丹念に拭き上げる。これを何か所か移動しておこなう。
昼はルート上にある神社でサンドイッチ。大木の木漏れ日をフィルムカメラに収める。
清掃がすべて終わると自宅へ戻り、すぐに着替えて自転車に乗って銭湯へ。たっぷりのお湯に顔まで沈める。さっぱりして脱衣所で相撲を見ながら火照りを冷やす。帰りに自転車で地下にある大衆居酒屋に。ビールとつまみを頼み、TVから流れるプロ野球をみながら簡単な夕食。千円とちょっとを払い、自宅へ戻る。布団に入って休日に古本屋で買った幸田文やパトリシア・ハイスミスの本を電気スタンドの灯りで読みながら、うとうとして入眠。そして、朝がきて、また道を掃く音で目覚める。。。
仕事が休みの日は「フィルムを現像に出す&受け取り」「焼きあがった写真の選別」「コインランドリー」「古本屋で本を吟味」「ちょっと贅沢して小料理屋へ」になる。
慎ましいけれど、とても幸福で豊かな日々。(まさにPERFECT DAYS。)
自分に与えられた仕事・社会への貢献を全うし、充実感をもって銭湯とビールで労う。
植物を育て、様々なジャンルの古本で知的好奇心も満たし、音楽も楽しむことができる。木漏れ日や空をちゃんと感じることもできる。。何より木漏れ日に気づけるということは、うつむかずに上を見上げているということ。「上を見上げる」というのは気が良くなるよ。自分も見習おう。
高級車とタワマンをローンで買い、企画やプロジェクトやら1日で区切れない仕事にあくせくして達成感もなく、スマホのために下を向いてばかりで木漏れ日に気づくこともできない。肥大化して、余裕を失った日々。。
何のための人生か?何のために働いているのか?本当に幸せなことは何か?
忘れていたものを再度気づかせてくれた映画。
思わず笑みがこぼれる一服の清涼剤のような映画。
※関東平野の朝焼け。壮観な広大さ。綺麗。
※フィルムカメラ、現像、カセットテープ、ラジカセ、ガラケー、アナログ文化が滅茶苦茶かっこいい! スマホがない生活、いい。豊かだ。
※若い娘を銭湯に連れてきた平山を見た、銭湯の常連たちが微笑ましい。
※石川さゆりの小料理屋。絶対通うよ! むっちゃ似合う。歌うますぎ。(当たり前か。)
「ギターでちゃったかあ~。」たまらん!
※三浦友和とのやりとり微笑ましかった。何も変わらなかった、意味はなかったなんてことはない。影は濃くなっている! (大人のオッサン二人の影踏み、微笑ましい)
「謝りたいではちょっと違う。会っておきたくなった。」この思い、なんとなく分かる。
※1日のルーティン。でもいつも同じ日ばかりではない。色々ある。
※家の戸締りをしないのは気になるよ。
※一緒に働いている若者のタカ、いい加減なやつかと思ったら性根の優しい面も。こりゃ憎めないわ。
※浅草の下町、いいわー。スカイツリーがいつも見える町。紫や赤の電気がまた似合う。
※トイレ掃除の格好をしていても、雨合羽を着ていてもカッコ良くなってしまう役所広司。
※色んな公衆トイレあるんだなあ。ドアが透明から色付きに変化するトイレには驚いた。
下記の涙の意味は大事に考えたい。
・軽バンの中でのアヤの涙
・平山の妹と、妹と別れるときの平山の涙。
・最後のシーン。車のハンドルを握りながら涙ぐむ平山の涙。(ここ名演だった。)
それでも世界は美しく、目を凝らせば刹那の幸せがある
心が洗われる映画を久しぶりに見た気がする。日常の風景の小さな美しさ、小さな満足感を大切にする平山の生き方に惹きつけられた。
トイレ清掃員平山の日常、それも起きてから寝るまでのルーティンを淡々と追う。話の骨組みはそれだけだ。
風呂のない古びたアパートは今の時代では一見寒々しいものだが、大量の古本とカセットテープが整然と並んだ簡素な和室で規則正しく寝起きする平山には、一片の侘しさもない。
朝は竹箒の音で目覚め、缶コーヒーとカセットテープの音楽と共に出勤する。昼は神社の境内で木漏れ日をフィルムカメラに収めたり、樹木の新芽を摘んで楽しむ。決められた仕事を精一杯した後は、銭湯でさっぱり汗を流し、行きつけの居酒屋でいつもの酒を飲む。古書店で見つけた本を読みながら床に就く。
そんな生活をしていても、彼の心を揺らす小さな出来事はたくさん起こる。判で押したような日常など、本当はありえないのだ。
平山の過去を明確に示す描写はほとんどないが、彼の嗜好や、日々の出来事に対する姿勢からうっすらと推し量れる部分はある。役所広司の表情の繊細な変化が、彼の周囲の人々に対する気持ちの動きなどを雄弁に語る。
音楽の趣味や読書の嗜み、清貧に楽しみを見出せるメンタリティなどから、過去に経済的な豊かさを経験している人なのだろうとは思った。果たして、実家は相当裕福なようで、妹は今もその恩恵に預かっていたが、父と平山の間には、彼に生きる世界を変えさせるほどの断絶が横たわっていた。普段心の底に沈めている記憶がよみがえった時、彼が流した滂沱の涙。それは心の古傷の生々しさからか、もう取り戻せない過去を悔いるものなのか。
そんな平山に、家庭で生きづらさを感じている姪のニコは、同じように親族に馴染めない者として、幼い頃からどこかシンパシーを感じていたのかもしれない。昔彼からもらったフィルムカメラを大切に持ち続けていたのもそのためだろう。
ひとりでいたら何をするかわからないとうそぶき、「十一の物語」に魅入られ、最後に母が迎えに来た時平山に「ヴィクターみたいになっちゃうかも」とニコは訴えた。この短編集に収録された作品「すっぽん」に登場する少年ヴィクターは、高圧的な母を刺し殺す。彼女の抱える閉塞感が滲む。
それを踏まえて振り返ると、夕暮れの橋の上でニコが平山を誘って行こうとした海が、なんだか人生の終着や死を暗示するもののようにも思えてくる。
だから、平山がそれを断り、「今度は今度、今は今」とふたりで楽しそうに繰り返したことに少しほっとした。
過去への陰鬱とした思いを胸の奥にしまって、日々小さなことに満足し、時々困ったりもしながら生きてゆく平山。昨今持て囃される、個性を発揮するとかクリエイティブであるなどと言われる生き方とはある意味対極の生き方だ。それでも平山の生活がどこかまぶしく見えるのは、彼の目が日々刹那の幸せをきちんと捉えていて、そのことによって過去の絶望や、無常がもたらす不安に打ち勝っているからではないだろうか。
ラストの平山の表情のうつろいは圧巻だ。彼がこれまでの人生に感じてきたこと全てが、あのシーンに詰まっている気がした。最初笑顔だった平山の目に涙が浮かんできた時点で、私も胸がいっぱいになった。わけもなく、「ああ人生ってこうなんだな」と思った。
台本には「平山は突然泣く」としか書いていなかったそうだ。ひとことの台詞もないそんな場面を、表情だけで1本の映画のクライマックスにしてしまう。名優の面目躍如。カンヌで主演男優賞を取るわけだ。
平山の生き方を見ているうちに、こちらも自分の日々同じなようでいて変わりゆく生活をもっと慈しみ、信じてみたくなる。心の風通しがよくなるような作品。
2023年末に日本で公開された、2023年公開作品で最高峰の「世界的に評価されるべき奇跡的な作品」!
本作で主演の役所広司が2023年・カンヌ国際映画祭で「男優賞」を受賞したのは十分に納得できます。
本作の主人公は普通に話すことができるのに、基本、話さずに表情やしぐさで訴え掛ける物静かな人物。
それもあり、役所広司の演技力が極めて自然な形で国境を超えるレベルにまで発揮されていています。
2006年・カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した「バベル」で、話すことができない役の菊地凛子が、アカデミー賞の「助演女優賞」にノミネートされたのと似た構造を感じます。
東京の公衆トイレをクリエイティブに改修する「THE TOKYO TOILET プロジェクト」に関連した映像化の話にドイツのビム・ベンダース監督が賛同する奇跡的な動きが生まれ、トイレの清掃員の日常を描き出す流れで「トイレ清掃員のプロフェッショナルな平山」に命が宿りました。
赤いライトを中心に独自性のある自然なライティングによって、より深みのある映像に仕上っているのも重要な要素ですが、何といってもエグゼクティブプロデューサーも務める役所広司の存在感が最大のカギだと感じます。
リハーサルを一切せずにドキュメンタリー映画の如くいきなり本番という最も効率的で役者力が試される現場で、わずか16日の撮影で「最高峰の映画」が完成するという奇跡が起こりました。
世界の人たちが本作を見れば、日本に関心を持って「平山に会いに日本を訪れる」など日本経済にも効果をもたらすことでしょう。
ちなみに、平山が毎日飲んでいる缶コーヒーは、やはりアレなのですね(笑)。
これほど説教臭くなく、生き方や価値観を静かに揺さぶる映画は久しぶり
日本でこのような作品が生まれるのは驚きであり喜びだ。主人公の平山は無口であまり言葉を発しない。だがその分、彼の生き様は、朝起きてから夜の微睡に包まれるまでの一挙手一投足でもって、観る者の心に深く染み入っていく。彼は決して世捨て人ではない。無心になって仕事をこなし、瞳には優しさと温かさが宿り、彼なりのやり方で物事を無駄なく楽しみ・・・そうやって築かれた最小限の日常で、すべてを大切に受け止め、決して悔いを残さない。こんな暮らしに少なからず憧憬の思いが込み上げるのは、我々が何事も過多な現代社会で多くのものを取りこぼし、後悔を感じて生きているからだろう。トイレから人々を見つめる平山の姿はどこかヴェンダース映画における天使のよう。と同時に、日々を真っ新な気持ちで生きようとするその姿は、人生という旅路をひたすら歩み続ける、これまたヴェンダース作品特有のロードムービーの主人公のように思えてならなかった。
街の息づかいを撮った作品
寡黙なトイレの清掃員の日々を美しく撮っている。渋谷のデザイン・トイレのパブリックリレーションの役目を負った作品であるが、トイレの先進的なデザイン性とその清掃員の住む古い木造アパートは対照的である。しかし、ヴェンダースは新しいものを良く見せているわけでも、古いものをみすぼらしく見せるでもなかった。むしろ、新旧のものが共存している東京の街並みに関心を寄せている。カセットテープの音楽を聴き、フィルムのカメラを趣味とする役所広司演じる主人公は、古いもの代表なわけだが、周囲の新世代に振り回されながらもなんとなく共存していく。東京という街は、近代的なものと古いものが混在している場所として多くの海外旅行者にも認識されているのだが、そういう目線がここにはある。しかし、旅行者目線とは異なる視線でそれを成立させていることにこの作品の美点があるだろう。街を撮るというのはなかなか難しいことで、そこに生きる人の息づかいみたいなものがないといけない。この映画はそれが感じられる。
“日常”の有難さを知った2020年代に響く人間賛歌
昨日と今日、そして明日もだいたい同じ一日が繰り返される。当たり前だったそんな日常が、コロナ禍で一変した。職場や学校に通い、人に会って話をし、店で飲み食いする、そんな普通のことでさえも困難になったあの時期を経て、日常の有難さが世界中で認識された今、この「PERFECT DAYS」が世に出るのはまさに完璧なタイミングだ。
成立過程はかなりユニーク。2018年に「THE TOKYO TOILET」プロジェクトがスタートし、渋谷区内17カ所に著名な建築家やクリエイターらが設計した公共トイレが順次設置された。そのPRの一環としてまず短編映画の企画が立ち上がり、役所広司とドイツの名匠ヴィム・ヴェンダースの参加が決まってから長編劇映画として再構想されたという(おおよその経緯はWikipediaの「THE TOKYO TOILET」と「PERFECT DAYS」の項で確認できる)。
小津安二郎への敬愛をドキュメンタリー「東京画」で示したヴェンダース監督らしく、本作の主人公であるトイレ清掃員の平山は実直で心優しく日常を大切に生きる男で、物語はさほど大きな事件が起きることもなく淡々と進む。近所の老婆が通りを竹ぼうきで掃く音で目覚め、仕事道具を積んだ車で担当する渋谷区の公衆トイレに向かい、丁寧に便器や手洗い場や床を清掃する。樹木を好み、木漏れ日をフィルムのカメラに収め、銭湯に通い、馴染みの飲み屋に寄り、文庫本を読んで寝落ちする。そこには、平山というひとりの人間の生きざまをそっと見守り讃える温かなまなざしが確かに感じられる。
寡黙な平山の心情を代弁するかのように、彼がカーステレオや自室のラジカセで流すカセットテープの60~70年代の洋楽が、夜明けと朝日の美しさ、一日の始まりの高揚や感謝、日曜の午後の気分などを歌い上げる。どの曲もシーンに合っているが、とりわけラスト近くで流れるニーナ・シモンの「Feeling Good」と役所広司の表情の相乗効果が抜群で、ヴェンダース作品としてだけでなく邦画史においても屈指の名場面として大勢の観客の心に残るはずだ。
役所広司が差し出す新たな引き出し
毎朝、木造アパートの一室に敷いた布団から起き上がり、植木に水をやり、自販機でコーヒーを買って飲み、トイレ清掃に向かう男。平山というその男性の日々のルーティンが、関わる人々とのやり取りによって微妙に揺れ、それでも基本型はキープしたまま進んでいく。
なんとミニマムで上手い構成かと恐れ入る。与えられる情報の積み重ねによって、平山の背景が垣間見えて来るのだ。なぜ、彼はアパートに一人暮らしなのか、なぜ、トイレ清掃員なのか、という疑問が、本当に微かではあるが、腑に落ちて、ビム・ベンダースの脚本と演出の妙に心を奪われてしまった。
世界的な建築家たちが携わった東京・渋谷にある17のおしゃれトイレが舞台というのも上手いと思う。しかし何よりも、平山を演じる役所広司の、人を遠ざけず、かと言って近づけず、日々の生活を存分に楽しんでいるようで、実は心の底には深い悲しみを湛えている、ハッピーでアンハッピーな表情と演技が凄くてまいる。ベンダース演出の下、彼はまた新たな引き出しを差し出してきた。
映画の光と影、孤独=自由を享受する
役所広司が演じる平山は寡黙な男であり、規則正しく、ルーティンをこなす。毎朝植木に水をやり、仕事を終えると銭湯に行き、居酒屋で酒を飲み、部屋では古本を読みながら寝落ちするのもその一つ。極力他人と関わらないことで“孤独”であることを忘れようとしているのかもしれませんが、“孤独”=自由を享受しているようにも見えます。
50歳をゆうに過ぎているであろう男が、なぜアパートで一人暮らしをして、清掃員の仕事を黙々としているのでしょうか。その研ぎ澄まされたような姿は悟りに至った僧侶のようにも見えます。
でも、そんな彼が見ている世界、ふとした時に向ける視線の先には木々や光が溢れているのです。朝日、木漏れ日、夕日、街並みや公園、トイレ、運転中の車のフロントガラスなどの光の屈折や反射。ヴィム・ヴェンダース監督の過去作品を見ていれば、ここに過去のシーンを重ね、敬愛する小津安二郎監督作品の面影も感じ取ることができるのではないでしょうか。
Snapshot of Today's Tokyo
Wim Wenders' slice of life drama about a toilet janitor in Shibuya shows an appreciation for one the city's most prestigous whilst undervalued services. The act of toilet cleaning gets a lot of screentime while showing off the city's rich assortment of commode architecture. Lighthearted and at times cheesey, the mystery behind Koji's cleaner's past is left to interpretation upon veiled sadness.
平穏こそ「10段階の10」であると感じた🚻
近年は人心の荒廃により、どこに行っても自分勝手な人に遭遇する様になったと感じますが、そんなものは無く、仕事と生活に専念できるのは、おっさんとは言え幸せに感じました。トイレ掃除は、単独・集中・浄化等を表していると思います。女性を抱きたくなりますが、これは主人公ではなく若い同僚の担当で、ああ主人公じゃないのかと少しずるく感じました。行きつけの店のママ(謎の熱唱シーンあり)、また姪が登場するものの特に何も無く、Feeling Goodが流れて気持ち良いエンドでした。
究極の毎日?
役所広司さんの芝居が素晴らしかった
まさにトイレ清掃員そのもの。朝早く起きて毎日同じルーティンを繰り返すのだが、無駄がなく洗練されている。一人暮らし一人仕事が基本なので誰とも話すことなく淡々と仕事をこなしていく。キレイにすることが好きで仕事をキチッとこなしていた。淡々とそして魂を乗せて。そこにかっこよさがあった。ささいな趣味もあった。フィルムカメラ、木々を愛したり、お気に入りの音楽をカセットテープで聴くこと。人にも優しく困っている人を助けた。まさにPERFECT DAYS。セリフは少なくとも考えさせられる場面や、人間くさい場面が多々あり、そこに良さを感じた映画だった
全1021件中、1~20件目を表示