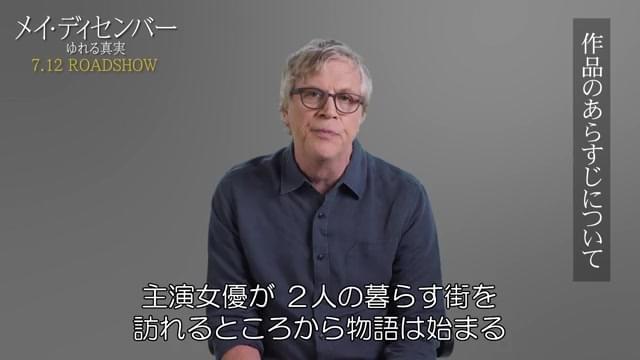「モデルにされた男性への配慮に欠け、後味も苦い」メイ・ディセンバー ゆれる真実 高森 郁哉さんの映画レビュー(感想・評価)
モデルにされた男性への配慮に欠け、後味も苦い
本作は米国で実際に起きた事件をモデルにしている。1996年、当時34歳で既婚の小学校教師メアリー・ケイ・ルトーノーは、13歳の教え子ヴィリ・フアラアウと性的関係を持ち妊娠、児童レイプの罪で実刑判決を受け、服役中に出産。メアリーは夫と離婚し、出所後にヴィリと結婚して家庭を持った。スタンダードナンバー『September Song』の歌詞から、メイ・ディセンバー(5月と12月)が親子ほど歳が離れたカップルを意味する慣用句になったが、メアリーの事件も“メイ・ディセンバー事件”と呼ばれた。なお、ケイト・ブランシェットが演じる中学校教師が15歳の教え子と関係を持つ2006年の英国発「あるスキャンダルの覚え書き」も、同じ事件をモデルにした小説の映画化だ。
「メイ・ディセンバー ゆれる真実」の成り立ちはというと、キャスティングディレクターとして長年キャリアを積んだサミー・バーチが書いた初の長編映画用脚本がプロデューサーのジェシカ・エルバウムの目に留まり、脚本を気に入ったナタリー・ポートマンも製作に参加。監督は「キャロル」のトッド・ヘインズに決まった。
本作は事件そのものを描くのではなく、世間を騒がせた出来事から20数年後、穏やかに過ごしているグレイシー(ジュリアン・ムーア)とジョー(チャールズ・メルトン)と子供たち家族のもとに、事件を題材にした映画の役作りのためハリウッド女優エリザベス(ナタリー・ポートマン)が訪れるところから始まる。エリザベスは近くのホテルに部屋を取りしばらく滞在して家族と数日を過ごし、今の暮らし向きから事件当時のことまでさまざまな質問を浴びせ、グレイシーの言動を観察し、キャラクターに近づこうとする。
物語の軸は主に2つあって、1つは成人女性と未成年男児がセックスしたときの心理的な関係性はどうだったのか(どちらに主導権があったかなど)を解き明かそうとするエリザベスの試み。もう1つは、長年好奇の目と非難にさらされ嫌がらせも受けてきた夫婦のプライベートな領域に、取材という名目で踏み込んでいく映画人(より大きくとらえるならメディア業界)の危うさについての自己言及だ。
鑑賞しながら気になったのは、モデルになった家族たちを実際に取材し了解を得た内容なのかということ。映画ではグレイシーの元家族も登場し、息子は母が起こした事件の影響で精神的な問題を抱える青年として描かれている。特に行き過ぎた創作だと感じたのは、ホテルの部屋でエリザベスに誘惑されたジョーが行為に及ぶエピソード。映画がフィクションであり実在の人物に無関係というのが建前とはいえ、女性に言い寄られたら(妻も子供もいるという)立場や倫理観から自制することもなくあっさり事に及ぶ男性だという印象を、間接的にせよモデルにされたヴィリに与えることになるのではないか。観終わった後に調べてみると、メアリーは10数年の結婚生活ののち2018年にヴィリと離婚、2020年に58歳で死去していた。米国での映画公開後、業界誌The Hollywood Reporterから取材されたヴィリは、本作を観て「気分を害した」と明かしている。製作陣から連絡を受けたことは一度もなく、彼の人生の物語と苦痛から「ハリウッドとメディアが搾取している別の例」だと感じたという。
たとえば「スポットライト 世紀のスクープ」「ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男」「SHE SAID シー・セッド その名を暴け」のように、さほど年月の経っていない大事件をスピーディーに劇映画化する米映画界の機動力とジャーナリスティックな志には敬意を表するし、邦画界と比べて羨ましくも思う。だが「メイ・ディセンバー」は、先に挙げた3作に比べると作り手の志も、作品の社会的意義もずいぶんと低いように感じる。大勢に影響を及ぼした権力者の性加害や大企業による不正を題材にすることは、啓発により将来の類似の事件と被害者を防ぐ効果も見込めるだろう。だが、長年にわたり興味本位の報道と世間からの誹謗中傷にさらされてきたメイ・ディセンバー事件の当事者たちを題材に、存命中の男性が気分を害するような創作を加えてまで映画を作る意義は果たしてあるのか。
エリザベスが行為のシーンの撮影に臨むラストにしても、映画人の自己批判を含むブラックユーモアのつもりかもしれないが、当事者への配慮と敬意を欠く作り手の尊大さと傲慢さが強調されるばかりで、後味の苦さがいつまでも残り続けた。