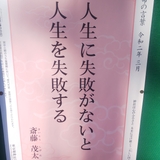落下の解剖学のレビュー・感想・評価
全330件中、221~240件目を表示
自殺ってことで良いんじゃないの?
大音量で繰り返されるラテンミュージックの中行われるインタビュー。繰り返される客観性に乏しい主張を繰り返す法廷劇。そして視覚障害。
作品の主旨としては真実を明らかにするタイプのものとは、感覚的にも異なる。何だったんだ?という余韻に、きっと作品のユニークさがある。ほんやくコンニャクを使って犬の意見も聞いてみたい。
白黒決着は最初からついている上での不条理劇
こんな素材で映画が一本出来上がるなんて、驚きな程に会話中心の作劇、しかも舞台は山荘のような自宅と裁判所のみ、なのにこの緊張感を維持するところが凄く、カンヌでもアカデミー賞でも評価されるだけのことはある。なにしろ徹底的に人物にフォーカス、しかもドキュメンタリー調のカメラで、これはこれで映像としての映画がちゃんと成立している。タイトルが恐ろしいけれど、夫が事故死?した真相をこれでもかの粘着質で追及する。その過程ではあらいざらい事象を解剖するかのように暴いて行く、だから解剖学なのでしょう。
冒頭からの親子三人の日常の一コマが描かれるが、ここをぼんやり見てたら元も子もない。すべての発端がこの数分の映像に絡んでくる。で、雪中を散歩に出かけた息子と愛犬(老犬)が家へ戻り犬がすぐさま反応して父親の転落死で映画の幕が上がる。家族しかいないこんな山中で何故? と数多のサスペンス劇場では謎解きが始まるパターン通り、警察から弁護士と入れ代わり立ち代わり検証が始まるのもよくある展開。ただし、大きく異なるのは解くべきヒーローがここには不在だと言う事。ヒーローを主役としたエンターテイメントとは違いますよと明確にしている。
それでは何が主役と言えば、家族三人のこれまでの「わだかまり」を引きずり出し、その見えなかった実態こそが主役と言う事、だから解剖なんですね。であればこそ演ずる役者へのフォーカスは必須要件で、それを担うサンドラ・ヒュラーの演技にクオリティは委ねられる。彼女の演技から明々白々なのは。彼女は完全に「白」だと言う事。図らずも被疑者扱いに陥ったとしても、その困惑と冷静な所作にミリ単位たりとも疑念の余地はない、監督も主演もそのように演じたはず。さて、裁判の行方は・・・、なんて煽る類の映画ではないのです。どんなに不利な状況が暴かれようと、してない事をしていたと誤認されようと、それを跳ね除ける真実の所在を信じている強さこそを観て欲しい。どれほど絶望的な喧嘩をしようと、夫婦だからこその喧嘩であり、根底にある「愛」を見誤ってはいけません。そこに価値があるから本作の出色の傑作ぶりが証されるのです。
それにしても赤いマントに身を包んだ検察官の妙に若いこと! 執拗に言葉を歪曲し単純化する悪意には辟易させられる程のパワーを見せつける。対する弁護士は加藤雅也にそっくりなイケメンで、彼女の支えとして寄り添う様が温かい。要は視覚障がいを持つ11歳の息子の存在で、目撃とは文字通り見えることだから、ここでは聞こえた事実のみが映画にサスペンスを与える。法廷でUSDに録音された音声で喧嘩の様子をスピーカーで流される際のご本人の辛さたるや、到底自分だったら耐え難いと思わざるを得ない。
こと左様に本作では「音」が絶大な効果を発するのです。もとより明るいスティールパンが響き渡るカリビアン・ミュージックが事故の根幹に大音量で響き、息子のピアノの音色、そして法廷での録音と、耳を澄ませて聞き入る努力が観客にも要求される。それともう一つ、言語です。本作はフランス資本の映画であるものの、夫がフランス人設定、妻がドイツ人設定、でイギリスでの生活が長く、金銭的問題によりフランスのペンション経営に至った経緯から、家庭内では英語設定、社会すなわち法廷ではフランス語設定。で、彼女はフランス語は苦手のもどかしさが全編を覆う仕掛け。
ことにも、いよいよの大詰め、息子が最後に証言するシーンが秀逸である。愛犬を病院に運ぶ際の映像が再現されるも、父親の喋る画に息子の声でシンクロのようにセリフが聞こえる。父親の死生観が明らかにされるが、ちょっと息をのむ程に凄いシーンだと私は思う。声質こそ少年のものだが、抑揚から息遣いまで父親の再現です。これをも検察はあくまで主観であり証拠にはならないと声を荒げるものの、陪審員にはそうは聞こえなかったようで。
「私は殺してません」「いや、それは問題ではない、人の目にどう映るかかだ」に端的に示されるように、客観的判断がつかないからこそ、公共の場で白黒決着をつけようと言う裁判制度。無実の彼女に冤罪を着せるリスクが却って増大してしまうと言うのに、この不条理。実に恐ろしい、社会は個人のミスを一切見逃さない正義感が、却って邪悪に見えてくる。傑作です。
夫婦の解剖学
夫婦の解剖学
カンヌ パルムドールという看板に加え、“雪山”というキーワードに惹きつけられて観賞。
【物語】
舞台はフランスの山間部(多分アルプス山麓)。
ベストセラー作家のサンドラ(ザンドラ・ヒュラー)は、夫と11歳の息子(ミロ・マシャド・グラネール)と人里離れた山間部暮らしていた。ある日息子が犬と散歩から帰って来ると、家の前で父親が血を流して倒れていた。息子の叫び声を聞いたサンドラが駆け付けるが、夫は命を落す。
屋根裏部屋から落下したことは明らかだったが、事故か、自殺か、殺人か。目撃者はおらず、物証も限られており、真相は謎に包まれる。警察は捜査の結果、殺人の容疑でサンドラを殺人容疑で逮捕。真相究明は法廷の場に委ねられる。
サンドラは旧知の弁護士を雇い、無実を主張するが、・・・
【感想】
冒頭、サンドラと取材に来た女学生の会話シーン。
バカでかい音量の音楽と噛み合わない会話にイラっとする。その状況も後の法廷で論点となる。
そして取材の女学生が帰ってほどなく、夫の死亡。序盤から不穏な立ち上がり。
一方で何度も映される、サンドラの家の周囲から見渡せる雪の山々がとても美しい。最寄りの都市はグルノーブルということのようなので、アルプスに違いない。
そんな癒しもあり、前半は不穏ではありながら、さほどピリピリとした空気は感じない。
が、法廷シーンに入り、中盤から終盤に向けては、グサグサと胸をえぐられるような思いだった。
本作、既婚者と未婚者では感じ方がだいぶ違うのではなかろうか。
俺は結婚して今年で35年。なんとか、結婚生活は継続しているけれど、その間他人は話したくないようなことも多々有った。 激しい喧嘩も一度や二度では無いし、相手への不満も言い出したらキリが無い。 程度の差はあれど、大半の夫婦は似たようなことを乗り越えながら暮らしているのではないだろうか。感情を時には爆発させながらも怒りは胸にしまって、喜びもまた共にして人生を過ごして行くのが夫婦ではないかと思う。
夫婦の諍いは、親しい友人に愚痴をこぼすこともあろうが、誰しも世間に晒したくはない。しかし、本作の法廷では容赦なく他人の前で晒されてしまう。しかも、自分を責める材料として。
こんなのは自分には耐えられないという思いに駆られる。
人には見られたくない、最もプライベートな夫婦の関係を公衆の面前で奥深くまで解剖されていくような感覚だ。
また、「衆人に晒される」とは別に、夫婦喧嘩のシーンは身に覚えのあるようなセリフが飛び交い、ホントにグサリグサリと・・・
面白いと言うよりは、俺にとっては胸に刺さる作品だった。
ミステリーではあるが、結末も“種明かしでスッキリ!”と言う作品ではないのでご注意。
ミステリーの作りではあるが、どこまでもヒューマンドラマだ。
勝手に期待していたより…
面白いフランス裁判映画
犬は一応無事です
夫殺しの容疑で起訴された妻の裁判を通して、夫婦と親子・家族の実情が詳らかにされるストーリー。
自分は事前の作品紹介からサスペンスやミステリーのような印象を受けており、そのジャンルの映画がカンヌで評価されるのを意外に思っていたのだが、実際に作品を観て納得がいった。本作はサスペンスでもミステリーでもない法廷劇で、ほぼ自宅と法廷における会話のみで構成された骨太の作品であった。
まともな物証がないため、裁判の決め手は陪審や裁判官の心証となる。それで現代の公判が維持できるのかは置いておくとして、法廷では、私小説的な作品で有名な女性作家が夫の故郷の静かな山林でスローライフを送っている、というイメージの下にあった実体を下世話な程に暴き立てていく。
事件の真実ではなく私的な暗部を暴かれる脅威とその先にある境地を作品のメインに据え、その物語を会話だけで進めてみせた脚本の力は見事である。登場人物の恐れや不安を疑似体験させるような、地味に不快感を煽る演出が続くのも挑戦的だった。
じっとりとした緊張が続く快適とは言い難い時間なのに、最期まで目を離せない不思議な2時間半だった。
ラストを迎えた時、妻の帰る場所であろうとし続けた夫も、息子との時間のために様々なものを投げうった父も、もうどこにもいないのだと思うとやるせない気持ちになった。
この一家にも壁の写真に納められているような笑顔の時間は確かに存在したのだろう。家族三人が揃って映った写真が無いのは、ただの核家族の事情なのか、それともこの結末を暗示していたのだろうか。
落下するボール、落下した夫、落下していく?ベストセラー作家。 ボー...
期待していたが
真実よりどう思ったか
パルムドールを取ったこともあり、どんなラストを見せてくれるんだろうと、期待しすぎてしまっていた。フランス映画なので、結構ぬる〜っと終わる。まぁなんと言うか、思ったのと違った。やっぱり、できればアカデミーやカンヌで賞を取る前に、公平な目で映画は見たいよね。
この映画はどちらかというと絶壁に立たされた時の人間の心理描写等が秀逸な作品であるため、どんでん返し・衝撃のラストを彷彿とさせる予告自体、ナンセンスなんだろう。タイトルの「落下の解剖学」も微妙にズレている気がしたけど、原題の直訳なんだね。にしても、映画は靴紐のようにきちんと結んで終わって欲しいたちなので、本作のように緩いままだと締まりが悪くてスッキリしない。観客に投げかけるような作りでは無いものの、作り手なりの解釈・回答は作品の性質上示して欲しかったなぁと思ったり。
2時間半越えかつ、会話劇と言っても過言では無い法廷ドラマなのに、退屈を感じさせない作りになっているのは凄い。音楽の色やタイミング、多方面から読み解く展開も見事だった。盲目の男の子の非常にリアルな演技には驚かされたし、彼の心情をそっくりそのまま代弁するピアノも、家族の崩壊を暗示しているようで恐ろしかった。更にはワンちゃんの演技にも目を奪われる。品質に関しては申し分無くて、ノミネートも納得。観客の心を掴む、作り込まれた映画的な表現は素晴らしかった。
ただ、もっと<正義とは何か>みたいな思い悩まされるメッセージが込められていると想像していたから、この点数になってしまった。正直、テーマとしては在り来りのように見えてしまうし、この作品ならではの斬新な切り口で見解していたら好きになれたんだろうなぁと思った。
これはSNS社会にも通じるのでは…
とても良い映画でした。
お気に入りなのは序盤の一節です。
"待って、私は殺してない"
"そこは重要じゃない"
本作では決して真実を追求せず、状況証拠や証言から妥当な結末を議論していきます。
この映画は観客に見せている部分と見せていない部分の線引きが上手で、どちらとも取れるように最後まで着地しません。観た後に語りたくなる映画です。
どの役者さんも演技が上手で、惹き込まれるものがありました。主人公サンドラが夫を捲し立てるシーンがあるのですが、説教の内容が痛いぐらいに刺さりました。弁護士のヴィンセントを演じたスワン・アルローさん、とても顔がタイプです。
見ていて思ったのは、昨今のSNS社会に通ずるものがあると感じました。ポスト・トゥルースという言葉があるように、真実かどうかは重要ではなく感情に訴えかけるものが支持を得やすいです。
セクシー田中さんの事件がありましたが、結局真実は本人にしか分からなくて、「脚本家のインスタグラムの投稿が〜」等と騒ぎ立てるのは劇中の傍聴人やワイドショーと重なるものがありました。
まじでhot lawyerだし、話も面白かった
Xで海外レビューがあまりに’hot lawyer!’ばっかだったので、予告では惹かれなかったがその噂の弁護士を鑑賞しに行くか〜と見たんだけど、話も面白かった!
予告編とは違い8割裁判所でのセリフ劇なので、セリフの情報量が多い系苦手な人は、このREALLY hot lawyer見ていればよろし(すぐ出てくる)。
犯人これ妻っしょと、このふさふさグレーロングヘアー仏英話者スタイルも良いsexy hot弁護士に騙されないぞと見てたんだけど、
坊主の検察官の妄想決めつけboyっぷりがやばくて、とくに最後の方ゲラゲラ笑ってしまった。。
たぶんだけどこれはもはや愛すべき人物!
小説には私生活が投影されているはずだの演説、せめて投影されているはずという主張の根拠を本人インタビュー記事なり何なり持ってきなよ!みたいな。
赤いタートルネック着た息子の証言の時に「その結果の要因は2つ考えられるよね?どうして1つに決めつけてるの?」っていうポンコツ坊主検察boyの発言に対し、12歳の息子めちゃいいこと言った!(思わず拍手)
「原因が分からない時は根拠を考えれば良いと思うけど、母にその根拠となるような理由がない」
検察坊主12歳に言われちゃったね、って私は母のような目で見守ってた。
てか最後の中華料理屋でのY-shirt HOT LAWYER、ありがてぇ...という境地で眺めてた。
明日からも頑張ってこのつまらない日常生きられるわ!
24-030
「真実」は時に虚構を事実にする。
真実は時に真実でないし、真実である必要もない。という事を酷く痛感します。
我々は人間として生きる上で、自分を取り巻く世界を自分の中に構築しますよね。それは自分にとって真実ですが、自分以外の人間にとっては真実ではないこともしばしばあります。それを酷く実感させられました。
最終証言は果たして真実だったのか。
被疑者サンドラが言い渡された判決は果たして真実に迫れていたのか。
「真実」とは一体なんなのか。を、考えさせられる作品でした。
それはさておきスワン・アルローの顔が良すぎて惚れ惚れしながら見てました。津田健次郎さんに似てません?
夫婦のことは2人だけにしか理解できないことがたくさんあるし、どちら...
マジックショーのようだった。
ただただ芝居の技術の高さを楽しむ作品。
スタニスラフスキーはもちろん、
ステラ・アドラー方式の、
お互いの関係性の中で、
芝居をビルドアップしていく中でちょっとした仕草、表情を複数重ねて試行錯誤して取捨選択していくような、
訓練を受けた人たちの、
マジックショーのようだった。
状況を客観的に話す芝居、
客観的から主観が入ってくる芝居、
感情的な芝居、
それぞれ相手の芝居によってシフトチェンジ、減速加速、出力高低、すべてコントロールしている。
小説家同士、その内容と現実、
録音部分の構成等、
シナリオでもうまい部分もあるが、それらのセリフのキャッチボールが素晴らしい。
欧米複数国で、
オーディションを行なった事があるが、毎回、技術の引き出しの多さに驚く。
ロゴス(論理)、エトス(倫理)、パトス(情熱)、同じシナリオでも、
それぞれの違う伝え方、
論理だけでは人は動かない、
倫理が無ければ観客は納得しない、
情熱との按分の割合、センス、
そんな技術に関して、芝居の技術に関して、youtubeで話してます。
スヌープ・ドギー・ドッグまで、いい芝居していた。
圧倒的有利な状況
全330件中、221~240件目を表示